公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。
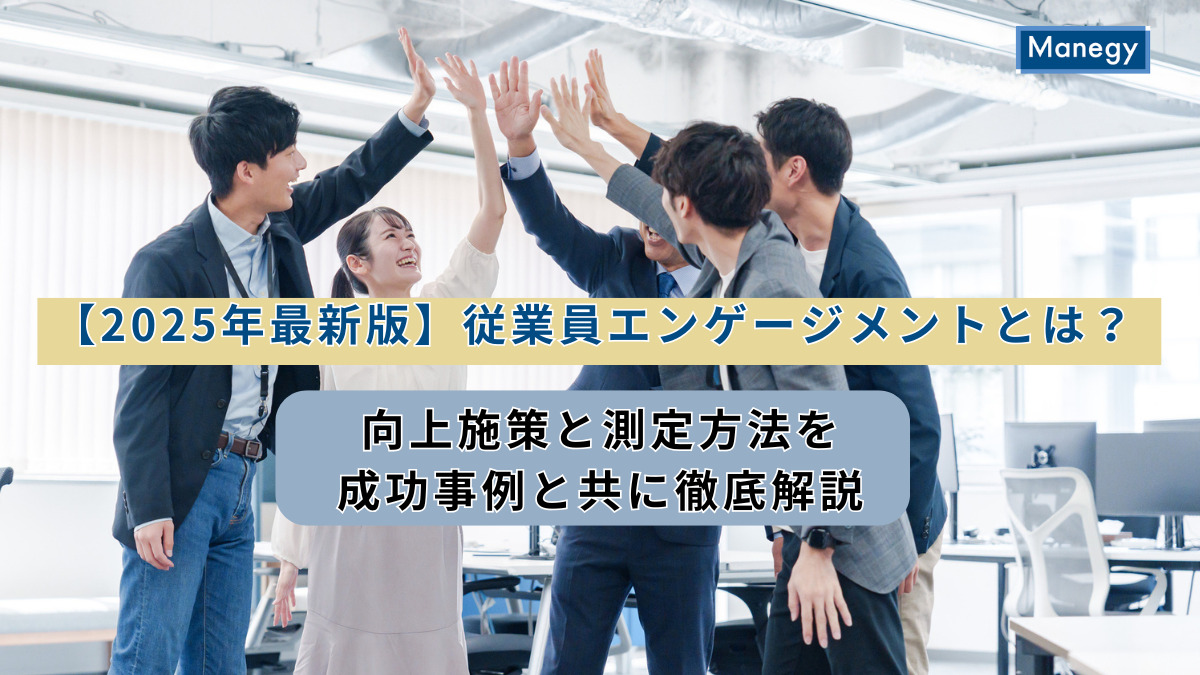
「若手社員の離職が止まらない」「会議を開いても意見が出ず、組織に一体感がない」──そんな“静かな危機”を感じていませんか。
これらの背景にあるのが、従業員と組織との関係性を示す指標である エンゲージメント の低下です。
エンゲージメントは、従業員満足度やモチベーションとは異なり、企業と個人が同じ方向に成長していけるかを測る“組織の体温”とも言える存在。
近年は人的資本経営の観点からも、経営層が注目すべき最重要テーマとなっています。
本記事では、2025年最新版の情報をもとに、エンゲージメントの定義から測定方法、向上施策、さらに国内外の成功事例までを徹底解説します。
まずは自社の現状を把握し、改善への第一歩を踏み出してみましょう。
近年、企業価値を財務指標だけでなく「人材の活用度」で測る 人的資本経営 が注目を集めています。
その中で、従業員と組織の関係性を測るエンゲージメントは、単なる人事指標ではなく、経営全体に直結する最重要指標として位置づけられています。
ここでは、その理由を整理します。
エンゲージメントとは、従業員が「仕事や組織にどれだけ前向きに関わっているか」を表す概念です。
学術的には以下の3要素で説明されます。
熱意:仕事に誇りを持ち、意欲的に取り組んでいる状態
没頭:業務に深く集中し、時間を忘れて取り組める状態
活力:心身ともに活力があり、困難に直面しても粘り強く取り組める状態
これらが揃っていると、従業員は「自分の成長と会社の成長が重なっている」と実感でき、自然と貢献意欲が高まります。
しばしば混同されがちなのが「従業員満足度」や「モチベーション」との違いです。
従業員満足度:職場環境への快適さや満足感を測る指標(=居心地の良さ、現状維持)
モチベーション:個人が持つ動機ややる気の度合い(=個人の内的要因)
エンゲージメント:従業員と企業が同じ方向を向き、互いに成長を促し合う関係性(=貢献意欲と相互成長)
つまり、エンゲージメントは「従業員が企業にどれだけ深く結びつき、力を発揮しているか」を測るものであり、人的資本経営に直結する指標と言えます。
各種調査では、エンゲージメントの高い企業は以下の点で業績に好影響を与えることが示されています。
生産性向上:従業員が自律的に動き、業務効率が高まる
離職率低下:会社に愛着を持つため、長期的に働き続ける傾向が強い
顧客満足度向上:エンゲージメントの高い従業員は、より良いサービスや対応を顧客に提供する
イノベーション創出:挑戦や改善に積極的となり、新しいアイデアが生まれやすい
このように、エンゲージメントは人的資本経営の成果を測るうえで不可欠な指標であり、企業の競争力強化に直結しています。
エンゲージメント向上の第一歩は、現状の「組織の体温」を正しく把握することです。
いきなり施策を打つのではなく、まずはサーベイ(調査)を通じて客観的なデータを集めることが欠かせません。
健康診断で数値を測らずに治療を始めないのと同じで、エンゲージメント改善も“診断”から始まります。
エンゲージメントサーベイには大きく2種類があります。
【質問例】
Q. あなたは自分の仕事を誇りに思いますか?
Q. 上司はあなたの成長を支援してくれていますか?
Q. 職場には意見を安心して言える雰囲気がありますか?
Q. 今後もこの会社で働き続けたいと思いますか?
このような問いを盛り込むことで、組織の強みと課題を明確にできます。
サーベイを実施したら、集めたデータを「全社平均」だけで評価するのは不十分です。
部署・職種・年齢層・勤続年数などの属性別に分けて分析することで、課題の所在が見えてきます。
例えば、若手社員のエンゲージメントが低ければ「キャリアパスや成長機会の不足」が課題である可能性があります。
ある部署だけ数値が低ければ「マネジメントスタイルや職場環境」に改善の余地があるかもしれません。
エンゲージメントを高めるには、場当たり的な施策を並べるのではなく、従業員がエンゲージメントを感じる根本的な要因(ドライバー)に基づいて取り組むことが重要です。
学術研究や実務事例から抽出される代表的な4つのドライバーを軸に、具体的な施策例を紹介します。
従業員が自社の存在意義や未来像に共感できるかどうかは、エンゲージメントに直結します。
経営層の思いや戦略を「伝える場」を定期的に設けることが欠かせません。
ポイントは「一方通行の発信ではなく双方向の対話」を重視することです。
従業員が日々の仕事を通じて成長を実感できるかどうかも大きな要因です。
挑戦機会や学習機会の提供が欠かせません。
「やらされ感のある仕事」から「自分の成長につながる仕事」へと意識を変える仕組みが必要です。
職場の人間関係はエンゲージメントに最も直結する要素のひとつです。
特に上司との信頼関係は離職率にも大きく影響します。
「心理的安全性」を醸成する取り組みは、創造性や主体性の発揮にもつながります。
従業員の努力が正しく評価され、待遇に反映される仕組みがなければ、エンゲージメントは下がってしまいます。
公平感と承認の仕組みは、モチベーションを維持し、組織への貢献意欲を高める基盤となります。
エンゲージメント向上は、一部門だけの取り組みでは成果が限定的です。
経営層を巻き込み、全社的なプロジェクトとして推進することで初めて、組織文化に根づかせることができます。
ここでは、プロジェクトを成功に導く3つのポイントを解説します。
エンゲージメント向上は「人事施策」ではなく、経営戦略の一環として扱うことが重要です。
経営層が自らメッセージを発信し、プロジェクトを全社的な課題として掲げることで、従業員にも本気度が伝わります。
実務担当者は、エンゲージメントが業績や人的資本経営に直結することをデータで示し、経営層を巻き込む材料を用意すると効果的です。
施策を漫然と進めるのではなく、サーベイ結果から特に課題が顕著な層(例:若手社員、ある部署)を特定し、優先度を決めます。
そのうえで、改善効果を測定するために KPI(例:離職率、従業員推奨度スコア、研修参加率) を設定します。
KPIは「数値で追えるもの」にすることで、施策の有効性を検証できるようになります。
設定した施策は一度きりではなく、実行後に効果を測定し、改善を繰り返すことが欠かせません。
例えば、半年ごとにサーベイを実施し、前回との変化を分析するのが有効です。
PDCA(Plan→Do→Check→Act)サイクル を定着させることで、施策が形骸化せず、継続的にエンゲージメントを高める文化が醸成されます。
エンゲージメント向上は理論や施策の紹介だけでは実感が湧きにくいものです。
実際に成果を上げている企業の事例を知ることで、具体的なイメージが掴めます。
ここでは国内と海外から2つの成功事例を紹介します。
ある国内の中堅IT企業では、若手社員の離職率が高いことが長年の課題でした。
そこで取り組んだのが、1on1ミーティングの全社徹底です。
週1回、上司と部下が30分間対話する時間を設け、業務の進捗だけでなくキャリアの悩みや将来の希望を気軽に話せる仕組みを整えました。
結果、社員が「自分を理解してもらえている」という実感を持ちやすくなり、心理的安全性が向上。
若手社員の早期離職率は2年でおよそ半減し、同時にエンゲージメントサーベイのスコアも改善しました。
米国の大手テック企業では、イノベーション創出に不可欠な要素として 「心理的安全性」 を重視しました。
従業員が自由に意見を言える文化を醸成するために、会議での発言ルールを工夫し、階層や役職に関係なく誰もが提案できる仕組みを整えました。
加えて、失敗を責めるのではなく「学びの機会」として評価する制度を導入。
これにより従業員の積極性が高まり、革新的なアイデアが継続的に生まれる環境を実現しています。
この事例は、エンゲージメントが高まることで組織が持続的に成長できる ことを示す典型的な例です。
エンゲージメント施策を進める過程で、多くの担当者が抱える細かい疑問に答えます。
よく検索されるテーマをFAQ形式で整理しました。
A. 年1回の大規模調査に加えて、四半期ごとの「パルスサーベイ」を組み合わせるのがおすすめです。
年1回では変化が見えにくいため、短い質問を定期的に実施し、組織の“温度”を継続的に把握しましょう。
A. まずは全社的に一気に解決しようとせず、スコアが低い部署や属性を特定し、優先課題を絞り込むことが重要です。
例えば「若手社員のキャリア不安」が浮き彫りになった場合には、1on1面談やキャリア研修から着手するのが効果的です。
A. 部下との信頼関係を築くことです。
特に、定期的な1on1やフィードバックを通じて「自分を理解してもらえている」という実感を与えることが大切です。
マネージャーの関わり方ひとつで、チーム全体のエンゲージメントは大きく左右されます。
A. 無料ツールを使った簡易サーベイや、経営層からの定期的なメッセージ発信、1on1の導入など、コストをかけずに実践できる施策は多数あります。
重要なのは「会社が従業員に関心を持っている」と伝わることです。
小さな工夫でも効果が出やすいのが中小企業の強みです。
従業員エンゲージメントは、一度の施策やキャンペーンで劇的に改善できるものではありません。
エンゲージメントとは、従業員と企業の間に信頼と共感が根づき、時間をかけて醸成される 「組織文化そのもの」 です。
大切なのは、完璧な制度を一気に整えることではなく、まずは現状を正しく把握し、優先課題に合わせた小さな改善を積み重ねること。
サーベイで現状を可視化し、対話を通じて課題を共有し、改善のPDCAを回す。
その繰り返しが、結果として離職防止や生産性向上、企業価値の向上につながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

英文契約書のリーガルチェックについて

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
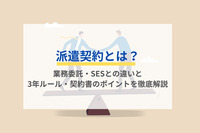
派遣契約とは?業務委託・SESとの違いと3年ルール・契約書のポイントを徹底解説
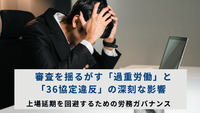
審査を揺るがす「過重労働」と「36協定違反」の深刻な影響:上場延期を回避するための労務ガバナンス
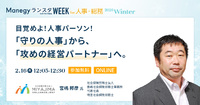
「守りの人事」から、「攻めの経営パートナー」へ【セッション紹介】

勢いづくりの五原則/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第4話】

早期退職制度を正しく運用するには?社員の納得を得るための実践知

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?

ラフールサーベイ導入事例集

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
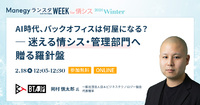
「脱・便利屋」管理部門・情シスの進むべき道を解説【セッション紹介】

人事制度を「義務」から「自発性」へ変える組織原理とは?①〜構造変化時代に求められる自発性とエンゲージメント〜
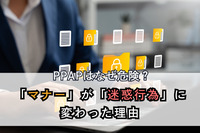
PPAPはなぜ危険?「マナー」が「迷惑行為」に変わった理由
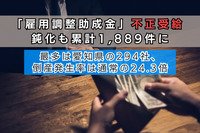
「雇用調整助成金」不正受給 鈍化も累計1,889件に 最多は愛知県の294社、倒産発生率は通常の24.3倍
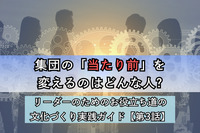
集団の「当たり前」を変えるのはどんな人?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第3話】
公開日 /-create_datetime-/