公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
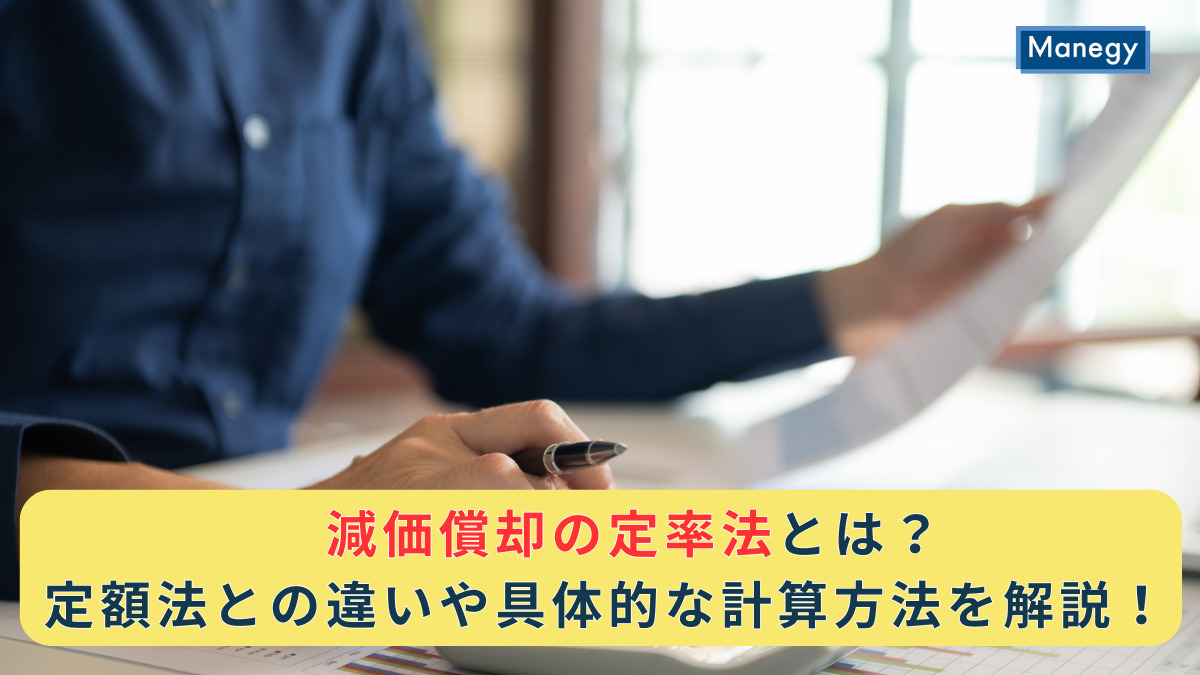
減価償却は、企業の財務における会計処理のひとつで、中でも「定率法」は、初期に多くの費用を計上できることから、資金繰りの観点で多くの企業に採用されています。
本記事では、経理・財務の実務担当者に向けて、定率法の仕組みや計算方法、定額法との違いなどをわかりやすく解説します。
企業が設備投資を行う際、購入した資産の価値は時間とともに減少していきます。
この価値の減少を会計上適切に反映させる仕組みが減価償却です。
たとえば、100万円の社用車を購入した場合を考えてみましょう。
この100万円を購入年度に「車両費」として一括計上するのではなく、その車両が実際に事業に貢献する期間(耐用年数)に応じて、毎年段階的に費用として処理していきます。
このようにして、資産の経済的価値の減少を各年度に適切に配分するのが減価償却の基本的な考え方です。
この記事を読んだ方にオススメ!
減価償却制度は、会計の基本原則である「費用収益対応の原則」に基づいています。
固定資産は購入年度だけでなく、複数年にわたって収益獲得に貢献するため、取得費用もその期間に応じて配分する必要があります。
仮に高額な設備をすべて購入年度に費用計上した場合、その年の利益は大幅に減少し、翌年以降は費用負担がないため利益が急増するという、実際の事業実態とはかけ離れた業績変動が生じてしまいます。
減価償却を通じて損益を平準化することで、企業の経営実態を正確に伝えることができるのです。
減価償却の対象となるのは「減価償却資産」と呼ばれる固定資産で、以下の条件を満たす必要があります。
なお、土地や骨董品のように時間が経過しても価値が減少しない資産は、減価償却の対象外となります。
この記事を読んだ方にオススメ!
定率法は減価償却の計算方法の一つで、毎年度の期首における資産の未償却残高(帳簿価額)に一定の償却率を乗じて減価償却費を算定する方法です。
定率法の最大の特徴は、取得初年度の償却額が最も大きく、年数が経過するにつれて償却額が徐々に減少していく点にあります。
これは、毎年の計算基準となる未償却残高が、前年度の減価償却により年々小さくなっていくためです。
減価償却の計算方法には、「定率法」のほか、代表的なものとして「定額法」があります。
定率法と定額法の違いを表で整理すると以下のようになります。
| 項目 | 定率法 | 定額法 |
|---|---|---|
| 計算方法 | 未償却残高 × 償却率 | 取得価額 × 償却率 |
| 費用の計上パターン | 初期多額→徐々に減少 | 毎年同額 |
| 計算の複雑さ | やや複雑 | シンプル |
定額法は耐用年数にわたって毎年同じ金額を経費として計上するため、計算が非常にシンプルで理解しやすいのが特徴です。
これに対して定率法は、初期に多くの費用を計上できるため、初年度の税負担を抑えつつキャッシュフローを改善できる点が特徴です。
特に技術革新の影響を受けやすい資産を多く保有する企業や、積極的な設備投資を行う企業に選ばれることが多くあります。
定率法による減価償却計算は、次の3段階のプロセスで進められます。
定率法の基本となる計算は、各年度の期首帳簿価額に償却率を乗じて当期の減価償却費を求めることです。
減価償却費 = 期首帳簿価額 × 定率法の償却率
減価償却費の具体的な計算例を見てみましょう。
取得価額200万円、耐用年数5年、定率法償却率40%(200%定率法)の資産の場合:
このように計算していくと、年数が経過するにつれて減価償却費が徐々に減少していくことがわかります。
定率法では、償却費が極端に小額となって長期間続くことを防ぐため、「償却保証額」という基準が設けられています。
償却保証額 = 取得価額 × 保証率
保証率は耐用年数に応じて税法で定められており、毎年度の通常の定率法による減価償却費がこの償却保証額を下回った場合には、次の段階である改定償却率による計算に切り替わります。
今回のケースでは、
取得価額が200万円、保証率が0.108なので、償却保証額は21.6万円となり、4年目以降の減価償却費が償却保証額を下回っていることが分かります。
償却保証額を下回った年度以降は、「改定償却率」を使用した均等償却に移行します。
改定償却率は以下の式で計算されます。
改定償却率 = 1 ÷ 残存耐用年数
改めて今回のケースに当てはめると、
4年目の残存耐用年数は2年のため、改定償却率は50%となり、4年目以降を含めた減価償却費は以下のようになります。
ただし、最終年の処理は、期首未償却残高を1円になるよう償却するため、21.6万円から1円を引いた215,999円となります。(備忘価額)
この仕組みにより、定率法の「初期に多く償却する」という特性を保ちながら、耐用年数内での完全償却を確実に実現しています。
定率法は、初年度に多くの減価償却費を計上できるため、初年度の利益が大きい場合や、設備投資の頻度が高い企業、資金繰りを重視する企業に向いています。
一方、定額法は、利益が安定している企業や、将来の税率上昇を見込む企業に適しています。毎年の費用が一定なため、損益の予測がしやすいのもメリットです。
中古資産にも定率法は適用可能です。
ただし、耐用年数は新品と異なり、既経過年数を差し引いたり(見積法)、簡便法(法定耐用年数の20%)を使って算出します。
定率法を採用するには、「減価償却資産の償却方法の届出書」を確定申告期限までに税務署へ提出する必要があります。
届出を怠ると、法定の償却方法(建物は定額法、機械装置は定率法など)が自動適用され、定率法の申告が否認されるリスクがあります。
定率法は、資産価値の減少を現実的に反映できる減価償却方法として、多くの企業で活用されています。
初期に多くの償却費を計上でき、初年度の税負担を抑えてキャッシュフローを改善できる点が大きなメリットです。
一方で、償却保証額や改定償却率など独自のルールがあり、計算が複雑になるため、制度の正確な理解が不可欠です。
導入を検討する際は、収益状況や資金繰り、資産の性質を踏まえ、税理士など専門家の助言を得て、自社に最適な償却方法を選ぶことが大切です。
減価償却は企業経営に直結する重要な要素であるため、戦略的な活用が求められます。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集
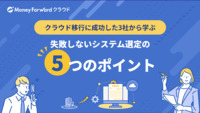
クラウド移行に成功した3社から学ぶ失敗しないシステム選定の5つのポイント

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!

又は・若しくはの違いとは?意味・使い分けと契約書での注意点を例文で解説

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

介護休業制度とは?―2025年法改正と制定経緯から考える、仕事と介護の両立支援の本質―

上場企業の経理担当者が知っておくべきPMIの基礎知識

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

中堅企業はココで選ぶ! 会計システムの選び方ガイド

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!
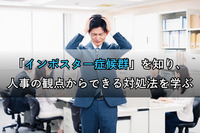
「インポスター症候群」を知り、人事の観点からできる対処法を学ぶ

過重労働の判断基準と健康リスクを徹底解説 ─ 厚労省ガイドラインで学ぶ企業の防止策
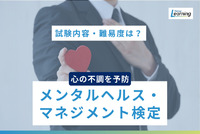
メンタルヘルス・マネジメント検定試験は社会人に役立つ資格?試験の内容や難易度は?

6割の総務が福利厚生と従業員ニーズのギャップを実感するも、3割超が見直し未実施
公開日 /-create_datetime-/