公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。
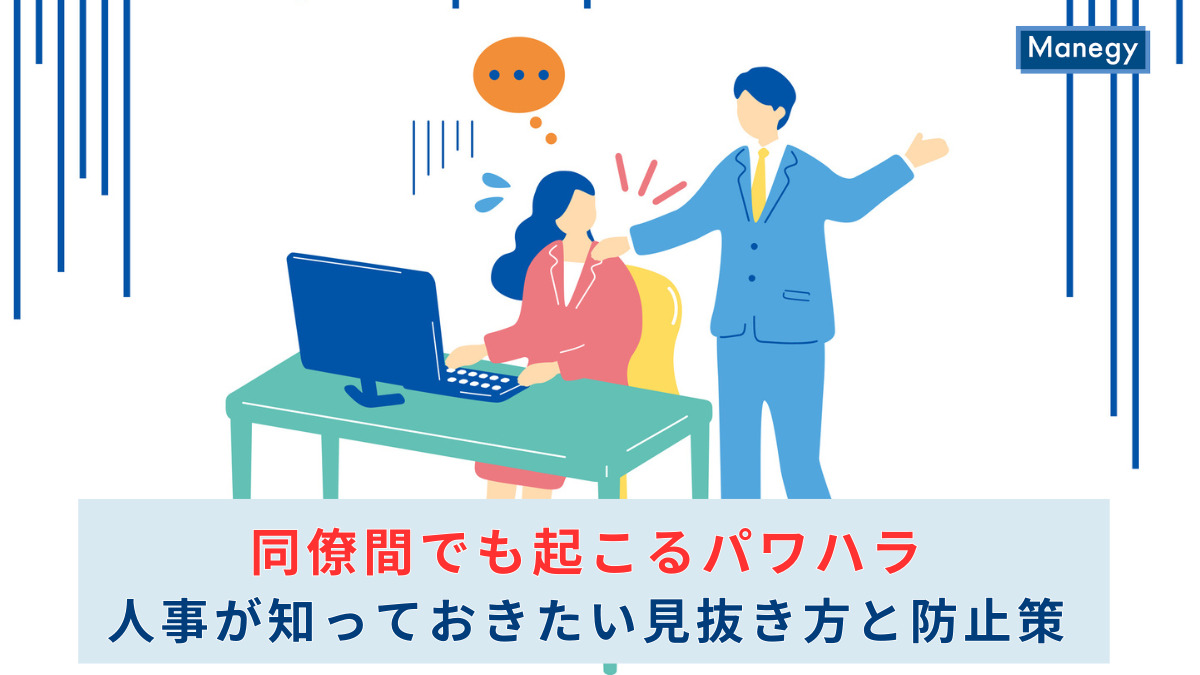
上司と部下の関係だけでなく、同僚同士のトラブルを背景とした“同僚間パワハラ”も増加傾向にあります。
陰口や情報をわざと共有しないといった行為は、外からは気づきにくいものの、長期化すると被害者のメンタル不調や退職につながり、企業にとっても法的リスクとなり得ます。
人事担当者は、こうした同僚間パワハラの兆候を早期に見抜き、予防と再発防止の仕組みを整えることが重要です。
本記事では、よくある事例や見抜き方、法的義務、組織としての防止策までを整理し、職場環境の改善に役立つ実務ポイントを解説します。
「パワハラ」とは、職場での上位関係を背景に、業務上の適正範囲を超えた言動により、労働者に精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為を指します。
一般には「上司→部下」の構図で想起されがちですが、実務上は同僚間であっても「優越性」が認められる関係性があれば、パワハラが成立しうるとされています。
参考URL:厚生労働省「職場におけるハラスメント関係指針」
近年の働き方や価値観の変化が、同僚間パワハラを顕在化させやすくしています。
成果主義・競争原理の強化
業績評価や成果重視の制度が浸透する中、同僚同士の比較意識や対立が助長され、無意識の圧力や嫌がらせに至るケースが増えています。
働き方の柔軟化・分散勤務
リモートワークやフレックス制の導入で、オフィスの目が届きにくくなり、チャット上での否定的表現などがエスカレートしやすくなっています。
メンタルヘルス問題の顕在化と被害者意識の高まり
過去には見過ごされがちだった心理的ストレスの実態が、労働者側からの相談や訴訟で可視化され、企業責任も問われやすくなっています。
このような流れにおいて、人事部門や管理部門には、先手の抑止策と兆候の把握がこれまで以上に求められています。
厚生労働省の指針では、パワハラに該当しやすい典型的言動を、次の「6類型」に整理しています。
※あくまで主な例を示したもので、他のケースも存在します。
参考URL:厚生労働省「NOパワハラ」
「同僚間パワハラ」が成立しうるためには、形式的には対等な関係に見えても、実質的な優越性が存在している必要があります。具体的には、以下のような要素が影響します。
業務上の知識・専門性・経験
ある社員が特定分野で圧倒的な知識を持ち、それを背景に発言力を持つ場合、優越性が認められる可能性があります。
業務分担・影響力の差
同じ職級・等級であっても、プロジェクトリーダー格やキーマン扱いの者には事実上の影響力があることがあります。
集団的・心理的優位性
所属チームや事業部での影響力(人間関係、発言力、信頼性)によって「空気を作る」力を持つ者も、優越性を帯び得ます。
雇用形態・立場の差
正社員と非正規社員、勤務年数や社歴の違いなどが無意識に力関係を作ることがあります。
このような実質的優越性を背景に、同僚がパワハラ加害者になることがあります。逆に、形式的な立場の差(体格・性格・発言力など)だけでは優越性とは認められにくいともされています。
同僚同士のパワハラは、表面的には業務上のやり取りや軽い雑談の延長に見えることが多く、第三者からは問題として認識されにくいのが特徴です。ここでは、人事担当者が押さえておきたい代表的な事例を整理します。
同僚間で最も起こりやすいのが、人間関係からの切り離しにあたる行為です。具体的には、次のような行為が挙げられます。
こうした行為は「軽いいじり」と誤解されることもありますが、受けた側の心理的負担は大きく、長期化すると退職やメンタル不調に直結するケースも少なくありません。特定の社員を排除するような行為は業務上の合理性がないため、パワハラに該当する可能性が高いと考えられます。
次に多いのが、業務上の優位性を背景とした嫌がらせです。
このような行為はパワハラ防止法の「過大な要求」や「情報の切り離し」に該当しやすいものです。業務の遅延やミスが被害者の評価を下げる結果となり、本人だけでなく組織全体の生産性にも悪影響を及ぼします。
職歴の長い社員や、専門知識が豊富な社員が、正式な役職がないにもかかわらず部下のように扱ったり、過度に叱責したりするケースもあります。
こうした行為は一見“指導”に見えても、業務上の必要性や相当性を超えて精神的な圧迫を与えている場合はパワハラにあたる可能性があります。特に新人や派遣社員など立場が弱い人に対して起こりやすいため、人事や管理職は注意が必要です。
テレワークの普及により、対面では見えにくい嫌がらせがチャットやSNSで行われるケースも増えています。
デジタル上でのやり取りはログが残るため、後から証拠として確認できる一方で、相手の感情やトーンが伝わりにくく、心理的負担が深刻化しやすい点が特徴です。リモート環境では、こうした兆候を早めに拾う仕組みづくりが求められます。
同僚同士のパワハラは、特定の個人だけでなく、職場の環境や組織文化によって助長されるケースが少なくありません。以下の特徴に心当たりがある場合は、未然防止のための仕組みづくりを早急に検討する必要があります。
部署間の連携が乏しく、日常的なコミュニケーションが限られている職場では、誤解や不信感が生じやすくなります。こうした環境では、特定のグループに属さない人が孤立しやすく、無視・仲間外れなどの行為が常態化しやすい傾向があります。
成果主義や数字至上主義の職場では、業績を上げることが最優先となり、人間関係への配慮やモラルが後回しにされがちです。このような風土は、職場の心理的安全性を損ない、陰湿な嫌がらせや排他的な行為を生みやすいリスクがあります。
長時間労働や慢性的な人員不足が続く職場では、社員のストレスが高まり、ちょっとした摩擦がハラスメントへと発展しやすくなります。
パワハラ防止は一度の対応で終わりではなく、“起こさない仕組みづくり”と“継続的なフォロー”が重要です。ここでは、企業が取り組むべき4つの実務ポイントを紹介します。
パワハラを早期に把握するには、安心して相談できる窓口の存在が欠かせません。特に中小企業では、社内だけでは対応が難しい場合が多いため、外部窓口の活用が被害者保護と早期解決の両面で効果的です。
制度があっても従業員に知られていなければ機能しません。書面だけの規定でなく、実効性のあるものにすることが重要です。「見たことはあるけど内容は知らない」という状態をなくし、行為者が“知らなかった”と弁解できない環境を作ることが、抑止力につながります。
再発防止には、全社員の理解度向上と意識改革が不可欠です。研修は単なる座学ではなく、社員が「自分ごと」として捉えられる工夫が必要です。
パワハラ防止は、制度を整えるだけでは不十分です。日常のフォロー体制が職場環境を守るポイントになります。継続的なフォローが、パワハラの“芽”を摘み、従業員の心理的安全性を高めることにつながります。
同僚間パワハラは、目立たず進行しやすい職場リスクであり、被害が拡大すると従業員の離職やメンタル不調、さらには企業の法的責任にもつながります。
本記事では、よくある行為のパターン、発生しやすい職場環境、企業に求められる法的義務と実務対応、再発防止の仕組みまで解説しました。
まずは、自社の相談窓口や就業規則が現行法に沿って整備・周知されているかを確認することが第一歩です。
小さな見直しの積み重ねが、安心して働ける職場づくりにつながります。今日からできる取り組みを一つずつ始めてみましょう。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
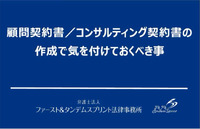
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
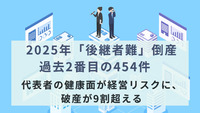
2025年「後継者難」倒産 過去2番目の454件 代表者の健康面が経営リスクに、破産が9割超える

トータルリワード時代の新しい人事制度 ~役割の「拡大 × 深化」を実現する役割貢献制度~

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!

振り返りが回り始めた組織で起きる次の壁 ― 変革を続けられるかどうかを分ける「継続の関所」―<6つの関所を乗り越える5>
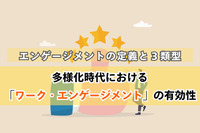
エンゲージメントの定義と3類型:多様化時代における「ワーク・エンゲージメント」の有効性

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念

ヒエラルキー組織における意思決定の高速化と最適化
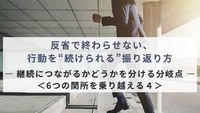
反省で終わらせない、行動を“続けられる”振り返り方 ― 継続につながるかどうかを分ける分岐点 ―<6つの関所を乗り越える4>

ライセンス契約とは?主な種類・OEM契約との違い・契約書の記載項目までわかりやすく解説

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く
公開日 /-create_datetime-/