公開日 /-create_datetime-/
法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?
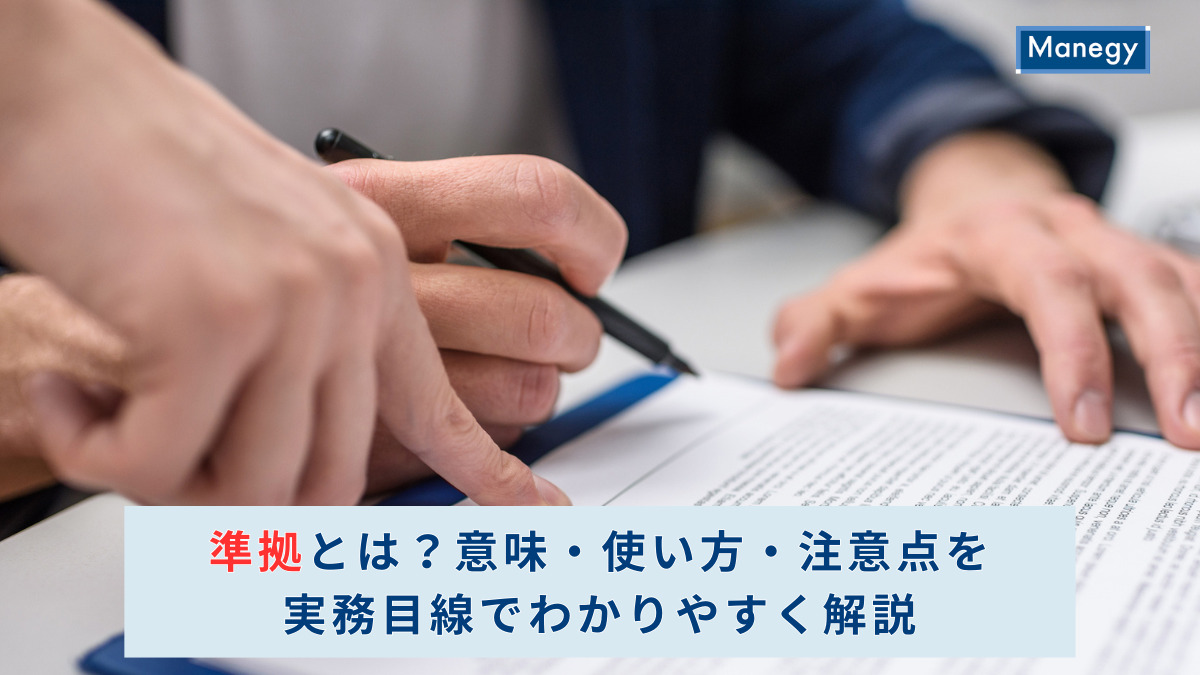
契約書や社内規程を作成する際、「準拠」という言葉を目にする機会があるでしょう。
しかし、「遵守」や「適合」との違いを曖昧にしたまま使うと、文書の意図が正確に伝わらず、誤解を招くおそれがあります。
本記事では、「準拠」の正しい意味と使い方、契約書やビジネス文書での実務上のポイントをわかりやすく解説します。
「準拠」とは、ある基準や規則、法律などを根拠として従うことを意味します。 ビジネスの場面では、「○○に準拠する」「本契約は△△法に準拠する」などの形で使われ、文書や制度の内容がどのルールに基づいているかを明確にするための言葉です。
「準拠」は、さまざまな業務文書で“どの基準をもとにしているか”を示すために使われます。
とくに契約書・社内規程・システム設計書など、法的・制度的な根拠が求められる文書では欠かせない表現です。
ここでは、管理部門でよく登場する3つのシーンに分けて具体例を紹介します。
契約書での「準拠」は、契約内容をどの法律に基づいて解釈・運用するかを定める目的で使われます。このときの「準拠法」は、契約書の中でも特に重要な条項の一つです。
例文
本契約に関して生じた紛争は、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
「準拠法」は、契約当事者が異なる国・地域にいる場合など、法解釈の基準を統一するために定めます。明示しておくことで、法的トラブル時にどの法律を適用するかを明確にでき、紛争リスクを低減できます。
社内規程やマニュアルにおける「準拠」は、運用ルールがどの法令や社内方針を根拠としているかを明示するために使われます。特に人事・労務・総務領域では、労働基準法や個人情報保護法などの法令準拠が求められるケースが多いです。
例文
本規程は労働基準法および関係法令に準拠して定める。
製品仕様書やシステム設計書など技術文書における「準拠」は、国際規格や業界標準に従っていることを示すために使われます。特に品質保証・情報セキュリティ・データ保護など、外部基準が関係する領域で頻繁に登場します。
例文
本システムはISO/IEC 27001(情報セキュリティマネジメントシステム)に準拠している。
海外企業との契約書では、「This Agreement shall be governed by the laws of Japan.(本契約は日本法に準拠する)」という文言をよく見かけます。この「準拠法(governing law)」とは、契約の解釈・履行・紛争解決に適用される法律を明確に定める条項のことを指します。
国際取引では、当事者が異なる国に所在するため、どの国の法律を適用するかが不明確なままだと、トラブル時に重大な混乱を招くおそれがあります。そのため契約書に「準拠法条項(governing law clause)」を設け、法解釈の基準をあらかじめ合意しておくことが国際取引の基本ルールです。
例文
The governing law of this Agreement shall be the laws of the State of California, USA.
「本契約の準拠法は、米国カリフォルニア州の法律とする」
選定する「準拠法」は、契約当事者の所在地、取引実態、リスク分担のバランスなどを踏まえて決定されます。また、準拠法とは別に、紛争が発生した場合の裁判管轄(jurisdiction)を定める条項を併記するのが一般的です。
「準拠」は、「遵守」や「適合」と似た意味で使われることが多く、日常業務の中でも混同されやすい言葉です。ここでは、それぞれの違いを整理します。
「遵守」は、定められたルール・法律・規程を“守る”ことを意味します。つまり、「準拠」が“ある基準に従って作る・定める”のに対し、「遵守」は“その基準を守って行動する”という違いがあります。
使い分けの例
・本規程は労働基準法に準拠して定める。
→ 規程の内容を作る際の基準を示す。
・従業員は本規程を遵守しなければならない。
→ 運用時にルールを守る義務を示す。
したがって、「準拠」は制度設計や文書作成の段階で使われ、「遵守」は実際の行動・運用の場面で使われることが多い言葉です。
「適合」は、ある基準や条件に“合っている”状態を指します。「準拠」が“従って作られている”プロセスを示すのに対し、「適合」は“結果として合致している”ことを表します。
使い分けの例
・当システムは国際規格ISOに準拠して設計されています。
→ 設計段階でISOを基準としている。
・当システムはISO規格に適合しています。
→ 結果としてISOの要件を満たしている。
このように、「準拠」は基準への“方向性”を示し、「適合」は基準との“一致”を示す表現です。品質保証・監査・システム評価などでは、「準拠」と「適合」を正しく区別することが信頼性の担保につながります。
「非準拠」とは、定められた基準や規格に従っていない状態を意味します。特にISO認証やセキュリティ監査などでは、「非準拠項目(non-conformity)」として指摘されるケースがあります。
使用例
・一部の手順がガイドラインに非準拠である。
・監査の結果、データ管理体制に非準拠項目が確認された。
① 「何に準拠しているか」を明確に書く
「ガイドラインに準拠」とだけ書くのではなく、出典や年度を示すことで信頼性が高まります。
例:「厚生労働省が2025年に公表した安全衛生ガイドラインに準拠」
② 文書トーンに合わせて使い分ける
「準拠」はフォーマルな文体に適しており、社内文書では「〜に基づき」や「〜を参考に」と言い換えると自然です。
③ 文書レビュー時に根拠の整合性を確認する
法令改正や基準変更により、古い「準拠先」が残っていないかを定期的にチェックしましょう。管理部門では、法改正対応をレビュー項目に加えておくと安心です。
「準拠」は単なる文書上の形式ではなく、組織の信頼性と説明責任を支える要素です。法令やガイドラインが頻繁に変わる今こそ、“根拠を明示した文書運用”が求められています。規程や契約書を作るだけでなく、常に最新の基準と整合させる仕組みづくりが重要です。まずは自社文書の「準拠先」が現行法に沿っているかを確認し、アップデートの習慣をつけましょう。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
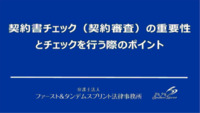
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

経理業務におけるスキャン代行活用事例

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

【2026年新春】総勢300名様にAmazonギフトカードが当たる!Manegyお年玉キャンペーン開催中

管理部門担当者は何学部が多い?アンケート調査で見えた管理部門の出身学部とキャリアの関係

ランサムウェア感染経路と対策|侵入を防ぐ
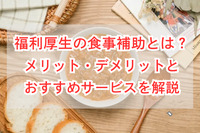
福利厚生の食事補助とは?メリット・デメリットとおすすめサービスを解説

2026年の展望=2025年を振り返って(13)
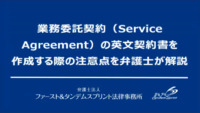
業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
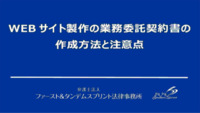
WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
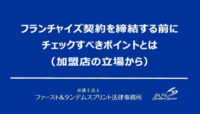
フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

監査ログ活用術|セキュリティ強化を実現するログ分析
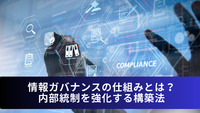
情報ガバナンスの仕組みとは?内部統制を強化する構築法
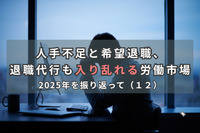
人手不足と希望退職、退職代行も入り乱れる労働市場=2025年を振り返って(12)

焼津市の建設会社・橋本組、「えるぼし認定」最上位に 女性活躍推進法に基づく全項目をクリア

オフラインアクセスは危険?クラウドストレージの安全な活用
公開日 /-create_datetime-/