公開日 /-create_datetime-/
法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?

取引条件の変更や退職合意、共同開発の取り決めなど、ビジネスの現場で「合意書」が必要になる場面は多くあります。
ただし、契約書・覚書・同意書との違いを理解しないまま作成すると、思わぬトラブルに発展することもあります。
本記事では、合意書の正しい位置づけと法的効力、実務での使い分け方を、管理部門の担当者向けにわかりやすく解説します。
合意書とは、当事者が合意に至った事実とその内容を確認するために作成する文書です。
契約書と同様に法的効力がありますが、一般に契約締結というよりは、既存の取引や雇用関係における条件変更・確認などを簡潔に記録する目的で用いられます。
業務上の取り決めを文書化する際、「合意書」「契約書」「覚書」「念書」「誓約書」など、似たような文書が登場します。
いずれも“約束を明文化する”という点では共通していますが、目的や法的効力、当事者の立場が異なります。
同意書は、当事者が相手の提示条件を承諾した事実を明確にする書面です。
合意書のように当事者双方の話し合いによる取り決めではなく、一方的な承諾を示す性質があります。
ただし、内容が具体的で署名・押印がある場合には、契約の一部として法的効力(証拠力)が認められることもあります。
契約書は、当事者双方が合意した内容に基づき、権利と義務を明確に定める正式な文書です。
署名・押印(または電子署名)によって効力が発生し、債権・債務関係の発生や損害賠償請求などの法的根拠となります。
一方、合意書は、契約関係や雇用関係など既存の関係の中で、条件の変更・確認・補足を目的として作成されることが多く、契約書ほど厳格な様式は求められません。
つまり、契約書が「新たな取引や契約を締結するための文書」であるのに対し、合意書は「既存の条件を確認・修正・補足するための文書」として位置づけられます。
覚書は、すでに締結された契約の内容を補足したり、一部を変更したりする際に作成される文書です。
契約書を一から作り直すのではなく、当事者間で合意した追加事項や修正点を明確にしておく目的で用いられます。
実務上は、覚書は「契約書の付属文書」や「補足資料」として扱われることが多く、当事者双方が署名・押印を行い、内容が具体的であれば契約書と同様の法的拘束力を持つと判断されます。
たとえば「納期を1週間延長する」「支払条件を一部変更する」といった限定的な修正を記録する場合に使われます。
念書や誓約書はいずれも、一方の当事者が自らの義務や行動を約束するための文書ですが、念書は「相手に対して約束を示す」目的で作成されるのに対し、誓約書は「自らの遵守を誓う」特徴があります。
念書は、トラブル発生後に「再発防止」や「損害補償」などの対応を約束する際に作成されることが多く、特定の出来事に対処する性質を持ちます。
一方、誓約書はより一般的に用いられ、入社時の秘密保持やコンプライアンス遵守など、日常的なルールや行動指針への誓いを記す場合に使われます。
いずれも一方的な誓約を記録する点で、当事者双方の合意を前提とする「合意書」とは異なります。
ただし、署名・押印がある場合には、一定の拘束力を持ち、内容によっては証拠書類としての役割を果たします。
「合意書に法的効力はあるか」は、管理部門や法務担当者が判断に迷いやすいテーマですので、以下に整理します。
合意書が法的効力を持つためには、いくつかの条件を満たしていることが重要です。まず前提となるのは、「当事者の意思の一致」があることです。
口頭で合意した内容を後から文書にまとめる場合でも、当事者双方が署名または押印を行い、「この内容で間違いない」と確認していることが求められます。
次に大切なのが、内容の具体性です。「できる限り」「原則として」といった曖昧な表現が多いと、履行範囲や責任の範囲が不明確になり、後の解釈トラブルにつながるおそれがあります。
たとえば「納期を短縮する」「追加報酬を支払う」といった合意であれば、期日・金額・支払方法を具体的に記すことで、履行や請求の根拠が明確になります。
さらに、社会通念上妥当な内容であることも欠かせません。
一方に著しく不利な条件や、公序良俗(民法第90条)に反する内容は、当該条項が無効となる可能性があります。
事情によっては、合意全体の効力にも影響する場合があります。
特に、労働条件の変更や取引条件の見直しを伴う合意書では、労働基準法や独占禁止法などの関連法令との整合性を、あらかじめ確認しておくと安心です。
合意書は、契約ほど形式ばらないものの、後々のトラブルを防ぐための重要な証拠書類です。ここでは、合意書の作成が必要になる4つのケースを紹介します。
既存契約の変更は、合意書・覚書のほか、契約条項に基づく改訂版(アメンドメント)や付属合意として整備する方法もあります。
いずれの場合も、変更内容・適用開始日・署名を明確にしましょう。たとえば、取引先からの要望で納期を延長したり、仕入価格を見直したりするケースです。
こうした変更は口頭で済ませてしまうこともありますが、後日「言った・言わない」の争いを防ぐためには、変更内容と合意日を明確に残すことが不可欠です。
人事・労務領域では、退職や雇用条件の変更をめぐって合意書を作成するケースがあります。
たとえば、退職の意思確認や最終出勤日、退職金の有無などを取り決めた「退職合意書」や、「勤務時間・勤務地変更」に関する合意書が該当します。
こうした書面は、労働トラブルを防ぐうえで重要な証拠となり、企業・従業員双方のリスクを最小限に抑える効果があります。
新規取引や共同開発の初期段階では、正式契約の前に業務範囲や責任分担、情報管理のルールを取り決めることがあります。
このような「前提条件の確認書」として合意書を交わしておくと、正式契約に至らなかった場合でも、機密情報の漏えい防止や責任の所在を明確化できます。
スタートアップやプロジェクト型業務では、こうした暫定的な取り決めを合意書で管理するケースが増えています。
取引先との支払トラブルや和解交渉の際に、一部の債務を免除したり、支払いスケジュールを変更したりする場合にも合意書を作成します。
この場合、合意書は「和解契約書」に近い効力を持ち、後に再度の請求や争いを防ぐ役割を果たします。特に金銭の授受が絡む場合は、支払条件・免除範囲・清算方法を明確に記載しておくことが重要です。
当事者間の合意内容を明確にし、後から誤解や争いが生じないようにするためには、必要な項目を過不足なく盛り込み、誰が読んでも理解できる文面にすることが大切です。ここでは、基本構成と実務上の注意点を整理します。
一般的な合意書には、次の要素を順に記載します。文書の形式自体は自由ですが、最低限の要素を押さえておくことで、法的にも信頼性の高い内容になります。
タイトル:内容が一目でわかるよう、「○○に関する合意書」と明示します。
日付:合意が成立した日を明確に記します。日付が抜けていると、合意の有効時期を特定できません。
当事者情報:企業名や住所、代表者名など、合意に関わる当事者を正確に特定します。
合意内容:最も重要な部分です。誰が、何を、いつまでに、どのように行うのかを具体的に記載します。
署名・押印:当事者双方が内容を確認し、合意の意思を示すためのものです。電子契約の場合は電子署名でも問題ありません。
これらはすべて「合意の存在を証明するための要素」です。特に日付・当事者・署名がそろっていない場合、裁判などで「正式な合意の証拠として不十分」と判断されるおそれがあります。
内容に応じて、次のような条項を盛り込みます。契約ほど複雑ではない場合でも、合意の性質に応じて最低限の枠組みを設けておくと安全です。
目的条項:合意に至った背景や目的を明示します。後の解釈を統一する効果があります。
履行条項:どのように合意内容を実行するかを定めます。期日・方法・責任範囲などを具体的に記載します。
損害賠償条項:一方が合意内容に違反した場合の対応を定めます。
管轄裁判所条項:紛争が生じた場合に、どの裁判所で解決するかをあらかじめ指定します。
これらを記載しておくことで、後から「どちらに責任があるか」「どの範囲で履行義務があるか」が明確になります。
特に、金銭や納期など定量的な要素を含む合意では、履行条項と損害賠償条項の整備が実務上の安心材料になります。
A. はい、問題ありません。電子署名法に基づき、電子署名・タイムスタンプなどによって本人確認ができる形式であれば、紙の署名・押印と同等の効力を持ちます。
ただし、PDFに単なる入力や画像署名を添えるだけでは、電子署名法が求める「署名者の本人性・専有管理」や「改ざん検知性」を満たせず、証拠力が弱まるおそれがあります。
信頼性の高い電子契約サービスの利用を推奨します。
A. 一般的には、契約書と同様に少なくとも5年程度の保管が推奨されます。
取引や雇用関係に関する合意書は、税務・労務・監査対応の観点から、保存期間中に参照できるよう管理しておくことが重要です。
紙の場合はコピーを当事者双方で保管し、電子契約の場合はシステム上でバックアップを確保しておきましょう。
実務上は、債権の消滅時効(原則5年)や税務書類の保存期間(原則7年)等も考慮し、関連する権利義務が残る間は7〜10年程度の保管を検討すると安心です。
合意書は、契約書ほど形式に縛られず柔軟に使える一方で、記載内容や当事者の意思が明確であれば、契約書と同様の法的効力を持つことがあります。
トラブルの多くは「認識のずれ」や「証拠の欠如」から生じます。
だからこそ、どんな小さな取り決めでも、当事者の合意内容を明確に書面化しておくことが、企業を守る最も確実なリスク管理策です。
まずは、自社で運用している合意書のフォーマットや管理方法を見直し、法的にも実務的にも安心できる形に整備していきましょう。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ
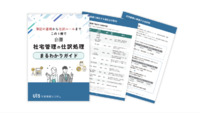
簿記の基礎から実務まで!社宅管理の仕訳処理 まるわかりガイド

1月の提出期限に間に合わせる!支払調書作成効率化の最適解とは?
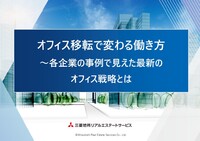
オフィス移転で変わる働き方

2025年の「負債1,000万円未満」倒産 527件 3年ぶり減少も2年連続の500件台で高止まり

社員が自走する! 働きがいの溢れるチームの作り方【セッション紹介】

海外進出を成功させるグローバル人材育成戦略とは
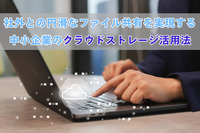
社外との円滑なファイル共有を実現する中小企業のクラウドストレージ活用法
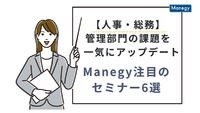
【人事・総務】管理部門の課題を一気にアップデート。Manegy注目のセミナー6選

人的資本開示の動向と対策
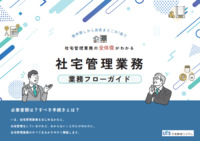
社宅管理業務の全体像がわかる!社宅管理業務フローガイド

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

クラウドストレージの安全な導入ガイド
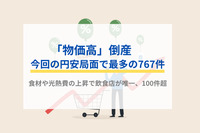
「物価高」倒産 今回の円安局面で最多の767件 食材や光熱費の上昇で飲食店が唯一、100件超
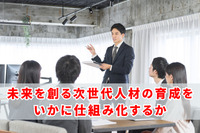
未来を創る次世代人材の育成をいかに仕組み化するか

中小企業のBCP対策を強化するクラウドストレージ
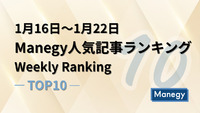
1月16日~1月22日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
公開日 /-create_datetime-/