公開日 /-create_datetime-/
法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?

ブランド毀損は広報やマーケティングの問題と思われがちですが、実は契約・コンプライアンス・情報管理など、法務領域と深く関係しています。
本記事では、ブランド毀損の定義から原因、企業法務が取るべき対応策、そして発生時の初動対応までを網羅的に解説します。
ブランド毀損とは、企業や商品・サービスに対する社会的な信頼や評価が低下し、結果としてブランド価値が損なわれることを指します。
単なるイメージダウンではなく、売上や取引、採用活動などに実際の悪影響が及ぶ点が特徴です。
類似する言葉には「信用毀損」や「風評被害」が挙げられます。
信用毀損とは、虚偽の風説を流したり、偽計を用いたりして他人の経済的信用を傷つける行為を指し、刑法233条に定められた犯罪です。
人の社会的評価を害する「名誉毀損罪」(刑法230条)とは異なります。
一方、風評被害は、事実関係の有無にかかわらず、噂や誤情報が広がることで生じる実害を意味します。
つまり、信用毀損が法律の視点、風評被害が情報の伝わり方の視点だとすれば、ブランド毀損は企業経営やブランド戦略の視点から捉えられる概念といえるでしょう。
ブランド毀損は、企業の内外にあるさまざまな要因によって起こります。特に、日常業務の中に潜む小さなミスや対応の遅れが、信頼を大きく揺るがすきっかけになることもあります。
ここでは、ブランド毀損の主な原因を見ていきましょう。
製品やサービスの品質は、企業ブランドの根幹を支える要素です。不具合や事故が発生すれば、たとえ一部の商品であっても「この会社は大丈夫か」という不信が一気に広がります。
社内で起こる不祥事は、ブランドイメージの低下に最も影響します。不正会計や情報改ざん、ハラスメントなどが明るみに出ると、法的責任だけでなく「企業体質そのもの」への不信感が強くなってしまうでしょう。
クレーム対応の遅れや説明不足、担当者の不適切な発言なども、ブランド毀損のきっかけになります。
一人の対応が企業全体の印象を左右する今、「顧客の声にどう応えるか」は、ブランドイメージを決める重要な要素です。
また、個人情報や顧客データの漏えいは、信頼を一瞬で失う致命的なリスクなので注意が必要です。
自社が直接関与していなくても、取引先や委託先の不祥事が原因でブランドが損なわれるケースがあります。
消費者からは「関連企業」として同一視されるため、被害の範囲が広がりやすい傾向があります。
ブランド毀損は、企業の信頼を失うだけでなく、法的・経営的に大きなダメージを与えるリスクです。
一度の不祥事や炎上が、取引や採用、ガバナンス体制にまで波及することもあります。
ここでは、代表的な4つのリスクを整理します。
ブランド毀損には、法的責任が伴うケースも少なくありません。
企業は、他社から不当な情報発信によってブランドを傷つけられる「被害者」となる一方で、自社の発信が誤解を招いた場合「加害者」にもなり得ます。
虚偽の情報発信や誤認を与える広告は、「信用毀損罪」や「業務妨害罪」に問われるおそれがあります。
また、不祥事や情報漏えいによって顧客・取引先に損害を与えた場合には、民事上の賠償責任を負うことになるでしょう。
日頃から契約内容や広告表現をチェックし、法令違反や誤情報を未然に防ぐ仕組みを整えておくことが重要です。
社会的信用を失うと、取引先や顧客との関係にも影響します。法令違反や不祥事が発覚すれば、行政指導や契約解除、取引停止などの対応を受けることもあります。
とくに上場企業や公共事業の契約では「信用失墜による解除条項」が設けられており、ビジネスの継続に直結する問題です。
日常的にコンプライアンス状況を確認し、信頼維持のためのリスクチェックを怠らないことが求められます。
ブランドの失墜は、経営全体にも波及します。投資家や金融機関の信頼を失えば、株価の下落や資金調達の難航につながります。
また、「不祥事のある企業」と見られれば、採用活動にも影響し、優秀な人材が集まりにくくなります。
信頼の回復には時間がかかるため、平時から透明性の高い経営と誠実な情報開示を行うことが大切です。
ブランド毀損は、企業統治の評価にも影響します。不正や事故が起きれば、「内部統制が機能していない」とみなされ、監査法人や株主からの信頼を損なうことがあります。
重大な不備が公表されれば、新たなレピュテーションリスクを招くことにもなります。
ガバナンス体制を形だけで終わらせず、実効性のある仕組みとして運用することが、信頼維持の秘訣になります。
ブランドを守るためには、トラブルが起きた後の対応だけでなく、平時からの予防体制づくりが欠かせません。
法務・総務・人事など管理部門が中心となり、契約・社内ルール・教育・監視の4つの観点から仕組みを整えておくことが重要です。
自社のブランドを守るためには、外部との契約書に「ブランド毀損防止条項」を盛り込むことが基本です。
広告代理店や制作会社、インフルエンサー、委託先などの行為によって評判が損なわれた場合、契約上の注意義務や損害賠償責任を明確にしておくことで、トラブル時の対応がスムーズになります。
特にSNSや動画広告のように発信内容が企業イメージに直結する契約では、投稿前の確認手続きや、炎上時の報告義務なども条項に含めておくと安心です。
従業員の発信や行動が、企業の印象を左右する時代です。業務上の情報発信だけでなく、個人のSNS投稿が原因で炎上するケースも増えています。
こうしたリスクを防ぐには、社内ガイドラインやSNSポリシーを明確にし、「どんな行為がブランド毀損につながるのか」を全社員が理解できる形で周知することが大切です。
社外発信だけでなく、日常の言動や写真投稿にも注意が必要であることを具体的に示し、誰もが守れる実践的なルールにしておくと、現場に浸透しやすくなります。
この記事を読んだ方にオススメ!
どんな制度を整えても、最終的にブランドを守るのは「人」です。
従業員一人ひとりが企業の顔であるという意識を持つことが、ブランド毀損防止の最も確実な方法です。
ブランド毀損の多くは、「気づくのが遅れた」ことで被害が拡大します。
自社や商品の評判、SNS上の動向を定期的にモニタリングし、異変を早期に察知できる体制を整えておくことが重要です。
また、社内での不正やハラスメントを早期に把握するためには、匿名の内部通報制度や外部窓口を設けることも効果的です。
現場の声が経営や法務部門に届く仕組みがあれば、問題の芽を小さいうちに摘み取ることができます。
リスクは「ゼロ」にはできませんが、「早く見つけ、正しく対処する」ことは可能です。
その仕組みを持つことこそが、結果的にブランドの信頼を守る最善策となります。
ブランド毀損は、企業の信頼を一瞬で揺るがす深刻なリスクです。
品質不良や不祥事、SNS炎上など、原因はさまざまですが、共通しているのは「日常業務の延長線上で起こる」ということ。
だからこそ、特別な危機対応よりも、平時からの仕組みづくりと意識づけが最も有効な防止策になります。
契約内容の見直し、SNSガイドラインの整備、定期的な研修や情報監視など、小さなことでも継続的に取り組み、ブランドの信頼を確実に守っていきましょう。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
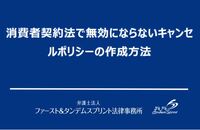
消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法
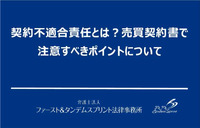
契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
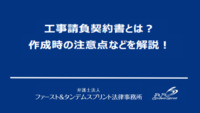
工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

労務コンプライアンス経験は転職で強い?求められるスキルと成功事例を徹底解説(前編)

2025年の「負債1,000万円未満」倒産 527件 3年ぶり減少も2年連続の500件台で高止まり
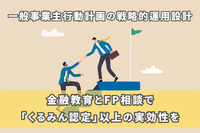
一般事業主行動計画の戦略的運用設計: 金融教育とFP相談で「くるみん認定」以上の実効性を

社員が自走する! 働きがいの溢れるチームの作り方【セッション紹介】

海外進出を成功させるグローバル人材育成戦略とは

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
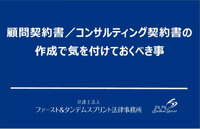
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
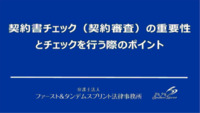
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
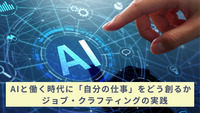
AIと働く時代に「自分の仕事」をどう創るか —ジョブ・クラフティングの実践
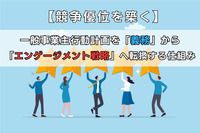
【競争優位を築く】一般事業主行動計画を「義務」から「エンゲージメント戦略」へ転換する仕組み
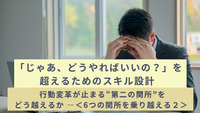
「じゃあ、どうやればいいの?」を超えるためのスキル設計― 行動変革が止まる“第二の関所”をどう越えるか ―<6つの関所を乗り越える2>

【社労士執筆】2026年度税制改正 年収の壁、年収178万円で合意!基礎控除・給与所得控除の変更点と実務対応
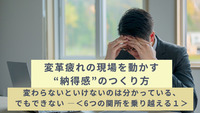
変革疲れの現場を動かす“納得感”のつくり方 ― 変わらないといけないのは分かっている、でもできない ―<6つの関所を乗り越える1>
公開日 /-create_datetime-/