公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
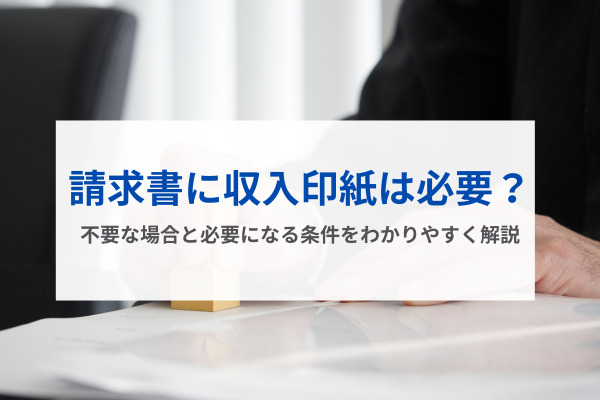
請求書を発行するときに「収入印紙は必要か?」と迷う経理担当者もいるのではないでしょか。
収入印紙とは、印紙税の納付を証明するために書類へ貼り付ける証票で、契約書や領収書など一定の課税文書に貼ることが義務付けられています。
本記事では、請求書に収入印紙が必要となるケースと不要となるケースを解説します。
さらに、取引金額に応じた印紙税額や正しい貼り方、万が一誤った貼付・未貼付した場合の対応策まで、実務で役立つ情報を網羅的にご紹介します。
この記事を通じて、収入印紙に関する疑問を解消し、適切な処理を行うための知識を深めていきましょう。
結論として、請求書そのものには収入印紙は不要です。
印紙税法で課税対象とされるのは「契約書」「領収書」「約束手形」などの課税文書に限られており、代金の支払いを請求するだけの書類は該当しません。
つまり、単に「○月分の代金をお支払いください」と記載した一般的な請求書
であれば、収入印紙を貼る必要はありません。
あわせて読みたい
前述したとおり、請求書は原則として収入印紙の対象外ですが、特定の条件を満たすと課税文書とみなされます。
最も典型的なケースは、請求書が領収書を兼ねる場合です。
たとえば、代金の受領を示す「相済」「了」「受領印」などを押した場合、単なる請求書ではなく領収書(印紙税法第17号文書)として扱われます。
このとき、取引金額が5万円以上であれば収入印紙を貼る義務が生じます。
具体的には、商品やサービスの代金を請求すると同時に、その場で現金を受け取るような取引です。
請求書に「確かに受け取りました」と記載すれば、それは請求と領収の両方を証明する書類となり、印紙税の対象になります。
請求書は原則として非課税文書である一方、記載内容によっては課税文書に変わる可能性があります。
経理や総務担当者は、文言の有無をしっかりと確認し、不要な印紙の貼付や逆に貼り忘れるミスがないように十分な配慮が求められます。
あわせて読みたい
収入印紙を貼る必要がある場合は、貼付すべき印紙の金額(印紙税額)を正しく把握することが大切です。
印紙税額は、文書に記載された「受取金額」に応じて決まります。
| 記載受取金額 | 印紙税額(1通あたり) |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税(印紙不要) |
| 5万円以上~100万円以下 | 200円 |
| 100万円超~200万円以下 | 400円 |
| 200万円超~300万円以下 | 600円 |
| 300万円超~500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超~2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超~3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円超~3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円超~5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超~10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円超 | 200,000円 |
| 記載受取金額なし | 200円(記載金額がない場合の特例) |
出典:「印紙税額の一覧表」|国税庁
記載金額が5万円未満であれば非課税となるため、収入印紙を貼る必要はありません。
しかし、300万円を超えるあたりから税額が高額になり、1,000万円を超えるとさらに高い印紙税が課される点には注意が必要です。
また、金額の記載がない文書については、一律200円の収入印紙を貼ることが定められています。
これらのルールを正しく理解し適用することで、適切な税務処理が可能となり、不要な税負担や貼り忘れのリスクを未然に防ぐことができます。
収入印紙は、単に貼り付ければよいというものではありません。
貼る位置や消印(割印)の方法を誤ると、印紙税を納付したことにならず、過怠税の対象となるリスクがあります。
逆に、不要な書類に誤って貼ってしまうと無駄な税負担となり、還付や交換の手続きを取らなければなりません。
ここでは、実務担当者が押さえておきたい収入印紙の正しい貼付方法と、誤った場合の対応について解説します。
収入印紙は請求書兼領収書の余白に貼り、印紙と書類にまたがるよう割印(消印)を押します。
印鑑は法人印でなくても社判・担当者印で問題ありません。
不要な書類に貼ったり高額の印紙を誤って貼った場合は、過誤納還付の対象となります。
「印紙税過誤納確認申請書」を添えて税務署に提出すれば、払い過ぎた分の還付や交換が可能です。
収入印紙を貼らずに課税文書を交付した場合、印紙税の不納付となり、税務調査
で発覚すれば「本税+2倍(合計3倍)」の過怠税が課される可能性があります。
ただし、自主的に税務署へ申出を行えば1.1倍に軽減されます。
日常的に社内で確認ルールを設け、貼り忘れを防ぐことが重要です。
A. 原則不要です。
請求書は印紙税法上の課税文書に該当しません。
A. 請求書が領収書を兼ねる場合です。
代金の受領を示す「受領印」「相済」「了印」「受け取りました」などの記載があると、領収書(第17号文書)とみなされ、5万円以上の取引では収入印紙が必要になります。
A. 印紙税の不納付にあたり、税務調査で発覚すれば本税+2倍(合計3倍)の過怠税が課される可能性があります。
ただし、自主的に税務署へ申出を行えば、1.1倍に軽減されます。
A. 「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に提出すれば、誤って納付した分について還付や交換を受けられる場合があります。
請求書そのものには収入印紙は不要ですが、受領印や「相済」「了」といった記載を加えると領収書として扱われ、5万円以上の取引では収入印紙が必要になります。
印紙税額は記載金額に応じて細かく定められており、実務担当者は金額区分を正しく理解しておくことが欠かせません。
さらに、収入印紙の貼り忘れは過怠税(本税+2倍)の対象となり、自主的に申告すれば1.1倍に軽減される一方、不要な印紙を貼った場合には税務署への申請で還付を受けられる可能性があります。
請求書の性質を正しく判断し、貼付の要否を確認することが、無駄な税負担やリスクを避けるうえで重要になります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
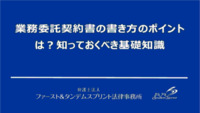
業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
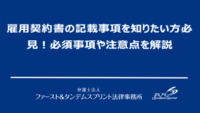
雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
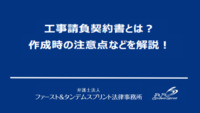
工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

労務コンプライアンス経験は転職で強い?求められるスキルと成功事例を徹底解説(前編)

2025年の「負債1,000万円未満」倒産 527件 3年ぶり減少も2年連続の500件台で高止まり
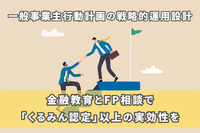
一般事業主行動計画の戦略的運用設計: 金融教育とFP相談で「くるみん認定」以上の実効性を

社員が自走する! 働きがいの溢れるチームの作り方【セッション紹介】

海外進出を成功させるグローバル人材育成戦略とは

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

1月の提出期限に間に合わせる!支払調書作成効率化の最適解とは?
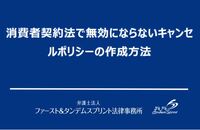
消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
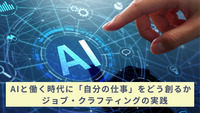
AIと働く時代に「自分の仕事」をどう創るか —ジョブ・クラフティングの実践
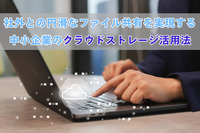
社外との円滑なファイル共有を実現する中小企業のクラウドストレージ活用法

OEM契約とは?メリット・デメリットからOEM契約書の重要条項まで整理
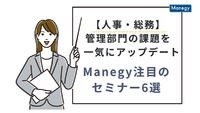
【人事・総務】管理部門の課題を一気にアップデート。Manegy注目のセミナー6選

クラウドストレージの安全な導入ガイド
公開日 /-create_datetime-/