公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
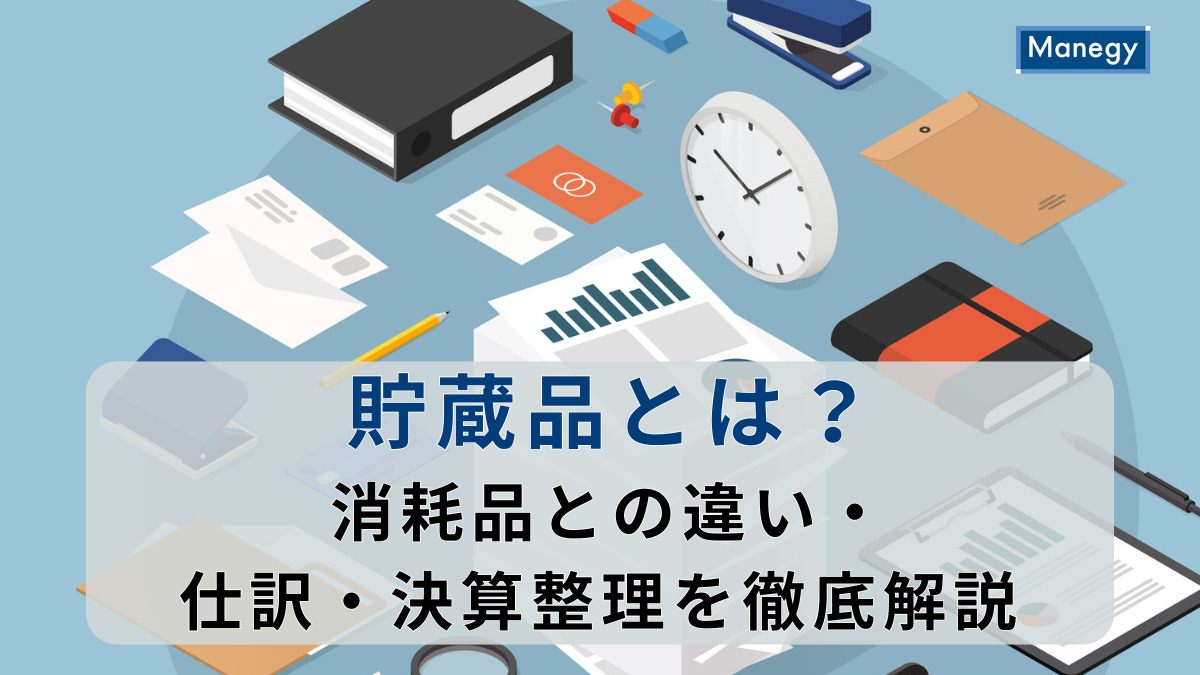
経理業務のなかで、文房具やプリペイドカードなどの「未使用物品」をどう処理するか、迷ったことはありませんか。
これらは「消耗品」ではなく、「貯蔵品」として資産計上が必要となる場合もあります。
本記事では、貯蔵品とは何かを基本から整理し、消耗品との違い・仕訳の考え方・決算整理の実務手順までをわかりやすく解説します。
「貯蔵品」とは、購入してまだ使用していない物品を、一時的に資産として計上するための勘定科目です。
事務用品や切手、収入印紙、ノベルティ等が典型例です。
未使用であること・期末に合理的に残高評価できることが前提で、固定資産に該当する高額備品は対象外となる場合があります。
「貯蔵品」と混同されやすいのが、同じく棚卸の対象となる「棚卸資産」や「消耗品」です。
棚卸資産は、商品や原材料など販売や製造を目的として保有する資産であり、業務で使用するための貯蔵品とは性質が異なります。
また、消耗品は購入と同時に使用することを前提とした物品であり、通常は「消耗品費」として購入時点で費用処理します。
したがって、購入したもののまだ使用していない場合は「貯蔵品」、購入後すぐに使用する前提のものは「消耗品」として扱います。
あわせて読みたい
日常的な会計処理では、購入 → 使用 → 決算整理の3段階で処理が変わります。
まず購入時に「貯蔵品」として資産計上し、実際に使用・消費した時点で「消耗品費」や「通信費」などの費用勘定へ振り替えます。
貯蔵品を資産計上する目的は、企業の実態を正しく財務諸表に反映させることにあります。
もし未使用の物品をすべて購入時に費用処理してしまうと、実際にはまだ使用していないのに当期の費用が過大となり、期間損益の対応関係が崩れてしまいます。
これは、会計の基本である「費用収益対応の原則」に反する処理です。
発生主義会計のもとでは、費用はその効果が発生した時点で認識する必要があります。
貯蔵品を資産として計上しておけば、翌期以降に実際に消費されたタイミングで費用化できるため、各期の損益が正確に比較可能になります。
貸借対照表では、企業の資産・負債・純資産を網羅的に示します。
未使用の貯蔵品を資産に含めることで、企業が保有する資産の実態を正しく把握できるようになります。
逆に、すべてを費用処理すると資産が過少に表示され、財政状態を正確に示せなくなります。
税務上も、未使用の貯蔵品を費用処理したままにすると、損金算入の時期が早まり、過少申告とみなされるリスクがあります。
実際、税務調査では未使用物品の棚卸を怠っている点が指摘されることもあります。
そのため、期末には棚卸を実施し、未使用分を「貯蔵品」として資産計上することが、税務上の基本対応とされています。
なお、金額がごく少額で重要性が乏しい場合には、社内規程で「購入時に費用処理」と定める簡便的な方法も認められています。
ただし、その基準は明確に定義し、継続して適用することが求められます。
貯蔵品は、購入から使用までのタイミングで勘定科目が変化する点に注意が必要です。
ここでは、日常取引における基本的な仕訳の考え方と、会計ソフト入力時のポイントを整理します。
貯蔵品を購入した時点では、まだ使用していないため費用ではなく資産として計上します。
例: 事務用品を現金で5,000円購入した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 貯蔵品 | 5,000 | 現金 | 5,000 |
購入時点では「貯蔵品」勘定を使い、実際に使うまで費用処理しません。
貯蔵品を使用した時点で、対応する費用勘定に振り替える必要があります。
例: 当期中に事務用品を使用した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 5,000 | 貯蔵品 | 5,000 |
この仕訳により、未使用分(資産)から使用済み分(費用)へと適切に振り替わります。
費用勘定は使用目的に応じて「通信費」「広告宣伝費」「福利厚生費」などに分けても構いません。
また、決算時に棚卸を行うことで、期末残高を再確認し、実際の在庫と帳簿を一致させることが重要です。
あわせて読みたい
期末決算では、貯蔵品の棚卸を行い、未使用分を資産計上(または翌期に繰り越し)する必要があります。
これは、当期に実際に使用した分だけを費用として認識するための重要な作業です。
期末時点で保管している未使用物品を集計し、その金額を「貯蔵品」として資産計上します。
棚卸では、現物の確認と帳簿との照合を行い、数量 × 単価で期末残高を算出します。
例: 期末棚卸の結果、未使用の事務用品が3,000円分あった場合
期末仕訳
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 貯蔵品 | 3,000 | 消耗品費 | 3,000 |
翌期首仕訳(逆仕訳)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 3,000 | 貯蔵品 | 3,000 |
このように、期末に資産化 → 翌期首に費用化という流れを取ることで、期間損益を正しく対応づけることができます。
貯蔵品の決算整理では、次のようなミスが発生しやすいです。
いずれも年度をまたぐ処理のため、事前のチェック体制を整えておくことが重要です。
棚卸リストの更新漏れ
現物確認を怠ると、帳簿残高と実際の在庫にズレが生じます。月次または四半期ごとに簡易棚卸を行い、リストを定期的に更新しておきましょう。
翌期首の逆仕訳忘れ
期末に資産計上したまま、翌期首の逆仕訳を忘れると費用が過少になります。会計ソフトの自動仕訳設定を活用し、処理の抜け漏れを防止します。
少額物品をすべて費用処理してしまう
社内規程で金額基準が定まっていないと、担当者の判断にばらつきが出ます。たとえば「1万円未満は費用処理」といった基準を明文化し、監査時にも説明できるようにしておきましょう。
棚卸評価額の誤り
数量や単価の誤差による評価ミスもよくあります。過年度のデータと比較したり、別の担当者がダブルチェックする体制を整えると安心です。
特に、翌期首の逆仕訳を忘れると、同じ金額が二重計上されて費用が過少になるため注意が必要です。
また、プリペイドカードや切手などの少額資産は現金残高と混同されやすいため、管理表を作成して定期的に残高確認を行うことをおすすめします。
日常業務で「これは貯蔵品にすべき?」「棚卸はどこまで必要?」と迷う場面は少なくありません。
ここでは、実務担当者から特に質問の多いポイントをQ&A形式でまとめました。
A. 原則として、未使用の事務用品などは貯蔵品として資産計上する必要があります。
ただし、金額がごく少額であったり、期末時点での残数量が僅少な場合は、「重要性が乏しい」として費用処理を認めることも可能です。
実務的には、社内で「1万円未満」「10万円未満」などの少額基準を明文化した会計処理方針を設けるのが一般的です。
基準を明確にしておくことで、期末ごとに判断がぶれず、監査対応や税務調査時にも説明しやすくなります。
A. プリペイドカードや切手、クオカードなどは、使用前であれば原則として貯蔵品に該当します。
ただし、業務上すぐに配布・利用する予定が明確な場合には、購入時点で費用処理することも実務上は認められます。
また、金券類は金銭性資産(現金等)に近い性格を持つため、残高管理の観点から「貯蔵品」として棚卸し、数量と残額を毎期確認しておくのが望ましい対応です。
A. 期末時点で未使用の貯蔵品がほとんどない場合は、棚卸を行ったうえで“ゼロまたは僅少”として記録して問題ありません。
ただし、「残高が少ない=棚卸不要」ではありません。数量を確認したうえで記録を残しておくことで、翌期以降の在庫推移を追跡しやすくなります。
なお、残高がわずかでも、前年まで資産計上していた場合は前期比較の整合性を保つために、少額でも計上を続ける方が望ましいです。
A. 棚卸の目的は、実際の未使用分を正確に把握し、帳簿残高と一致させることです。
次のような形式で「棚卸表」を作成しておくと実務がスムーズです。
| 品目 | 数量 | 単価 | 金額 | 保管場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事務用品(ボールペンなど) | 50本 | 100円 | 5,000円 | 本社倉庫 | 期末残数確認済 |
| クオカード | 20枚 | 1,000円 | 20,000円 | 経理課金庫 | 残高一覧表と一致 |
棚卸表は、経理担当者と確認者(上長など)の署名を付け、証憑として保存しておくと安心です。
Excel管理でも構いませんが、クラウド会計ソフトの在庫管理機能を利用すれば、過年度比較や履歴管理も容易になります。
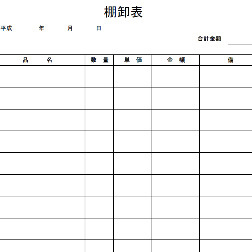
A.貯蔵品の購入は課税仕入に該当します。未使用であっても、購入時点で仕入税額控除の対象です。
ただし、非課税取引(収入印紙など)を含む場合は控除対象外となるため注意が必要です。
貯蔵品は、購入したもののまだ使用していない物品を資産として一時的に計上する項目です。
正しく処理することで、期間損益の対応関係が保たれ、税務上のリスクも防ぐことができます。
一方で、少額品をすべて費用処理してしまったり、棚卸を怠ったりすると、決算数値に誤差が生じるおそれがあります。
まずは、自社でどの物品が貯蔵品に該当するかを整理し、社内規程を整備するところから始めましょう。
正確な処理を積み重ねることが、信頼できる決算づくりへの第一歩です。
あわせて読みたい
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!

【離職率を改善】タレントマネジメントシステムの効果的な使い方
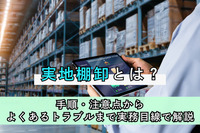
実地棚卸とは?手順・注意点からよくあるトラブルまで実務目線で解説

2026年1月の「物価高」倒産 76件 食料品の価格上昇で食品関連が増勢

【図解フローチャート付】出張ガソリン代の勘定科目は?旅費交通費と車両費の違いを仕訳例で徹底解説
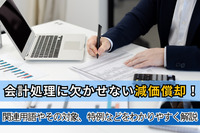
会計処理に欠かせない減価償却!関連用語やその対象、特例などをわかりやすく解説

新入社員の育成・活躍を促進するオンボーディングとは?

【1on1ミーティング】効果的な実践方法と運用時のポイント

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
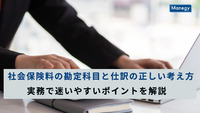
社会保険料の勘定科目と仕訳の正しい考え方|実務で迷いやすいポイントを解説

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に

決算整理仕訳とは?仕訳例でわかる基本と実務の注意点
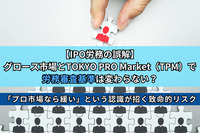
【IPO労務の誤解】グロース市場とTOKYO PRO Market(TPM)で労務審査基準は変わらない?「プロ市場なら緩い」という認識が招く致命的リスク

消費税の特定課税仕入れとは?仕入税額控除の際の注意点
公開日 /-create_datetime-/