公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。
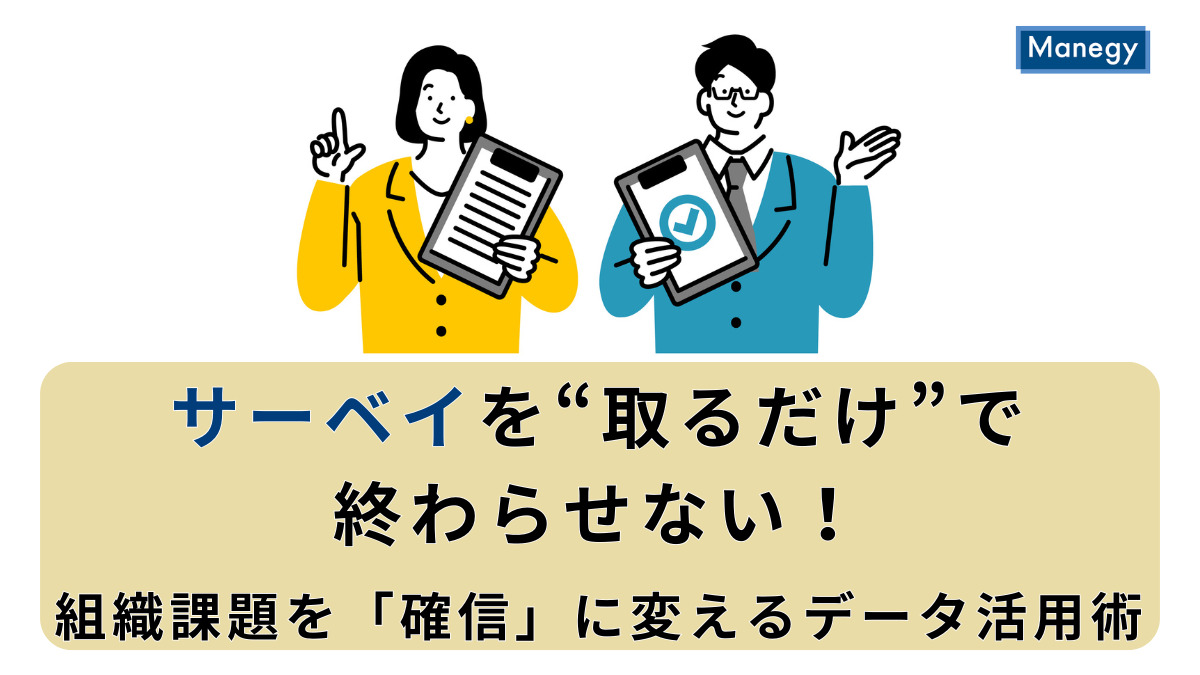
近年、メンタルヘルスやエンゲージメント向上への関心の高まりから、サーベイを導入する企業が急増しています。
一方で、「毎年実施しているが、組織が改善している実感がない」という声も少なくありません。
本記事では、サーベイを“取るだけ”で終わらせず、組織課題の分析やアクション検討を「勘」から「確信」へと進化させるための、データ活用と仕組みづくりのポイントを解説します。
組織課題を解決するために導入したはずのサーベイが、かえって改善を妨げてしまうことがあります。
その原因は、サーベイの実施自体が目的化し、形骸化している点にあります。
「サーベイを実施している」という事実が、経営層や人事に「組織の問題に向き合っている」という錯覚を生み、次のアクションを検討する議論を停滞させることがあります。
例えば、設問内容が現状に合っていなかったり、結果が現場へ適切にフィードバックされなかったりすると、従業員は「どうせ何も変わらない」と回答への意欲を失い、サーベイへの回答精度の低下にも影響してしまいます。
サーベイを実施しているのに組織が変わらない企業には、いくつかの共通点が見られます。
目的が不明確である
「他社もやっているから」という理由でサーベイ等の組織診断ツールを導入したことで、自社において何を明らかにし、その結果をどう活かすのかというゴール設定が曖昧であるケース。
実行体制が未整備である
担当者がサーベイ結果の分析に追われ、現場での改善アクションを促すための体制(マネージャーへの権限委譲や教育)が整っていないケース。
単なる「点」のデータとして扱っている
サーベイ結果を、過去のデータや、勤怠情報、評価情報等、他の人事データと関連付けて分析する視点がないケース。
数値化だけで満足している
漠然とした「エンゲージメントスコア」の良し悪しに一喜一憂するだけで、その裏にある具体的な要因を深く掘り下げていないケース。
サーベイを有効活用するためには、それぞれの特徴を理解し、目的とフェーズに合わせて適切に使い分けることが重要です。
主な手法の違いとしては、「パルスサーベイ」と「センサスサーベイ」があります。
パルスサーベイは、「脈拍」を意味する「パルス(Pulse)」という言葉の通り、組織の状態を短いスパンで継続的にチェックしていく手法です。
特徴: 設問数が少なく(5問~15問程度)、従業員の回答負担が軽いため、週次/月次といった高頻度での実施が可能です。
目的:
組織の小さな変化や「今」のコンディションをリアルタイムで把握し、早期に課題の芽を摘むための「モニタリング」に適しています。
特に、組織変更時や大規模プロジェクト実行後の従業員の心理状態把握に有効です。
センサスサーベイは、組織全体を対象に、多角的な視点から詳細な情報を集める手法です。
特徴:設問数が多く(50問~100問以上)、回答に時間がかかるため、半年に1回や年1回といった低頻度で実施されます。
目的:組織の構造的な課題、本質的な文化、制度に対する評価など、中長期的な視点での「要因の特定」と「深い傾向の把握」に適しています。
いわば“組織全体の健康診断”のような役割を果たします。
センサスサーベイで大枠の構造的課題を特定し、パルスサーベイで具体的な施策実行後の効果や日々の状況を追跡するというように、 両者を連携させることで真価を発揮します。
サーベイの最大の価値は、経営層や人事が肌で感じている定性的な“空気感”を、「客観的な数値データ」として捉え直すことができる点にあります。
「最近、現場の雰囲気が悪い気がする」「なんとなく離職が増えている」といった“勘”を、 「〇〇部署の上司・部下間の信頼スコアが全社平均を10ポイント下回っている」 「評価の仕組みへの納得感が前四半期比で15%低下している」といった“信頼性のある情報”に変えるのです。
この数値化によって、属人的な経験や勘に頼るしかなかった課題分析や施策検討を、 データに基づいた論理的で再現性の高いプロセスへと進化させることができます。
サーベイデータを単なるアンケート結果で終わらせず、「信頼性のある情報」へと昇華させるには、「データの一元化」と「相関分析」がポイントとなります。
例えば、「エンゲージメントスコアが低い」という結果が出たとき、 優秀な組織コンサルタントは経験から「人事評価制度もしくはマネージャー育成に問題があるだろう」と推測するかもしれません。
しかし、データ活用によって、この“推測”をより“確信”へと変えることができます。
サーベイデータを「信頼性のある情報」に変えるには、他の人事データとの連携が不可欠です。
勤怠や人事評価データなど、あらゆる人事データを一つの基盤で管理していると、
データの掛け合わせがスキル不要でリアルタイムに行うことができます。
例として、以下のような効果が挙げられます。
ハイパフォーマーの離職防止
「評価は高いのに昇給率が低い」従業員のエンゲージメント低下を特定。
「評価と報酬の連動性」という制度課題をデータで裏付け、改善に着手できます。
メンタル不調の予防
特定部署の「残業時間増加」と翌月の「コンディション悪化」の相関を早期に発見。
マネージャーがパフォーマンス低下前に介入し、予防的なケアを実現します。
オンボーディングの改善
「中途入社1年未満」の層に絞り、成長実感スコアの低下を可視化。
「中途向け研修の見直し」など、的を射た育成施策につなげます。
このように、さまざまな人事データと掛け合わせて、
人事が「分析」と「次のアクション」に集中できる環境づくりがとても大切です。
サーベイは「何のために取るのか」という目的の明確化が必須です。
例えば、目的が「メンタルヘルス不調の早期発見」なら、心理的安全性等に関する設問に重点を置く必要があります。
また、設問が抽象的すぎると回答も曖昧になります。
「この会社で働くことに満足していますか?」ではなく、「あなたの仕事における意思決定の権限に納得していますか?」といったように、具体的なアクションに直結しやすい“問いの質”が、データ結果の分析と施策改善の質を大きく左右します。
サーベイ結果を「点」ではなく「線」で捉えるためには、「部署」「勤続年数」「評価」などの他の人事データと紐づけて分析することが不可欠です。
例えば、「中途入社3年未満」の従業員だけを抽出してサーベイ結果を見ると、 「人材育成制度への満足度が極端に低い」といった傾向が見えてくることがあります。
こうした分析から、「入社時研修の見直し」など、実際の現場課題に即した施策を設計できるようになります。最も重要なのは「サーベイ実施後の動き」です。
アクション設計でつまずかないためのポイントは、分析結果を現場へフィードバックし、現場主導の改善を促すことです。
フィードバック:全体の結果だけでなく、各チーム・部署ごとの結果(特に改善が必要な項目)をマネージャーにフィードバックする。
対話と計画:マネージャーは、フィードバック結果をもとにチームメンバーと「なぜこのスコアなのか?」を話し合う場を設ける。
その対話を通じて、チーム独自の具体的な改善アクション(例:毎週水曜日はノー残業デーの徹底、1on1の実施強化)を計画する。
追跡と検証:次のパルスサーベイで、そのアクションがスコアの改善につながったかを追跡し、施策の効果を検証する。
このサイクルを回すことで、人事・経営層は全社の課題解決の方向性を打ち出しつつ、 現場は自分事として具体的な改善を進めるという、協働的な組織改善が実現します。
サーベイは、組織の課題を明らかにするための単なる「測定器」ではありません。
組織を良くしたいという従業員と企業の意志を数値化し、勘を確信に変えるための強力な「対話のツール」となり得ます。
サーベイの真の価値は、「どれだけ正確にデータが取れたか」ではなく、 「その後の分析によって、どれだけ精度の高い施策が生まれたか」、そして 「現場を巻き込んだ改善のサイクルが回っているか」で決まります。
現在、サーベイの効果を実感できていないのであれば、 実施目的、問いの質、そして何よりサーベイ実施後のデータ活用と現場連携のプロセスを再設計し、 サーベイを組織改善のエンジンとして最大限に機能させてはいかがでしょうか。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集
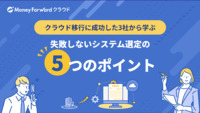
クラウド移行に成功した3社から学ぶ失敗しないシステム選定の5つのポイント

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!

又は・若しくはの違いとは?意味・使い分けと契約書での注意点を例文で解説

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

介護休業制度とは?―2025年法改正と制定経緯から考える、仕事と介護の両立支援の本質―

上場企業の経理担当者が知っておくべきPMIの基礎知識

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

中堅企業はココで選ぶ! 会計システムの選び方ガイド

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!
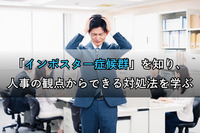
「インポスター症候群」を知り、人事の観点からできる対処法を学ぶ

過重労働の判断基準と健康リスクを徹底解説 ─ 厚労省ガイドラインで学ぶ企業の防止策
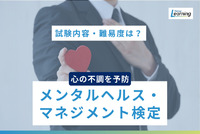
メンタルヘルス・マネジメント検定試験は社会人に役立つ資格?試験の内容や難易度は?

6割の総務が福利厚生と従業員ニーズのギャップを実感するも、3割超が見直し未実施
公開日 /-create_datetime-/