公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
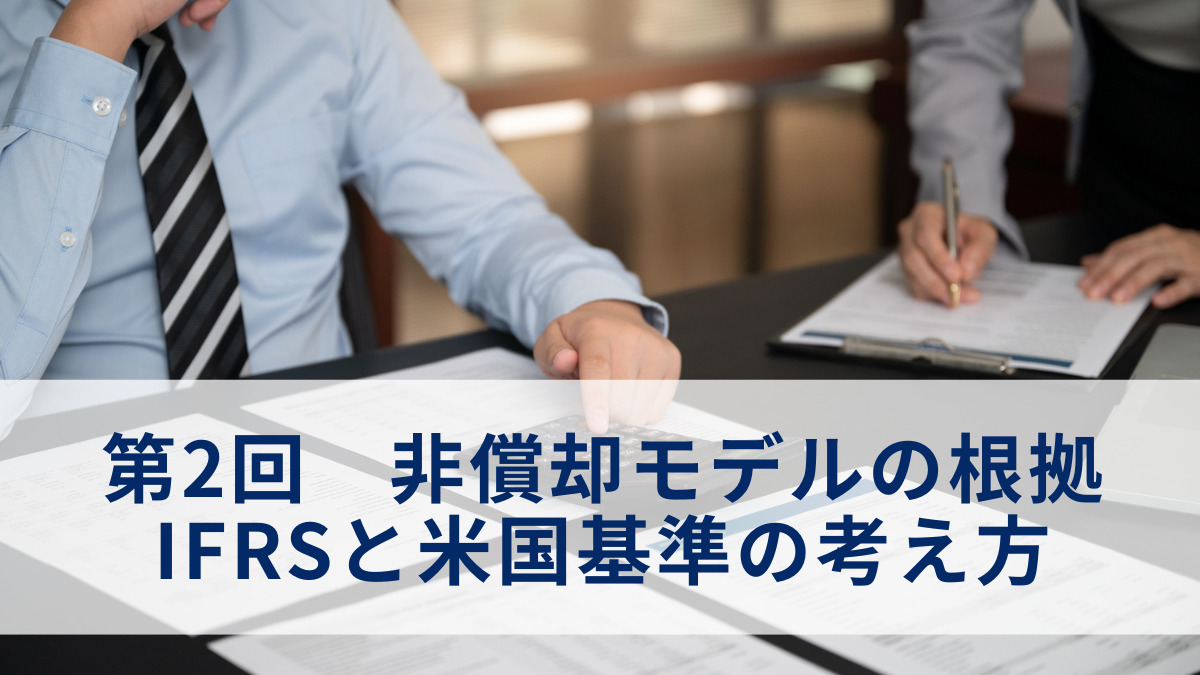

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
日本・米国公認会計士・税理士 大樂 弘幸
のれんの償却・非償却を巡る国際的議論と、M&A促進へ国内基準見直しの動き及び国際的な開示強化の動きについて解説する。
当コラムのポイント
国際財務報告基準(IFRS)および米国会計基準(US GAAP)は、長年の議論を経て、のれんを原則として費用計上しない「非償却・減損モデル」を採用しています。このモデルは、のれんの資産としての性質に関する、日本とは異なる根本的な定義に基づいています。
非償却モデルの支持者は、のれんは特定の期間内に価値が消滅すると断定できる普通の資産とは違うものだと主張します。のれんは、買収によって生み出された相乗効果(シナジー)やブランド価値、組織文化といった要素の集合体であり、これらの価値は、買収後の継続的な努力によって維持され、場合によっては強化される可能性があると考えます。
したがって、のれんの価値の寿命は「期間の定めのない(無限定)」の可能性があり、価値が毀損していないにもかかわらず、規則的な償却を行うことは、企業の真の収益獲得能力を歪め、投資家にとって「真に意味のある情報」(関連性)を損なう勝手な費用配分にすぎないという批判が、非償却モデルの理論的な根拠となっています。このモデルでは、償却費という名目上の費用を計上するよりも、のれんの価値が実際に傷んだタイミングで、その全額を減損損失として一括で認識する方が、投資家に対して企業の真の状況を伝える上でより役立つ情報を提供できると考えられています。
この記事を読んだ方にオススメ!
記事提供元

上場企業を中心とする大企業向けに提供している「TKC連結グループソリューション」は、現在、日本の上場企業の4割超をはじめ、5,900グループでご利用いただいております。
そのシステム活用を全国1,600名を超える税理士・公認会計士が支援し、経理部門の生産性やコンプライアンス向上に貢献するための活動を展開しております。
▼過去のコラムのバックナンバーはコチラ
▼IPOに関する最新情報はコチラ
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
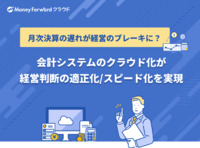
会計システムのクラウド化が経営判断の適正化・スピード化を実現

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

上場企業の経理担当者が知っておくべきPMIの基礎知識
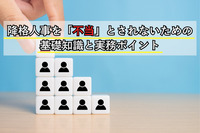
降格人事を「不当」とされないための基礎知識と実務ポイント

従業員満足度(ES)とは?向上させるための7つの方法
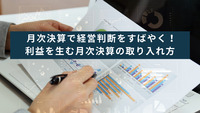
月次決算で経営判断をすばやく!利益を生む月次決算の取り入れ方

賃上げ実施も9割超が「生活改善せず」と回答 従業員の8割が望む「第3の賃上げ」の実態を調査

経理の予算管理とは?基本から予実管理・差異分析・ツール活用まで実務目線で解説
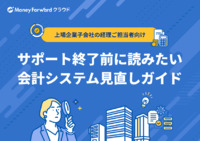
サポート終了前に読みたい会計システム見直しガイド

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
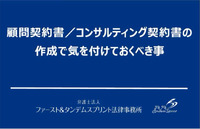
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!

又は・若しくはの違いとは?意味・使い分けと契約書での注意点を例文で解説

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

介護休業制度とは?―2025年法改正と制定経緯から考える、仕事と介護の両立支援の本質―
公開日 /-create_datetime-/