公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

労働時間管理とは、労働者が「どれだけ・いつ・どのように」働いたかを、企業が正確に把握し、法令に基づいて適切に管理することを指します。これは単なる勤怠データの収集にとどまらず、業務命令の有無や健康配慮、安全配慮義務といった観点も含めて、広く“働いた時間”をどう認識し、処遇に反映させるかという企業の重要な責任でもあります。
では、労働時間を管理する責務は誰が負っているのでしょうか?
実際に働く労働者側でしょうか?それとも企業側でしょうか?
厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)によると、「労働基準法(以下、労基法)においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している。」として、企業側に責任があることを明確にしています。
また、労働安全衛生法(以下、安衛法)では、「事業者は、医師による面接指導を適切に行うために、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない」と定められています(安衛法第66条の8の3)。これは長時間労働者の健康リスクを未然に防ぐための規定であり、企業には健康管理の観点からも労働時間の把握が求められていることを意味します。
整理すると、労基法では「適正な賃金の支払い確保」を目的として、安衛法では「健康を管理する面接指導の実施」のため、両法で労働時間管理を“企業の責務”としているのです。
このガイドラインは、未払賃金や過重労働が社会問題化する中、2017年1月に厚生労働省によって策定されたものです。ガイドラインそのものは法的拘束力を持つものではありませんが、このガイドラインで記載された労働時間の適正把握義務については、そのまま安衛法に組み込まれ、2019年4月に施行された働き方改革関連法の中核となりました。つまり、労働時間の適正把握義務は法令として格上げされ、法的拘束力を持つことになったのです。
それにより労働基準監督署では、労働時間の適正把握義務を明確な根拠として取り締まり、違反した場合は「是正勧告書」を交付して指導し、結果の報告も求めるという厳しい対応ができるようになりました。指導について、具体的な手法や運用はガイドラインに記載された内容に基づいて行うため、ガイドライン自体も、労働時間管理において非常に重要な位置づけとなっています。
以下では、ガイドラインに示されている「労働時間」の定義と適用範囲を引用して解説します。
参考)厚生労働省PDF「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 」
記事提供元

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
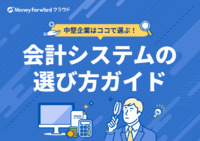
中堅企業はココで選ぶ! 会計システムの選び方ガイド

経理業務におけるスキャン代行活用事例

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

【ランスタ特別企画】『ManegyランスタWEEK -FY2025 ハイライト-』で自信を持って新年度を迎えよう!
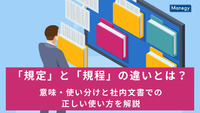
「規定」と「規程」の違いとは?意味・使い分けと社内文書での正しい使い方を解説
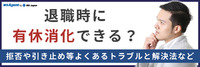
退職時に有休消化できる?拒否や引き止め等よくあるトラブルと解決法など
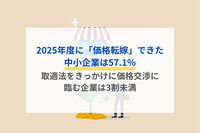
2025年度に「価格転嫁」できた中小企業は57.1% 取適法をきっかけに価格交渉に臨む企業は3割未満

又は・若しくはの違いとは?意味・使い分けと契約書での注意点を例文で解説

優秀な退職者を「もう一度仲間に」変える 人材不足時代の新採用戦略
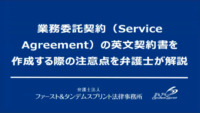
業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下
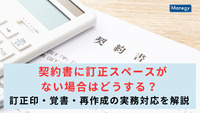
契約書に訂正スペースがない場合はどうする?訂正印・覚書・再作成の実務対応を解説
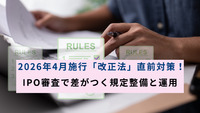
2026年4月施行「改正法」直前対策!IPO審査で差がつく規定整備と運用

契約書の条ずれを発見したらどうする? 正しい修正方法と注意点を解説
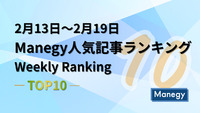
2月13日~2月19日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
公開日 /-create_datetime-/