公開日 /-create_datetime-/
法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?
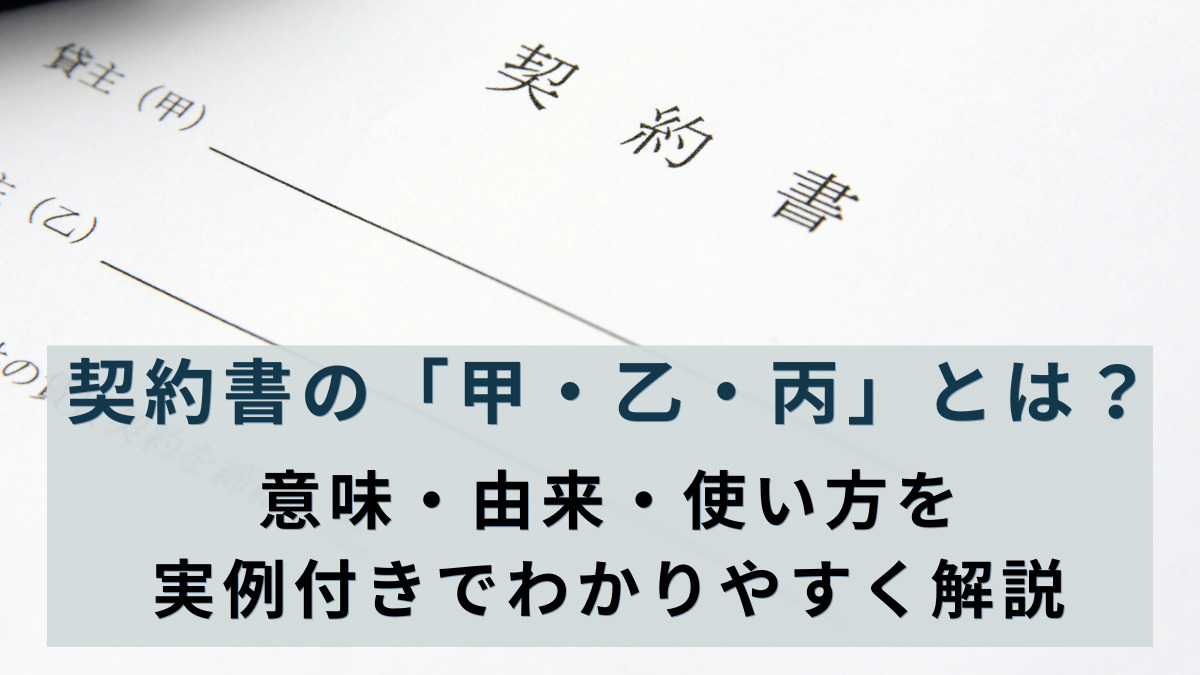
契約書でよく見る「甲・乙・丙」。
契約書で頻繁に目にするものの、「なぜこの表記なのか」「どんな意味があるのか」を正確に説明できる人は多くありません。
この記事では、「甲・乙・丙」の由来から契約書での使い方、注意点までを実例付きで解説します。
「甲・乙・丙」とは、契約書などで複数の当事者を区別する際に使われる呼称です。
「甲・乙・丙」は、もともと中国で使われていた暦や時間の区分を示す「十干(じっかん)」に由来します。
十干には、「甲(こう)」「乙(おつ)」「丙(へい)」「丁(てい)」「戊(ぼ)」「己(き)」「庚(こう)」「辛(しん)」「壬(じん)」「癸(き)」の10種類があり、十二支と組み合わせて「六十干支(ろくじっかんし)」として暦に用いられてきました。
したがって、「甲・乙・丙」は本来、順序を示すための呼称として使われていました。
契約書で「甲・乙・丙」を使う場合、「甲=上位」「乙=下位」といった優劣関係はありません。
ただし、実務上は「取引先を甲、自社を乙とする」ケースが多く、結果的に「甲=主たる当事者」とみなされる場面もあります。
「甲(こう)」は、当事者の名称を簡略化して示す最初の呼称です。
実務では、発注者や貸主など比較的立場が強い側を甲とする運用が広く見られます。
ただし、これはあくまで便宜上の区分であり、「甲=上位当事者」という法的な意味はありません。
この区分によって、どの当事者がどの義務を負うのかを条文中で明確に示せるようになります。
「乙(おつ)」は、甲の相手方に付ける2番目の呼称です。
受託者や借主など、発注者側(甲)の相手方が乙となる例が多く、実務では顧客(甲)/自社(乙)の割り当てが一般的です。
甲乙表記を用いることで、当事者名の重複を避けつつ、主語・義務の特定を明確にできます。
「丙(へい)」は、三者以上が関与する契約で用いる第3の呼称です。
例:顧客(甲)/開発会社(乙)/法律事務所(丙)など。
再委託・共同開発・守秘情報の三者共有といった場面で、主体ごとの義務(守秘・成果物・責任範囲)を切り分ける目的で用いられます。
条文上の誤解や責任関係の混乱を防ぐうえでも有効です。
契約書で「甲・乙・丙」を用いるのは、形式的な慣習ではなく、契約実務を円滑かつ正確に進めるための合理的な仕組みです。
ここでは、その主な3つの理由を整理します。
契約書では、当事者名を何度も繰り返すと文面が長くなり、読みにくくなります。
そこで、「株式会社A(以下「甲」という)」のように定義しておくことで、その後は「甲」「乙」「丙」と略して記載でき、文章を簡潔にまとめることができます。
特に、数ページにわたる契約書や複数当事者が登場する場合に有効です。
当事者名を毎回記載すると、表記ゆれや主語の曖昧さによって誤読・誤解が生じるおそれがあります。
「甲」「乙」「丙」と呼称化しておけば、主語が誰なのかを明確に示せるため、契約内容を一義的に理解できます。
また、訴訟やトラブル時に「どの当事者の義務か」を明確に特定できる点もメリットです。
「甲・乙・丙」の記載は、契約書作成ツールやテンプレートにも共通仕様として組み込まれており、修正やレビューの効率化が図れます。
加えて、契約担当者や法務チェックの段階で、当事者名を一括で置換・確認できるため、ヒューマンエラーの防止にも役立ちます。
契約書で「甲・乙・丙」を用いることで文書は簡潔になりますが、記載方法を間違えると誤解やトラブルの原因になります。
ここでは、実務上特に注意すべき3つのポイントを確認しましょう。
もっとも基本的で重要なのは、契約書の冒頭にある当事者定義部分を正確に記載することです。
「株式会社」「有限会社」などの法人格を省略したり、「㈱」など略称で表記したりすると、契約上の当事者を特定できず、無効とみなされるおそれがあります。
また、冒頭で「株式会社A(以下「甲」という)」と定義した場合は、本文中では必ず「甲」を使用し、表記を統一します。
当事者名の不一致は、契約の有効性や責任範囲をめぐる争点となることがあります。
「甲」「乙」「丙」を使う場合、主語と述語の対応関係を崩さないことが大切です。
複数の当事者が登場する契約書では、誰の義務・責任かが曖昧になることがあり、誤解の原因になります。
特に修正や追記を行う際は、主語が途中で入れ替わっていないか、述語との対応関係が崩れていないかを丁寧に確認しましょう。
3社以上が関わる契約では、「甲」「乙」「丙」などの割り当て順を明確に定義することが重要です。
一般的には、主たる当事者を「甲」、次に関与する当事者を「乙」「丙」と設定します。
ただし、共同開発契約などでは立場が入れ替わる場合もあるため、「誰が何を行うのか」を契約本文で明確に記載しましょう。
当事者が多い場合は、契約書冒頭に「当事者一覧表」や「定義表」を設けることで、読み手が混乱せず内容を把握できます。契約書で「甲・乙・丙」を使うときは、当事者の立場や契約内容によって表現が少しずつ異なります。
ここでは、実務でよく見られる2つのケースを紹介します。
たとえば、A社が発注元、B社が受託先、C社が協力会社として関わる場合、それぞれを「甲」「乙」「丙」として区別します。
甲(A社)は、乙(B社)に対し、本件業務の一部を委託し、乙はこれを受託するものとする。
乙は、業務遂行にあたり、丙(C社)を再委託先として利用することができる。
このように、複数の当事者が関わる契約では、「甲・乙・丙」を使うことで、文中の関係性を明確に整理できます。
それぞれの立場(発注者・受託者・再委託先など)を最初に定義しておくことが重要です。
不動産売買契約や工事請負契約などでも、「甲・乙」または「甲・乙・丙」が使われます。たとえば、次のような文面です。
甲(発注者)は、乙(請負者)に対し、別紙仕様書に基づき工事を請け負わせるものとする。
乙は、甲の承諾を得たうえで、丙(下請事業者)に本工事の一部を再委託することができる。
このように「甲=発注者」「乙=受託者」「丙=再委託先」という構成が一般的です。 なお、丙が登場する場合は再委託に関する条項を必ず設け、契約責任の所在を明確にしておく必要があります。
契約書では以下のような定型表現が多く使われます。
甲は、乙に対し、本酒約に定める業務を委託し、乙はこれを受託する。
この表現をベースに、契約の目的や範囲を具体的に追記するのが一般的です。 「甲・乙・丙」は、こうした定型文の中で文脈を整理し、責任関係を明確にするための記号として機能します。
「甲・乙・丙」は契約書だけでなく、さまざまな制度や資格区分、商品分類などにも使われています。もともと十干(じっかん)に由来する“順序を示す呼称”のため、今でも等級や区分を表す表現として広く用いられています。
消防法に基づく「危険物取扱者」資格は、甲種・乙種・丙種の3区分に分かれています。
・甲種:すべての危険物を取り扱い・立会い・指導できる最上位資格
・乙種:特定の種類(第1〜第6類)の危険物を取り扱える資格
・丙種:ガソリンや灯油など、限られた危険物を扱える資格
このように「甲・乙・丙」は、資格や権限の範囲を区別する等級表示として機能しています。
不動産登記簿でも、土地の分筆や区分所有に関する表記に「甲区」「乙区」などの区分が使われます。
・甲区:所有権に関する事項(例:所有者の住所・氏名、持分割合など)
・乙区:所有権以外の権利(例:抵当権、地上権、賃借権など)
この「甲区」「乙区」も、契約書の「甲・乙」と同様に情報を整理・区分するための呼称として用いられています。
酒税法では、焼酎は製造方法の違いによって「甲類焼酎」と「乙類焼酎」に区別されています。
・甲類焼酎:連続式蒸留機で製造されるアルコール36%未満の焼酎です。
・乙類焼酎:単式蒸留機で製造されるアルコール度数45パーセント以下の焼酎です。
この分類は「優劣」を示すものではなく、製法や特徴の違いを示す区分です。それぞれの性質を理解し、用途や嗜好に応じて選ばれています。
「甲・乙・丙」は、契約書で広く用いられる呼称です。
当事者を明確に区別し、責任範囲や義務の取り違いを防ぐことで、文書作成の効率化と契約トラブルの防止を図ります。
契約書を作成・確認する際は、まず誰が甲で誰が乙かを特定し、表記を全編で統一することが大切です。
あわせて読みたい
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割
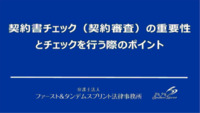
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増

【日清食品に学ぶ】健康経営は「福利厚生」から「投資」へ。手軽に導入できる「完全メシスタンド」とは【セッション紹介】

7割の企業がファンづくりの必要性を実感するも、約半数が未着手。

今、何に貢献しますか?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第7話】

6時間勤務の休憩時間は何分必要?休憩なしは違法かまで詳しく解説

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築
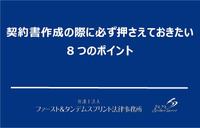
契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

経理業務におけるスキャン代行活用事例

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!

テレワークの勤怠管理完全ガイド!法的義務や管理方法、ルール作りを徹底解説

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

越境ECで売上を伸ばす海外レビュー戦略とは?重要性・実践方法・注意点を解説

〈2025年度第3回 中小企業経営実態調査〉人手不足倒産が過去最多の中*、中小企業経営者の5割以上が「人手不足、人材の確保・育成」を経営課題に
公開日 /-create_datetime-/