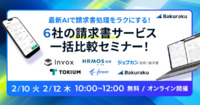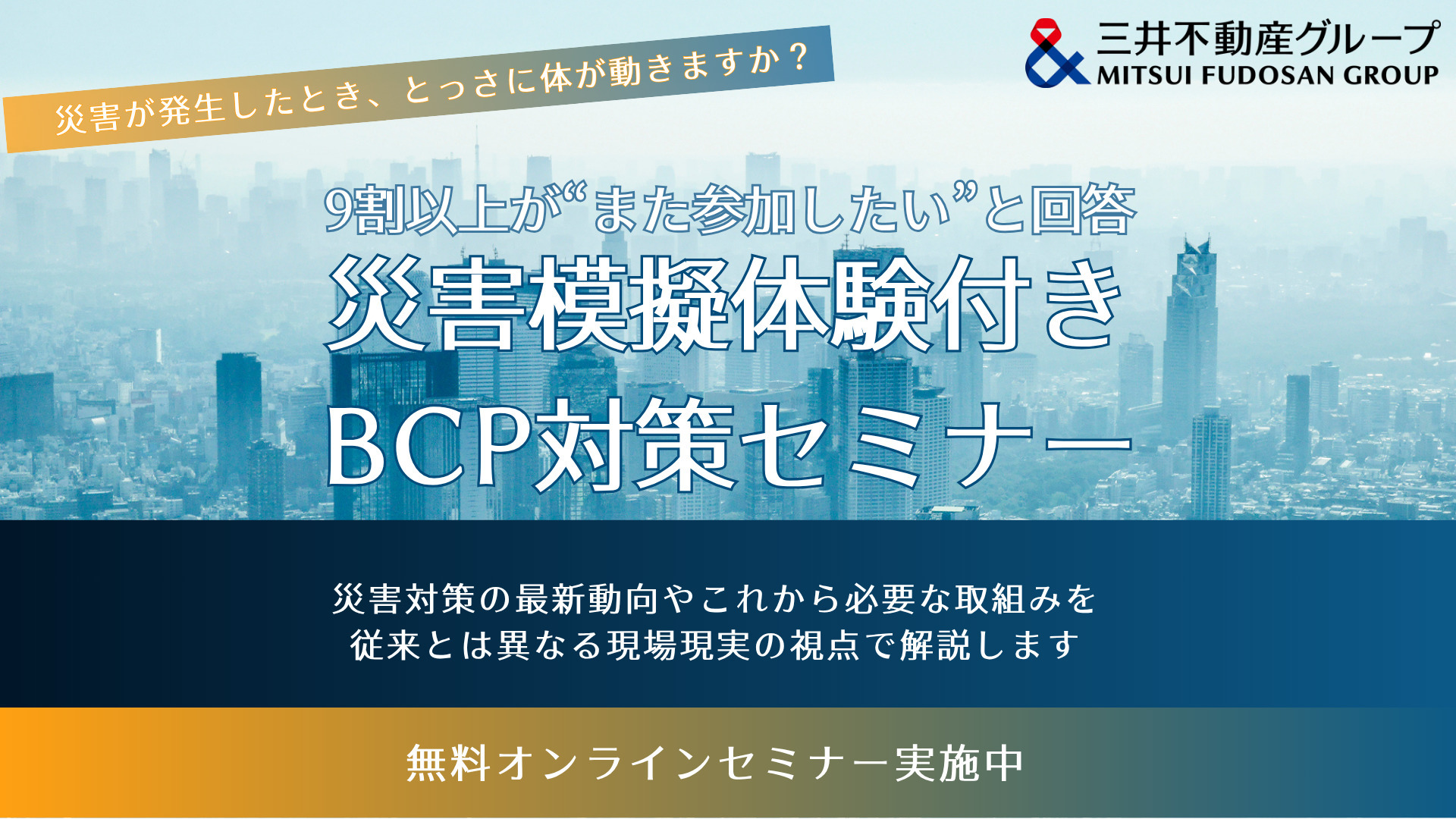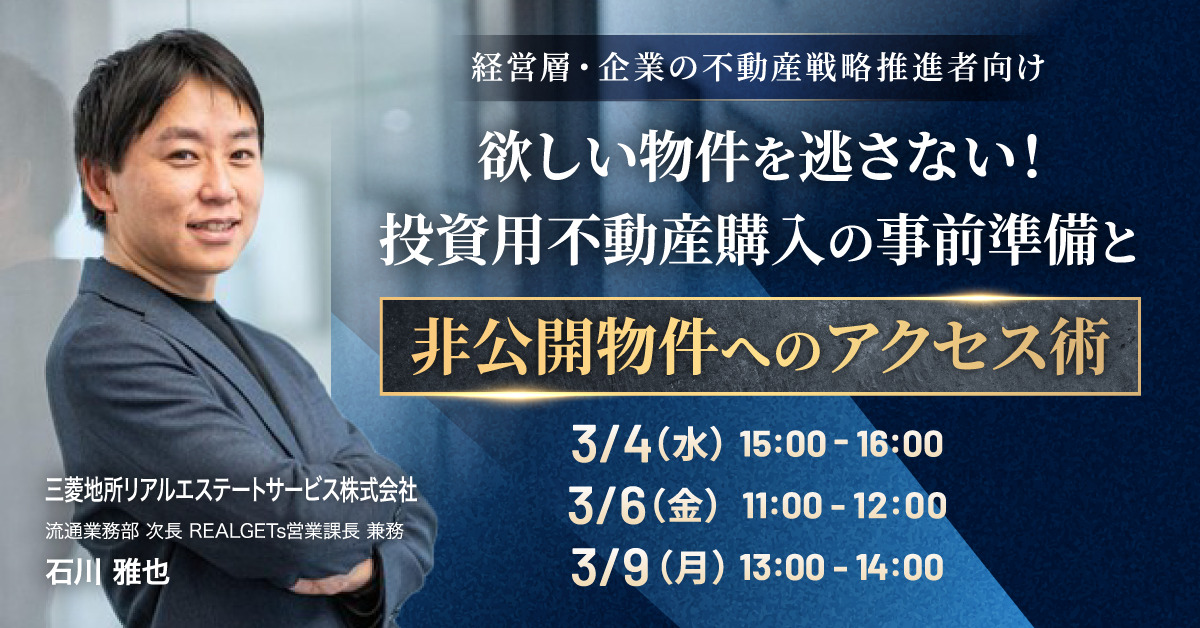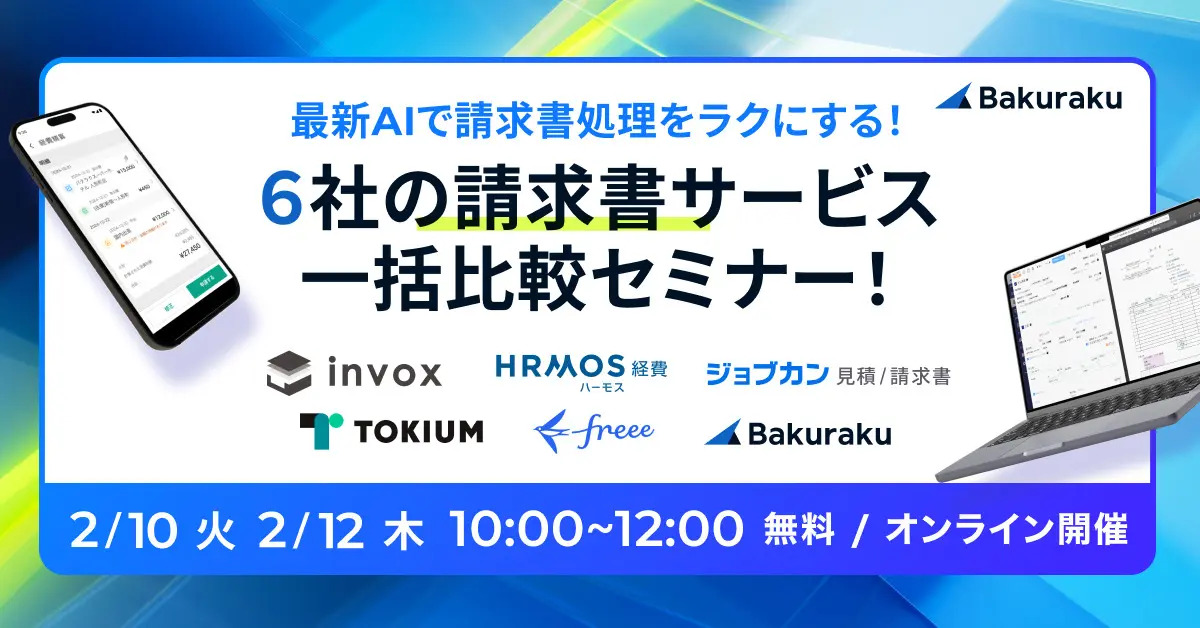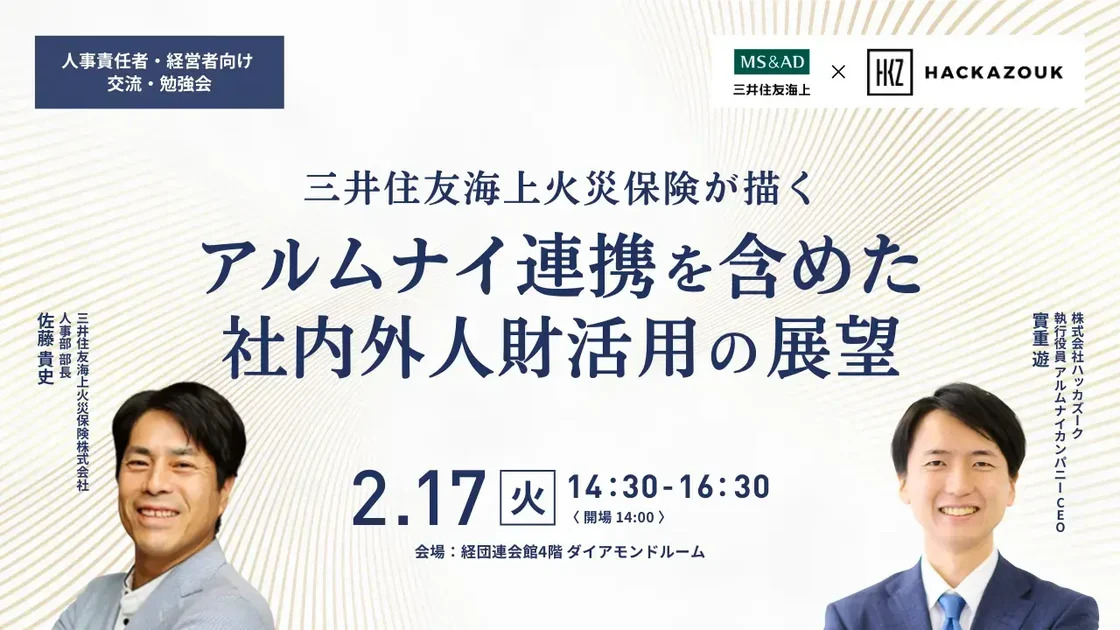公開日 /-create_datetime-/

決算月は国の年度に合わせて3月としている会社が多いですが、9月、12月の会社も増えています。そもそも法人の決算月は会社が自由に決めてよいものですが、会社によって決算月が異なる理由について説明します。
目次【本記事の内容】
3月決算が多い理由
日本の会計年度の区切りは4月から3月です。そのため国や地方公共団体などの公的機関を取引先としている会社は、決算月を合わせた方が予算などの関係上、都合がよいため3月決算にしている企業が多いのです。
国の年度が4月始まりになったのは明治時代からで、現在まで約130年間も続いています。4月が新年度となった理由は諸説あり、①納税の時期 ②稲作の準備の開始時期 ③徴兵制度の変更に合わせたなどと言われています。
学校関連も運営に必要な資金援助を国から受ける必要があるため、年度を合わせるようになりました。そのため、新卒を多く採用する大企業にとって4月新年度は都合がよいという面もあります。
また、日本では税法に関する法律改正が4月1日付けで適用されることが多く、会社にとって期の途中で変更する手間が省けるという利点もあります。
次に決算の多い月は9月、そして12月
3月に次いで多い月は9月です。
4月は人事異動や新入社員の入社など、社内イベントが多いため、慌ただしい時期とかぶらないようにしていることが理由のようです。
また、監査法人や税理士の繁忙期である年末から3月、4月を避けるという点もあるようです。
12月決算の会社は9月と同程度に増えています。海外企業の多くが12月決算としており、中国は法令で12月決算と決められています。そのため外資系企業の日本法人の場合、同様に12月決算としています。
日本企業でも大企業の中には12月決算に移行する会社が増えています。最近のグローバル化の波により、日本企業も次々に海外に進出し子会社を持つようになりました。国際会計基準(「国際財務報告/IFRS)では、親会社と子会社を一体とみる連結決算の作成ルールとして、決算期を統一しなければならないとされています。
日本の連結財務諸表規則では、親会社と子会社の連結決算日の差異が3カ月を超えなければ当該事業年度の財務諸表を基礎として連結財務諸表を作成すればよい、とされていますが、国際会計基準では「実務上不可能な場合に限る」とされています。そのため欧米や中国に進出する企業にとって、国際会計基準に対応し、決算業務スムーズに行うため子会社に合わせる企業が増えているのです。
決算月を決める基準とは
会社を設立する際、日本では各企業の諸事情に合わせ決算月を自由に決めてよいので、上記以外の月でも、一度決めた後に変更することも問題ありません。一般的に以下のようなことを考慮して決めています。
会社の繁忙期を避ける
決算業務は経理部門だけではなく、社内の他部門も年度内に処理すべき書類の提出や、棚卸しなどで携わることになります。また、取引先や仕入先への連絡が必要な場合もあります。会社の繁忙期に決算月を合わせると、各部門は本業に忙しく、決算業務に関わっている時間がないということもあるでしょう。
また、繁忙期の売上は多いものの年ごとの変動も大きいため、予想を上回る利益が出たりその逆のこともあります。繁忙期と決算月をずらすことにより、決算までに節税対策を行ったり、業務の回復を図り売上を伸ばすための対策を考える時間を持つことができます。
会社の繁忙期に合わせる
繁忙期に売上の多くが集中している会社は、あえて決算月を合わせているところもあります。社内全体が慌ただしく大変なものの、決算に向けて追込みムードを作り、売上を伸ばすために気運を高めようということがあります。
節税対策のため会社設立時期に合わせる
資本金額が1,000万円未満の株式会社は、設立第1期目と第2期目の消費税の納税義務の免除を受けることができます。(ただし、前期の上半期の課税売上高が1,000万円超であるかどうかで当期の課税事業者になるか判定されます。)
消費税の納税免除期間を少しでも長くするためには、設立年月日からできるだけ離れた月を決算月にするとよいことになります。つまり、4月1日が設立であれば3月を決算月とすれば免除期間が2年間となります。
税金の支払い時期と支出が多い月を避ける
会社は決算日から2ヶ月以内に法人税、住民税、事業税及び消費税を納付する義務があります。
これらの税金の支払いは、会社にとって通常大きな資金の支出です。
会社の資金繰りへの影響を少なくすることを目的として、税金の支払時期と他の大きな支出が発生する時期を考慮し、決算月を決める会社もあります。具体的には、具体的に夏、冬のボーナスの他に、源泉所得税や労働保険料の納付月などがあります。
まとめ
企業は会社設立時に決算月を決める必要がありますが、会社により決算月が違うのは諸事情がそれぞれ異なるからです。どの点を重要視するかはその会社の判断によります。あなたの会社の決算月も上記の理由があってその月に決まったのかもしれません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
おすすめ資料 -
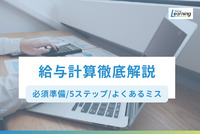
【人事・経理の基本】給与計算のやり方、何から始める? 必須準備から5ステップ、よくあるミスまで徹底解説
ニュース -

会社の存在理由から、法人の税金ルールを理解しよう
ニュース -
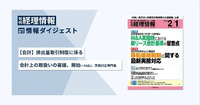
旬刊『経理情報』2026年2月1日号(通巻No.1766)情報ダイジェスト②/会計
ニュース -

売上1千億円を目指す企業で「半歩先を見据え、変化を楽しむ管理部門」の魅力【CFOインタビュー SmartHR 取締役CFO 森 雄志氏】
ニュース -

お金の流れと損益が一致しない『減価償却費』を理解しよう
ニュース -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?
おすすめ資料 -

フリーアドレスの成功事例 ご紹介
おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -

労働保険料の勘定科目を完全解説|仕訳処理と経費計上の正しい考え方
ニュース -

上場企業も暗号資産で一攫千金?投資事業への参入相次ぐ
ニュース -
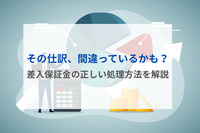
その仕訳、間違っているかも?差入保証金の正しい処理方法を解説
ニュース -

インボイス制度の経過措置はいつまで?仕入税額控除の計算方法を解説
ニュース -

領収書の偽造は犯罪!刑罰・見破り方・防止策を徹底解説
ニュース