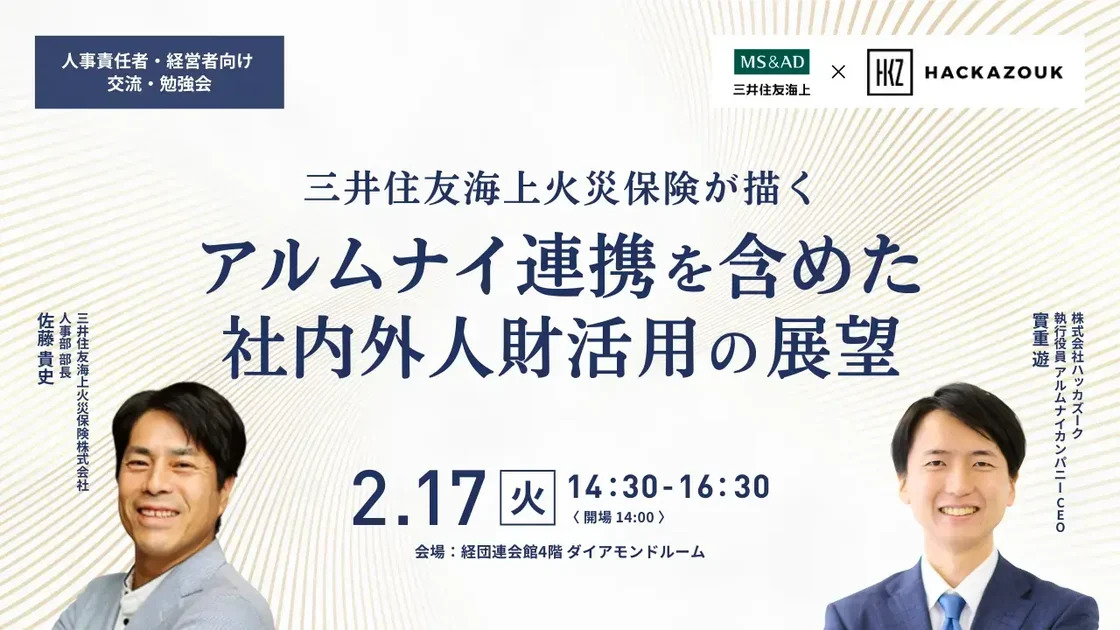公開日 /-create_datetime-/
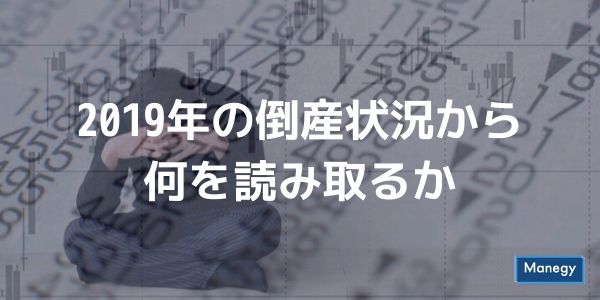
東京商工リサーチによると、2019年の負債総額1,000万円以上の倒産は8,383件で、11年ぶりに前年を上回る結果となった。景気の後退局面を示すデータが次々と公表されているだけに、2020年はさらに増えるのかどうかが気になるところだ。
この倒産件数は、バブル崩壊以降の30年間では下から3番目に低いもので、東京商工リサーチによると、決して“倒産件数が増加傾向にある”ということではないようだ。むしろ、注目すべきは負債総額1,000万円未満の倒産件数の方である。
その負債総額1,000万円未満の2019年の倒産は512件である。この倒産件数は、リーマン・ショック直後の2009年の520件、2010年の537件に匹敵する件数ということは、押さえておく必要がありそうだ。
業種別では、繊維関係やアパレルの倒産増加が目立つが、これは「百貨店の苦戦の背景と似ている」と、東京商工リサーチは指摘している。また、昨年12月単月では、飲食料品が製造・卸・小売の全てで増加していることも明らかになった。
さて、倒産の原因だが、東京商工リサーチによると、「赤字累積」、「販売不振」、「売掛金等回収難」による倒産を「不況型倒産」と定義している。この定義による2019年の不況型倒産は6,961件で全体の83.0%を占めている。
やはり、後退局面にある景気の動向が、企業経営に影響を及ぼしているようだが、東京商工リサーチの分析では、「不況型と文字通りに捉えるのではなく、競争力のない企業の淘汰と見た方がいい」ということである。
同社が保有する企業データから、約70万社を対象に直近業績を分析した結果は、増収は全体の47.6%だった一方、増益は35.1%にとどまっている。つまり、売上が伸びていながら利益が出ていないという状況だ。
倒産件数そのものは、低水準で推移しているものの、減収減益が21.5%に及び、制度融資などさまざまな支援を受けながらも、業績が回復しない企業は決して少なくない、いわゆる“息切れ型”ともいうべき倒産件数が、これから増えていくのではないだろうか。
財務担当者は、自社の財務状況を的確に把握し、“息切れ“しないような財務体質にしていくことが求められことになりそうだ。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも
ニュース -

労基法大改正と「事業」概念の再考察 ~事業場単位適用の実務~
ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第3回 自社利用のソフトウェアの定義と会計処理等(企業会計と税務会計の違い)
ニュース -

新聞図書費とは?経理が押さえておきたい対象経費と仕訳の基本
ニュース -

AIの反社チェック・コンプライアンスチェック 信じちゃダメです。本当に絶対ダメです。
ニュース -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

オフィスステーション導入事例集
おすすめ資料 -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

②労災事故発生時の対応と届出│労働者死傷病報告提出のタイミング~労働者死傷病報告の方法と内容
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月20日号(通巻No.1768)情報ダイジェスト①/税務
ニュース -

採用計画で市場価値を上げる8つのスキル|戦略人事へのキャリアパスを徹底解説【転職成功事例つき】(前編)
ニュース -

フランチャイズ契約とは?ロイヤリティ・テリトリー・競業避止など契約条項を徹底解説
ニュース -
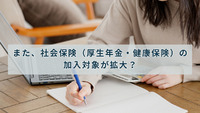
また、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象が拡大?
ニュース