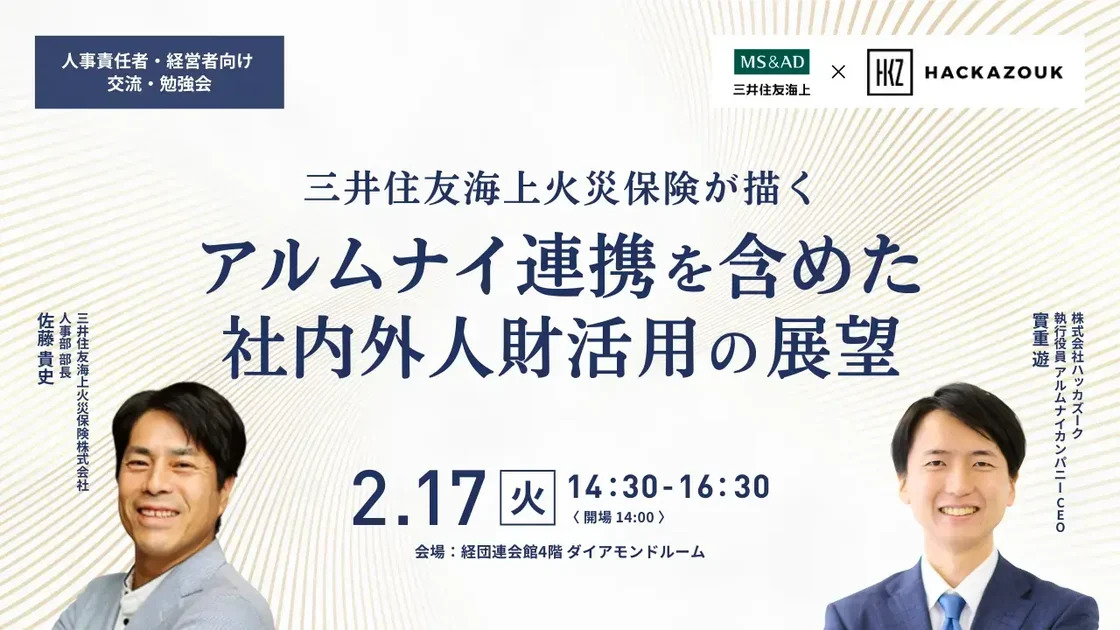公開日 /-create_datetime-/
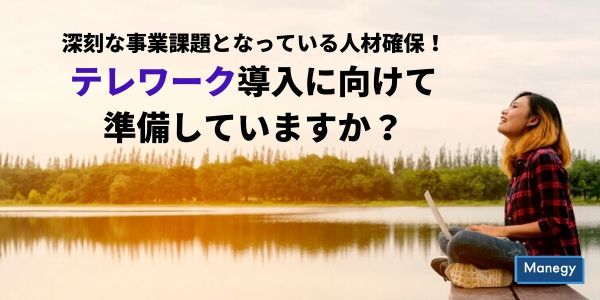
優秀な人材確保や離職率の低減が、事業運営の重要な課題となっています。帝国データバンクによる2017年の調査によれば、日本の企業のうち約44%が正社員不足を感じており、この数値は直近10年間で最も高い数値だそうです。
人材不足は求人に関わるコストの問題だけではなく、事業の効率にも大きな影響をもたらします。総務省は人材不足の解決策として労働生産性と労働参加率の向上を挙げていますが、特に労働参加率向上の鍵となるのがICTの利活用を通じたテレワークの普及だと言われています。優秀な人材の流出を防止し、作業の効率を高めるテレワーク。導入への準備は進めていますか?
厚生労働省の掲げる「テレワーク人口倍増アクションプラン」
厚生労働省は2007年に、テレワーク推進に関する関係省庁連絡会議で「テレワーク人口倍増アクションプラン」を策定しました。その背景には、加速が止まらない日本の生産年齢人口(労働人口)の減少があります。
2017年の日本の生産年齢人口は、6,530万人。それが2025年には6,082万人、2040年には5,234万人になると試算されています。20年あまりで約20%の生産年齢人口が減ってしまうわけですが、一番の原因は出生率の低下と、それを要因とする高齢者の割合増加(高齢化)です。2018年の出生数は約92万人ですが、死亡数は約137万人。日本は生産年齢人口だけでなく、人口の減少問題にも直面しています。これはそのまま国力の低下につながるので、国は危機感を強めているのです。
出生率の低下にもさまざまな対策がされていますが、生産年齢人口の減少に対する歯止め策の一つが「テレワーク人口倍増アクションプラン」です。本アクションプランでは、「2020年までにテレワーク導入企業を2012年度比で3倍」、「週1日以上終日在宅で就業する雇用型在宅型テレワーカー数を全労働者数の10%以上」とする政府目標が設定されています。
テレワークがもたらす数々のメリット
「テレワーク人口倍増アクションプラン」には、国が支援するテレワーク推進のための施策が盛り込まれています。テレワーク共同利用型システムの実証実験や、テレワーク環境整備税制の制定、「国家公務員育児休業法」をはじめとする各種法律の整備、在宅就業者支援事業の実施などです。では国がこのように力を入れるテレワークには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
<テレワーク導入の主なメリット>
・少子化、高齢化問題等への対応
育児・介護と就労の両立が可能(離職率の低減)
在宅ワークによる女性や高齢者、障害者の就業機会の拡大(人材確保)
・有能な人材の確保、生産性の向上
有能な人材の確保と流出防止(離職率低減、人材確保)
外出時のテレワークによる営業効率の向上、顧客満足度の向上(効率向上)
・地域活性化の推進
UターンやIターンに関わる人材流出の防止(離職率低減、人材確保)
地方での起業による地域活性化(地域活性化)
・コスト・時間削減
事務スペースや通勤費の削減(コスト低減)
通勤・移動時間の削減(効率向上)
・ワークライフバランスの向上
テレワークを導入することにより、人材確保の問題解決だけでなくコスト削減や作業の効率向上にも寄与することがわかります。
テレワーク導入に向けて準備すべきこと
では実際にテレワークを導入するには、どのような準備を進めておくべきなのでしょうか?テレワークの形態は「在宅型」、「モバイル型」、「施設利用型」と大きく3つに分かれますが、そのキモとなるのは情報通信技術(ICT)です。まずはセキュリティを確保した、有効なテレワークシステムとネットワーク環境が必要になります。また会社から持ち出すPCや、自宅で使うPCの管理(データの暗号化、パスワードの徹底)なども必要です。
上記のような技術的問題は外部業者に依頼することでも解決できますが、実は最も重要なのはテレワークの運用に関わる制度策定です。まず社外で勤務することへの労使の合意が必要になります。テレワーカー(テレワークを利用する勤務者)の勤務時間帯と日常生活時間帯が混在せざるを得ない働き方であることを考えれば、労務管理をどのように行っていくかは前もって決めておかねばならない問題です。本件に関しては厚生労働省が、「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」や「テレワークではじめる働き方改革 テレワークの導入・運用ガイドブック」等の資料を公開していますので一度確認しておくと良いでしょう。
また「テレワークの実施範囲(対象者や対象業務)」、「ルール・制度の策定(運用方法や人事評価)」、「教育・研修(テレワーク導入のための教育や研修)」などを決めていくために、社内にプロジェクトを立ち上げるのも良いでしょう。総務や経理、営業、技術などの担当者を集め、ゴール(開始時期)を定めてそれぞれのエキスパートと問題を解決していくことが重要です。
まとめ
台風や大雨などの災害だけでなく、コロナウィルスの流行や東京五輪による混雑の緩和など、これからも利用シーンが増えていくであろうテレワーク。正しく運用すれば労使双方にメリットの多いテレワークですが、労働環境が劇的に変化することへの配慮も忘れるわけにはいきません。一度定めた制度であっても定期的に見直し、運用の状況に合わせて柔軟に改善していくことが大切です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

フリーアドレスの成功事例 ご紹介
おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -

ラフールサーベイ導入事例集
おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも
ニュース -

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ
ニュース -

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増
ニュース -

【日清食品に学ぶ】健康経営は「福利厚生」から「投資」へ。手軽に導入できる「完全メシスタンド」とは【セッション紹介】
ニュース -

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!
ニュース -

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ
おすすめ資料 -

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -
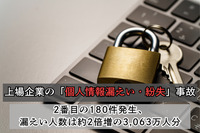
上場企業の「個人情報漏えい・紛失」事故 2番目の180件発生、漏えい人数は約2倍増の3,063万人分
ニュース -

2026年4月「育休取得率・賃金格差」開示義務化直前!IPO審査で問われる数値の裏付け
ニュース -

内部統制報告書とは?提出が義務付けられる企業、記載事項・作成手順を解説
ニュース -
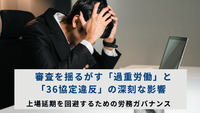
審査を揺るがす「過重労働」と「36協定違反」の深刻な影響:上場延期を回避するための労務ガバナンス
ニュース -
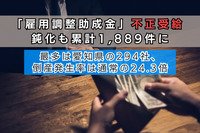
「雇用調整助成金」不正受給 鈍化も累計1,889件に 最多は愛知県の294社、倒産発生率は通常の24.3倍
ニュース