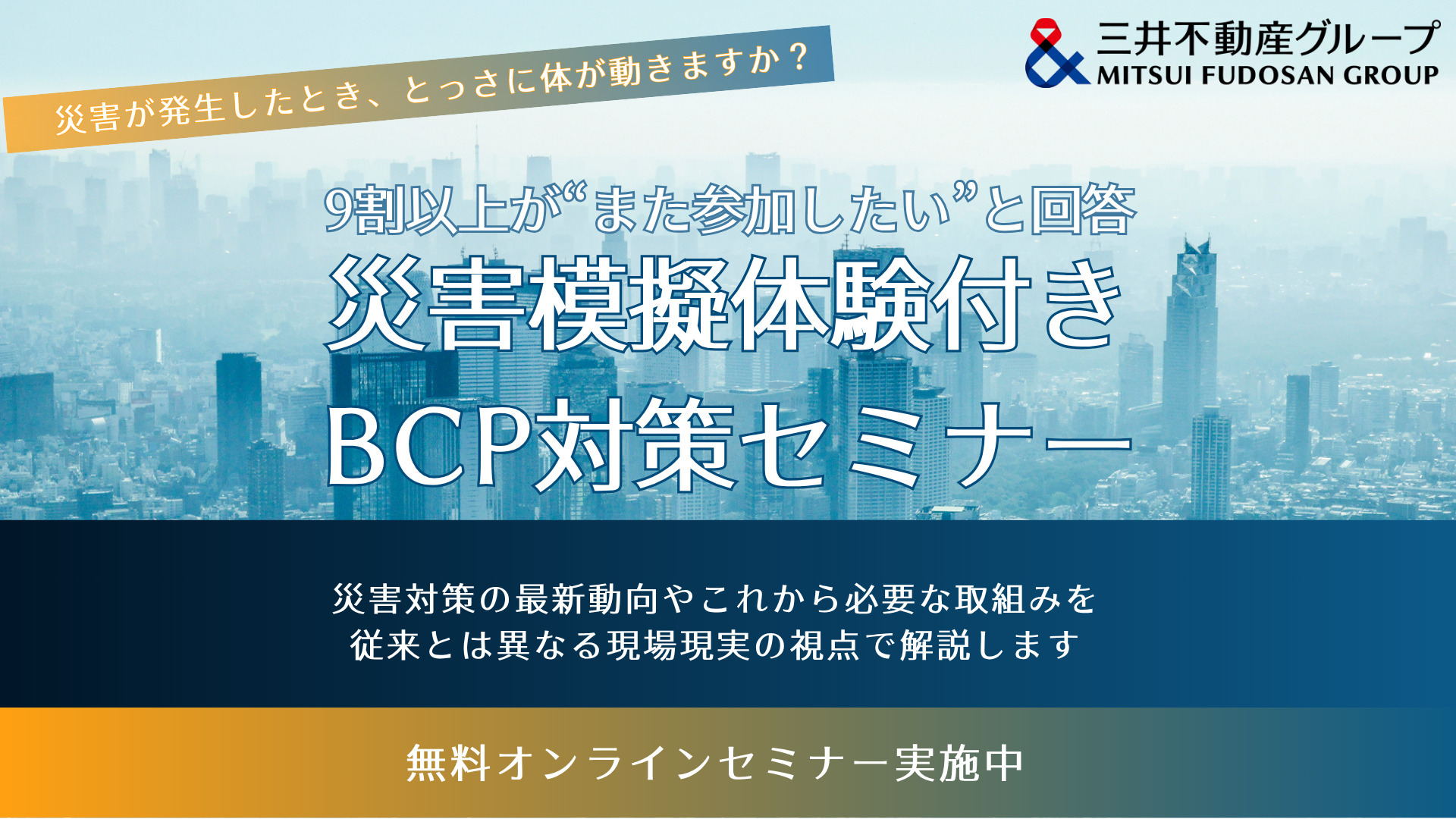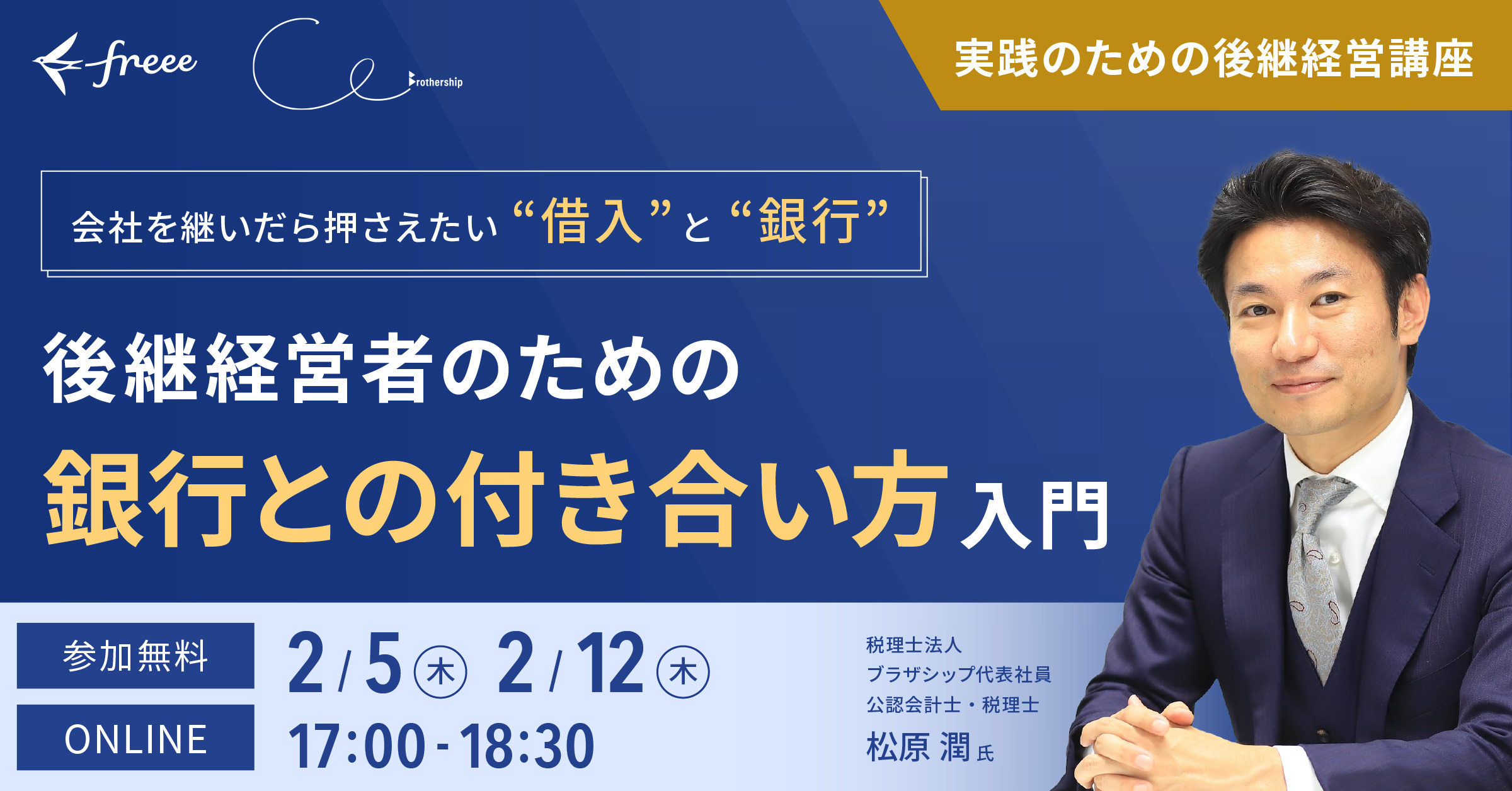公開日 /-create_datetime-/

企業の経理部門に所属する方にとって業務に役立つ資格をご紹介します。資格の中でも級によって難易度や試験内容は全く異なりますので、ご自分のレベルや将来のキャリアプランと照らし合わせ、ぜひ資格取得の際の検討材料にしてください。
1. 日商簿記
会計資格といえば簿記ですが、簿記の中でも日商簿記(主催:日本商工会議所)、全商簿記(主催:全国商業高等学校協会)、全経簿記(主催:全国経理教育協会)があります。
全商簿記は高校生が簿記の習得をするための試験であり、社会人ではほとんど評価されません。全経簿記は全商簿記よりも評価は高いものの、日商簿記の方が圧倒的に知名度は高く、企業の経理部門の募集の際では「日商簿記2級以上」が要求されることが多いです。
よって簿記の勉強を始めるにはまず日商簿記を受けることを前提に学習し、時間と金銭的余裕があれば日商簿記よりも比較的難易度が低い全経簿記を受験してみてもよいでしょう。
また、全経簿記上級と簿記1級の合格者は税理士試験の受験資格を得ることができます。
日商簿記は1級から3級までありますが、経理部門に所属しているのであれば2級を取得しておいた方がよいでしょう。1級は格段に難易度が上がりますので、簿記を極めたい人はぜひ目指してください。
試験内容と特徴
3級:商業簿記
経理の基礎知識や確定申告の青色申告書類程度の作成ができる
2級:商業簿記、工業簿記
財務諸表の作成および内容を理解し、業務上で活用した上で経営内容を把握することができる
1級:商業簿記、工業簿記、会計学、原価計算
商業簿記+工業簿記の応用スキルに加え、会計基準や会社法などの法的知識を理解し、経営分析を行うことができる
2. 税理士
日本の納税制度は複雑なため、所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、事業税、固定資産税といった多様な税金を円滑に計算する「税金のプロフェッショナル」である税理士が必要とされます。
税理士事務所に所属する人だけでなく、一般企業の財務・経理部門で働きながら税理士資格を取得する人も大勢います。
専門的な税務の知識により一般会計だけでなく、月次決算、年次決算処理などの主計業務、管理会計による経営分析や予算実績差異分析、事業画書の作成など会社の経営面に携わり活躍する分野を広げることが可能になります。
受験資格について
税理士資格を取得するには、ほとんどの人が税理士試験を受験することになりますが、ただし受験資格があります。
大学等で法律学または経済学を履修した人、会計士や税理士、公認会計士、弁護士事務所に所属し補助事務に従事した人、銀行などで資金の貸付・運用業務に従事した人など、ある条件の職歴がある人に限られています。
学識や職歴以外では、前述したように「全経簿記上級」または「簿記1級」に合格すれば受験資格を得ることができます。
試験について
税理士試験は、全11科目のうち5科目に合格すれば資格を取得できる科目合格制で、会計科目の2科目は必須科目です。
税理士試験は国家試験の中でも難解な資格であり、仕事と税理士の勉強を両立させるのは大変です。しかし税理士はネームバリューが大きく、一度合格した科目の経歴は一生残るため、合格するまで毎年受験することができます。
まずは会計2科目の合格を目指し、会計の知識を本気で究めたいと考えるのであれば、科目合格で終わらせることなく、3年から5年ほどで税法科目の合格を目指しましょう。
<会計科目>
簿記論
財務諸表論
<税法科目>
所得税法
法人税法
相続税法
消費税法
酒税法
国税徴収法
固定資産税
事業税
住民税
3. ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー(FP)は、職業としては個人の収入・支出、資産・負債、保障などお金に関する情報をもとにライフプランをアドバイスする仕事です。
最近では一般企業、特に金融機関でその知識を活用し、業務の幅を広げるために取得する人も多いです。
金融経済、不動産、住宅ローン、税制、保険、年金、相続など広範囲な知識を習得するため、経営企画業務で財務分析の他に企業の経営目標を理解した上で、業務運営の戦略を立て問題提起を行うことが可能になります。
FPの試験概要
民間資格(NPO法人 日本FP協会 認定):「CFP®資格」(上級資格)・「AFP資格」
国家資格(一般社団法人 金融財政事情研究会 実施):「FP技能士」(1~3級)
難易度はAFPとFP技能士2級、CFPとFP技能士1級がほぼ同等の水準といわれています。
FP技能士の資格は一度合格すれば生涯有効です。
またFP技能士2級に合格すれば、日本FP協会が認定する研修を受講し登録の手続きをするだけでAFPの資格も取得することができます。
社内の評価や転職の際のアピールにするには、まずFP技能士2級を目指すとよいでしょう。
FP技能士2級 試験科目
ライフプランニングと資金計画
リスク管理(保険制度等)
金融資産運用
タックスプランニング
不動産
相続・事業承継
経理は企業が事業活動を数字に表す必要不可欠な業務です。経験が重要であり、ある程度の経理経験があれば会計資格がなくても業務を行うことはできます。しかし業務内容は多岐にわたるため、会計知識を体系的に整理し、将来的に業務範囲を拡大しキャリアアップをしたいと考えるのであれば、上記の資格は必ず役に立つでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
MS Agentに掲載中の求人
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは
おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧
おすすめ資料 -
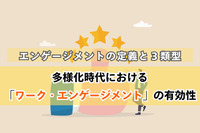
エンゲージメントの定義と3類型:多様化時代における「ワーク・エンゲージメント」の有効性
ニュース -

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念
ニュース -

ヒエラルキー組織における意思決定の高速化と最適化
ニュース -
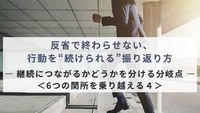
反省で終わらせない、行動を“続けられる”振り返り方 ― 継続につながるかどうかを分ける分岐点 ―<6つの関所を乗り越える4>
ニュース -

なぜ使われない?クラウドストレージ定着を阻む3つの壁
ニュース -
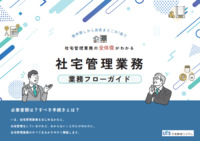
社宅管理業務の全体像がわかる!社宅管理業務フローガイド
おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
おすすめ資料 -

ライセンス契約とは?主な種類・OEM契約との違い・契約書の記載項目までわかりやすく解説
ニュース -

多角化する企業グループで重宝される「子会社管理経験」|経理のキャリア価値とは(前編)
ニュース -

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く
ニュース -

2025年「ゼロゼロ融資」利用後倒産 433件 増減を繰り返しながらも月間30件台を持続
ニュース -
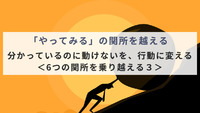
「やってみる」の関所を越える ― 分かっているのに動けないを、行動に変える ―<6つの関所を乗り越える3>
ニュース