公開日 /-create_datetime-/

Q:当社の従業員の過失により、回収できない商品代が出てしまいました。
役員から当該社員へ話があり、この方に未回収の商品代を負担させるということになりました。支払い方法は毎月の給与から天引きです。
本人は役員じきじきに話をされたこともあり、また反省もあり「払う」といっていますが、会社としてこれは大丈夫なのでしょうか?
もしこの従業員が返済前に退職になったら?そもそも会社あるいは役員が訴えられたら?疑問ばかり出てきます。
法的な観点と、会計的な観点、労務的な面などそれぞれの見解をいただけますと幸いです。
A:法的な観点から述べさせていただきます。結論からいいまして、両者ともに違法です。
①回収不可の金額を従業員に請求することについて
この件につきましては、会社に生じた損害を従業員に転嫁するものですから、会社から従業員への損害賠償請求と同視し得る(若しくは損害賠償請求権の行使そのもの)と考えます。厳密な説明は、報償責任に基づく信義則上の問題としてなどになり難解になりますので、簡単にいいます。
つまりは、「従業員を使って普段利益を上げているのに、損害を被ったときだけ、従業員のせいにするな」ということです。
極論として、裁判をしても、従業員が適切な訴訟活動をすればですが、勝てることはほぼないと考えます。
仮に、従業員に故意や重大なミスがあったとしても、全額について認められることはまずないでしょう。
②給料からの天引きについて
労働法上の原則として、「給料全額払いの原則」というのがあります。この意味は読んで字の如くです。
給料から一定額の貸付金などを天引きすることは、原則として、この給料の全額払いの原則に反し、違法となります。
例外としては、調整的相殺の場合などがあるのですが、今回はこの例外については、考慮する必要はないと考えます。
簡単にですが、法的観点からは、以上になります。
労働者の損害賠償責任とその制限について
民事上の原則では、従業員が必要な注意を怠り、労働契約上の義務に違反した場合は、損害賠償責任を負うというのが一般的な考えですが、そこにはいろいろな制約があります。
過去の裁判例を見ても、たとえ労働契約上の義務違反が認められた場合であっても、故意や重大な過失があるとき以外は、損害賠償責任は認められていません。また、損害賠償の請求額もかなり制限されているのが実状です。
というのも、事業を進めていくうえで、ある程度のリスクは避けることはできません。
会社は、従業員を雇うことで利益を上げているわけですから、業務上から生じるリスクについても、会社が負担すべきという考え方が、根底にあるようです。
従業員が損害賠償義務を負うケース
では、従業員が損害賠償を負うことがあるのは、どのようなケースでしょうか。
まず、従業員の加害行為によって、使用者に直接の損害を与えた場合、民法上の損害賠償責任を負うことがあります。
たとえば商品や機器、機材の損傷や紛失などによる損害などですが、従業員の行為が労働契約上の債務不履行(民法415条)、または不法行為(民法709条)に該当する場合です。
また、従業員のミスによる交通事故や、取引先をはじめ第三者への損害が発生した場合、使用者は被害を受けた第三者に対して損害賠償責任を負う必要がありますが、民法715条3項に、その負担を従業員に求めることができるとあります。
しかし、その場合、危険責任・報償責任の原則や、使用者と従業員の経済的格差への配慮、従業員の地位・職責・労働条件、加害行為の予防や損失の分散(保険の利用など)について、使用者側の対応判断材料となり、従業員の賠償責任は制限されています。
また、花田亨先生の回答にもあるように、給料から天引きすることは、法律違反となります。労働基準法24条1項には、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」とあります。
従業員のミスで会社に損失が生じた場合、損害賠償請求をすることは可能ですが、認められるケースは少なく、たとえ認められても請求額には制限があります。また、いろいろな法律がからんでくるため、専門家とよく相談して対応する必要があります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
おすすめ資料 -

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】
ニュース -

「アサーティブコミュニケーション」の重要性と実践に向けた具体的な手法を学ぶ
ニュース -

労働基準法の知られざる機能ーマズローの【欲求】とジラールの【欲望】から読み解く
ニュース -

朱に交われば赤くなる!?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第1話】
ニュース -

面接日程調整の“理想”は「当日~翌日」も、実態は「1~5日」…採用現場のスピード対応に潜む課題とは
ニュース -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?
おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

採用だけの人事経験は転職で不利?評価されるスキルとキャリアの広げ方を徹底解説(前編)
ニュース -
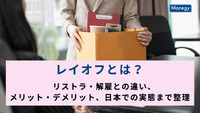
レイオフとは?リストラ・解雇との違い、メリット・デメリット、日本での実態まで整理
ニュース -
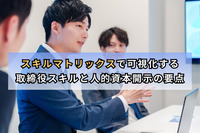
スキルマトリックスで可視化する取締役スキルと人的資本開示の要点
ニュース -

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着
ニュース -

ケアの倫理から労働の倫理を問い直す②~法の精神が要求する新たな組織原理~
ニュース



































