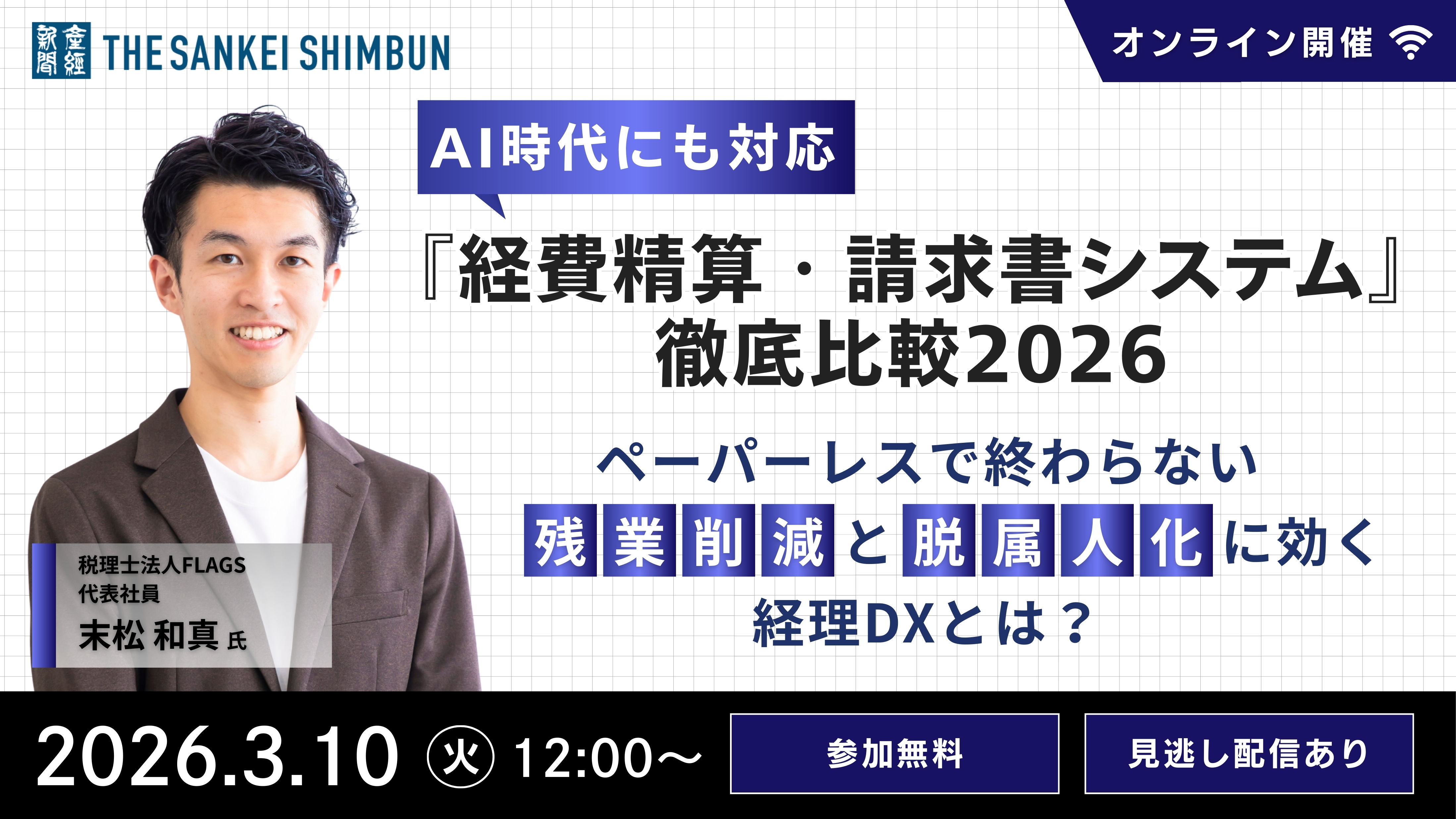公開日 /-create_datetime-/
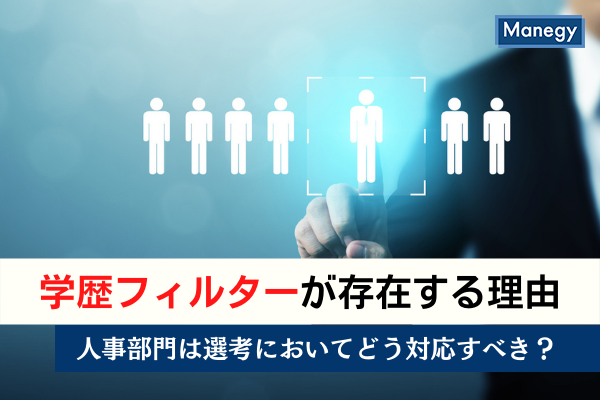
最近、インターネット上で「学歴フィルター」が物議を醸しています。
事の発端は、ある就職支援サービスの運営事務局が、「大東亜以下」と題したメールを就職活動中の学生に誤送信した問題です。
応募者を学歴フィルターで振り分けているのではないか、という意見が広がりました。就職支援サービス側は、あくまで学生を区分するためのもので、所属大学を採用の指標として使用していないことを訴えています。
今回考えてみたいのは、出身大学が選考や合否に影響する問題を、人事部門または人事担当者はどのように考えるべきかというテーマです。
ここでは、学歴フィルターが存在する理由を解説しながら、人事担当者として取るべき対応について探っていきます。
学歴フィルターとは
学歴フィルターとは、企業が新卒採用を実施する際、大学名などの学歴を基準に学生を選別することを指します。偏差値が一定以上の基準に満たない応募者を、採用選考から除外する目的で実施されます。
大学のランクは一般に、旧帝国大学をトップに以下のように階層化されています。
- 旧帝国大学(東京大学、京都大学、大阪大学など)
- 超難関私立・国立大学(慶応義塾大学、早稲田大学、上智大学、東京理科大学など)
- 難関私立・国公立大学(学習院大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学など)
- 準難関私立・国公立大学(日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学、京都産業大学、近畿大学、甲南大学、龍谷大学など)
- 中堅私立・国公立大学(大東文化大学、東海大学、亜細亜大学、帝京大学、国士舘大学など)
冒頭で述べた「大東亜以下」というのは、大東文化大学、東海大学、亜細亜大学のことです。新卒採用活動の指標として、このような区分を利用することが学歴フィルターです。
先ほどの就職支援サービスは、出身大学の偏差値が採用の合否に影響していることを否定しましたが、実際の就職活動ではどのような状況なのでしょうか。
ここで日本労働組合総連合会の『就職差別に関する調査2019』のアンケート結果を紹介します。
全回答者(1,000 名)に、就職活動をしていて学歴フィルターを感じたことがあるか聞いたところ、以下の回答が明らかになりました。
【全体】
「ある」と回答した人の割合: 40.2%
【男女別】
男性の割合:44.4%、
女性の割合:36.0%
【最終学歴別】
高等学校:25.2%
専門学校・短期大学:18.9%
四年制大学・大学院:46.4%
男女別では、女性よりも男性のほうが学歴フィルターを実感した経験のある人が多いようです。また最終学歴が大学・大学院の人は、学校名が採用に影響していると感じた人が多いことも明らかになりました。
学歴フィルターが存在する理由
なぜ、学歴フィルターは存在するのでしょうか。
結論からいえば、学歴が高いということは、優秀な人材である確率が高いと考える企業が存在するからです。
社会人になると、さまざまな能力が求められます。たとえば、論理的思考力や目標達成能力、コミュニケーション能力、業務遂行力などです。
しかし、応募者にどんな能力があるのかを、採用前から見極めることは簡単ではありません。そこで、わかりやすい指標として出身大学のランクが役立ちます。
偏差値が高い大学に合格している学生は、高い目標を設定して、実現するための努力を継続してできる、もしくは効率的に学習できる力があると判断できるからです。
受験勉強で発揮した能力が、企業においても発揮されるであろうという仮定で、学歴が重視されています。
実際、高学歴の学生が、優秀なビジネスパーソンになるケースは珍しくありません。企業に利益をもたらし、さらには経営的な手腕を発揮する人材になることも期待できます。
東京商工リサーチによる「全国社長の出身大学」調査では、東京大学や慶応義塾大学、早稲田大学など、トップレベルの大学出身者が経営者になっていることが明らかになっています。
このような背景から、優秀な人材となる候補者を採用するために、偏差値の高い大学の学生を獲得する手段として、学歴フィルターが有効だと考えられています。
しかし、高学歴だからといって必ずしも期待通りの活躍をしてもらえるとは限りません。
また、出身大学だけでは、人柄や価値観などの人間的な素質や、企業との適性を見抜くことは極めて難しいでしょう。
人事は学歴フィルターにどう対応すべきか?
人事部門または人事担当者は、学歴フィルターに対してどのように対応するのが正解でしょうか。
まずは、新卒採用のスタンスと目的をはっきりさせることが重要です。公平な評価をして、企業に合った人材を採用するためには、必要な情報を複合的に収集しなければなりません。
具体的にはエントリーシート、SPIなどの採用テスト、適性検査の結果が挙げられます。学歴も重要な情報の1つで、否定されるわけではないでしょう。
学歴フィルターの問題は、出身大学の偏差値だけで、人材の能力や適性を判断して選別することです。
人材マネジメントの1つに、論理的誤差という用語があります。これは論理的に分析するあまり、関連性がない事実でも似たような事柄を紐づけて考えてしまい、誤った推論をしてしまうことです。高学歴を理由に優秀な人材になるだろうと過度に期待することも、論理的誤差の一種だといえます。
難関大学に合格するための努力や工夫をできることは、評価すべき事実の1つです。ほかの情報とあわせて適切に評価しながら、学歴に依拠しない選考を進めていかなければなりません。
まとめ
「応募者が多すぎて選考が難しい」と悩んだり、「なるべく優秀な人材を確保したい」と考えたりすることは、人事担当者にとって自然なことです。しかし、そのために学歴フィルターを通して新卒採用をするのは適切ではありません。
なかには、能力があったとしても「家庭の経済的な事情で希望する大学に進学できなかった」「偏差値は少し低くなるが、どうしても学びたい学科があった」という応募者もいます。学歴にとらわれることで、優秀な人材確保の可能性を下げてしまいかねないでしょう。
就職活動中の学生が企業のブランド力や知名度だけで企業に応募をしても、適切な判断をすることは困難です。採用側も同じく、学歴に依存せず、複合的な情報から正しい人材の選別ができる力を鍛えなければなりません。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

又は・若しくはの違いとは?意味・使い分けと契約書での注意点を例文で解説
ニュース -

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識
ニュース -

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下
ニュース -

介護休業制度とは?―2025年法改正と制定経緯から考える、仕事と介護の両立支援の本質―
ニュース -

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!
ニュース -
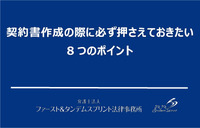
契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -
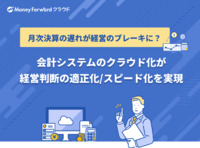
会計システムのクラウド化が経営判断の適正化・スピード化を実現
おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -
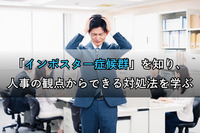
「インポスター症候群」を知り、人事の観点からできる対処法を学ぶ
ニュース -

過重労働の判断基準と健康リスクを徹底解説 ─ 厚労省ガイドラインで学ぶ企業の防止策
ニュース -

6割の総務が福利厚生と従業員ニーズのギャップを実感するも、3割超が見直し未実施
ニュース -
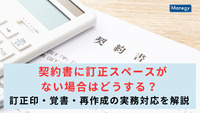
契約書に訂正スペースがない場合はどうする?訂正印・覚書・再作成の実務対応を解説
ニュース -

介護短時間勤務制度とは?―制度の概要と制度設計に必要な視点を考える―
ニュース