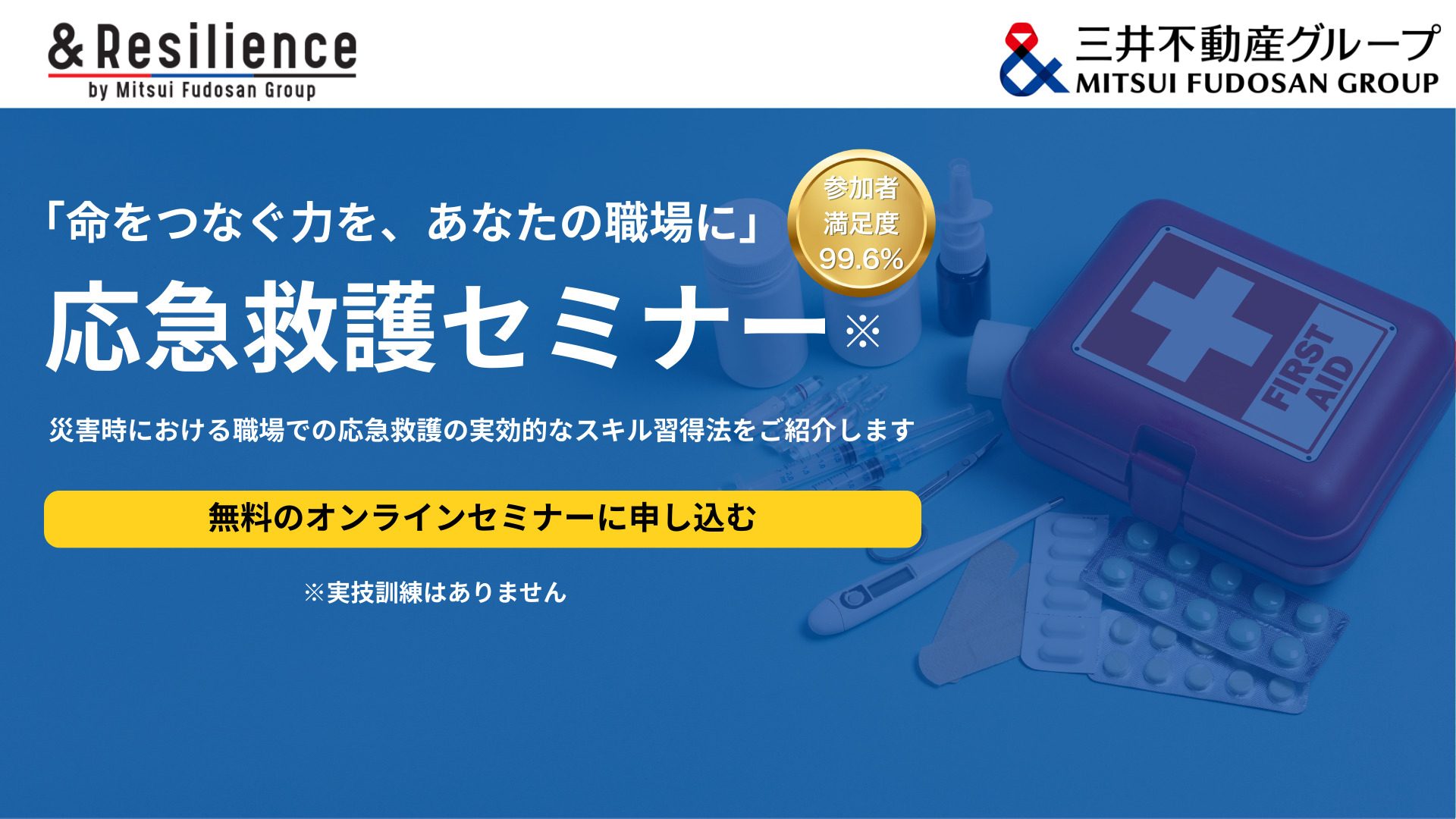公開日 /-create_datetime-/
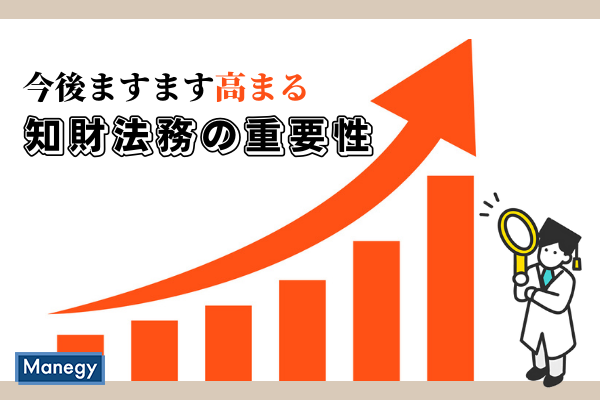
日本国内で1年間に出願される特許の件数をご存じでしょうか。大まかな数字でいうと、毎年約30万件の特許が出願されています。この膨大な数の特許が、日常生活やビジネス分野で利用されているのです。
特許・意匠とは企業にとって非常に大きな価値をもつもので、業界での競争力にも直結し、企業経営を左右するほど重大な資産です。今回の記事では一般にはなじみの薄い、知的財産に関するテーマをとり上げます。
日本国内の特許・意匠登録状況
特許・意匠という無形の資産は、日本国内のみならず海外企業との競争においても、重要な戦略的位置づけにあります。これらをどれだけ多く生み出せるかは、企業の将来を決定するほどの影響力を持ち、日々世界中の企業がしのぎを削っています。
特許庁が2021年に公開した資料によれば、その前年1年間に最も多く特許登録をした企業は、電気機器の上場大手で3,680件でした。特許を多く登録している企業ランキングには、電気機器、輸送用機器などの名だたるメーカーが名を連ねています。
一方で意匠登録をした企業は、同じく電気機器の大手で362件。やはり意匠登録が多い企業にも、電気機器、輸送用機器の大手メーカーのほか、化学や金属関連メーカーなどが含まれています。いずれも日本を代表する企業であり、いかに特許・意匠がビジネス戦略に重要であるのかがわかります。
知財法務とは?
企業にとって極めて重要な特許や意匠は、一般的に「知的財産」と総称されます。それら知的財産を専門的な知識によって保護・管理することを「知財法務」と呼びます。知財法務に関わるのは、行政書士や知的財産管理技能検定などの有資格者で、非常に高度な専門的知識が求められる法律のプロです。
実際の業務では、出願する知的財産を選び出す出願戦略や、各種資料などを作成する出願準備、さらに出願手続きそのものから権利の管理など、知的財産に関わるあらゆる仕事を担当します。そのため知的財産を扱う企業では、必ず社内に担当責任者を置くか、専門の法律事務所に業務を委託することになります。
知財法務の中核「知的財産」とは?
ある企業が独創的に開発したモノが、競合相手にとっても価値がある場合、開発した企業が権利を主張しなければ、ほかの企業が自由にそのモノを使ってしまいます。そこで特許や意匠などは、知的財産として一定の期間使用する権利が制限されます。
もちろん独占的に使用できるのは開発した企業であり、ほかの企業でどうしても必要になった場合には、知的財産に対する使用料を支払わなければなりません。こうして厳重に扱われる知的財産には、主に以下のようなものがあります。
・特許権(発明品などの保護)
・意匠権(形状やデザインの独創性を保護)
・実用新案権(形状や構造の独創性を保護)
・商標権(文字やマークの独創性を保護)
・著作権
・商号
・商品表示/商品形態
これらの中で、特許権・意匠権・実用新案権・商標権の4つは「産業財産権」と総称され、とくにビジネスの分野では重要な戦略的価値を生み出します。産業財産権は特許庁が管理し、申請した企業(個人)の権利を保護して、無断流用や模倣を防いでいるのです。ただし決められた期間がすぎると、一般に公開され誰でも使用できるようになります。
経営戦略に活用される知財法務
現代ビジネスでは情報のデータ化が進み、無形の資産である知的財産も急激に増加しています。今後もインターネットに関わる技術や、AI、メタバースなどが発展することから、知的財産がさらに増加することは間違いないでしょう。
企業にとっては知的財産への投資が、これまでよりも経営戦略的に重要度を増すかもしれません。とくに大きな意味でのソフトウェア全般を扱う場合、知的財産を創出することは、競合相手を制してビジネスを成功に導くための強力な武器になるはずです。つまり、知的財産を生み出すことが、企業の経営を左右するわけです。
ほかにも世界市場でビジネスを行う場合、知的財産を管理することは日本国内以上に重要になります。欧米のように法律による規制が極めて強い地域から、中国のように知的財産権が未熟な地域まで、さまざまなケースに合わせて知的財産を保護する必要が生じるからです。
また別な方面に目を向けると、知的財産権は国内でも多くの法律と関わっており、管理方法を誤ると独占禁止法に抵触する恐れもあります。知的財産権の行使は、こうした法律に関する知識をもとに、経営の一環として計画的に行われるべきものなのです。今後はますます、企業内における知財法務の重要性が高まることになるでしょう。
まとめ
企業にとっての資産が、現実的な物品からデジタル化された情報にまで拡張される中、知的財産という概念もさらに広がりを見せています。しかも企業にとって知的財産は、経営戦略上で強力な武器にもなるのです。
今後は各分野の企業にとって、知的財産権の管理が今まで以上に重要になることは間違いありません。それは知財法務の重要度が高まることにもつながります。経営者としては、知財法務に関わる人材の育成が、将来的なビジネスの成功に欠かせないテーマになるでしょう。
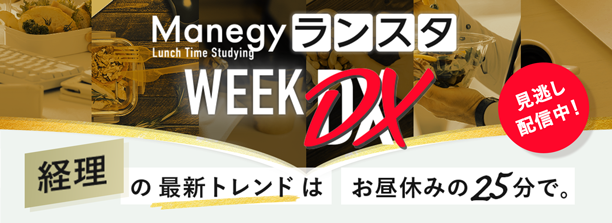
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
新着動画
関連情報
-

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -
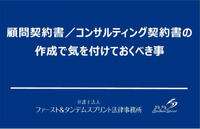
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -
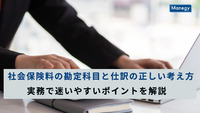
社会保険料の勘定科目と仕訳の正しい考え方|実務で迷いやすいポイントを解説
ニュース -

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に
ニュース -

決算整理仕訳とは?仕訳例でわかる基本と実務の注意点
ニュース -

消費税の特定課税仕入れとは?仕入税額控除の際の注意点
ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第5回(最終回) ソフトウェアと循環取引
ニュース -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -

フリーアドレスの成功事例 ご紹介
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割
おすすめ資料 -

2025年上場企業の「不適切会計」開示43社・49件 11年ぶり社数・件数が50社・件を下回る、粉飾は7件
ニュース -

リバースチャージ方式の会計処理とは?仕訳例や消費税申告の考え方を解説
ニュース -

未払金と未払費用の違いとは?仕訳例を使い経理担当者にわかりやすく解説
ニュース -

消費税仕入税額控除の計算方法2つと、個別対応方式と一括比例配分方式、変更のタイミングを解説
ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第4回 ソフトウェアの導入費用の取扱い
ニュース