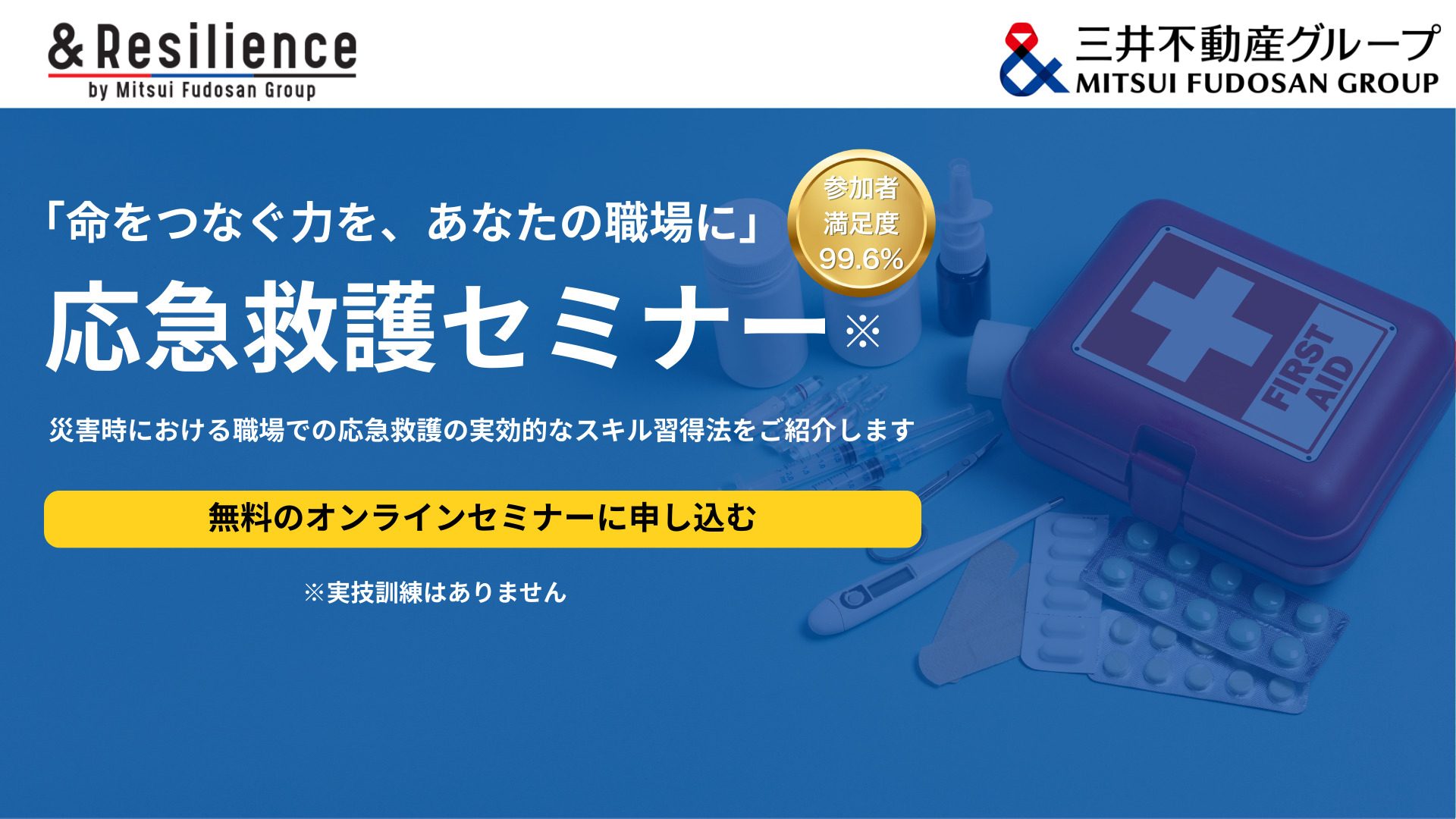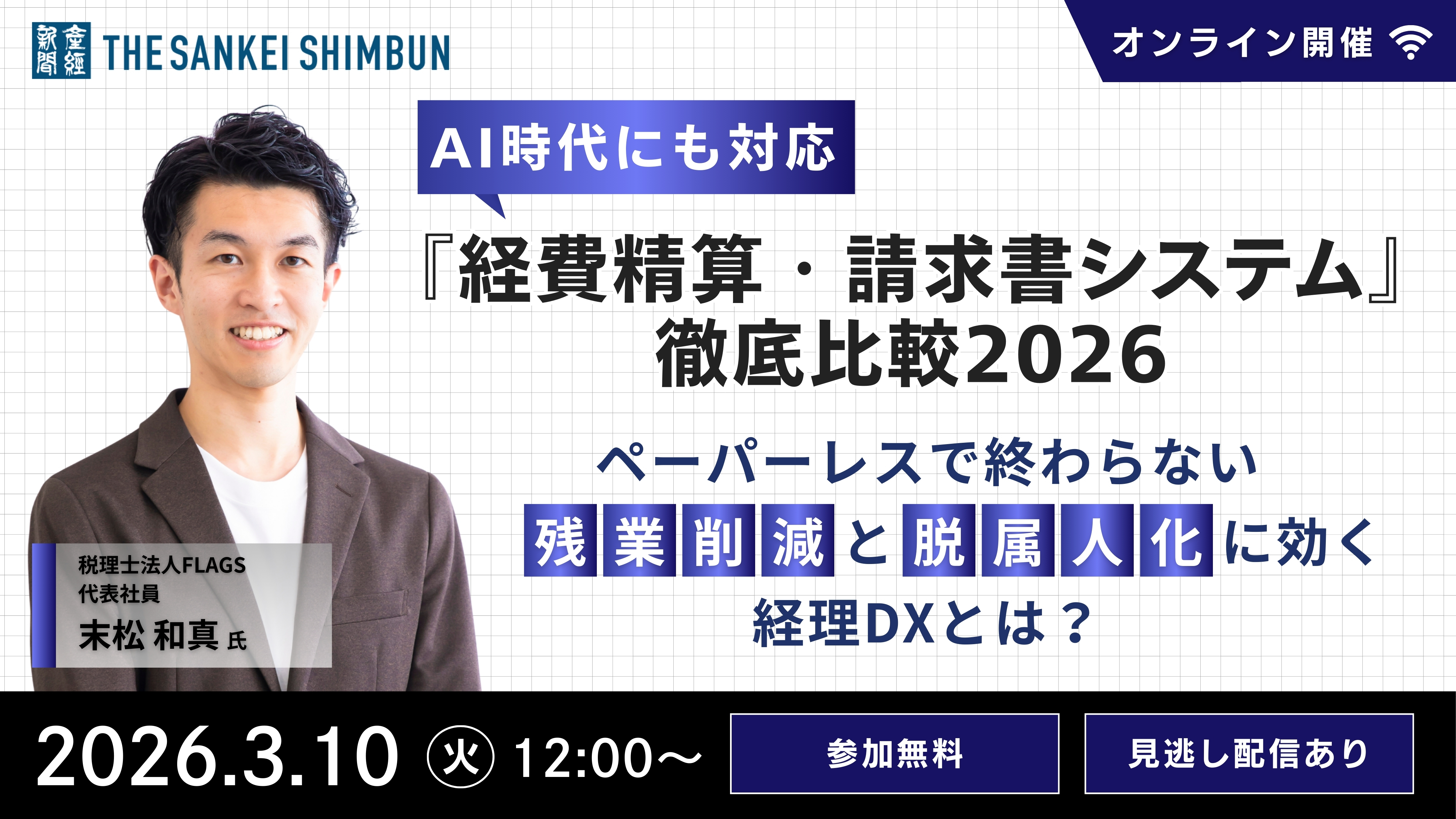公開日 /-create_datetime-/
企業の借り入れは無形資産も担保になる?事業成長担保について解説
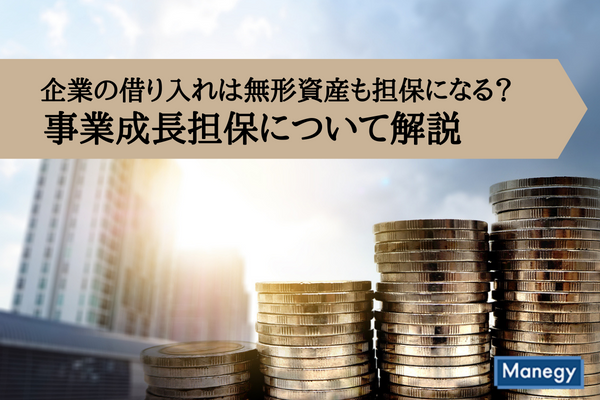
企業活動を活性化させるために欠かせないのが資金調達です。これまで、企業の借り入れ時には、土地や建物のような不動産を担保として位置づけていました。
しかし政府は、有形資産だけでなく、無形資産も担保にできるよう新法の制定を目指しています。これによって、中小企業やスタートアップ企業にとって、資金を調達しやすくなる環境が整うでしょう。今回は、企業の借り入れについて解説します。
現行の民法における担保権
現行の民法では、企業の資金調達をどのように定めているのでしょうか。ここで重要になってくるキーワードが「担保権」と「有形資産」です。
担保権は、借り入れをしていた債務者が返済できなくなった際に、対象の資産を換金することによって弁済に充てられる権利です。融資を受ける際は、何かしらのモノを「担保」にします。
融資をする銀行にとっても、債務者がちゃんと返済してくれないといったリスクがあります。しかし事前に「担保」を定めておくことによって、もしものことがあっても債権を回収できるのです。
企業が銀行から融資を受ける際の担保として有効なのは、土地や設備、機械のような有形資産になります。かつての日本は製造業が中心で、工場の設備を担保として融資を受けている企業が多くありました。そのため現在でも、有形資産は担保になる重要な資産となります。
有形資産と対になるのが、形を持たない資産である「無形資産」です。たとえば企業の技術は、確かに重要な資産ではありますが、形を持っている「土地」「設備」のような有形資産とは性質が異なります。企業の特許やブランドのようなものも同様です。
そしてこれらの無形資産は、現行の民法では、融資を受ける際の担保になりません。しかし政府は、これらの無形資産も担保にできるよう、法整備を進めています。
政府は何をしようとしているのか
政府が具体的にやろうとしているのは、民法の特別法として、有形資産と無形資産を組み合わせた事業資産全体を「事業成長担保」とすることです。これによって従来の不動産だけでなく、企業が持っている技術やブランドも担保にできます。
最近ではDX(デジタルトランスフォーメーション)がよく知られているように、情報技術を用いた次世代型の企業が増えています。しかしそれらの企業は、必ずしも充実した設備をそろえているわけではないでしょう。有形資産が乏しいものの、豊富な無形資産を有している企業にとって、「事業成長担保」の存在はとても重要になります。
特にスタートアップの企業は、赤字が続いているケースも多く、すみやかに多くの資金を調達する必要があります。スタートアップ企業が優れた無形資産を有していれば、それが「事業成長担保」として評価され、借り入れがしやすくなるでしょう。
事業成長担保を導入するメリット
事業成長担保を導入するメリットはさまざまです。何度も触れているように、不動産を持っていない企業であっても資金調達をしやすくなるのは大きなメリットでしょう。単純に資金調達の手段が多様化するため、より良い企業活動につながります。
従来のルールを考えるのであれば、不動産を持っている企業が有利になります。一方、どれだけ優れた技術を持っていたとしても、有形資産を持っていない企業であれば資金調達面で不利です。こうした有利・不利の問題をフラットにできるのは、事業成長担保の魅力といえるでしょう。
また事業成長担保は、融資をする側である銀行にもメリットがあります。これまでの融資の形は、銀行が企業に対して融資し、一定の金額を回収する味気ないものでした。当然不良債権のような問題もあるため、銀行側としても融資の判断は慎重になります。
しかし事業成長担保を導入することで、銀行は有形資産と無形資産を合わせて、企業を総合的に評価できます。融資先の企業と、「事業の継続や成長」といった目標を共有できるのも大きいでしょう。
たとえば、ある程度成長している中堅企業が、調子の良い事業(成長事業)と調子の悪い事業(不振事業)の両方を抱えていたとします。これまでの価値基準に照らして考えると、追加で融資をするかどうかは微妙になるでしょう。
しかし事業成長担保が浸透していれば、こうしたケースであっても、追加で融資できます。もちろん企業が不振事業を抱えているのは事実なので、事業の撤退に関するモニタリングなどを徹底しなければなりません。創業時や成長時、衰退時に至るまで、企業のライフサイクルに柔軟に対応できるようになるでしょう。
まとめ
事業成長担保が浸透すれば、従来の有形資産だけでなく、企業ブランドなどの無形資産も担保となります。不動産を持っていない企業であっても、資金調達がしやすくなる環境になるため、より事業の多様性が見込まれるでしょう。
事業成長担保を導入するためには、事前に環境をしっかりと整える必要があります。特に従来に比べて手続きが煩雑になることが想定されるため、十分なサポート体制を敷かなければなりません。また担保権の悪用・濫用も考えられるため、事前に防止するためのシステムも必要になるでしょう。
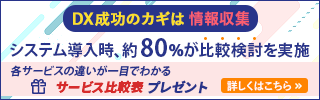
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集
おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~
おすすめ資料 -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -

不登校やきょうだい児も対象に 住友林業が最大3年の「ファミリーケア休業」新設、離職防止へ
ニュース -
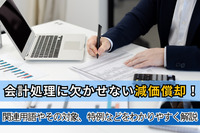
会計処理に欠かせない減価償却!関連用語やその対象、特例などをわかりやすく解説
ニュース -

契約審査とは?担当者が迷わない流れとチェックポイント
ニュース -

新入社員の育成・活躍を促進するオンボーディングとは?
ニュース -
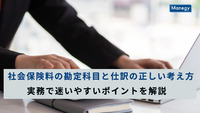
社会保険料の勘定科目と仕訳の正しい考え方|実務で迷いやすいポイントを解説
ニュース -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -

アルムナイ制度導入ケーススタディ+チェックリスト36項目
おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

法務FAQ構築の手順とポイントを解説|AIを活用した効率的な運用・更新手法も紹介
ニュース -

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に
ニュース -

AI時代のスキルと人材育成 ~AIが代替できない「深化」の正体とは?~
ニュース -

決算整理仕訳とは?仕訳例でわかる基本と実務の注意点
ニュース -
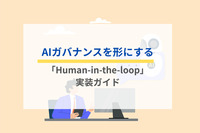
AIガバナンスを形にする「Human-in-the-loop」実装ガイド
ニュース