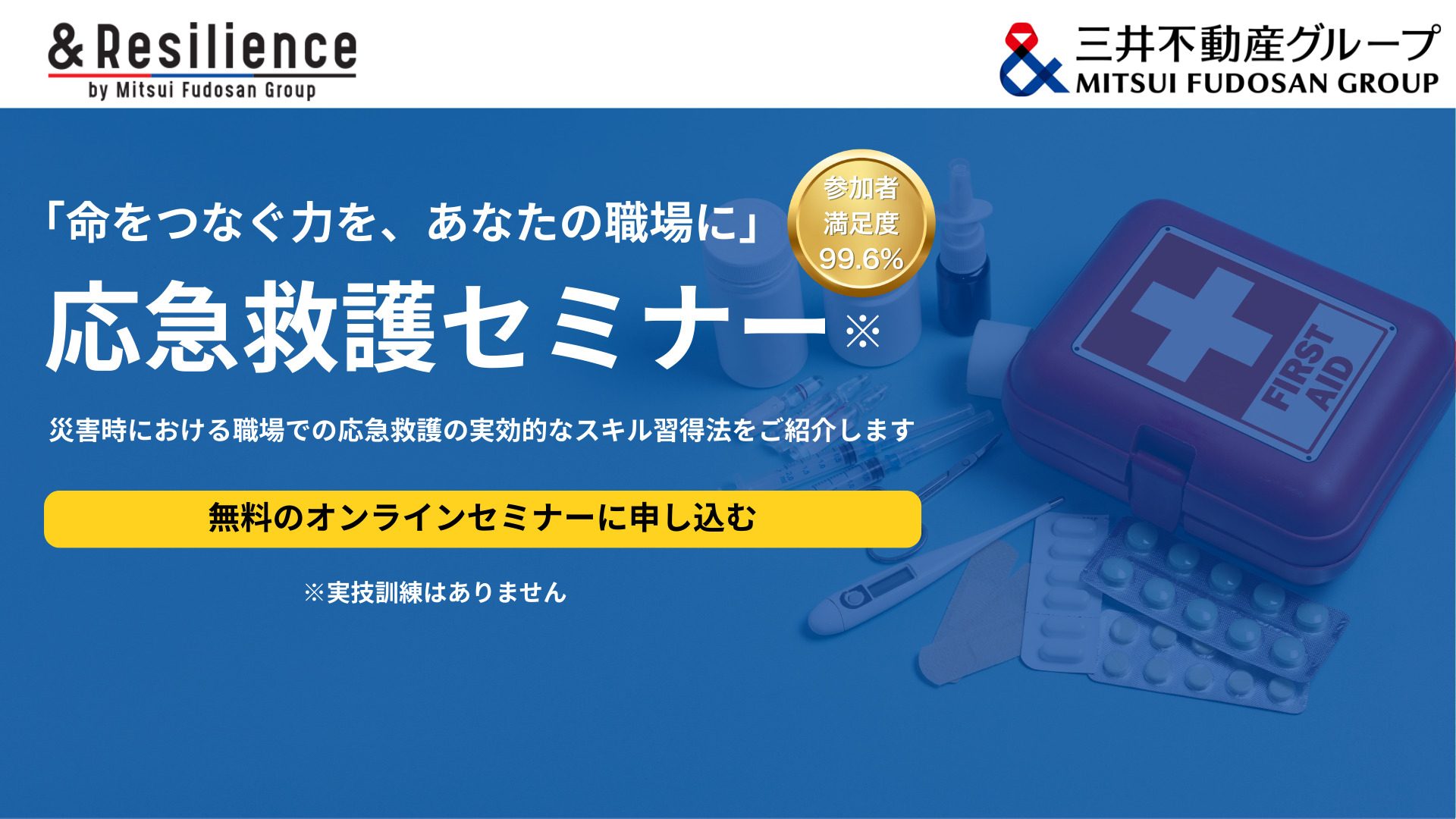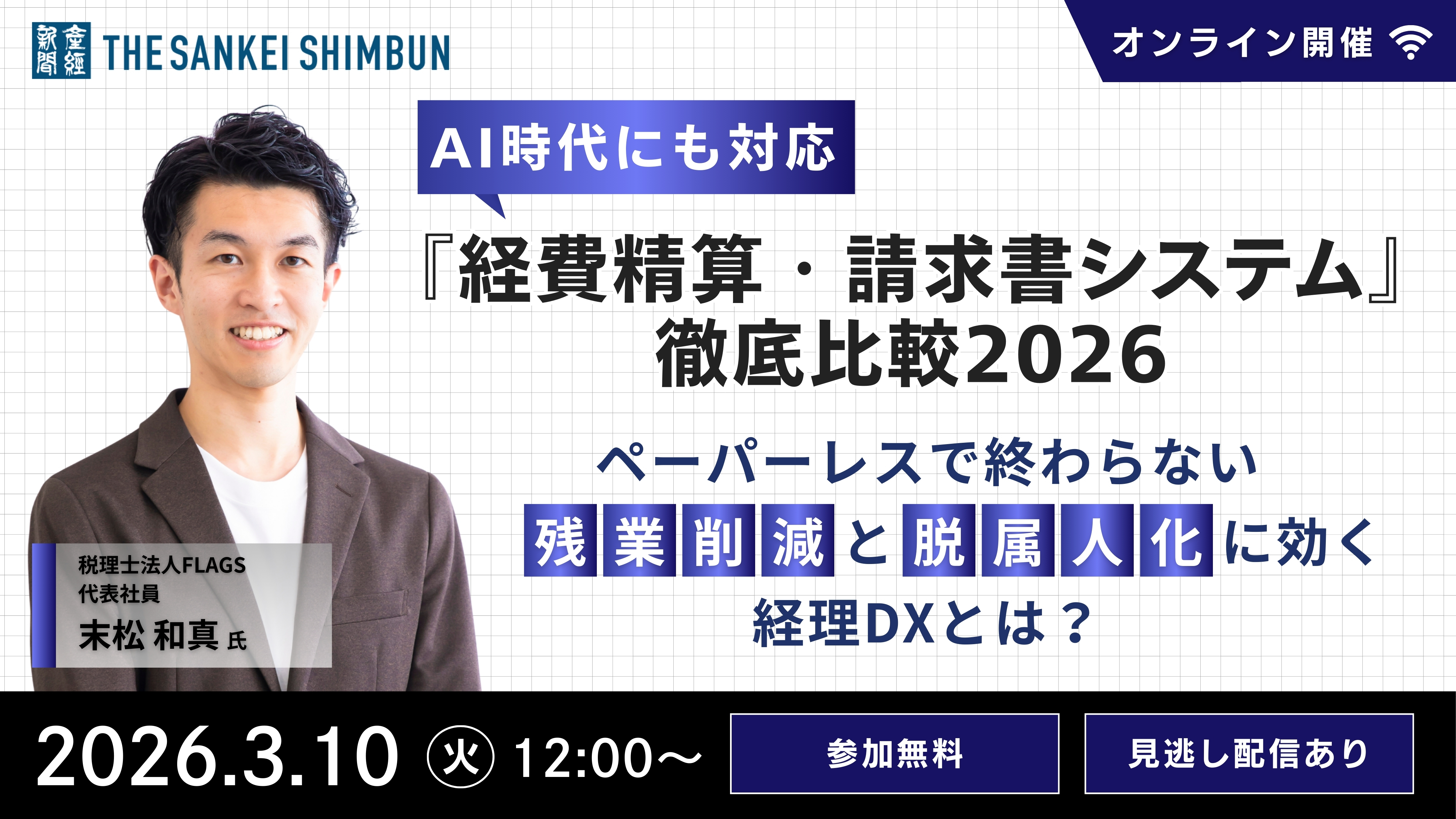公開日 /-create_datetime-/
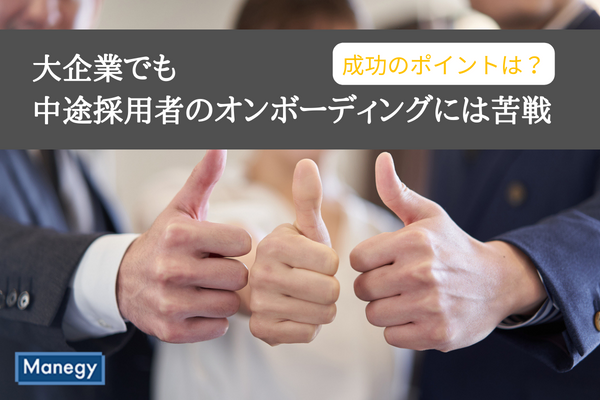
かつて日本式経営の三種の神器の一つとも呼ばれた終身雇用制度は、今や一般的な雇用形態とはいえません。人材の流動性が高まる中、企業側は中途採用の強化を進め、その戦力化・定着をスムーズに行えるようオンボーディングに力を入れています。
しかし実際のところ、経営資源が豊富な大企業であっても、オンボーディングには苦戦しているケースが多いです。
そこで今回は、そもそもオンボーディングとは何か、なぜオンボーディングが難しいのか、オンボーディングをうまく行うポイントは何か、について詳しく解説します。
オンボーディングとは?
オンボーディングとは、新規に採用した人材が職場に慣れ、戦力として活躍できるように、組織への順応を促進させる取り組みのことです。「飛行機や船に乗ること」という意味をもつ「On-boarding」を語源としています。
クルーまたは乗客として船や飛行機に乗る場合、すでに搭乗・乗船している人から適切なサポート・助言を受けられれば、特殊な環境に早く慣れることができます。ビジネスの分野でも、新人として企業組織に入る場合、仕事・職場に早く慣れるには上司・先輩・同僚・部下などによるサポートが有効です。
もしそのようなサポートをまったく受けられなかったら、新人は仕事をうまく覚えられず、職場にもなじめず、早々に転職を決断するでしょう。企業としては、新規雇用者に効果的なオンボーディングを行い、その戦力化・定着を図る必要があるわけです。
オンボーディングのメリット
企業側からすれば、オンボーディングを行うことにより、新たに入社した人材が早期に活躍できるようになるので、業績アップにつなげることができます。
また、職場に早く慣れてもらうことで、早期離職を防ぐことも可能です。オンボーディングによって離職率を下げられれば、採用にかけるコストの抑制にもつながります。
一方、従業員側にとってもメリットは大きいです。オンボーディングを通して社内のルールや他の社員とのコミュニケーションを促進でき、働きやすい環境を確保できます。さらに、早い段階から戦力として活躍できるので、仕事へのモチベーションを高め、意欲をもって日々の業務に取り組めるようになります。
オンボーディングを難しくする要因とは
しかし実際のビジネスの現場では、オンボーディングに苦戦している企業が多いです。
ユームテクノロジージャパン株式会社が行った大企業を対象としたアンケート調査では、「中途採用を強化している」との回答が約7割に上っている一方、「オンボーディングに苦労した経験がある」との回答は6割以上に上っていました。
調査概要:大企業の中途採用に関する実態調査
調査方法:IDEATECHが提供するリサーチPR「リサピー®️」の企画によるインターネット調査
調査期間:2022年7月5日〜同年7月6日
有効回答:大企業(従業員数1,000名以上)の人事105名
※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。
この調査結果からは、中途採用を進めている一方で、そのオンボーディングは必ずしもうまくいっていないという大企業の実情が読み取れます。また、同調査ではオンボーディングに苦労した点についてもアンケートを採っていて、社風の違い、コミュニケーションスタイルの違い、職場への不適応、業務の行い方の違い、などの回答が多くなっていました。
中途採用者のオンボーディングにおいては、採用者が前職で培った仕事のスタイルを維持しようとし、それが自社の方法と合わないために問題が起こりやすいと考えられます。
オンボーディングを成功させるポイント
大企業でも難しいことが多い効果的なオンボーディングの実施です。成功させるためのポイントの一つは、人事部門と配属先の部門との連携です。
一定以上の規模をもつ企業の場合、採用計画や育成のプロセスは人事部門が計画・運営し、OJTや上司による個別面談などは配属先の部門が担うのが通例です。
このとき両部門が十分に連携していないと、人事部門は現場での教育・対応がどのように行われているのかを把握できず、配属先の部門は人事部門の採用意図・育成プロセスの意図が理解できない状況に陥ります。このような状況では、効果的なオンボーディングは行えないでしょう。
実際、オンボーディングを成功させている企業の多くは、採用→職場への溶け込み→戦力化の過程のすべてにおいて、人事部門と配属先部門が連携・情報共有を行いながら取り組んでいます。
また、中途採用者のメンターをどう選ぶかも重要です。メンターとは「助言者」や「指導者」という意味を持ち、新人が早く職場になじめるように、特定の先輩・同僚がサポートすることをいいます。それなりの規模の企業であれば、新人に対するメンター制度を導入していることも多いですが、効果的なオンボーディングを行うには、メンター選びを慎重に行うことが大事です。
中途採用者がもつ前職の実績、仕事のスタイル、個性・性格などを十分に把握した上で、本人とマッチしそうな社員をメンターとして選べば、オンボーディングは成功しやすいです。一方、「たまたま手が空いている」などの理由で場当たり的にメンターを選ぶと、適切なオンボーディングを行えなくなる可能性があります。
まとめ
中途採用者の迅速な戦力化と職場への定着化を促進するには、オンボーディングを効果的に行うことが必要です。しかし、オンボーディングを適切に行うのは容易ではなく、大企業の6割以上が苦労しているとの調査結果もあります。
オンボーディングを成功させるためのポイントとしては、中途採用者の教育に関して人事部門と配属先の部門が密接な協力体制を構築すること、メンター選びを慎重に行うことなどを挙げることができます。
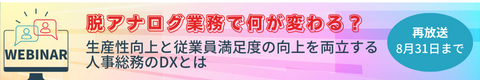
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
おすすめ資料 -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
おすすめ資料 -

労使および専門家の計515人に聞く 2026年賃上げの見通し ~定昇込みで4.69%と予測、25年実績を下回るも高水準を維持~
ニュース -

2026年1月の「物価高」倒産 76件 食料品の価格上昇で食品関連が増勢
ニュース -

労基法大改正と「事業」概念の再考察② ~場所的観念から組織的観念へのシフト~
ニュース -

【図解フローチャート付】出張ガソリン代の勘定科目は?旅費交通費と車両費の違いを仕訳例で徹底解説
ニュース -
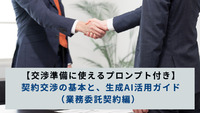
【交渉準備に使えるプロンプト付き】契約交渉の基本と、生成AI活用ガイド(業務委託契約編)
ニュース -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?
おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -
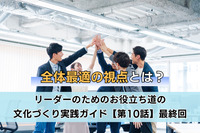
全体最適の視点とは?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第10話】最終回
ニュース -

不登校やきょうだい児も対象に 住友林業が最大3年の「ファミリーケア休業」新設、離職防止へ
ニュース -
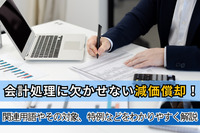
会計処理に欠かせない減価償却!関連用語やその対象、特例などをわかりやすく解説
ニュース -

契約審査とは?担当者が迷わない流れとチェックポイント
ニュース -

新入社員の育成・活躍を促進するオンボーディングとは?
ニュース