公開日 /-create_datetime-/
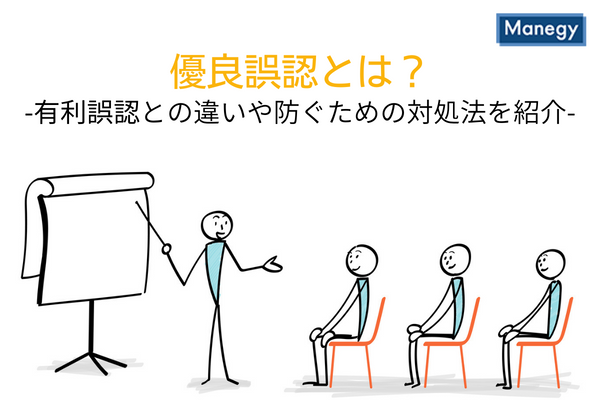
企業は自社の商品・サービスに対する印象を少しでも良くするために、広告やパッケージの制作に工夫を凝らし、多額の費用もかけています。
しかし、本来の商品・サービスよりも良く見せようとすることは、消費者に多大な損失を生じさせる必要があるため、景品表示法において禁止されています。そのような誇大広告の一つが「優良誤認」です。
今回は、優良誤認とは何か、消費者庁に疑われたらどうなるのか、防ぐためにはどうすればよいかについて詳しく解説します。
優良誤認とは?
優良誤認とは、自社商品・サービスの広告やパッケージなどに以下のような表示を行うことで不当に顧客を誘引し、消費者が合理的・自主的な選択を行うことを妨げる恐れがある表示のことです。
・実際よりも、著しく優良であると表示している。
・事実に反して、ライバル企業の商品・サービスよりも著しく優良であると表示している。
例えば中古自動車を販売するにあたって、広告に「走行距離5万キロ」と表示していたのに、実際には15万キロ以上走行していたことが判明した場合は優良誤認表示です。
また、ある企業が洗濯用洗剤を販売するにあたって、商品の背面に「業界初!99%の除菌効果」と表示していたとします。しかし、実際には90~95%ほどしか除菌できず、他企業の商品よりも優れてはいないことが判明した場合は優良誤認表示です。
なお、優良誤認表示と認められるのは「事業者が表示を行っている場合」「事業者が供給している商品・サービスに関する表示の場合」です。ここでいう事業者とは企業だけでなく、医療法人、社団法人、学校法人など、何らかの経済活動を行っているあらゆる事業者が対象とされます。
有利誤認との違い
優良誤認と似たものとして、「有利誤認」があります。有利誤認とは自社商品・サービスの広告やパッケージなどに、以下のような表示を行うことで消費者に誤認を与える表示を指します。
・事実に反して、価格その他の取引条件に関し、商品・サービスの購入者が著しく有利になると表示している。
・事実に反して、価格その他の取引条件に関し、ライバル企業よりも自社の商品・サービスを購入した方が著しく有利になると表示している。
例えば、金融機関が外貨預金の受取利息の金額を手数料抜きで広告表示していたのに、実際には手数料が差し引かれ、受取額が表示されていた金額の半額以下だった場合は、有利誤認表示に該当します。
また、引っ越し業者が「今月は3割引きで業界最安値!」と広告表示していたのに、実際には3割引きよりも高額で、業界最安値ではなかった場合は有利誤認表示です。
つまり、優良誤認が商品・サービスの品質の面で実際以上に優良であると表示するのに対し、有利誤認は商品・サービスの価格の面で実際以上に有利であると表示することです。
優良誤認の疑いを消費者庁に持たれたら
消費者など外部からの訴えなどがあり、消費者庁が特定の事業者に対して優良誤認の疑いを持ったときは、関連資料の収集および対象事業者への事情聴取などが行われます。
なお、消費者庁には景品表示法違反に関する情報提供を受け付ける専用の窓口があります。現在ではスマホ・パソコンを使ってインターネット上からでも情報提供が可能となっていて、消費者からの連絡は集まりやすい状況にあるといえます。
各種調査の結果、事業者側に景品表示法の違反行為が認められたときは、行政処分が行われる前に、事業者側に弁明の機会が与えられます。もし事業者側が申し出たい事項がある場合は、論拠となる資料を示しながら説明が可能です。正確な判断を行うために、消費者庁の方から事業者側に対し、言い分の合理的根拠を示す資料を出すように求める場合もあります。
事業者側の弁明が退けられ、違反行為があったと判断されたときは、行政処分が行われます。行政処分は大きく分けて措置命令と課徴金納付命令の2種類があります。
●措置命令
景品表示法第7条で規定されている行政処分です。①不当な表示によって消費者に与えた誤認を正すこと、②再発防止に取り組むこと、③①と②の実施に関連する公示を行うこと、④その他必要な事項、の4点に関して事業者側に命じます。②は消費者庁、③は消費者に向けての報告が必要です。消費者に向けての報告方法としては、日刊全国紙2紙での社告を求めるケースが多く見受けられます。
参照元:https://growth-law.com/page-1430/page-2702/#i-2
●課徴金納付命令
景品表示法第8条で規定されている行政処分です。課徴金の額は、課徴金対象期間中の対象商品・サービスの売上高の3%と定められています。課徴金対象期間は、原則として不当表示の開始日から不当表示の終了日までです。
参照元:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160208premiums_3.pdf
優良誤認を防ぐための対処法
事業者側が意図しない形で優良誤認表示を行う恐れもあるため、防ぐための対処法を考えておくことも大切です。
基本的な防止策としては、広告・パッケージの内容確認を担当部署以外が行うことが挙げられます。通常、広告・パッケージの制作はマーケティング担当者が行うのが通例です。しかし、別部署の人にもチェック担当の業務を担ってもらい、消費者の目線から問題がないかを確認してもらうと、不当表示を発見できる可能性が高まります。
また、「業界初!」などの表示をする場合は、その根拠となる資料を必ずそろえておきましょう。もし消費者庁から資料の提示を求められた場合、客観的なデータを示すことができれば行政処分を避けることができます。
消費者庁は「不実証広告ガイドライン」の内容をインターネット上で公表し、どのような資料が表示の合理的な根拠となるのか、その要件を示しています。資料を用意する場合は、消費者庁の要件をクリアするものを用意しておくことが必要です。その他にも、優良誤認にあたる具体例などが紹介されていますので、消費者庁のホームページを確認しておくと良さそうです。
まとめ
優良誤認表示とは、商品・サービスの品質が実際以上に優良であるとの偽りの表示を広告・パッケージにおいて行うことです。行政処分自体は、企業にとってはそれほど大きなダメージではないのかもしれません。しかし「行政処分を受けるような悪質なことを行っていた」というイメージを持たれることは、企業にとって大きなダメージです。そのことがきっかけで社会的信頼を失い、その後の売り上げが激減するという事態も招きかねません。
優良誤認は意図しない形で起こることもあるため、社内で広告・パッケージのチェック体制を整えることが大事です。また、自社の商品・サービスが特別優良であるような表示を行う場合は、その客観的根拠を示す資料を用意しておく必要があります。
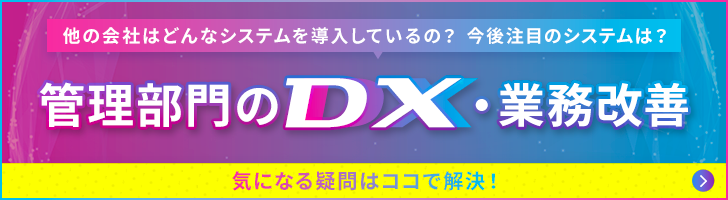
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-
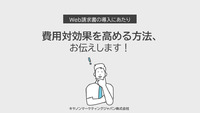
Web請求書の導入にあたり費用対効果を高める方法、お伝えします!
おすすめ資料 -
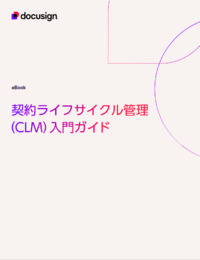
法務部の負担を軽減!「契約ライフサイクル管理システム(CLM)」のキホンを徹底解説
おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -
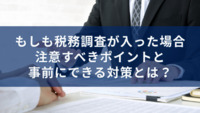
もしも税務調査が入った場合、注意すべきポイントと事前にできる対策とは?
ニュース -
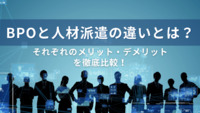
BPOと人材派遣の違いとは?それぞれのメリット・デメリットを徹底比較!
ニュース -

賃上げをサポートする「長崎県製造業賃上げ対応型投資促進補助金(物価高騰克服タイプ)」【長崎】
ニュース -
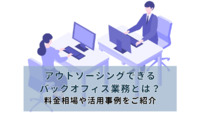
アウトソーシングできるバックオフィス業務とは?料金相場や活用事例をご紹介
ニュース -
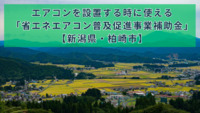
エアコンを設置する時に使える「省エネエアコン普及促進事業補助金」【新潟県・柏崎市】
ニュース -
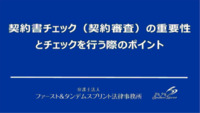
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -
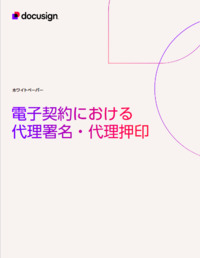
電子契約における代理署名・代理押印
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -
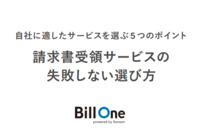
請求書受領サービスの 失敗しない選び方
おすすめ資料 -
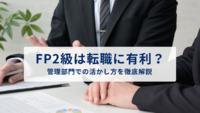
FP2級は転職に有利?管理部門での活かし方を徹底解説!
ニュース -

経費精算を正しくできていますか?税務署にチェックされやすいポイントも紹介
ニュース -

事業承継・M&A補助金 11次公募は専門家活用枠のみ!
ニュース -

オンライン秘書とは?起業家におすすめする理由と依頼できる業務を解説
ニュース -
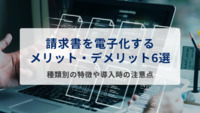
請求書を電子化するメリット・デメリット6選!種類別の特徴や導入時の注意点も解説
ニュース












