公開日 /-create_datetime-/
「法定雇用率」や「助成金制度」など、障害者雇用に関するルールの再確認

中央省庁による障害者雇用水増し問題が連日のようにニュースで取り上げられ、関心を寄せている方も多いのではないでしょうか。障害者の雇用に関して民間企業は、自社で働く労働者の2.2%に相当する障害者を雇用することが、「障害者雇用促進法」によって義務付けられていますが、詳細なルールはどのようになっているのでしょうか。
知らなかった!ではすまされない「障害者雇用に関するルール」を再確認しておきましょう。
障害者の法定雇用率は2.2%以上
「障害者雇用促進法」(43条第1項)には、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率=2.2%」以上にしなければならないと定められています。
つまり、単純計算で従業員45人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければならないということであり、守らなければ、ハローワークから行政指導を受けることになります。行政指導を受けた企業は、2年間で達成可能な計画を策定しなければなりません。そして、達成できない場合や指導にしたがわなかった場合には、社名が公表されることになっています。
また、法定雇用率に達していない企業のうち、常用労働者100人超の企業からは、障害者雇用納付金が徴収されることになっています。
障害者雇用率制度で定めている障害者の範囲は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者とされており、これらの人を実雇用率の算定対象としています。短時間労働者は原則0.5人としてカウントされます。
障害者雇用に対する助成制度
障害者を雇用して働いてもらうためには、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備をはじめ、障害者ならではの特別な雇用管理が必要となります。健常者の雇用に比べると、事業主には経済的負担もかかることから、負担軽減のために「障害者雇用納付金制度」が設けられています。
法定雇用率を達成している企業には、調整金、報奨金が支給されるほか、障害者を雇い入れるために作業施設や設備を設置する場合には、その費用に対して助成金が支給される制度です。
また、障害者雇用に関する助成金は、身体障害者手帳をもたない統合失調症や躁鬱病、てんかんの人も対象となります。さらに、ハローワークや地域障害者職業センターでは、「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」も支援の対象となるとしていますので、確認しておきましょう。
障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務
事業主は、労働者を募集・採用する際、障害者であることを理由に、賃金・教育訓練・福利厚生その他の待遇について、不当な差別的取扱いをしてはならないことが「障害者雇用促進法(第34~35条)」で定められています。
また、「障害者雇用促進法(第36条の2~36条の4)」には、障害の特性に配慮した施設整備や援助者の配置などの必要な措置を講じなければならないことも明記されています。ただし、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすような場合は、この限りではありません。
障害者を5人以上雇用する事業所は、「障害者職業生活相談員」を選任し、その者に障害のある従業員の職業生活に関する相談・指導をさせなければならないことも定められています(障害者雇用促進法79条)。
生きがいをもって働ける職場環境づくり
障害者を雇用するにあたっては、障害者の人権、障害者の特性に配慮した接し方や仕事の教え方などが必要であり、周りの従業員に対する研修が必要となります。また、障害者や家族からの苦情を処理する体制を整備することも重要です。
障害者も、能力や適性が発揮でき、生きがいをもって働けるような職場づくりをしなければならないことは「障害者虐待防止法第21条」によって定められています。
たとえば、マニュアルによる業務の可視化や、作業手順の簡略化など、障害者が業務を行うのに支障がないような工夫も行う必要が出てきます。ただそれは、障害者だけではなく、一緒に働く社員の職場環境や業務の見直しにもつながります。
管理部門には、障害者雇用に関するルールの再確認をするとともに、障害者、健常者に関係なく、すべての従業員が生きがいをもって働ける職場環境づくりに取り組んでいくことが求められているのです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
おすすめ資料 -

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト②/会計
ニュース -

棚卸評価損の仕訳とは?計算方法・仕訳例・評価方法をわかりやすく解説
ニュース -
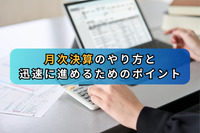
月次決算のやり方と迅速に進めるためのポイント
ニュース -

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増
ニュース -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -

軽減税率導入で複雑化する請求書の消費税処理、経理担当者の手間を軽減するには?
ニュース -

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!
ニュース -

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -

収入印紙の消印とは?正しい押し方・使える印鑑・注意点をわかりやすく解説
ニュース -
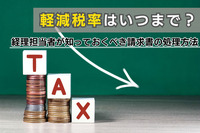
軽減税率はいつまで?経理担当者が知っておくべき請求書の処理方法
ニュース




































