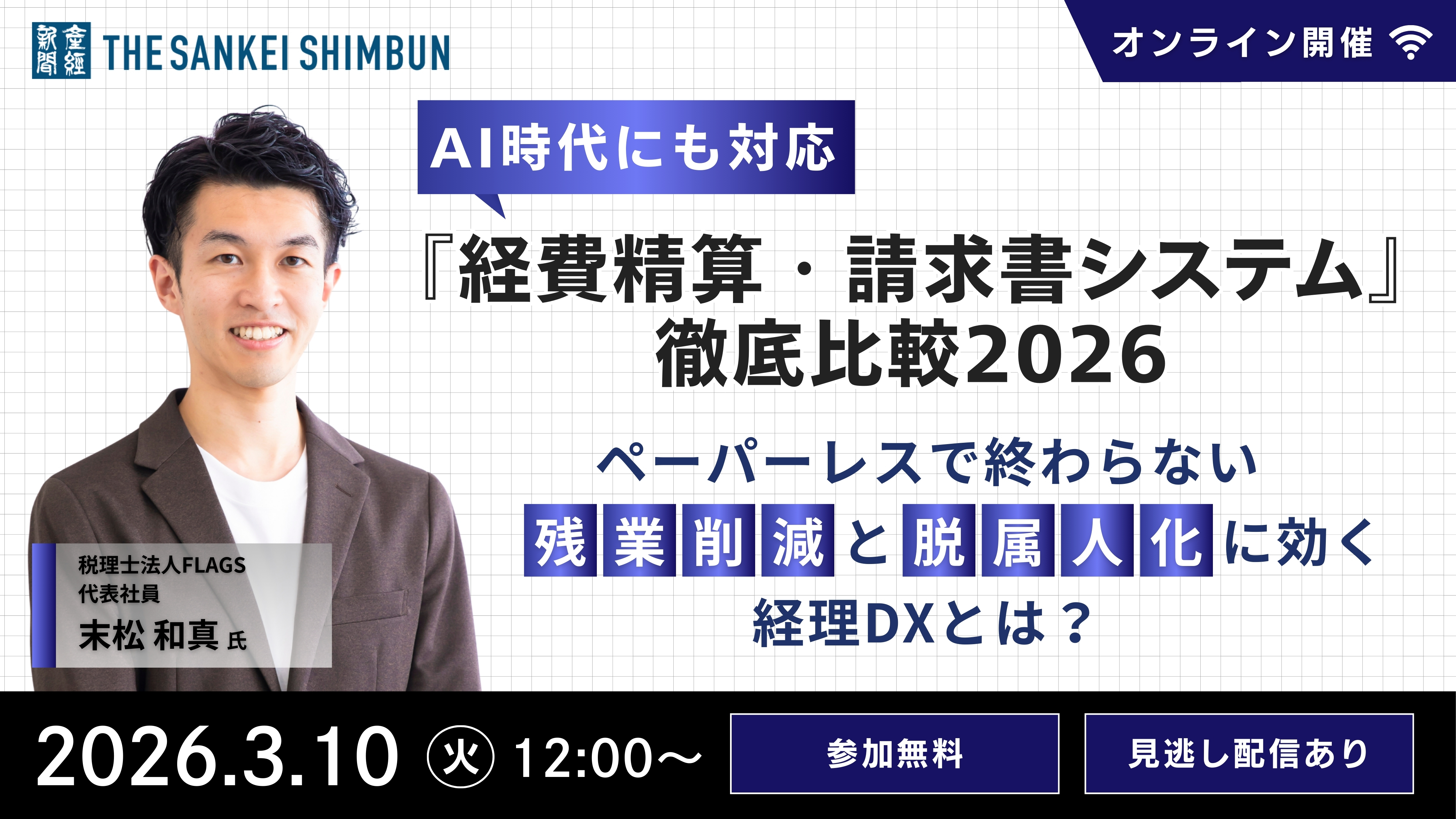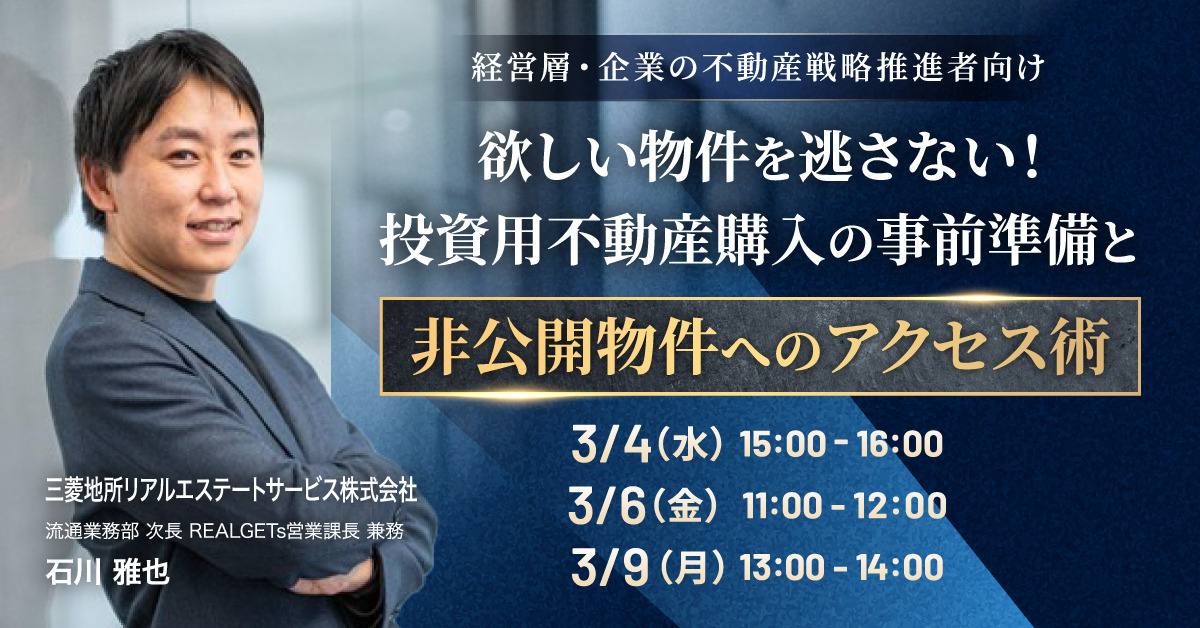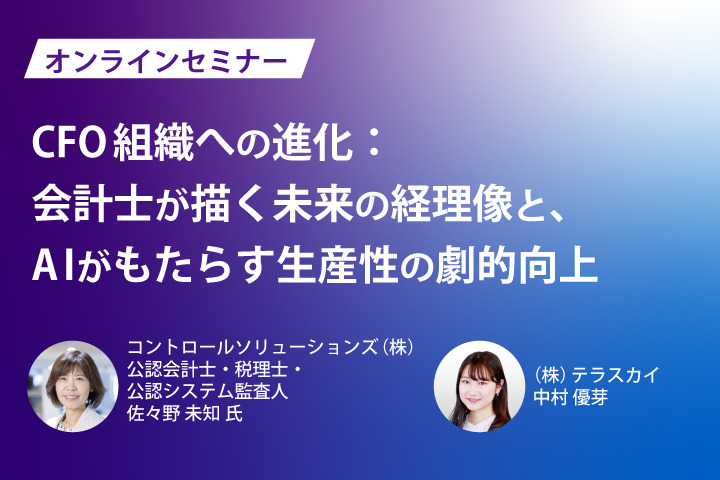公開日 /-create_datetime-/
「女性活躍推進」と「外国人採用」に積極的な企業は5~6割程度。今後取り組みを進める上でのポイントは?

先日、総合人材サービスのパーソルホールディングス株式会社が1,000社を対象に「女性活躍推進」と「外国人採用」に対する取り組み度合いを調べるアンケート結果*を公表しました。
それによると、女性活躍推進に「取り組めている」と回答した企業は58.0%、外国人採用に「取り組めている」と回答した企業は50.2%でした。女性・外国人の活用に取り組めていない企業が、4~5割に上る実態が明らかになっています。
今回は女性活躍推進、外国人労働者の採用に取り組む上でのポイントとそのメリットについて解説します。
女性活躍推進に取り組む際のポイント
企業が女性活躍推進に取り組む上で重要なポイントとなるのが、「女性活躍推進法」の内容です。
女性活躍推進法は2016年に成立し、従業員301人以上の企業に対して、女性が活躍するための行動計画を策定して公表するように義務付ける法律です。2019年には法改正が行われ、従業員101人以上の企業についても対象になることが決まり、2022年4月から義務化が施行されています。
この法律の施行により、対象企業は①採用人数に占める女性比率、②勤続年数における男女の差、③労働時間の実態、④管理職の女性比率、について調査をして課題を把握します。その上で、女性が活躍できるような行動計画を策定し、それを企業内外に公表する義務が発生します。また、策定した行動計画は都道府県の労働局への届出も必要です。
つまり、上記①~④の項目に関する情報把握、分析、行動計画は、従業員数101名以上のすべての企業が取り組んでいる内容であり、かつその内容が公表されているわけです。こうなると、少なくともこの①~④の項目については、どの企業がどの程度充実した取り組みをしているのか、どのような対策を立てているのかが誰でも簡単に比較可能となります。
たとえば女性の管理職の比率について、少なくとも101名以上の企業において、どの企業が率先して行っているのか、逆にどの企業では取り組みが進んでいないのかについて、公表情報を元に誰でも明確に把握できます。企業の評判・名声のことを考えると、これら比較項目になる取り組みを優先的に取り組むのが得策です。
外国人労働者を雇用する際のポイント
日本で就労できる外国人は、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者等」など、制限なく働ける在留資格を持つ場合、および特定の職業において就労資格を持つ場合です。
後者については、現行制度では19種類の業務(外交、経営・管理、公用、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計、教育、研究、興行、医療、技能実習、特定技能、介護、高度専門職、技能、企業内転勤、技術・人文知識・国際業務)が就労ビザの対象とされています。
以上の条件を満たさないのに外国人を採用すると、「不法労働助長罪」に問われるので注意しましょう。たとえば、アルバイトとして雇用できるのは、定住者、日本人の配偶者、永住者、永住者の配偶者、ワーキングホリデービザ取得者のみで、個別に許可を得ている場合に限り、「文化活動」「留学」「家族滞在(就労資格で在留する外国人の配偶者や子)」での在留資格でも雇用できます。
外国人労働者を採用する場合、在留資格申請や各種提出書類の準備、入国時・入国後の対応なども重要ですが、最もポイントとなるのは職場環境の整備です。職場で外国人労働者の同僚や上司となる人に納得してもらうこと、職場において文化の違いを理解できる対策を講じなければなりません。
なお、外国人だからといって、日本人と差別的な賃金体系で臨むことは労働基準法違反です。「同一労働同一賃金」「最低賃金」などの制度上の規定は、外国人に対しても同様に適用されます。
女性活躍推進、外国人労働者採用推進の背景にある「人手不足」
現在、日本ではコロナ禍から少しずつ経済活動が回復しつつありますが、それに伴い、よりいっそう深刻となりつつあるのが中小企業における人手不足です。各企業には多様かつ柔軟な働き方を推進し、人材確保のための自己変革が求められているといえます。
女性や外国人労働者の活用は、人材不足を補うための有効な対応策となります。外国人労働者が安心して働ける環境を生活面から整備する、女性が結婚・出産・育児を経ても正規社員として労働し、管理職まで進める環境を整備することが、企業には求められています。
まとめ
上述のアンケート結果によると、日本企業の4~5割程度が女性活躍推進や外国人労働者の採用にうまく取り組めていないのが現状です。しかしこのことは、女性、外国人労働者が活躍できる素地がまだ多くあり、現在取り組みを進めていない企業が今後取り組みを進めれば、女性の活躍、外国人労働者の雇用がさらに進展することを意味します。人手不足の問題の解消を目指すためにも、日本企業には自己変革が求められている時代が来ているといえます。
*【調査概要】
調査対象:25~69歳男女
※経営者・役員、および会社員(管理職/一般職員)のうち1年以内に人事・採用関連の業務について「最終決裁をする立場」または「選択肢を絞り込む立場」のいずれかにあてはまる人
※勤務先または経営する企業の従業員規模が30人以上の人
調査期間:2022年9月15日~16日
調査方法:インターネット
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!
おすすめ資料 -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

【期間限定】ログインするだけで毎週チャンス!Amazonギフトカードが当たるログインキャンペーン実施中!
ニュース -
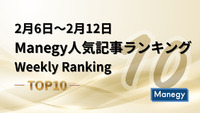
2月6日~2月12日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -

外国人を雇用する際の雇用保険はどうする?注意点について国際業務に詳しい法律事務所が解説
ニュース -

ダイバーシティ推進の現在地―人事1000名の声から読み解く現状と未来予測―
ニュース -
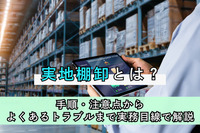
実地棚卸とは?手順・注意点からよくあるトラブルまで実務目線で解説
ニュース -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは
おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
おすすめ資料 -

労使および専門家の計515人に聞く 2026年賃上げの見通し ~定昇込みで4.69%と予測、25年実績を下回るも高水準を維持~
ニュース -

2026年1月の「物価高」倒産 76件 食料品の価格上昇で食品関連が増勢
ニュース -

労基法大改正と「事業」概念の再考察② ~場所的観念から組織的観念へのシフト~
ニュース -

【図解フローチャート付】出張ガソリン代の勘定科目は?旅費交通費と車両費の違いを仕訳例で徹底解説
ニュース -
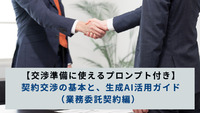
【交渉準備に使えるプロンプト付き】契約交渉の基本と、生成AI活用ガイド(業務委託契約編)
ニュース