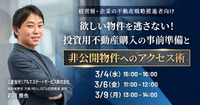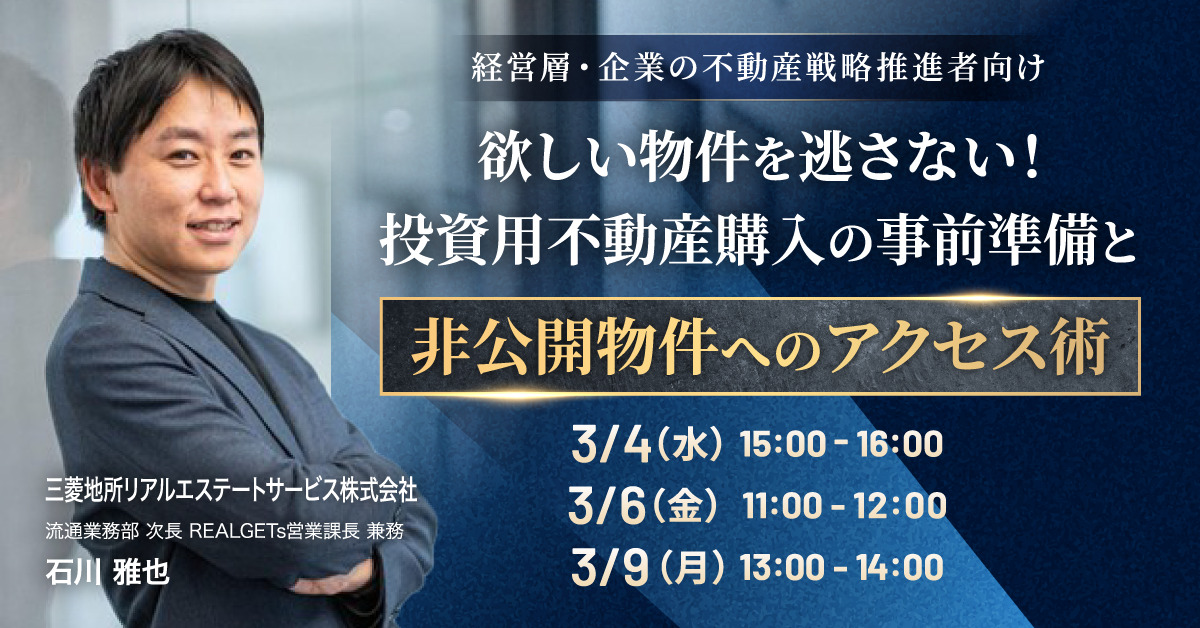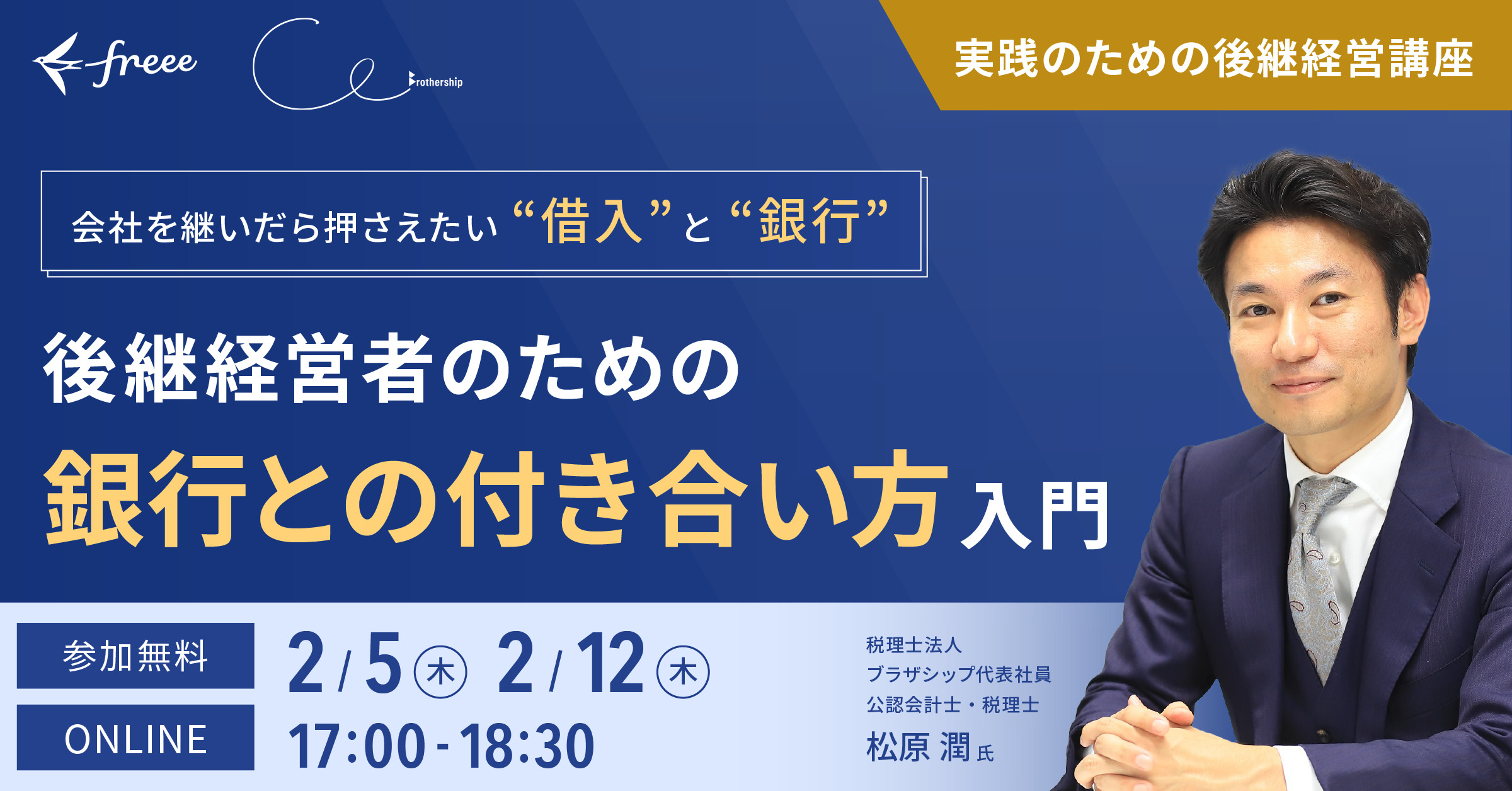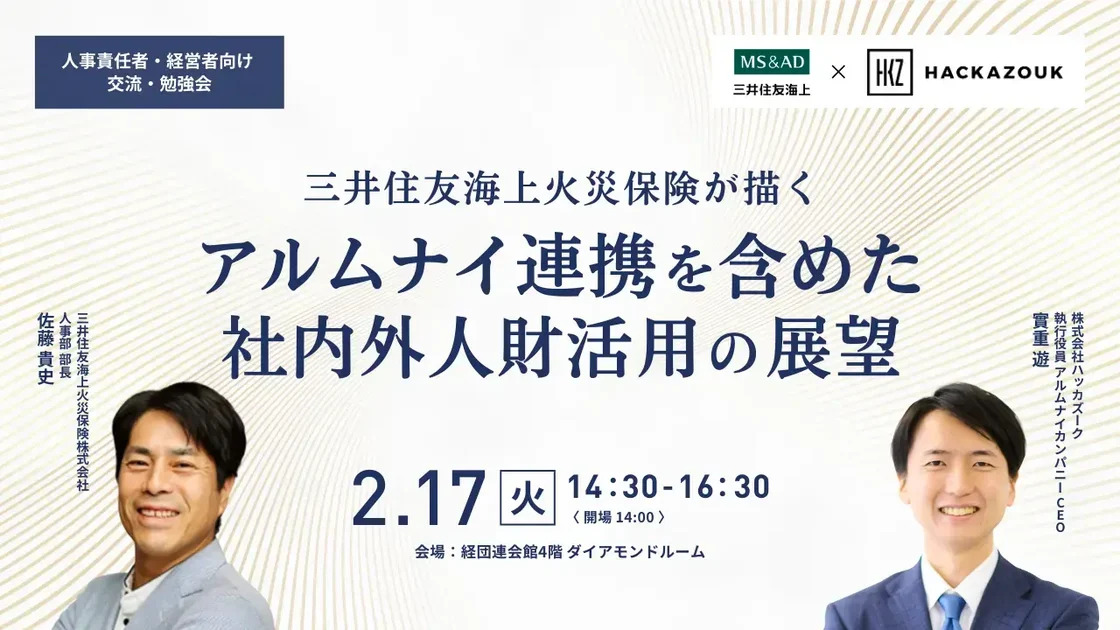公開日 /-create_datetime-/

「〇〇ホールディングス」のような名前の会社を見かけることが多くなりました。この「ホールディングス」とは「持ち株会社」のことを意味します。戦後の財閥解体にともない独占禁止法で全面禁止されていた持ち株会社は1997年に解禁され、それ以降、多くの持ち株会社が生まれています。
今回は、持ち株会社とは簡単にいえば何なのか、持ち株会社が禁止されていた理由、および持ち株会社のメリット・デメリットをご紹介します。
持ち株会社を簡単にいうと?
持ち株会社とは簡単にいえば、「事業の支配を目的として他の会社の株式を保有する会社」のことです。
一般に、株式を保有するのは投資が目的となりますが、持ち株会社は支配が目的であることが特徴です。持ち株会社は独占禁止法により長らく禁止されていました。しかし、1997年に解禁され、日本でも持ち株会社が多く誕生することとなっています。
持ち株会社には、自社では事業を行わず傘下の企業を支配することのみが目的の「純粋持株会社」と、自社でも事業を行うとともに傘下企業の支配も行う「事業持株会社」とがあります。自社で事業を行わない純粋持株会社の収益は、子会社からの配当によって上げることが一般的です。
持ち株会社は禁止されていた?
持ち株会社が独占禁止法により禁止されていたのは、戦後の財閥解体によるものです。それまで財閥は、財閥本社が持ち株会社として傘下の企業を支配することにより、一大コンツェルンを形成して日本経済に大きな影響を与えていました。解体された財閥の復活を阻止するために、独占禁止法により持ち株会社が全面禁止されました。
しかし、それからの産業構造の変化により、「持ち株会社が経営戦略上好ましい」との声が産業界を中心に高まったため、1997年に独占禁止法が改正され、持ち株会社が認められることとなりました。
持ち株会社の7つのメリット
持ち株会社が産業界からの声により解禁されたのは、さまざまなメリットがあるからです。どのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。
持ち株会社のメリット1.グループの意思決定が迅速になる
持ち株会社が許されていなかった従来のグループ会社では、本社は、自社の事業を運営するとともにグループの戦略決定を行わなければなりませんでした。そのために、グループ戦略の意思決定が遅れる恐れがありました。
それに対して持ち株会社は、グループの戦略決定などグループ全体の舵取りに特化することができ、事業は個々のグループ企業にまかせることができます。このように、戦略と事業を分離することにより、グループ戦略の意思決定を迅速に行うことができます。
持ち株会社のメリット2.事業会社の責任や権限が明確になる
また、持ち株会社のグループ企業はそれぞれ独立した会社ですので、権限と責任を、大幅に移譲して明確にすることができます。それにより、各事業会社が採算を重視するようになるのとともに、業績評価も容易になります。
持ち株会社のメリット3.リスクが分散される
持ち株会社とグループ企業を独立した会社として分離することにより、グループ経営におけるリスクが分散される効果もあります。仮にグループ企業に大きな損失が発生した場合でも、持ち株会社や他のグループ企業に影響が及ばないようにし、グループ全体が損失をこうむることを避けられるようになります。
持ち株会社のメリット4.グループ会社ごとに労働条件を設定できる
持ち株会社が支配するグループ企業はそれぞれが独立した会社ですので、労働条件をそれぞれで設定することができます。一般に、グループ企業のそれぞれが異なる事業を行う場合、休日や労働時間、人事制度などの労働条件を同一にするのは困難です。独立した会社であるグループ企業は、それぞれの事業の実態に合わせた労働条件を設定することが容易です。
持ち株会社のメリット5.買収を防衛することができる
一般のグループ企業では、親会社を買収することにより、間接に子会社を買収することが可能となります。しかし、持ち株会社のグループは株式所有が二重構造をしていて、各グループ企業はそれぞれが独立しています。そのために、仮に持ち株会社が買収を仕掛けられても、非上場の子会社の経営権を防衛するための対抗策を取ることが容易になります。
持ち株会社のメリット6.グループ企業の売却をスムーズに行える
持ち株会社のグループ企業は、それぞれが決算を独立で行います。そのために、グループ企業の企業価値やリスクなどの評価が容易になり、グループ企業を売却する際には手続きをスムーズに進めることができます。
持ち株会社のメリット7.企業の買収がスムーズに行える
企業を買収する際にも、持ち株会社のグループなら買収企業をグループ企業としてそのまま置くことが容易になります。そのために、企業の買収手続きもスムーズに進められます。また、買収した企業が企業文化の違いなどから他のグループ企業と摩擦を起こす場合にも、持ち株会社が統制役として機能するため、摩擦を最小限にすることができます。
持ち株会社の2つのデメリット
多くのメリットがある持ち株会社ですが、他方ではデメリットもあります。どのようなデメリットがあるのかを見ていきましょう。
持ち株会社のデメリット1.持ち株会社と各グループ企業との連携が難しくなる
持ち株会社のグループでは、各グループ企業はそれぞれが独立した会社として事業を行います。そのために、持ち株会社と各グループ企業との連携が難しくなることがあります。
持ち株会社とグループ企業は、それぞれが会社として独立しているために、まず意思疎通を図ることが難しくなります。また、経営方針についても各グループ企業の裁量の範囲が大きくなるため、グループ企業が持ち株会社の意図した通りに動くとは限らない場合もでてきます。
持ち株会社とグループ企業との連携は、最悪の場合には、次のようなことが起こることもあります。
・グループ企業が、持ち株会社やグループ全体にとって不都合な情報を隠蔽する
・グループ企業同士のあいだで上下関係が発生し関係が悪くなる
持ち株会社のグループでは持ち株会社に、強いリーダーシップを発揮することとともに、グループ全体の好ましい関係や信頼をどう構築するかが問われます。
持ち株会社のデメリット2.会社を維持するコストがかかる
持ち株会社のグループでは、グループ企業はすべて独立した会社です。そのために、グループ全体として会社を維持するコストが増加します。
その理由は、各グループ企業で部門の重複が起こるからです。特に、経理や総務、人事などのバックオフィス業務を行う部門は、独立した会社である各グループ企業に欠かすことができませんので、どうしても重複しやすくなります。
バックオフィス業務の重複は、そのままにしておくとグループの成長とともにコストが増加し、グループ全体の収益を圧迫することにもなりかねません。持ち株会社のグループが成長するには、バックオフィス業務のコストをいかに抑えられるかがポイントになるといえるでしょう。
まとめ
持ち株会社は、グループの戦略決定を迅速に行えるなど多くのメリットがある一方、グループ企業の連携が難しくなるなどのデメリットもあります。1997年に独占禁止法が改正されて以降、巨大なグループを抱える大企業にとって持ち株会社の設立は、スタンダードといえるものになりました。持ち株会社のメリットを生かし、デメリットを最小にする経営が求められているといえるでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

弁護士業におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧
おすすめ資料 -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料
おすすめ資料 -

朱に交われば赤くなる!?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第1話】
ニュース -

面接日程調整の“理想”は「当日~翌日」も、実態は「1~5日」…採用現場のスピード対応に潜む課題とは
ニュース -

採用だけの人事経験は転職で不利?評価されるスキルとキャリアの広げ方を徹底解説(前編)
ニュース -
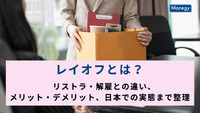
レイオフとは?リストラ・解雇との違い、メリット・デメリット、日本での実態まで整理
ニュース -
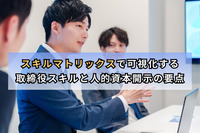
スキルマトリックスで可視化する取締役スキルと人的資本開示の要点
ニュース -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法
おすすめ資料 -

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着
ニュース -

ケアの倫理から労働の倫理を問い直す②~法の精神が要求する新たな組織原理~
ニュース -
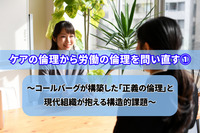
ケアの倫理から労働の倫理を問い直す①~コールバーグが構築した「正義の倫理」と現代組織が抱える構造的課題~
ニュース -

2025年、上場廃止への「TOB・MBO」は112社 TOBの買い手は約30%がアクティビストを含む「ファンド」
ニュース -
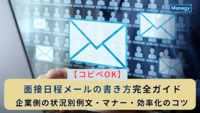
【コピペOK】面接日程メールの書き方完全ガイド|企業側の状況別例文・マナー・効率化のコツ
ニュース