公開日 /-create_datetime-/
法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?
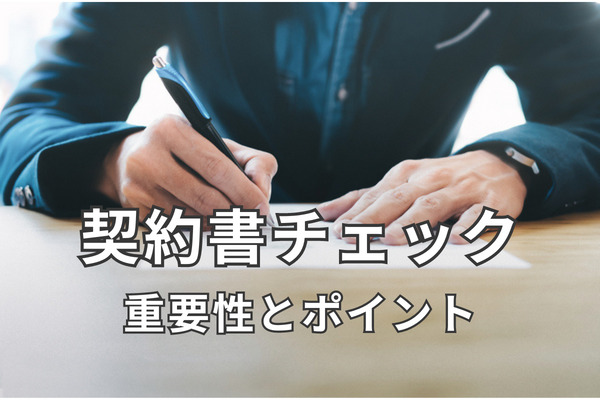
企業が取引を行う際には、必ず契約書を作成すべきです。
ただしネットなどで出回っている「雛形」「テンプレート」をそのまま使うとリスクが高いので、記名押印する前に弁護士などの専門家によるリーガルチェックを受けましょう。
契約審査(レビュー)を経て個別の契約に応じた内容に設定しておけば、効果的にトラブルを防げますし、万一トラブルが発生した際にも比較的スムーズに解決できるメリットがあります。
この記事では契約書チェックの重要性やレビューを受ける際のポイントをお伝えします。
当事務所では、一般的な弁護士によるリーガルチェックと比べてコストを抑え、スピード対応しています。
ビジネス専門の弁護士などの専門家がリーズナブルな価格で御社のご事情に応じた契約審査をさせていただきますので、ぜひとも一度、ご相談ください。
目次【本記事の内容】
そもそも契約書は何のために作成するのでしょうか?
契約書を作成する目的や役割を確認しましょう。
契約内容を明らかにする
契約書には、契約内容を明らかにする目的があります。
法的には口頭で成立する契約が多いので、あえて契約書を作成する必要はないともいえます。
ただ契約内容が複雑な場合、契約書がないと内容が不明確になってしまいます。そうなるとお互いにどのように行動してよいか判断がつきにくいでしょう。そこで契約内容を明らかにするために書面を作成するのです。
契約した証拠を残す
口頭で契約しただけでは、証拠が残りません。
後に紛争が生じたとき、相手から「そんな契約はしていない」といわれる可能性がありますし、約束した内容と異なる主張をされるリスクも発生します。
そこで契約した証拠を残すために契約書を作成します。
トラブル防止
契約書がないと、さまざまなトラブルが発生する可能性もあります。
お互いにどのように行動すればよいかわからず、認識に齟齬が発生してしまうためです。
お互いが共通認識をもって適切に行動するためにも契約書は必須といえるでしょう。
トラブルが発生したときの解決指針とする
契約書は実際にトラブルが起こったときの解決指針にもなります。
契約書に書かれている内容に違反していたら契約違反と主張できますし、自社が契約に従って行動していれば相手から責められる理由はありません。
契約書の種類は非常にさまざまです。以下では企業が締結することの多い代表的な契約書をいくつかご紹介します。
契約書例① 業務委託契約書
業務委託契約書は、企業が仕事を「外注」する際に相手方と締結する契約書です。
たとえばイラストや文書の作成、ソフトやアプリ開発、HPの制作、製造委託、情報収集などを外注する際には業務委託契約を締結する必要があります。
業務委託契約書には、発注する仕事内容や代金、代金支払時期や著作権などについて細かく記載しなければなりません。
契約書例② 秘密保持契約書
秘密保持契約書は、企業の重要な秘密を守るための契約書です。たとえば以下のような場合に秘密保持契約の締結が必要となるでしょう。
・従業員を雇い入れるときや退職するとき
・仕事を外注するとき
・M&Aを実施するとき
企業が秘密を漏えいされると、開発中のアイデアや技術をライバル企業に奪われて不利益を受ける可能性がありますし、自社に対する社会の評判が低下してしまうおそれもあります。
個人情報流出につながると個人情報保護法違反となり、信用低下をはじめとした大きな不利益を受けるリスクも発生します。 企業が安全に経済活動を行うため必須の契約類型といえるでしょう。
契約書例③ 取引基本契約書
取引基本契約書は、企業が取引に入る際に基本内容を取り決める契約書です。相手方とは継続的に取引を行うことが前提となります。
たとえば製品の受発注や請負などの契約を締結する際、個別にいちいちすべての条項について確認すると契約書の内容が長くなりすぎて煩雑でしょう。
そこでまずは取引基本契約書に基本となる事項をとりまとめて、個別取引の際には簡略な個別契約書のみを作成します。 企業が業務効率を向上させるには取引基本契約が非常に有用です。
契約書を作成するとき、どのような内容でもよいわけではありません。 特にネットなどで簡単に入手できる「雛形」「テンプレート」「書式」をそのまま適用すると高いリスクが発生します 以下では不適切な契約書にどういったリスクが潜んでいるのか、みてみましょう。
契約書の雛形などを利用してきちんとレビューをしなかった場合、本来必要な項目が抜けてしまう可能性があります。 たとえば中途解約に関する条項がないために、途中で解約できるのかどうかがわからなかったり、解約方法が不明確になってしまったりするケースもみられます。
損害賠償に関する規定がないためにどういった状況で相手に損害賠償請求できるかわからなくなってしまったり、納期や報酬支払時期について記載がないために取引が滞ったりする可能性もあるでしょう。 契約には「個性」があるので、事案の内容に応じて記載事項を確定しなければなりません。 記載項目に不備があると、トラブル予防やトラブルのスムーズな解決という契約書の目的を果たせなくなってしまいます。
契約書に不備があると、自社にとって不利な内容を見逃してしまう可能性があります。 たとえばイラストや写真などを外注する際、著作権譲渡に関する条項がなければ基本的に著作権は外注先がもったままとなります。すると、将来別メディアに掲載したり手を加えたりする際に、いちいち外注先の承諾をとらねばなりません。相手が納得しない場合、著作権の使用料を払わねばならない可能性もあります。
また民法や借地借家法の原則よりも自社に不利益に修正されている場合でも、気づかず契約してしまったら基本的に有効です。たとえば不動産を貸し付ける際に「賃料不増額特約」が入っていると、自社の側からテナント側へ賃料の増額請求ができなくなってしまいます。テナント側からは賃料減額請求ができるので、オーナー側に不利な契約内容となるでしょう。
契約書に不備があると、会社に損害が発生するリスクも高まります。 たとえば中途解約ができないために不要となった契約を延々と続けなければならなくなったり、相手から迷惑をかけられても損害賠償できなかったりすると、経済的な損失が発生するでしょう。 せっかく委託代金を払ってソフトやアプリなどの開発を行っても、著作権譲渡を受けなかったために自由に使えなければ発注した意義が半減してしまいます。
契約書に不備があると、相手方とトラブルになる可能性も高まり、お互いの信頼関係が失われます。 ビジネスを成功させるため、信頼関係が命ともいえます。それにもかかわらずトラブルになってしまったら、二度と円滑な取引ができなくなってしまうでしょう。 信頼関係が破壊されて取引のチャンスを失ってしまうことも、不備のある契約書に潜むリスクです。
契約書を作成する際には、以下のような事項を盛り込みましょう。
まずは契約目的を特定しなければなりません。 売買なら商品や製品、不動賃貸借なら目的物件、仕事の委託なら委託する仕事内容などを明確にしましょう。 契約書に示しきれない場合、別紙として図面や仕様書、工程表などをつける方法もあります。
代金や報酬としていくらをいつまでに支払うのか、明確にすべきです。 価額については税込みか税別かも明らかにすべきですし、契約時に具体的な金額を明示し難ければ計算式などを記入しましょう。 支払方法については一括か分割か、振込の場合は入金先の口座や振込手数料負担者についても記載しておいてください。 なお請負契約の場合、報酬支払い時期の取り決めがないと「工事が完成した後」に全額払う内容となってしまいます。一般的には契約書において数回の分割払いを定めて対応しています。
目的物をいつまでにどういった方法で引き渡すのかも決めておきましょう。 業務委託の場合にも、納期を定めておくべきです。 不動産売買の場合には、所有権移転登記についても記載しておくとよいでしょう。
お互いに契約を解除できるケースや方法について定めましょう。 法律上は基本的に催告を行った上での解除となるため、無催告解除を可能とする場合には、契約書に盛り込んでおくべきです。
どういった状況になれば相手に損害賠償請求できるのか、定めておきましょう。 損害額の計算方法や予定額を決めておくとスムーズにトラブル解決できるケースがあります。
たとえば目的物が天変地異で滅失してしまった場合などのように、当事者の故意、過失以外の要因で債務の履行が難しくなったときにどちらがリスクを負担すべきかも取り決めておきましょう。
契約不適合責任とは、納品物が契約目的に沿っていなかった場合に売主や請負人に発生する責任です。買主や発注者は相手方に対し、修補請求や代金減額請求、解除や損害賠償請求ができます。
民法の原則によると、まずは修補請求を行ってから代金減額請求を行う必要があり、契約不適合責任が発生する期間も定められています。 契約不適合責任の具体的な内容や期間について民法と異なる内容を定めたい場合には、必ず契約書に記載しておきましょう。
取引基本契約や業務委託契約、秘密保持契約、賃貸借契約などの継続的な契約の場合、契約期間を定める必要があります。期間満了時の自動更新についても記載しましょう。
中途解約ができるのか、できるとすればどういった条件を満たせば解約できるのか、解約の具体的な方法(事前告知や書面通知の有無)なども記載しましょう。
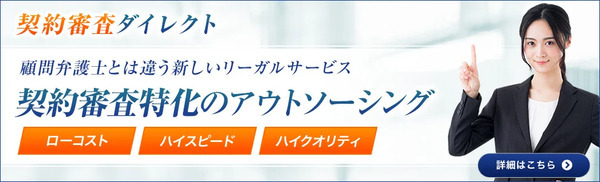
契約書を作成する際には、上記のようにたくさんの事項を盛り込まねばなりません。必要な条項に漏れがあったり、自社にとって不利な規定を見落としてしまうと、ビジネス上の大きなリスクにりますので、契約書の量が多い場合や、自社のみで判断が難しい場合には、
ビジネス専門の弁護士に契約書の審査・レビューを依頼して事前にチェックしておくことをお勧めします。契約書をチェックする際には最低限、以下の内容を確認しましょう。
契約書に必要な事項が網羅的に盛り込まれているかチェックすべきです。 何が必要かは個々の契約内容によって異なるので、個別対応が必要です。
契約書の内容が契約目的に合致しているか確認しましょう。 特に雛形を適用すると、目的と契約書の内容がずれてしまうケースが多々あります。
ズレを防止するためにはリ…
◆WRITER

弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
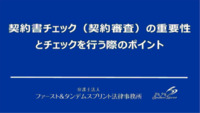
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築

税務・会計業務で使える生成AI実践セミナー【セッション紹介】
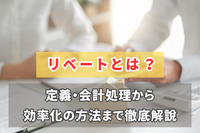
リベートとは?定義・会計処理から効率化の方法まで徹底解説

【2026年新春】総勢300名様にAmazonギフトカードが当たる!Manegyお年玉キャンペーン開催中

管理部門担当者は何学部が多い?アンケート調査で見えた管理部門の出身学部とキャリアの関係
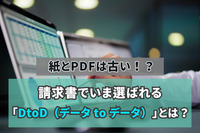
紙とPDFは古い!?請求書でいま選ばれる「DtoD(データ to データ)」とは?
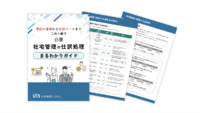
簿記の基礎から実務まで!社宅管理の仕訳処理 まるわかりガイド

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
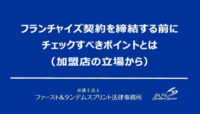
フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

2026年の展望=2025年を振り返って(13)

雑収入とは?仕訳方法・具体例・税金の扱いをわかりやすく解説
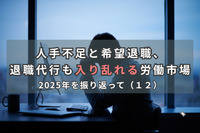
人手不足と希望退職、退職代行も入り乱れる労働市場=2025年を振り返って(12)

決算書が赤字の時に見るべき場所とは?原因の読み解き方と改善策を徹底解説

令和7年度 法人税申告書の様式改正
公開日 /-create_datetime-/