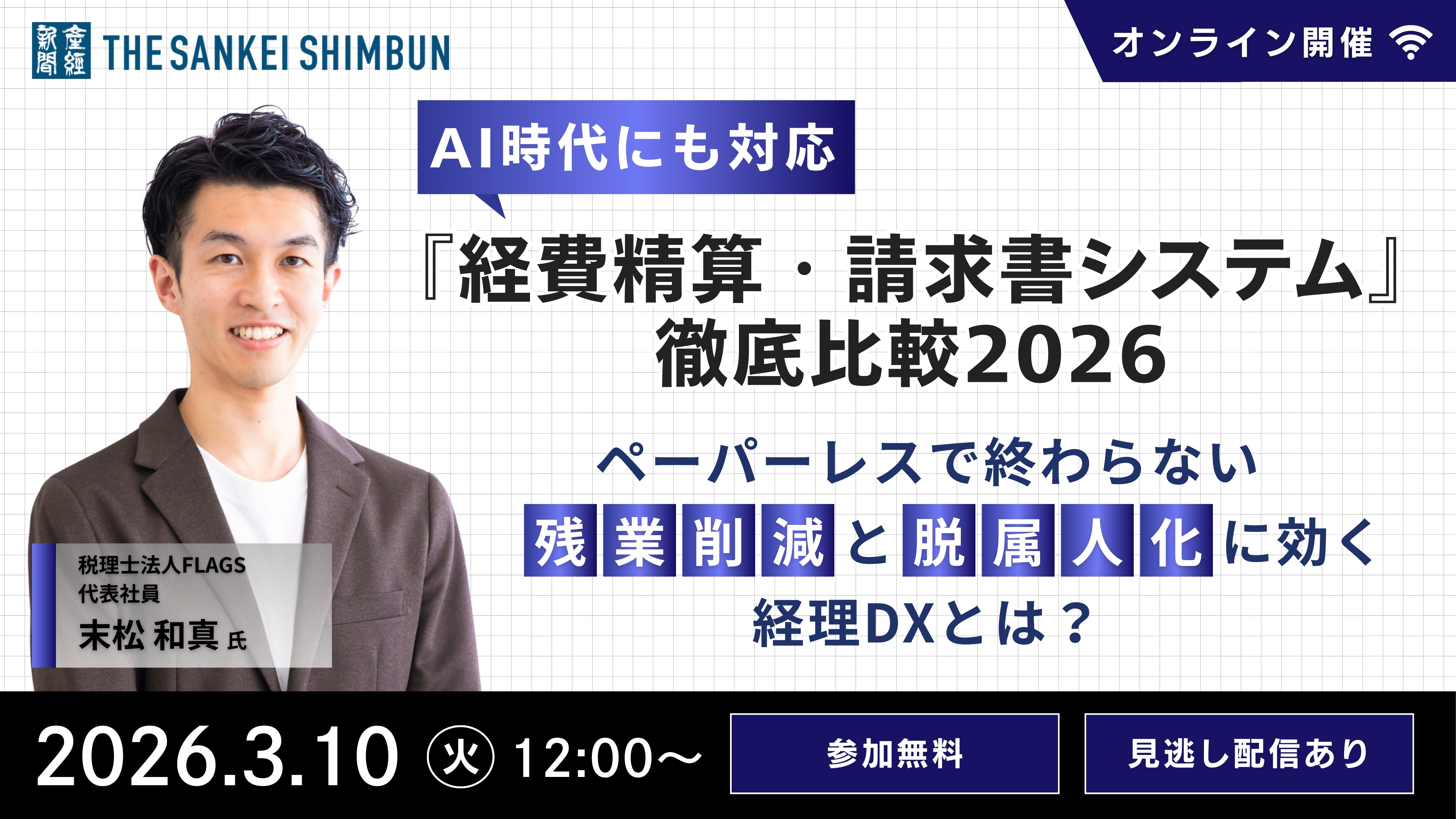公開日 /-create_datetime-/
「学歴は関係ない」はウソ?企業の採用活動で存在し続ける「学歴フィルター」とは
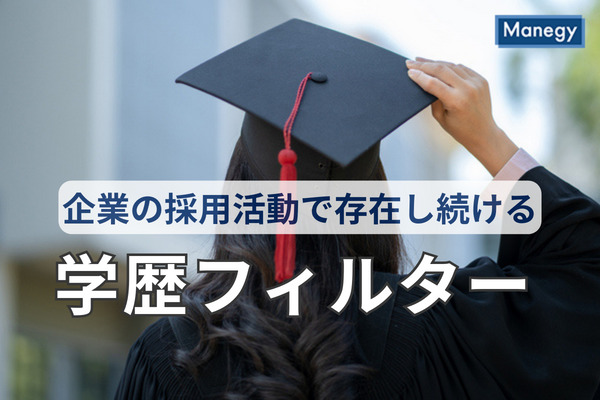
かつては大企業の新卒採用において「学歴フィルター」が設けられている、ということは暗黙の了解となっていました。
一方、「学歴は能力に関係ない」との声もよく耳にします。
そこで今回は、企業の採用活動における学歴フィルターの実情について深掘りしてみます。
目次【本記事の内容】
学歴フィルターとは?
学歴フィルターとは、入社希望者を在籍している大学名でふるいにかける採用システムのことです。この学歴フィルターにより、学校名で企業説明会の申込ができなかったりすることがあるようです。
具体例としては「国公立大学」や、「早慶以上(早稲田・慶應)」「MARCH(明治、青山学院、立教、中央、法政)」「関関同立(関西、関西学院、同志社、立命館)」などといった大学群以上の、いわゆる偏差値上位校かどうかで絞り込みが行われることがあります。
これらの大学以上の学生に対しては、ナビサイト上で説明会の予約ができるよう空席と表示され、それ未満の大学に在籍する学生には満席と表示されており予約ができない、というケースがあるのです。
学歴フィルターを企業が設ける理由
学歴フィルターを企業側が設ける理由の1つが、採用活動の効率化です。 大手・有名企業になるほど、少ない求人数に対して就職・転職志望者が殺到します。
採用担当者としては志望者すべての人柄、能力を吟味した上で採用したいところですが、採用担当の人員に限りがあるため、対応可能数には限度があります。そこで一定の条件を定めて書類選考の段階で分け、条件をクリアしている人だけ筆記・面接試験を受けさせる、という方法を取るわけです。
その際、基準とされているのが学歴です。学歴をフィルターとして設けている理由は、その学生が少なくとも「基礎的な学力を有している」「努力ができる人間である」と社内で説明しやすいからです。
とくに新卒・第二新卒の場合、企業としては採用した若い人材を育て、成長させることを大前提として採用します。学歴はそれらの教育をしっかりと吸収し、努力を続けられるかどうかと相関があると考えられているのです。
採用活動のオンライン化、デジタル化により学歴フィルターの重要性は低下
採用活動を効率化するために重視された学歴フィルターですが、近年、効率化という点での必要性は減少しました。というのも、IT技術の進歩により、オンラインによる迅速・効率的な筆記・面接試験が可能になったためです。
採用試験をオンラインで行えば、いちいち会場を用意したり、会場案内の書類作成をしたりする必要がなくなります。少数の採用担当者でも多数の入社志望者に対応しやすくなりました。
また、人材データのデジタル化により、入社志望者の学歴以外の特徴や能力(学生時代の社会活動経験、リーダー経験、アルバイト経験、クラブ・部活動の内容、取得済み資格など)も容易にチェック・検索できるようになり、学歴だけで分けることの重要性は減少しつつあります。
それでも依然として残る「学歴フィルター」
ところが、採用活動がオンライン化、デジタル化されてもなお「学歴フィルターを完全に取り払って良い」との見解は一般化しているわけではありません。ビジネスの場では、いまだに「学歴信仰」が存在しています。感覚的、習慣的に考える人はどの業界にも多数いるのが実情と言えます。
この点については、2021年に大手人材サービス会社で生じた、「大東亜以下」との件名を記したメールを学生に誤送信した問題が注目を集めました。この誤送信問題は、「採用活動のオンライン化・デジタル化の時代」においても依然として学歴フィルターが存在していることを、改めて証明することになったとも言えます。
学歴フィルターはインターンシップでも存在
新卒予定者の学生の能力を見極める場、さらに企業が求める人材として教育・研修する場として、学生インターンを募集する企業が近年多くみられます。とくに医療機器など理系人材を求める企業では、インターンに参加した学生の中から採用者を決めるというインターン選考を行うケースが多いです。
このインターンの場においても、参加学生に学歴フィルターを設ける事例が多くみられます。採用選考の意味合いがあるインターンの場合、やはり学歴フィルターを設けられている、という状況にあるようです。
まとめ
新卒採用を行う際の評価基準として、学歴が一定の基準になっている企業があるのは間違いないでしょう。いわゆる高学歴人材は、「継続的な努力ができる」「目標を達成する力がある」人材であることを一定程度証明できるからです。
しかし、学歴フィルターに頼りすぎることは、採用・選考基準の画一化をもたらし、採用する人材の多様性が欠けてしまうという面も否定できません。企業としては「学歴フィルター」に頼らず、自社の求める人材をできるよう採用活動を積極的に進めていく必要があるでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは
おすすめ資料 -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -
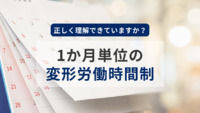
1か月単位の変形労働時間制|正しく理解できていますか?
ニュース -

業務改善とDXの基本から実践まで|成功事例と進め方をわかりやすく解説
ニュース -

採用を「運」から「設計」へ変える――役割貢献制度で実現する、ミスマッチゼロの要件定義とは?
ニュース -
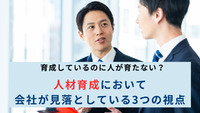
育成しているのに人が育たない?人材育成において会社が見落としている3つの視点
ニュース -

業務改善は「問題点の洗い出し」から|意味・手法・例までわかりやすく解説
ニュース -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
おすすめ資料 -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応
おすすめ資料 -

【中堅社員の意識調査】管理職志向のない中堅社員、管理職を打診されたら8.3%が「承諾」、25.1%は「辞退」
ニュース -

資本政策 事例|押さえるべき3つのポイントを事例を基に解説!
ニュース -

【調査】内定期間中に企業に求めるサポート1位「先輩との関係構築」。9割以上が人事の「不安・疑問への丁寧な対応」で入社意欲高まる
ニュース -

冬のボーナス支給、物価高の影響色濃く 日本インフォメーション調査
ニュース -
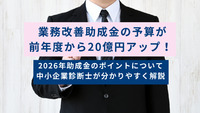
業務改善助成金の予算が前年度から20億円アップ!2026年助成金のポイントについて中小企業診断士が分かりやすく解説
ニュース