公開日 /-create_datetime-/
時価総額ランキング2023年版を解説!30年前と比べてどうなった?ランクインした日本企業は?

その企業がどれだけ社会の中で評価され、価値をもつ存在と認められているかどうかは、「時価総額」の指標で測ることができます。そして企業の時価総額を国ごとに見た場合、世界経済の実情を見る視点を得ることも可能です。
そこで今回は、1989年(平成元年)と2023年現在の世界の時価総額を比較し、約35年の間にどのような変化があったのかをひも解きます。
目次【本記事の内容】
時価総額とは
時価総額とは一般的に「株価×発行済株式数」で計算され、企業の価値を評価する指標となっています。
計算式からも明らかな通り、時価総額が大きいことは、それだけ投資家から「株式を購入したい」というニーズがあり、成長への期待が大きい企業であることを意味します。投資家に株式を買いたいと思わせているわけですから、時価総額が大きいほど、「業績がよい」「将来性がある」と投資家から評価されている企業なのです。
この時価総額は、国単位でまとめられ、各国間の比較指標として用いられることも多くあります。各国の上場企業の株式時価総額でまとめることで、「その国にどれだけ巨大な企業が存在しているのか」「業績がよく、将来性があると判断される企業がその国にどれだけ存在しているのか」を測定でき、各国の経済状況を比較することも可能です。
1989年(平成元年)は日本企業が世界時価総額ランキングのトップ10をほぼ占めていた
平成がスタートした1989年当時、日本はちょうどバブル期を迎え、経済は絶頂期にありました。「ビジネスウィーク誌(1989年7月17日号)」を元にダイヤモンド社が作成したデータによると、当時の全世界における時価総額トップ10は以下の通りです。
1位 NTT 1638億ドル
2位 日本興業銀行 715億ドル
3位 住友銀行 695億ドル
4位 富士銀行 670億ドル
5位 第一勧業銀行 660億ドル
6位 IBM 646億ドル
7位 三菱銀行 592億ドル
8位 エクソン 549億ドル
9位 東京電力 544億ドル
10位 ロイヤル・ダッチ・シェル 543億ドル
これは日本の時価総額ランキングではなく、全世界の時価総額ランキングです。つまり日本企業が世界のトップ10をほぼ占めていたのです。トップ10に入っている海外企業は3社だけで、残りの7社はすべて日本企業でした。
また、全世界の時価総額トップ50社で見た場合も、そのうち32社を日本企業が占めていました。平成元年には、日本企業はまさに世界に冠たる存在だったのです。
2023年9月時点の世界の時価総額ランキングは・・・
その後バブル崩壊が起こり、1990年代初頭には日本の地価や株価が急落し、景気も急速に冷え込んでいきました。その後も長い不況が続き、2010年頃には「失われた20年」、2020年頃には「失われた30年」と呼ばれたりもしました。この結果が時価総額ランキングにも明確に現れています。みずほ証券がまとめたデータによると、2023年3月末時点の世界の時価総額ランキングトップ10は以下の通りです。
1位 アップル 2兆6,090億ドル
2位 マイクロソフト 2兆1,460億ドル
3位 サウジ・アラビアン・オイル 1兆8,931億ドル
4位 アルファベット 1兆3,302億ドル
5位 アマゾン・ドットコム 1兆584億ドル
6位 エヌビディア 6,860億ドル
7位 バークシャー・ハサウェイ 6,756億ドル
8位 テスラ 6,564億ドル
9位 メタ・プラットフォームズ 5,494億ドル
10位 ビザ 4,753億ドル
2023年3月末の時価総額ランキングでは、10位以内に巨大IT企業(GAFA)など9社の米国企業がランクインしました。3位のサウジ・アラビアン・オイルはサウジアラビアの世界最大規模の石油会社です。4位のアルファベットは検索サイトや動画サイトのユーチューブを運営するあのグーグルの持ち株会社で、6位のエヌビディアはアメリカ最大の半導体大手企業です。
今や10位以内に日本企業は見る影もありません。同時期の日本企業トップはトヨタ自動車ですが、順位で見ると30位以内にも入っていません。
日本企業が時価総額ランキングの上位から転落した原因は?
現在の世界時価総額トップ10の状況から、日本企業の時価総額が伸び悩んだ要因が見えてきます。
2023年3月末時点のトップ10のうち、1~2位はいわゆるIT大手です。バブル期の頃、日本企業は世界時価総額トップを占めていました。当時はまだインターネットが社会に出回っていない時代で、当時の1位はNTTだったものの、基本的に電話通信業がメインでした。
バブル期が終わった1990年代後半以降、アメリカのアップル、マイクロソフト社などがけん引して世界的に情報革命が起こり、インターネットの時代が到来しました。その際、日本企業は、IT(情報技術)分野において自動車産業のような世界をリードする存在にはなれず、完全にアメリカ企業に追い抜かれました。
日本企業がIT分野の開発に遅れた理由は、「プログラミングに用いられる世界標準のプラットフォーム言語が英語であり、言葉の面でアメリカ企業より不利だったから」、「日本企業はハードウェア開発に偏ってしまい、ソフトウェアの開発と応用が遅れたから」などと言われています。
また、6位にアメリカ半導体大手のエヌビディアが入っているのも象徴的です。日本における半導体産業の衰退は、日本経済が伸び悩む一要因でもあるからです。
日本は1970年~80年代、世界の半導体市場で50%強のシェアを得ていましたが、2019年頃には10%程度まで減っています。 要因の1つとして、日本一強の状態に歯止めをかけるために、アメリカが「日米半導体協定」を結ぶよう要求したことが挙げられるでしょう。
この協定では「日本市場における外国製半導体の比率を20%確保する」といった取り決めがされ、これにより日本は外国製品の購買義務を負う形となりました(1986年に締結され、1996年まで継続)。完全に不平等な協定内容なのですが、これを受け入れたことで日本国内の半導体産業は下火になりました。
さらに製品に対する考え方の相違も挙げられます。日本企業は「耐久力があって長く使える質の高い半導体」を作ることに力を注ぎました。一方、韓国や台湾、中国などの企業は、「とりあえず数年動けばよい。どうせすぐにモデルチェンジもするから」という発想で国の保護を受けながら短期間のサイクルで製品開発を進めました。この違いが結果として、日本企業が最先端の半導体開発の場で後れを取る要因となった、といわれています。
まとめ
いまさら聞けないことは資料で解決!経理のお役立ち資料はこちら(無料)
1989年と2023年の世界時価総額のランキングを比較すると、30年前には存在しなかった米巨大IT企業(GAFAなど)が台頭し、日本企業のプレゼンスが非常に低下していることがわかります。国際競争力を高める人材への投資・イノベーションの創出が企業に求められています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧
おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは
おすすめ資料 -
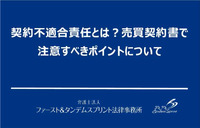
契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -
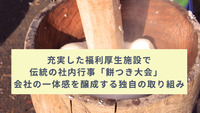
充実した福利厚生施設で伝統の社内行事「餅つき大会」 会社の一体感を醸成する独自の取り組み
ニュース -

キャッシュフロー計算書を武器にする|資金繰りに強い経理が転職市場で評価される理由(前編)
ニュース -
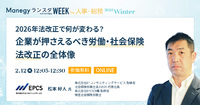
2026年法改正の全体像!労働・社会保険の実務対応を解説【セッション紹介】
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年1月10日・20日合併号(通巻No.1765)情報ダイジェスト①/税務
ニュース -

販売代理店契約における販売手数料の設計のポイントや注意点とは?サプライヤー側の契約審査(契約書レビュー)Q&A
ニュース -

生成AI時代の新しい職場環境づくり
おすすめ資料 -

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
おすすめ資料 -
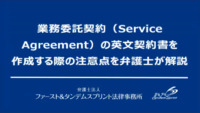
業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

事業用不動産のコスト削減ガイド
おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

「ディーセントワーク」の解像度を上げ、組織エンゲージメントを高めるには
ニュース -
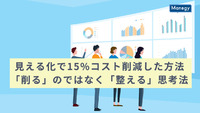
見える化で15%コスト削減した方法|「削る」のではなく「整える」思考法
ニュース -

法務担当者がM&Aに携わるメリットとは?市場価値を高める役割や必須スキルを解説(前編)
ニュース -
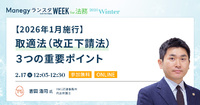
2026年1月施行!取適法の3つの重要ポイントを弁護士が解説【セッション紹介】
ニュース -
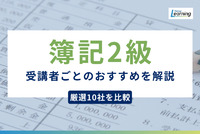
【厳選10社を調査】日商簿記2級講座の比較と受講者ごとのおすすめを解説
ニュース
























