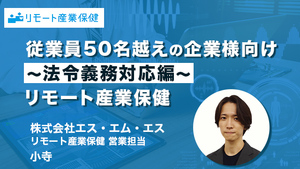公開日 /-create_datetime-/

企業が新規事業のために開発する新たな技術は、企業の財産と言えます。そんな財産である新たな技術を他社に模倣されないために、特許取得を考えることもあるのではないでしょうか。
今回は、特許の概要や申請方法を紹介します。
特許とは
特許とは、一定期間、一定条件のもとに、発明した技術を発明者が独占的に利用できるよう、特許庁が発明者に特許権を与えることをいいます。また、特許権そのものを意味する場合もあります。
特許庁によると、特許の根拠となる特許法の目的は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」こととなっています。
これは具体的には、特許を発明者に付与することで、下記を促進することを目的とします。
<特許の目的>
1.発明者が、他人に盗まれないよう発明したものを秘密にすることを防ぎ、発明者が有効的に発明した技術を活用できるようにする。
2.発明した技術を一般的に公開することで、他者が同一の技術開発のために研究時間や投資金を無駄にすることを防ぐ。
3.公開された技術を基に、さらなる改良や発展につながる機会を提供する。
このように、特許は発明者の開発した技術の保護という側面だけではなく、他者の技術開発を効率的に進めさせるという側面も持っています。
特許の取得方法
特許の取得は、①自分で申請し取得する方法と、②特許事務所などに所属する弁理士に依頼する方法があります。
自分で申請するメリットは、費用が抑えられる点です。
自分で申請する場合、20万円程度で申請できるのに対して、弁理士に依頼すると、40万円から100万円程度の費用がかかります。弁理士に支払う報酬には2種類あり、審査申込みをするまでの対価として払う手数料と、特許を取得できた場合に支払う成功報酬とがあります。どちらの報酬も、1案件に対して固定報酬で支払われる場合と、依頼案件の難易度によって報酬の金額が跳ね上がる場合とがあるので注意が必要です。
また、審査の過程で特許取得が拒絶された場合には、不服申し立てや特許申請内容の補正を行う必要があり、さらに弁理士への費用がかかります。
弁理士に依頼した場合、少なくとも自分で申請した場合の2倍は費用がかかることになるので、費用をできるだけ抑えたい人は自分で申請する方がよいでしょう。
一方、弁理士に依頼するメリットは、特定の知識を必要とする煩雑な手続きを特許取得の専門家にお願いできる点です。
特許承認は、発明した技術が自然法則を利用されているか、高度であるか、産業として利用できるか、新規性があるかなどにより総合的に判断されます。そのため、取得するためにはそれらの判断基準を踏まえて、発明技術を説明する細かな資料を作成しなければならないのです。場合によっては、かなり専門的な知識が必要になることがあります。
弁理士にお願いすれば、特許を取得するためのポイントを押さえながら、申込み資料の作製から、特許庁への申請まですべてをお願いすることができます。
特許の申請方法
それでは、特許の申請から取得までの流れをみてみましょう。
1.同一の発明がないかどうか確認する
まずは、自分が発明した技術と類似した技術が、既に特許を受けていないか確認しましょう。
特許情報プラットフォームで、自分の技術に関するキーワードを入力すると、キーワードに関連した特許があるかどうか検索することができます。
既に特許を受けている発明の場合は、残念ながら特許を取得することはできません。
2.申請書類を提出する
特許を申請するには、
- 特許願(願書。発明者や出願人を記載)
- 明細書(発明内容の記載)
- 特許請求の範囲(求める権利の範囲)
- 要約書(発明全体の概要)
- 図面(発明内容理解に役立つ図)
の5つの書類が必要です。特許の出願には14,000円の出願料がかかります。
出願手続きは、パソコンを使用した電子出願手続きと、特許庁への郵送もしくは窓口へ直接提出する方法があります。
3.審査請求の手続き
特許申請後から3年以内に、申請者は出願審査請求書を提出します。請求を受けて、特許庁は実体審査を行い、特許を付与できるかどうか判断します。審査請求料は118,000円+(請求項の数×4,000円)です。
4.審査結果
出願書類に法律上の不備がなく、実体審査で、特許を受けることができる発明と判定された場合は、特許査定が行われます。実体審査の結果、特許の拒絶理由を発見した場合、拒絶理由通知書が申請者に送られます。
5.審査結果への応答
拒絶通知書を受け取った場合、申請者は拒絶理由に対する意見書や、拒絶理由を解消するため申請書類を補正したものを提出します。そこで特許査定に進めなければ、さらに不服審判の請求や知財高裁への提訴などが必要になります。
6.特許の登録
特許を認められた申請者へ特許査定の謄本が送られるので、申請者は特許登録料1万円程度を納付しましょう。その後、数週間すると、正式に特許の登録が完了します。
まとめ
今回は、特許の取得には自分で取得する方法と、弁理士に依頼する方法があることや、特許登録までの手続きの流れを説明しました。
自信のある技術の開発に成功した企業の方は、費用対効果を考えながら、ぜひ特許を活用してみてください。
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-
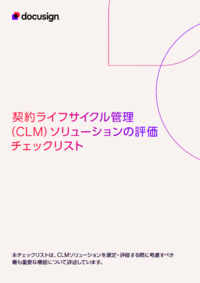
どう選ぶ?契約ライフサイクル管理(CLM)ソリューションの選定に役立つ評価チェックリスト
おすすめ資料 -
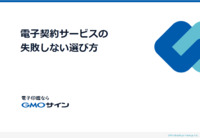
「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -
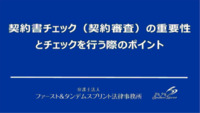
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -
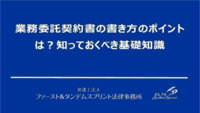
業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -
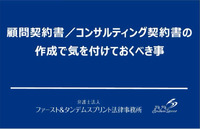
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -
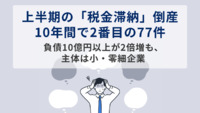
上半期の「税金滞納」倒産 10年間で2番目の77件 負債10億円以上が2倍増も、主体は小・零細企業
ニュース -

2025年「6月の振り返りと7月の準備」
ニュース -
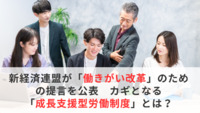
新経済連盟が「働きがい改革」のための提言を公表 カギとなる「成長支援型労働制度」とは?
ニュース -
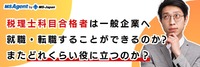
税理士科目合格者は一般企業へ就職・転職することができるのか?またどれくらい役に立つのか?
ニュース -
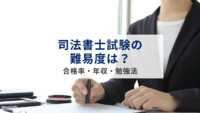
司法書士試験の難易度は?合格率・年収・勉強法まで徹底解説!
ニュース -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料
おすすめ資料 -
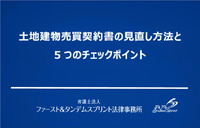
土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -
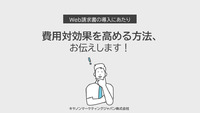
Web請求書の導入にあたり費用対効果を高める方法、お伝えします!
おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
おすすめ資料 -
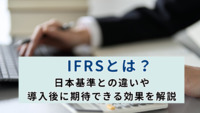
IFRSとは?日本基準との違いや導入後に期待できる効果を解説
ニュース -

【対談インタビュー】社員エンゲージメント向上はヒットを生み出すための事業戦略。株式会社ポニーキャニオンが取り組むデータドリブンな人事・組織改革とは
ニュース -
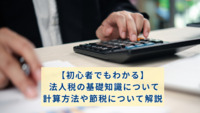
【初心者でもわかる】法人税の基礎知識について。計算方法や節税について解説
ニュース -

【法人向け】本当に安全なファイル共有ツールの選び方|セキュリティリスクと対策
ニュース -
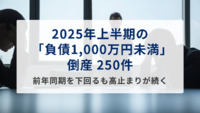
2025年上半期の「負債1,000万円未満」倒産 250件 前年同期を下回るも高止まりが続く
ニュース
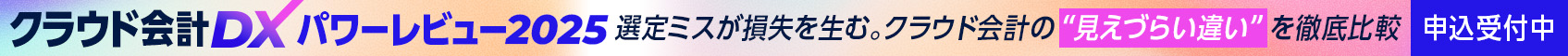









 ポイントをGETしました
ポイントをGETしました