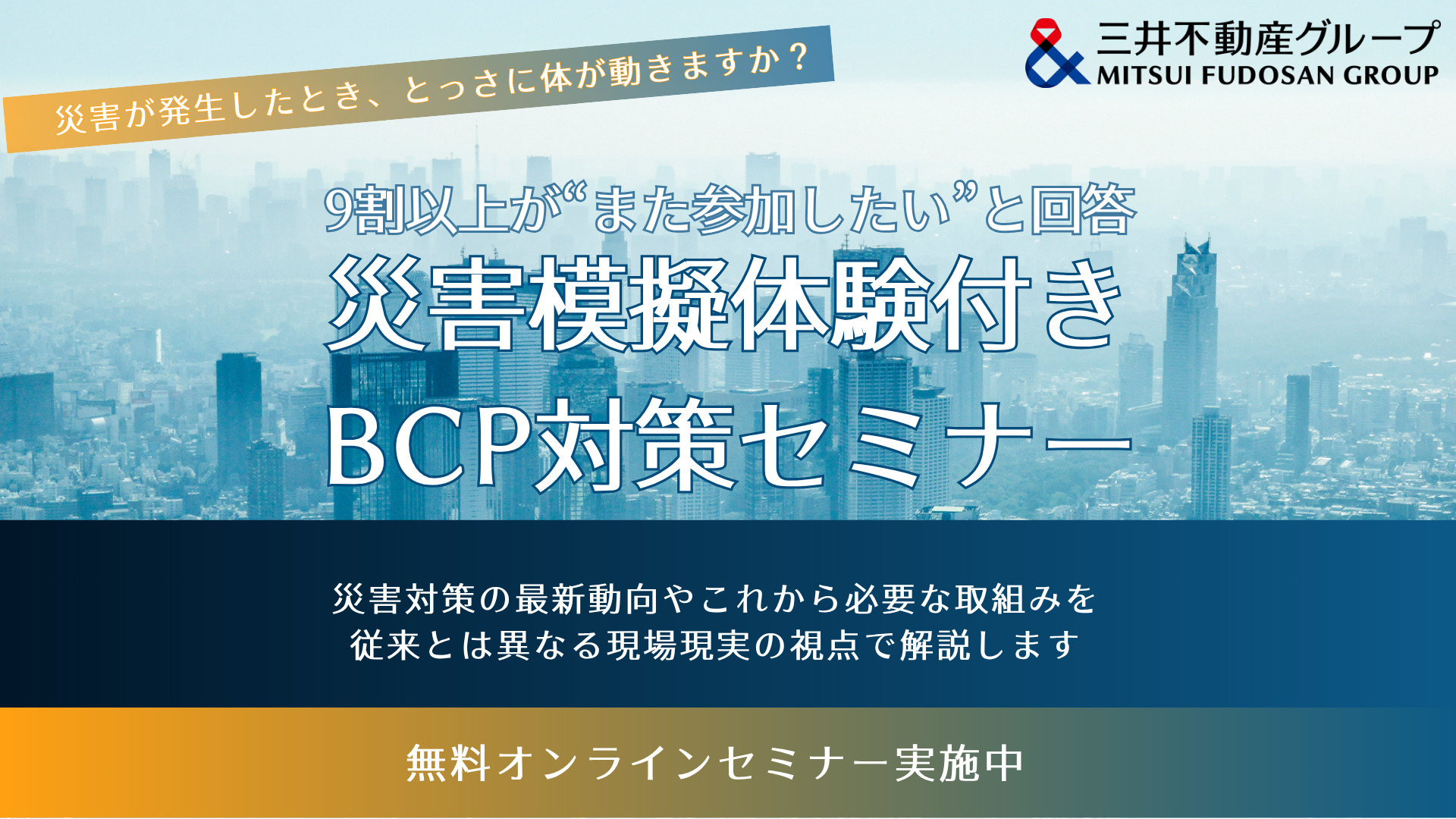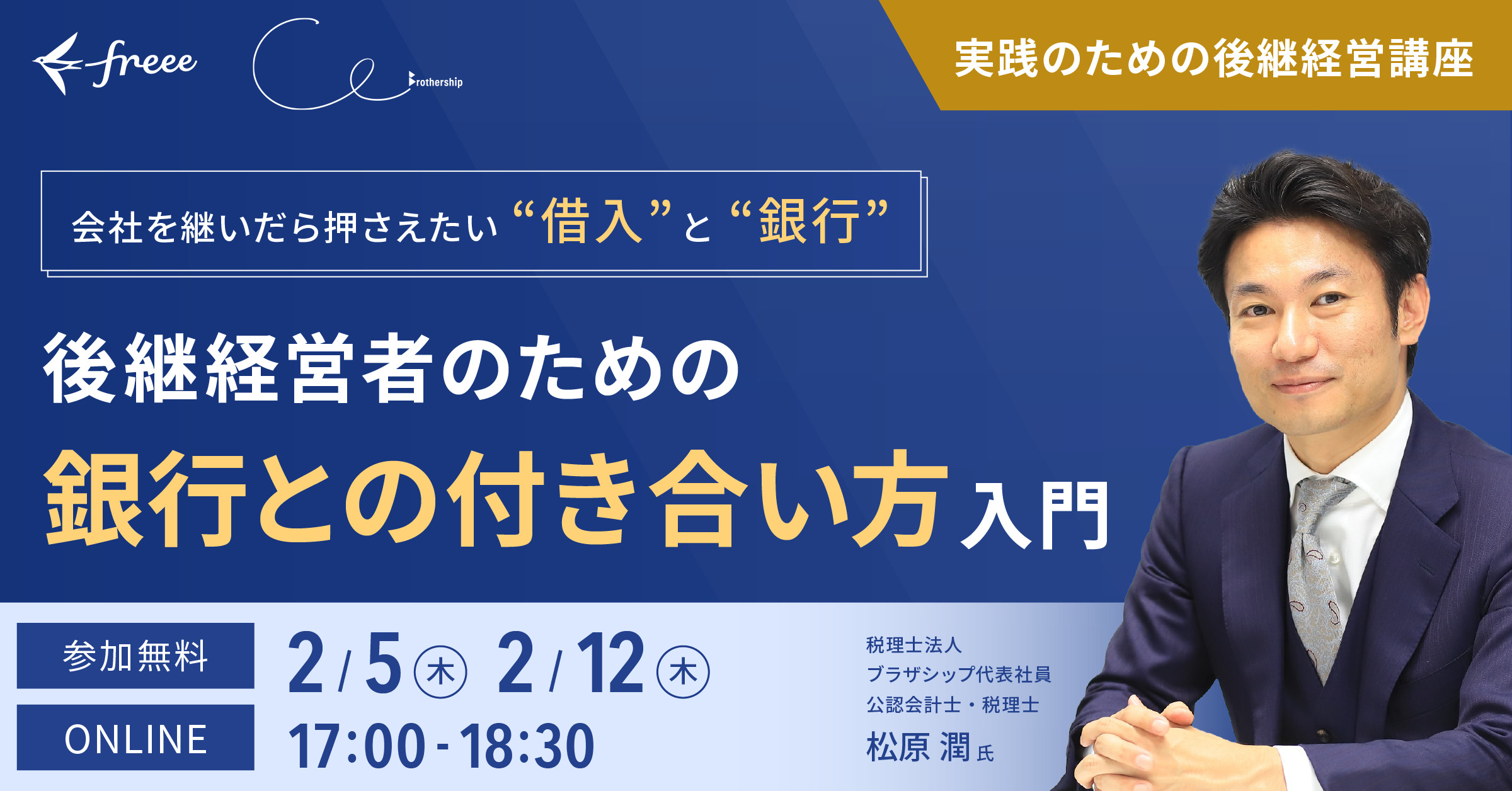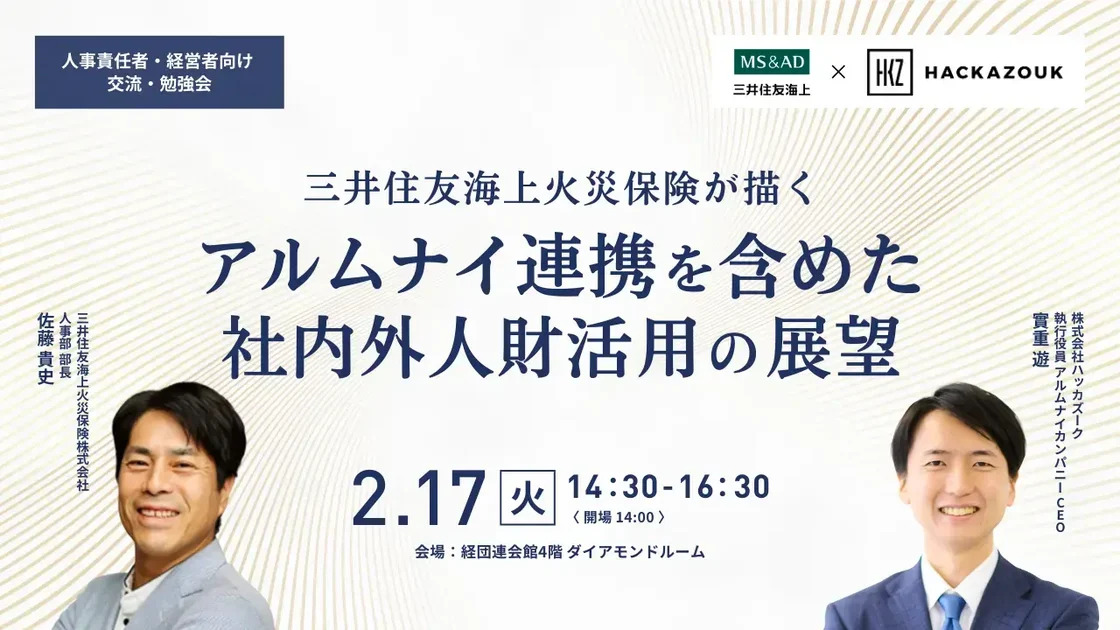公開日 /-create_datetime-/
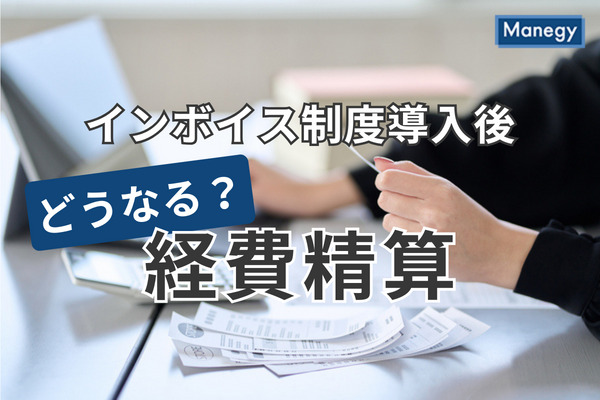
2023年10月1日からインボイス制度がスタートしました。今後は企業が仕入税額控除を受けるには、これまでの区分記載請求書ではなく適格請求書を受け取り、保管する必要があります。ただ、純粋な仕入れだけでなく、経費精算でもいくつかルール変更が生じているため、とくに経理担当の方は注意が必要です。 そこで今回は、インボイス制度施行後の経費精算のあり方について詳しく解説します。
インボイス制度がスタート
インボイス制度とは、仕入税額控除を受ける条件として「適格請求書(インボイス)」の受け取り、保存を定めた制度のことです。
仕入れ税額控除とは、消費税額の計算において仕入れにかかった分の消費税を差し引くことをいいます。消費税の二重課税を解消するために導入されています。
インボイス制度スタートの2023年10月1日からは、仕入先から「適格請求書(インボイス)」を受け取り、保管しなければ仕入税額控除は受け取れなくなります。適格請求書として認められるには、区分記載請求書の記載項目に加えて「適格請求書発行事業者としての登録番号」「税率ごとの消費税額」の記載が必要です。
仕入税額控除と経費の関係
インボイス制度で注意すべき点は、仕入先からの請求書だけでなく、コンビニのレシートや飲食店で受け取る領収書なども、「適格請求書」が必要になるという点です。
そのため、仕入税額控除を受ける場合は、取引を行う上で必要となった交通費、消耗品費、接待交際費など、従業員がいったん立て替えた経費についても金額にかかわらず、適格請求書である必要があります。もし適格請求書の要件を満たしていないときは、仕入税額控除は受けられません。
ただし、インボイス制度における経費の扱いに関しては細かい規定があるので注意が必要です。たとえば、従業員が出張する際に「出張旅費」として会社側が金額を支給する場合、「出張旅費特例」の対象となり、その際にかかる費用については一定事項を記載した帳簿のみの保存でよいとされています。
交通費に関しては、公共交通機関による運賃は3万円未満だと適格請求書が不要です。例外として、航空機・タクシーの運賃だと3万円未満であっても適格請求書が必要です。高速道路・駐車場の利用料も、金額に関係なく適格請求書が必要とされます。
接待交際費、消耗品費については、金額に関係なく適格請求書が必要ですが、「取引先と会議をする際に、提供用の飲み物を自動販売機で購入した」という場合は、「自動販売機特例」が適用され、3万円未満の金額であれば適格請求書は必要ありません。
インボイス制度施行後の経費精算のポイント
インボイス制度が施行された現在、経費精算を行う際は以下の点に注意する必要があります。
領収書がインボイス対応かどうかをチェック
現場で経費を立て替えた従業員が企業(経理部門)に提出する領収書などが、適格請求書の要件を満たしているかどうかをチェックする必要があります。
ただしこの際に注意すべきは、請求書を出している事業者が、「適格請求書発行事業者」ではなく「免税事業者」であることも考えられる点です。免税事業者が発行する請求書ではそもそも仕入税額控除は受けられないので、その点も含めて、領収書の内容を確認することが求められます。
税込3万円未満の場合でもインボイスを受け取っているか
以前は、仕入額が3万円未満の際は、必要事項が書かれた帳簿を保存さえしておけば仕入税額控除を受けることが可能でした。しかしインボイス制度施行後は、3万円未満の取引でも、仕入税額控除を受けるには適格請求書の受け取り・保管が必要です。
インボイス制度施行後の経費精算をスムーズにする方法
従業員への研修
経費精算で必要となる領収書、レシート、納品書なども適格請求書の対象となるため、従業員に対して、領収書等の内容を確認して適格請求書であるかどうかのチェック方法を周知することが大事です。
また、請求書の発行者が適格請求書発行事業者であるかどうかを確認してもらい、もし適格請求書を発行できないときの経費精算の方法などについても理解してもらう必要があります。新ルールを記載した簡単なマニュアル・資料を作成し、従業員に配布するのも1つの方法です。
免税事業者との取引方針
仕入先において、「適格請求書発行事業者」と「免税事業者」が分かれる場合も考えられます。その場合、免税事業者と引き続き取引を続けるのか、それとも適格請求書発行事業者とのみ取引を行うのかを検討する必要があります。免税事業者との取引を続ける場合、経費精算時にどのように報告するのかなど、一通り対応方法を事前に定めておくと経理業務をスムーズに行えます。
まとめ
インボイス制度の施行後は、仕入税額控除を引き続き受けるには適格請求書(インボイス)の発行が不可欠であり、これは原材料費だけでなく、交通費や消耗品費、接待交際費なども同様です。
しかも「3万円未満であるかどうか」など細かな規定もあるので、経費精算をスムーズに行えるように、経理部門のみならず従業員全体の間で新たなルールに対応できるよう対策をとることも大事といえます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -

【最大16,000円】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』に参加してAmazonギフトカードをGET!
ニュース -
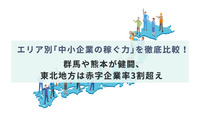
エリア別「中小企業の稼ぐ力」を徹底比較!群馬や熊本が健闘、東北地方は赤字企業率3割超え
ニュース -

出納業務とは?経理・銀行業務との違いや実務の流れをわかりやすく解説
ニュース -
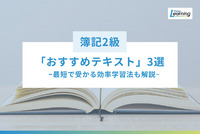
【社会人向け】仕事と両立で簿記2級に合格する「おすすめテキスト」3選。3級の知識が曖昧でも最短で受かる効率学習法も解説
ニュース -

レンタル料の勘定科目の考え方|賃借料・地代家賃・雑費の使い分けと仕訳例
ニュース -

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!
ニュース -
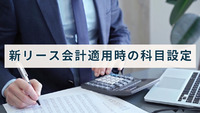
新リース会計適用時の科目設定
ニュース -

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念
ニュース -

多角化する企業グループで重宝される「子会社管理経験」|経理のキャリア価値とは(前編)
ニュース -

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く
ニュース