公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
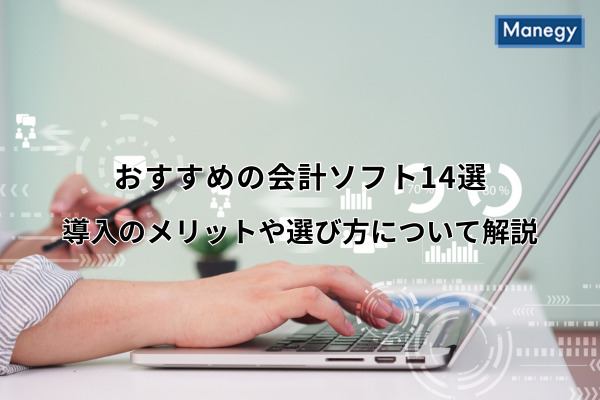
会計ソフトは会計業務の業務効率化に欠かせないシステムです。
会計業務は手間のかかる作業ですが、事業の売上や経費を管理し、適正な税金を納めるためにも避けられません。
会計ソフトは複雑な計算を自動で行い、会計業務の効率を上げてくれるため、ぜひとも導入したいシステムです。
しかし、会計業務に携わる人の中には、以下のようにお悩みの方もいるでしょう。
●どのような会計ソフトを選べばよいかわからない
●自社に最適な会計ソフトがわからない
●本当に導入する必要があるかわからない
本記事では、会計ソフトを導入するメリットや選び方のポイントを紹介します。
個人・法人別でのおすすめ会計ソフトや導入の流れについても解説しておりますので、会計ソフト選びの参考にしてください。
目次【本記事の内容】
会計ソフトは、売上や経費といった社内の金銭の動きを管理するソフトです。
複雑な計算や帳票の作成などの会計業務を効率的に行えるため、多くの企業で導入されています。
会計ソフトで作成できる具体的な帳票は以下のとおりです。
●現金出納帳
●賃借対照表
●損益計算書
●決算書
データを入力することで、帳票の作成時に必要な計算を自動で行え、業務を効率化できます。
会計ソフトを導入するメリットは以下のとおりです。
●業務を効率化できる
●ミスを軽減できる
●経費を抑えられる
●情報を一元管理できる
●経営判断の材料として使える
それぞれ解説していきますので、会計ソフトの導入に悩んでいる方は参考にしてください。
会計ソフトは業務を効率化するための機能が備えられており、記帳や帳票作成の手間を省けます。
たとえば、以下の機能が用意されています。
●各種帳票のフォーマット
●クレジットカードや銀行口座との連携機能
●自動仕訳機能
会計ソフトによっては、レシートの写真を撮るだけで自動で記帳してくれる機能やスマホ用アプリが用意されており、工数の短縮が可能です。
会計ソフトでは複雑な計算を自動化できるので、人為的なミスの軽減につながります。
主にキーボードの打ち間違いや、資料の見間違いなどによるケアレスミスの防止が可能です。
会計業務は事業規模が大きくなるほど、売上や経費などの数字が大きくなり、管理や計算が複雑になります。
帳票のミスは支払う税金にも影響を与え、大きな問題になりかねません。また、ミスをすると再度入力し直す必要があり、余分な工数が発生してしまいます。
ミスを減らすためにも会計ソフトの導入を検討しましょう。
法人の場合、経理業務に必要な人件費を削減できるため、会計ソフトの導入は、経費の削減につながります。
経理担当者の労力や手間を減らすことで、会計業務に使っていた時間を別の業務に取り組むための時間として使えます。
また、紙で帳票を管理している場合に発生する以下のようなコストも削減できます。
●紙代
●インク代
●封筒代
●切手代
2024年1月から電子データでの取引も義務付けられますので、会計ソフトを利用し、取引の電子化を進めていきましょう。
会計ソフトでは、ソフト内に帳票や顧客の情報を集約し一元的な管理ができます。
会計ソフト内でデータの保存が完了するため、紙で保存する必要がありません。
また、確認したい書類を簡単に検索できるメリットがあります。
紙で管理する場合、それぞれの取引を伝票に記載し、ファイリングしなければなりません。
必要な書類を探すのは時間がかかるうえに、保存する場所の確保も必要です。
しかし、データで一元管理することで、場所や必要書類を探す手間を省けるようになります。
取引が多い企業になるにつれて書類の数も増えていくため、会計ソフトで情報を管理することが重要視されています。
会計ソフトによっては、収支の分析レポートを作成してくれる機能がついています。
売上や経費から経営状況を判断でき、問題点の洗い出しが可能です。
たとえば、昨年同月の売上や経費のデータと比較し「売上が少ない」「経費を使いすぎている」などといった具合で、状況を報告してくれます。
自社のお金の流れをすべて把握し、合理的な経営を行う際にも、会計ソフトは一役買ってくれます。
会計ソフトのデメリットは以下のとおりです。
●コストがかかる
●操作スキルの習得に時間がかかる
●セキュリティに少し不安がある
メリットだけでなく、デメリットも把握することで、会計ソフトが必要かどうかをより深く検討できるようになりますので、ぜひ参考にしてみてください。
会計ソフトは導入費用と利用料がかかります。
一般的に、インストール型の場合は初期費用、クラウド型の場合は月々の利用料がかかるため、費用対効果を比較して導入する必要があります。
また、便利な機能が多数搭載されている高価な会計ソフトを導入しても、すべてを有効活用できなければムダな出費となります。
自社のニーズと各会計ソフトの機能を見比べ、最適なものを選びましょう。
会計ソフトの中には無料で利用できるものもあるので、コストを抑えたい場合は検討してみましょう。
会計ソフトの操作方法や機能を完全に理解するには時間がかかります。
とくに会計業務に不慣れな方は専門用語がわからず、マニュアルを読んでも理解できないことが多いです。
導入して最初のころは操作に慣れないため、一時的に工数が増えてしまうリスクがあります。
ただし、長期的には全員が使い慣れるようになるため、業務効率化につながります。
できるだけ早く操作を覚えられるよう、社内で研修を行うことも検討しましょう。
会計ソフトはデータが一元的に管理されているため、データの漏えいや不正アクセスが起こった際のリスクが大きくなります。
データの漏えいは、会社の評判を落とすことにつながるため、セキュリティ対策がしっかりとした会計ソフトを選びましょう。
会計ソフトの安全性の高さを調べる際は、以下のポイントを確認することをおすすめします。
●通信の暗号化の有無
●バックアップ機能の有無
●プライバシーマークの有無
会計ソフトだけではなく、社内のセキュリティ意識も重要となります。
IDごとの利用権限やデータの取り扱い方法を決め、社内での対策を徹底していくことが大切です。
会計ソフトを選ぶ際には以下の4つのポイントを押さえておきましょう。
●「個人事業主・フリーランス向け」か「法人向け」かで選ぶ
●「クラウド型」か「インストール型」かで選ぶ
●操作性で選ぶ
●機能で選ぶ
会計ソフト導入時の役に立ちますので、ぜひ参考にしてください。
会計ソフトを選ぶ際には、個人事業主・フリーランス向けの製品か、法人向けの製品かで選ぶことが大切です。
両者の具体的な違いは以下のとおりです。
会計ソフトは、「個人事業主・フリーランス向け」と「法人向け」で、機能の違いがあります。
「費用をかけて導入したのに欲しかった機能がない」という事態を防ぐために、事前の確認が重要です。
会計ソフトを選ぶ際には、クラウド型かインストール型で選ぶことも大切です。
クラウド型とインストール型のメリットとデメリットについては、以下のとおりです。
クラウド型はデータをクラウド上に保存するため、インターネットの接続があれば場所を選ばずに利用できます。
出張や社外での作業が多い場合におすすめです。
インストール型はPCや自社のサーバーにインストールするため、社内でしか利用できませんが、カスタマイズ性に富んでいます。
事務所でしか経理作業を行わない場合は、インストール型の会計ソフトがおすすめです。
会計ソフトは、操作性にも注目して選ばなければなりません。
操作性において、とくに以下のことを重視しましょう。
●動作の軽さ
●各書類のフォーマットの豊富さ
●操作画面のわかりやすさ
動作の軽さは、会計業務の作業スピードを上げるために重要な要素です。動きの遅い会計ソフトは、業務のスピードだけではなく、担当者のモチベーションにも関わるため、注意しましょう。
また、各書類のフォーマットが用意されているものを選ぶのもおすすめです。
すでにフォーマットが用意されている場合、Excelで関数を組んだり、表を作成したりする必要がありません。フォーマットに数値を入力するだけで書類の作成が完了するため、有効活用しましょう。
最後に、経理初心者の方でも操作できるかどうかも確認しましょう。専門用語が多い場合、内容を理解するだけで時間がかかってしまいます。
担当者が会計業務に不慣れな場合は、会計ソフトの操作画面のわかりやすさも重視してください。
自社のニーズに沿った機能をもつ会計ソフトを選びましょう。
会計ソフトによっては以下のような機能がついており、業務効率化を実現できます。
●AIによる勘定科目の自動仕訳
●クレジットカードや銀行口座との連携
●自社の基幹システムとの連携
ただし、便利な機能が増えるにしたがって、料金が上がる点には注意が必要です。
導入前に「必要な機能があるかどうか」「料金は予算の範囲内か」などを確認しましょう。
会計ソフトは、複数のプランが用意されていることも多いため、機能と料金のバランスを比較したうえで導入することをおすすめします。
会計ソフトを導入する際の流れは、以下の4つのステップに大別できます。
①導入の目的を定める
②導入スケジュールを立てる
③会計ソフトを決める
④会計ソフトを導入し、初期設定を行う
それぞれのステップについて解説していきますので、導入を検討している方は、参考にしてください。
会計ソフトを導入する前に、目的を明確にしておきましょう。
導入目的を明確にしておくことで、自社に適した会計ソフトを選べます。
目的を定めないまま会計ソフトを選んでしまうと、導入後に必要な機能がないことが発覚したり、余分な機能のあるソフトを導入して出費が高くなるリスクがあります。
目的を決める際には以下のポイントを意識してください。
●なぜ会計ソフトを導入するのか
●どのような問題を解決したいのか
自社のニーズに最適な会計ソフトを選ぶために、はじめに目的を明確にしましょう。
目的が決まったら、導入スケジュールを決めましょう。
導入スケジュールを事前に定めておくことで、スムーズに業務を移行できます。
会計ソフトの導入には、全社への周知や新たなマニュアルの作成など、多くの業務が必要です。
事前に必要なタスクを洗い出し、スケジュール通りに進めることで、チーム間で認識をあわせながら導入が可能です。
また、余裕を持ったスケジュールを組むことで、予想外のトラブルが起こった際にも対応できます。
社内から反対の声が上がったり、マニュアル作成が思うように進まなかったりした場合でも、柔軟な対処が可能です。
スケジュールの作成が決まったら、実際にどの会計ソフトを使用するか選びましょう。
基本的には導入目的に沿った会計ソフトを選べば問題ありません。ただし、条件を満たしているソフトが複数ある場合も想定されます。
無料トライアルを活用し、担当者が実際に使用した意見を参考にして絞り込むことをおすすめします。
会計ソフト選びが完了したら、実際に導入して初期の設定を行います。
具体的には以下のような項目を設定していきます。
●事業者情報
●会計年度
●消費税
●銀行口座
●開始残高
●バックアップの保存先
●パスワードや2段階認証
以上の設定が完了することで、運用を開始できます。
場合によっては会計ソフトが自社のパソコンで起動しなかったり、初期設定が思うように進まなかったりすることも考えられます。
トラブルが発生したら、初期設定サポートのサービスも行っているため、必要に応じてサービスを利用しましょう。
個人事業主・フリーランスの方におすすめの会計ソフトは、以下の7つです。
●freee会計
●やよいの青色申告オンライン・白色オンライン
●マネーフォワード クラウド確定申告
●HANJO会計
●みんなの青色申告
●やるぞ!青色申告
●勘定奉行
コスト面や機能など、個人事業主の方におすすめの会計ソフトをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
freee会計は、freee株式会社が運営するクラウド型の会計ソフトです。
クラウド型のため、Macユーザーの方でも使用できます。
AIによる自動仕訳機能がついているため、プライベートと事業用の口座を分けていない方でも、手間のかかる入力作業がいりません。
専用アプリも用意されており、スマホでレシートの写真を撮るだけで自動記帳が可能で、隙間時間を有効活用できます。
やよいの青色申告オンライン・白色申告オンラインは、やよい株式会社が運営する会計ソフトです。
青色申告オンラインと白色申告オンラインは、ともに個人事業主向けとなっており、自身の確定申告の種類に応じて選べます。
白色申告は完全無料で利用でき、青色申告は1年間の無料トライアルがついているため、開業を始めた方におすすめです。
マネーフォワード クラウド確定申告は、株式会社マネーフォワードが運営する会計ソフトです。
銀行口座との連携や、仕訳の自動入力機能を備えており、入力作業が簡単に行えます。
確定申告書の作成から書類データの提出まで作業を、出勤しなくても完了させられるため、在宅ワークの方に向いています。
HANJO会計は、カシオ計算機株式会社が運営するクラウド型の会計ソフトです。
飲食店経営に特化しており、会計業務に加えて事業推移や改善策の提案など、経営に関わるサポート機能が充実しています。
また、専用コールセンターも用意されているため、使用時に不明点があった場合も十分なサポートが受けられます。
飲食店を営んでいる個人事業主におすすめです。
みんなの青色申告は、インストール型の会計ソフトです。
「MoneyLink」があり、パソコンを起動するたびに金融機関から最新の利用明細のデータを受け取れます。
セキュリティーを重視しているかつ、便利な機能を求めている個人事業主に向いています。
やるぞ!青色申告は、インストール型の会計ソフトです。
macOSにも対応しているため、Macを使っているクリエイターの方でも安心して利用できる会計ソフトです。
パッケージ版とダウンロード版の2種類があり、どちらもAmazonや楽天といった大手ECサイトで購入可能なため、自宅に居ながら導入が完了します。
インストール型の会計ソフトを探している在宅ワークの個人事業主におすすめです。
勘定奉行は、株式会社オービックビジネスコンサルタントが発売しているインストール型の会計ソフトです。
Microsoft Officeと連携できるため、日々のデータをExcelで管理している場合でも簡単に移行できます。
Outlookと連携できるため、メールを使って帳票を送ることが多い方に最適です。
法人向けのおすすめの会計ソフトは以下のとおりです。
●弥生会計オンライン
●マネーフォワード クラウド会計
●freee会計(法人向け)
●弥生会計23
●フリーウェイ経理Lite
●Main財務管理
●会計王
それぞれ解説していきますので、法人向け会計ソフトを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
弥生会計オンラインは、弥生株式会社が運営する法人向けのクラウド会計ソフトです。
個人事業主向けとは違い、決算書の作成や「やよいの給与明細オンライン」と連携した給与管理が可能となっています。
また、データをクラウド上に保存しているため、どのパソコンからもログインが可能で、出張先やテレワーク時に自宅から会計業務を行える点も特徴です。
マネーフォワード クラウド会計は、法人向けのクラウド型会計ソフトで、決算書の作成が可能です。
また、従量課金制度を導入しており、以下のような業務に必要なものを選んで追加できます。
●クラウド請求書
●クラウド経費
●クラウド債務支払
●クラウド勤怠
●クラウド給与
●クラウド年末調整
●クラウド社会保険
●クラウドマイナンバー
●クラウド契約
請求書発行や給与管理といったメジャーな機能から、社会保険やマイナンバーの管理といったマイナーな人事労務まで、幅広く対応できます。
バックオフィス業務を一元化したい事業者におすすめです。
freee会計は、法人向けのクラウド型会計ソフトで、経理に不慣れな方でも使いやすいソフトです。
経理の入力作業を自動化してくれる上、インボイス制度や電子帳簿保存法にも完全に対応しているため、はじめての会計ソフトとして安心して利用できます。
個人事業主向けのサービスと同様、領収書の写真を撮ると自動で内容を読み取ってくれるため、入力の手間を省ける点も特徴です。
弥生会計23は、弥生株式会社のインストール型会計ソフトです。
初期設定の段階からサポートが手厚く、音声と動画による手順の解説や、業種別の勘定科目テンプレートが備えられています。
会計業務の効率化はもちろんのこと、資金繰りや経営分析・予算管理に関するレポートの作成ができるため、経営方針を決める手助けを行ってくれます。
フリーウェイ経理Liteは、Windowsでのみ利用できる無料会計ソフトです。
決算書や試算表などの帳票が、完全無料で作成から出力までできます。
また、会計ソフト以外にも以下のシリーズ製品が無料となっています。
●給与計算
●販売管理
●マイナンバー管理
●タイムレコーダー
必要最低限の機能がすべて無料で利用できるため、会計ソフトを無料で試してみたい場合におすすめです。
Main財務管理は、中小企業向けに開発された無料の会計ソフトです。
無料で決算書の作成が可能なため、コストを抑えたい事業者におすすめです。
また、財務管理に加え、以下の3つのシリーズ製品があります。
●販売管理
●給与管理
●グループウェア
すべてのソフトが無料で利用できるため、最低限の機能でも十分な人に向いています。
会計王は、27年のロングセラーを誇っているインストール型の会計ソフトです。
「みんなの青色申告」と同じ、ソリマチ株式会社が発売しており、MoneyLink機能を用いた金融機関との連携が可能です。
業種別のテンプレートや、仕訳に困った際に使える2,000件以上の事例を収録した「仕訳博士」など、初心者でも利用しやすい機能が揃っています。
青色申告決算書の作成にも対応しているため、法人だけではなく、個人事業主にもおすすめです。
しかし、多様な種類の会計ソフトがあるため、ソフト選びに悩んでしまいます。
自社の会計ソフトの導入する目的を明確にし、ニーズにあわせた会計ソフトの導入が重要になります。自社にあった会計ソフトを導入することで、経理や税務に関する業務負担を減らし、本業に力を注ぎましょう。
会計ソフト選びに迷った際は、本記事のおすすめや選び方を参考にしてください。
また、マネジーでは会計ソフトの資料をまとめて請求できるサービスを行っております。
導入前に資料を確認し、自社の業務効率アップにつなげましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

経理業務におけるスキャン代行活用事例

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
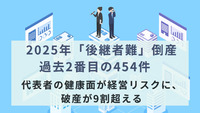
2025年「後継者難」倒産 過去2番目の454件 代表者の健康面が経営リスクに、破産が9割超える

トータルリワード時代の新しい人事制度 ~役割の「拡大 × 深化」を実現する役割貢献制度~

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!

セキュリティ対策評価制度自己評価の進め方

振り返りが回り始めた組織で起きる次の壁 ― 変革を続けられるかどうかを分ける「継続の関所」―<6つの関所を乗り越える5>

生成AI時代の新しい職場環境づくり

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

オフィスステーション導入事例集
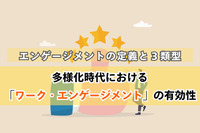
エンゲージメントの定義と3類型:多様化時代における「ワーク・エンゲージメント」の有効性

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念

ヒエラルキー組織における意思決定の高速化と最適化
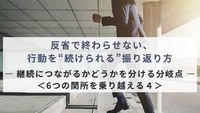
反省で終わらせない、行動を“続けられる”振り返り方 ― 継続につながるかどうかを分ける分岐点 ―<6つの関所を乗り越える4>

なぜ使われない?クラウドストレージ定着を阻む3つの壁
公開日 /-create_datetime-/