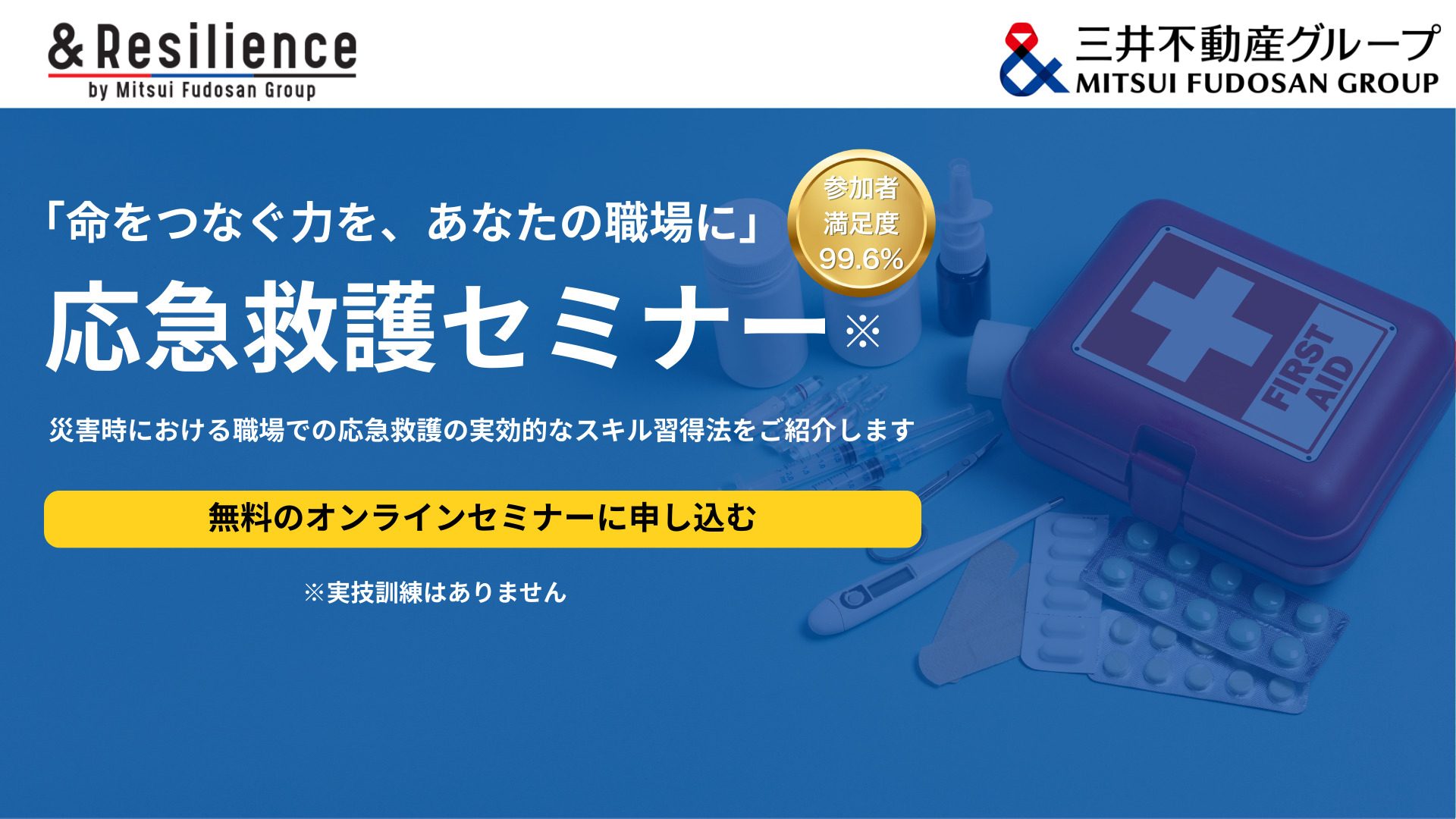公開日 /-create_datetime-/
2024年1月から贈与税の仕組みが変わる!改正のポイントをわかりやすく解説
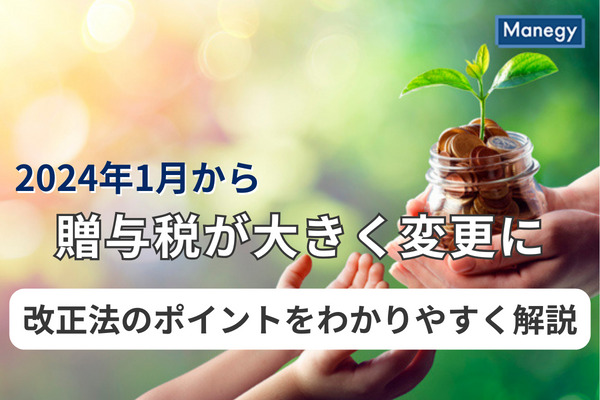
先日、税理士資格をもつYoutuber菅原 由一氏が全国の男女2,000人を対象にアンケート調査(株式会社スガワラくん調べ)*を行ったところ、2024年1月に贈与税が改正されることを知っている人が2割に満たないことがわかりました。
贈与税は相続に関わる重要な税制であるため、とくに高齢の親をもつ中高年世代は、ぜひ内容を押さえておきたいところです。そこで今回は、2024年1月から施行される贈与税の税制改正の内容について解説します。
贈与税とは?相続と密接に関わる税制
贈与税とは、存命の人から財産を譲り受けた際に課される税金です。「その年の1月1日から12月31日までの間にいくらの贈与を受けたのか」を元に計算されます。贈与税の対象となる財産には、現金だけでなく、不動産や自動車、貴金属なども含まれます。
なお、親が子どもに送る生活費、教育費などの仕送り、冠婚葬祭などの際にわたすお金、お正月のお年玉などは、高額でない限りは贈与税の対象とはなりません。
贈与税を理解する上でポイントになるのは、贈与税を支払う義務があるのは、財産を譲った人ではなく譲り受けた人、という点です。財産を譲り受けた人は、財産を受け取った翌年の確定申告期日(3月15日)までに税務署に申告する必要があります。
もう一つのポイントは、相続と密接に関係があることです。生きているうちに財産を譲り渡そうとすることを「生前贈与」といいますが、生前贈与の仕方によっては贈与税や相続税の課税対象になります。贈与をどのように受けるかによって、課税金額も変わってくるので注意する必要があるでしょう。
贈与税制で規定されている贈与の方法は、以下の2つがあります。
・暦年課税……1年間にもらう財産額が計110万円を超えた場合に、贈与税が発生する制度です。暦年課税制度にもとづいて贈与される場合、つまり贈与額が年間110万円までに収まっている限り、贈与税が課されません。ただし条件があり、現行法(2023年12月まで)においては、財産を譲り渡した人が贈与してから3年以内に亡くなった場合、譲り渡した財産は課税対象です。
・相続時精算課税制度……これは財産を譲り渡す父母・祖父母が60歳以上で、財産を譲り受ける子・孫が18歳以上である場合に選択できる制度です。相続時精算課税制度で財産を譲り受けた場合、その合計が2,500万円までで、かつ申告期限以内に申告すれば、贈与税は発生しません。2,500万円を超える分については課税対象とされます。
親・祖父母が子・孫に財産を贈与する場合、暦年課税か相続時精算課税のどちらかを選択する必要があり、一方を一度選んだら、選び直すことはできません。
なお、上記の内容は2023年12月31日までの規定です。2024年1月1日からは、改正税法が施行され、贈与税・相続税が改定されます。
2024年の贈与税および相続税の税制改革の内容
2024年1 月1日からの贈与税と相続税の改正される内容は、以下の通りです。
・暦年課税
譲り渡した財産のうち、年間110万円を超える部分について贈与税が発生する点は同じです。しかし、2023年12月31日までは、財産を譲り渡した人が亡くなる3年前から譲り受けた分が相続税の課税対象ですが、2024年1月1日からは、7年前から譲り受けた分が課税対象とされます。
・相続時精算課税
2024年1月1日からは、「年間110万円までは贈与税・相続税の対象外」とする新ルールが導入されます。累計2,500万円までは贈与税はかかりませんが、それを超過した部分には20%の贈与税がかかります。
税制改正を踏まえて節税のため対策すべきこと
税を納める側としては、当然ながら暦年課税と相続時精算課税のどちらがより節税できるかが注目ポイントです。この場合に重要になるのは、財産を譲り渡す側(親・祖父母など)の余命がどのくらいあるか、になります。「まだまだ健康で元気」であれば累計2,500万円という上限がなく、年間110万円以内であれば非課税になる暦年課税が有利です。
まとめ
コンプライアンスも扱う法務が業務に活かせる資料はこちら(無料)
2024年1月1日から施行される贈与税関連の改正税法をまとめると、
・暦年課税制度において、譲り受けた財産が相続財産に加算される期間は、「亡くなった時点の3年前」から「亡くなった時点の7年前」へと改定。
・相続時精算課税制度に基礎控除枠年110万円が設定。
の2点に集約できます。老親のいる方、あるいは自分の子・孫への財産の移転を考えている方は、早めに贈与・相続の対策を考えておくことをおすすめします。
*【調査概要】
調査期間:2023年12月5日
調査手法:インターネット調査
調査対象:40歳以上75歳未満の男女全国
サンプル数:2,000人
調査機関:Freeasy
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

優秀な退職者を「もう一度仲間に」変える 人材不足時代の新採用戦略
おすすめ資料 -

契約審査とは?担当者が迷わない流れとチェックポイント
ニュース -

新入社員の育成・活躍を促進するオンボーディングとは?
ニュース -
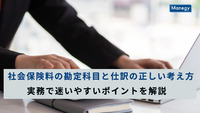
社会保険料の勘定科目と仕訳の正しい考え方|実務で迷いやすいポイントを解説
ニュース -

法務FAQ構築の手順とポイントを解説|AIを活用した効率的な運用・更新手法も紹介
ニュース -

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に
ニュース -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~
おすすめ資料 -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
おすすめ資料 -

AI時代のスキルと人材育成 ~AIが代替できない「深化」の正体とは?~
ニュース -

決算整理仕訳とは?仕訳例でわかる基本と実務の注意点
ニュース -
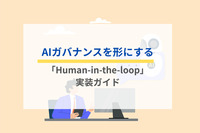
AIガバナンスを形にする「Human-in-the-loop」実装ガイド
ニュース -
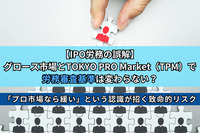
【IPO労務の誤解】グロース市場とTOKYO PRO Market(TPM)で労務審査基準は変わらない?「プロ市場なら緩い」という認識が招く致命的リスク
ニュース -

子育て座談会やバイアス研修で風土改革 モノタロウ、女性活躍最高位「プラチナえるぼし認定」取得
ニュース