公開日 /-create_datetime-/
法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?
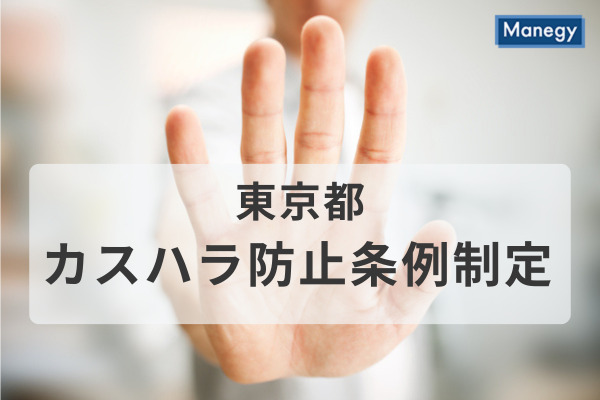
カスハラはカスタマーハラスメントを略した言葉で、パワハラやセクハラと並び、社会問題視されているハラスメントの一種です。現在、東京都が全国初となるカスハラ防止条例の制定を検討しています。4月22日に開催された検討会では、条例にてカスハラの定義、行為例の提示などを行うことが了承されました。条例制定に向けた動きが本格化しつつあります。
そこで今回は、東京都が条例で禁止しようとしているカスハラについて取り上げ、企業が取れる対策も含めて解説します。
昨年(令和5年)の10月、東京都では「カスタマーハラスメント防止対策に関する検討部会」を設立し、カスハラ防止条例の制定に向けて検討を始めました。自治体がカスハラに焦点を絞って条例制定を検討するのはこれまでに例がなく、先駆的な取り組みです。
東京都がこのような検討会を立ち上げた背景にあるのが、民間企業におけるカスハラ件数の増加です。
厚生労働省が民間のコンサルティング会社に委託し「職場のハラスメントに関する実態調査」を実施・公表しました(2020年10月3日~30日実施、全国の従業員30人以上の企業・団体を対象、回答回収数6,426件)。「過去3年間のハラスメント該当件数の傾向」を尋ねるアンケートでは、「顧客等からの著しい迷惑行為」について「事例の件数が増加している」との回答割合は19.4%でした。これはハラスメントの代表格とされてきたパワハラの11.4%、セクハラの8.1%を大きく上回る数値です。
しかも、パワハラとセクハラは「事例の件数は減少している」との回答割合が「増加している」よりも高く、総じて発生件数は減少傾向にあります。一方、カスハラの場合は「減少している」との回答割合は12.1%で、「増加している」の19.4%が大きく上回り、増加傾向が続いているのです。
パワハラ、セクハラは労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法などにおいて、ハラスメント対策が事業主に義務付けられています。しかしカスハラはそのような法的位置づけが不明確なのが実情です。このような状況に風穴を開けようとしているのが、東京都の条例制定に向けた動きであるわけです。
厚生労働省は、カスハラ防止に向けたマニュアルを企業向けに公表しています。その中ではカスハラのあり方として、「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く」「要求を実現するための手段・様態が社会通念上不相応」の2パターンが提示されています。
企業が提供する商品・サービスには瑕疵・過失が認められない場合や、要求の内容が企業の提供している商品・サービスとは無関係である場合に、商品交換や金銭補償、謝罪などを求める。
要求内容の妥当性に関係なく不相応とされる可能性が高い行為として、身体的な攻撃、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損など)、威圧的言動、土下座の要求、継続的で執拗な言動、拘束的な行動(居座り、監禁など)、差別的言動、性的言動、従業員個人への攻撃や要求が挙げられます。
こうしたカスハラ行為にともなって生じた行為に対しては、内容次第では傷害罪、暴行罪、恐喝罪、各未遂罪、強要罪、名誉棄損罪、侮辱罪、信用棄損および業務妨害罪、威力業務妨害罪、不退去罪などが適用されます。しかしこれらはカスハラに焦点を合わせた法律・罪ではないため、カスハラを抑止する効果は限定的といえます。
カスハラ防止条例の制定に向けた動きは始まったばかりで、しかも現状では東京都のみです。全国的にはこれからという段階で、実際にルール化がされるのはまだ先といえます。それまでは従業員を守るために、企業としてカスハラ対策を施していくことが重要です。
企業が取り組める対策としては、以下のものが挙げられます。
カスハラをしてくる顧客に対して、どのように対応すればよいのかをマニュアルとして現場社員に周知します。たとえば、顧客からの要求内容の事実確認を行う、現場の責任者を呼んで一人ではなく複数名で対応する、顧客の主張に耳を傾けるなどが挙げられます。どのような事態が起きた場合に、より上部の部署・機関(本部・本社を含む)に連絡すべきか、などの基準を設定することも必要です。
カスハラの判断基準や実際に起こったケース、発生パターン別の対応方法、苦情対応のフロー、顧客との話し方や接し方、記録の作成方法などを学習してもらいます。
カスハラに直面した従業員のケアを目的として設置します。従業員のその後の業務に支障が生じないように、臨床心理士との連携なども含めた必要な体制作りを行います。
企業・店舗数が多い東京都において、カスハラ防止条例の制定に向けた動きが生じるのは、近年のカスハラの増加傾向を踏まえるといわば自然な成り行きです。近年では、厚生労働省でもカスハラの調査や企業向けの指針策定を行っており、国・自治体が本格的に社会問題として扱い、解決に向けた施策を始めつつあるといえるでしょう。
ただ実際にカスハラに直面するのは企業であり、現場の従業員です。カスハラによって従業員の健康を損ねたり、離職者を増やしたりしないためにも、企業側は独自に対策を進める必要があるでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

経理業務におけるスキャン代行活用事例

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

2025年の「負債1,000万円未満」倒産 527件 3年ぶり減少も2年連続の500件台で高止まり
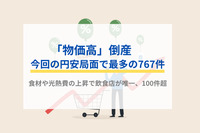
「物価高」倒産 今回の円安局面で最多の767件 食材や光熱費の上昇で飲食店が唯一、100件超
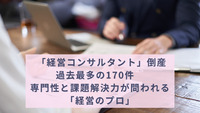
「経営コンサルタント」倒産 過去最多の170件 専門性と課題解決力が問われる「経営のプロ」
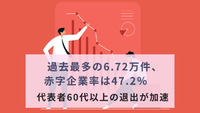
過去最多の6.72万件、赤字企業率は47.2% 代表者60代以上の退出が加速
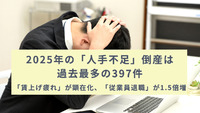
2025年の「人手不足」倒産は過去最多の397件 「賃上げ疲れ」が顕在化、「従業員退職」が1.5倍増

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
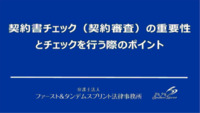
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

サーベイツールを徹底比較!
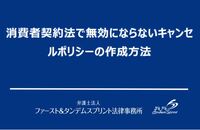
消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

旬刊『経理情報』2026年1月10日・20日合併号(通巻No.1765)情報ダイジェスト①/税務
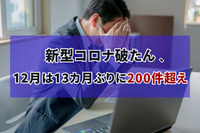
新型コロナ破たん、12月は13カ月ぶりに200件超え

【2026年新春】総勢300名様にAmazonギフトカードが当たる!Manegyお年玉キャンペーン開催中

2026年の展望=2025年を振り返って(13)
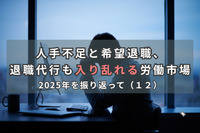
人手不足と希望退職、退職代行も入り乱れる労働市場=2025年を振り返って(12)
公開日 /-create_datetime-/