公開日 /-create_datetime-/
法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?
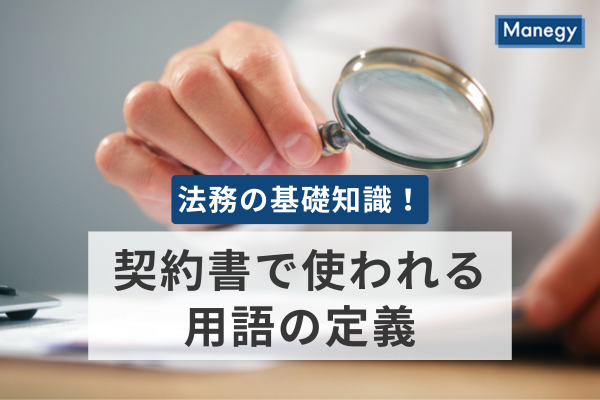
契約書には、法的な意味をもつ専門用語や定型句が多く含まれています。それぞれの表現を理解することで、契約内容を正確に把握し、誤解やミスを防げます。
相手方の提案に対して適切に反論したり、自分の希望を明確に伝えたりするためにも、専門用語や表現の知識が必要です。そこで今回の記事では、契約書で使われる用語をわかりやすく解説します。
契約書における「条」「項」「号」は、それぞれ異なる構造レベルを示す用語です。「条」は、契約書や法律の中で最も基本的な単位で、「第1条」「第2条」「第3条」のように数えられます。各条には、複数の「項」が含まれるのが一般的です。
「項」は、各条の中に含まれる細かい段落で、「第1条第1項」「第1条第2項」のように数えられます。それぞれの条でさらに具体的な規定や条件を示しており、項の中でさらに細かい内容や具体的な事項を「号」で表します。
まとめると、「条」「項」「号」の順に細かくなっていくため、基礎知識として押さえておきましょう。
契約書において「又は」と「若しくは」は、いずれも選択肢を示す言葉ですが、明確な違いがあります。「又は」は、同じレベルで並列する選択肢を示す際に使用されます。一方、「若しくは」は、「又は」によって区切られた選択肢をさらに細かく分ける場合に使う表現です。
実際の表現は、「契約の解除は、A若しくはB又はCによって行うことができる」といったイメージです。「AとB」「C」という大きなかたまりを「又は」でつなぎ、「AとB」をさらに細分化するために「若しくは」を使います。
もう少し日常的なもので考えてみると、たとえばマグロ、サーモン、牛肉の3つで表現する場合は、「マグロ若しくはサーモン又は牛肉」となります。
同じような話で、「並びに」「及び」も使い分けられます。大きい方に「並びに」、小さい方に「及び」を用いる形です。「並びに」が「又は」、「及び」が「若しくは」に対応すると理解するとわかりやすいかもしれません。
「善意」「悪意」も契約書によく登場し、混同しやすい表現として知られています。契約書や法律用語における「善意」と「悪意」は、当事者の心の状態や認識を示す言葉です。
「善意」とは、ある事実や状況について知らないこと、または気づいていないことを意味します。一般的には「知らなかった」や「認識していなかった」状態を指します。一般的な意味で使われる「善意」とは意味が異なるため注意してください。
「悪意」とは、ある事実や状況について知っていること、または気づいていることを意味します。一般的には「知っていた」や「認識していた」状態です。
たとえば「AさんがBさんから土地を購入した際、Aさんがその土地に未解決の抵当権が設定されていることを知らなかった」という場合、Aさんは善意の第三者とされます。「C社がD社から商品を購入した際、C社がその商品が盗品であることを知っていた」という場合、C社は悪意の第三者です。
「みなす」「推定する」は、一見同じような意味にも思われますが、厳密には異なる単語です。「みなす」とは、ある事実や状況が存在するものと確定的に扱うことを意味します。これは反証不可能であり、その事実が法律上の確定的な事実として扱われるのが一般的です。
たとえば「当該商品の納品は、甲の受領署名がある場合に完了したものとみなす」といった形で使用します。甲の受領署名があれば、納品が完了したと確定的に扱われ、異議を申し立ててもこの事実は変更されません。
一方で「推定する」は、ある事実や状況が存在すると仮定することを意味する表現です。その仮定は反証可能で、証拠や異議申し立てにより覆される可能性があります。たとえば「保証期間は、購入日から開始されたものと推定する」といった形で使用します。
まとめると、「みなす=確定的な事実であり、反証不可能」「推定する=仮定的な事実であり、反証可能」です。
契約書を読む場合のポイントは、契約書の全体をざっと読み、内容の大まかな構成や重要なポイントを把握することです。どのような項目があるのか、どの部分が重要そうかを理解します。
契約書の冒頭にある定義条項を確認し、契約書内で使用される専門用語や、特定の言葉の意味を理解するのも重要です。今回紹介したように、意味を混同しやすい表現もいくつかあるため、知識として蓄えておくことをおすすめします。
契約書の内容について、必要があれば相手方に確認することも重要です。相手方の理解や意図を確認すれば、誤解やトラブルを防ぎやすくなります。
契約書は法律的な文書であり、専門用語が頻繁に使用されます。また、複雑な文構造をもつことが多く、一文が長くなりがちです。日常生活ではあまり使われない用語も多く登場するため、内容の理解が難しくなるケースも多いでしょう。
契約書の内容を正確に理解することで、意図しないリスクを避けられます。契約書の書き方や読み方に関する知識をつけると、法務としての仕事もやりやすくなるでしょう。
■参考サイト
契約書管理システムとは? 活用するメリットと導入時に注意すべきポイントを解説
契約書レビュー必勝ガイド:法律知識不要で理解する方法
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
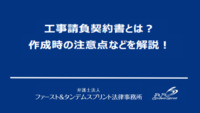
工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
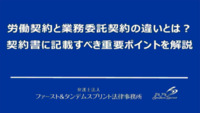
労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

弁護士業におけるスキャン代行活用事例
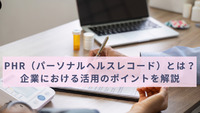
PHR(パーソナルヘルスレコード)とは?企業における活用のポイントを解説

賞与計算の実務ガイド|社会保険料・所得税の計算手順と注意点をわかりやすく解説

「ピープルマネジメント」で社員の能力を引き出す方法

SOMPOホールディングス、国内社員約3万人にAIエージェントを導入。業務プロセスを再構築し、生産性向上とビジネスモデル変革を加速

ビジョン浸透が組織を変える

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
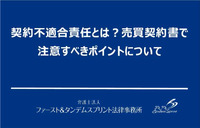
契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
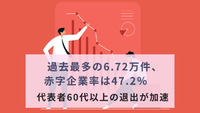
過去最多の6.72万件、赤字企業率は47.2% 代表者60代以上の退出が加速

ポジティブフィードバック/ネガティブフィードバックとは?使い分け・効果的なやり方をSBIモデルで解説

40年ぶりの労働基準法“大改正”はどうなる?議論中の見直しポイントと会社実務への影響を社労士が解説
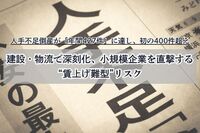
人手不足倒産が「年間427件」に達し、初の400件超え。建設・物流で深刻化、小規模企業を直撃する“賃上げ難型”リスク
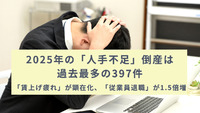
2025年の「人手不足」倒産は過去最多の397件 「賃上げ疲れ」が顕在化、「従業員退職」が1.5倍増
公開日 /-create_datetime-/