公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。

業務の効率化アップ、人手不足対策の手法として、企業において業務委託を活用するケースが目立ってきました。また、最近では働き方の多様化やネットを通して仕事を探しやすくなったことにより、業務委託で仕事をしようとする個人もいます。業務委託を巡っては、仕事を任せたい側、仕事を受けたい側の双方のニーズが高まっているのが現状といえるでしょう。
そこで今回は、業務委託とはどのような契約なのか、雇用契約との違いやメリット、デメリットについて詳しく解説します。
業務委託契約とは、企業・組織が業務の一部を外部の企業・個人に委託する際に結ぶ契約のことです。
近年では企業において、自社の従業員をコア業務に専念させるため、非コア業務を外部のフリーランスなどに業務委託するケースが増えています。またビジネスパーソンの間でも、最近では収入アップのための副業・兼業、パラレルワークに対する関心が高まりつつあり、その際に締結されるのが業務委託契約です。
委託の対象となる業務は多岐にわたり、製品製造、営業の代行、広告出稿、研修実施、コンテンツ制作、システム管理などがその一例です。
「業務委託契約」には、法律上の定義・位置づけはありません。しかし民法において業務委託契約の法的根拠とされる規定があり、その契約形態としては請負契約、委任契約、準委任契約の3種類が定められています。
民法632条において規定されている業務委託契約方式で、成果物の対価として報酬を支払うとする契約のことです。
契約上では、成果物を完成させて納品したかどうかのみが報酬を支払う上での条件であり、成果物を作るためどのような方法を採ったのか、どのくらいの時間をかけたのかなどが問われることはありません。デザイナーやプログラマー、ライター、自動車の整備士などが請負契約を結ぶことが多いです。
民法656条において規定され、法律行為ではない業務の遂行に対して報酬を支払う契約のことです。医療、研究・調査、受付、事務、マッサージ、不動産鑑定士サービス、コンサルタントなど、法律行為ではない業務を委託する場合に準委任契約が締結されます。こちらも委任契約の場合と同じく、所定の業務を遂行することで報酬が支払われます。
業務委託契約においては委託者側の企業が報酬を支払い、受託者側の企業・個人が報酬を受け取りますが、使用者(雇用主)と労働者(被雇用者)に分かれる雇用契約とは異なり、あくまで両者は対等な立場です。
業務委託契約の場合、委託する側には指揮命令権などはなく、どのように業務に取り組み完了させていくかは、受託者側が自らの裁量で決める形となります。
雇用契約では勤務時間、賃金、勤務地などの労働条件が事前に定められ、「労働への対価」としての報酬が支払われます。一方、業務委託契約では労働面の条件などはなく、支払われるのはあくまで「特定の業務の遂行、成果物への対価」としての報酬です。
業務委託契約のメリットとしては、委託者側、受託者側それぞれに以下の点があります。
委託者側の企業にとっての最大のメリットは、人手不足を補える点です。
業務によっては高度な専門スキル・知識も必要になりますが、それに見合った能力をもつ人材に、業務委託契約を通して業務を任せられます。デザイナーやシステムエンジニアなどがその典型例です。
また、企業として一時的に繁忙期が生じたとき、妊娠・出産などで一時的に従業員が欠員したときも、業務委託契約によって特定の期間だけ業務を任せることもできます。
さらに外部の企業・フリーランスに社内の周辺業務を任せることで、自社の正社員がコア業務に専念できます。社内の人材の効果的・効率的な活用が可能になるのです。
たとえば、受付業務や単純な事務作業、コールセンター業務などは、正社員でなくても業務委託契約で外部の人に任せることは十分に可能です。そうした業務を業務委託契約により外部の企業・個人に取り組んでもらうことで、自社の社員は本業に関わる重要な仕事に多くの時間を割けるようになります。外部の受託者には健康保険料・校正保険料の労使折半なども生じないので、その点でのコスト減も可能です。
受託者側の最大のメリットは、業務委託契約では業務を行う上で、契約相手から指示や命令を受けないため、伸びのびと自由度の高い仕事ができる点です。雇用契約のように労働時間や勤務場所の縛りもありません。
さらにどの業務を受けるかは、受託者側が選択できます。自分の自信のある分野で、報酬の高い業務に取り組めるように案件を厳選することも可能です。自らの意思で収入アップを目指しやすいです。
一方で業務委託契約においては、委託者、受託者のそれぞれに以下のようなデメリットもあります。
専門性の高い業務を委託しようとするほど、コストが高くなります。たとえば有名なクリエーターに発注すると、業務の遂行・成果物の質は高いですが、報酬額も大きくなってきます。また委託先によって遂行される業務の質、得られる成果物の質が変わることも多いので、どこに委託するかの選定に時間がかかることが多いです。
さらに業務委託契約では、業務を外部の企業・個人に丸投げする形となるため、自社の社員が業務を通して経験・スキルアップさする機会を奪い、社内にノウハウの蓄積も生じません。
収入・キャリアの安定が難しい点が大きなデメリットです。得意とする分野について業務委託しようとする企業が常にあるとは限らず、仕事をしていくには自分で案件を見つけていく必要もあります。
また個人の場合、社会保険料の支払い、帳簿管理、確定申告などをすべて自分で行う必要があり、本業以外の作業も多いです。労働基準法で定められている各種労働者保護の規定は、フリーランス・個人事業主には基本的に該当しないため、休日の確保や体調管理はすべて自分で行う必要があります。
近年ではIT分野に代表されるように、自由な働き方をするために、雇用契約から業務委託契約への変更を臨むビジネスパーソンも登場しています。労働時間や勤務場所に捉われず、自分の力量に応じた報酬をもらえるので、その点に魅力を感じるのでしょう。また企業側にとっても、人材不足の解消・即戦力の活用などを目的に、業務委託契約を活用しようとする動きが増えています。
しかし業務委託契約には、受託者側と委託者側の双方にとってデメリットがあるのも確かです。実際に契約を締結する際はメリットとデメリットを比較し、得られる利得の方が大きいかどうかを十分に検討する必要があります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!

ライセンス契約とは?主な種類・OEM契約との違い・契約書の記載項目までわかりやすく解説

2025年の「負債1,000万円未満」倒産 527件 3年ぶり減少も2年連続の500件台で高止まり

OEM契約とは?メリット・デメリットからOEM契約書の重要条項まで整理
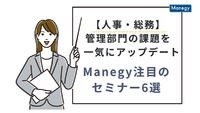
【人事・総務】管理部門の課題を一気にアップデート。Manegy注目のセミナー6選

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

生成AI時代の新しい職場環境づくり
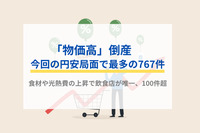
「物価高」倒産 今回の円安局面で最多の767件 食材や光熱費の上昇で飲食店が唯一、100件超
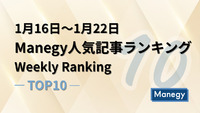
1月16日~1月22日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
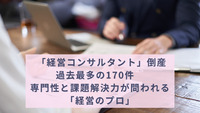
「経営コンサルタント」倒産 過去最多の170件 専門性と課題解決力が問われる「経営のプロ」
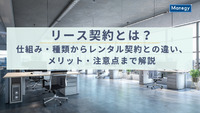
リース契約とは?仕組み・種類からレンタル契約との違い、メリット・注意点まで解説
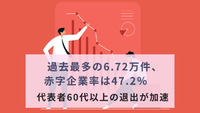
過去最多の6.72万件、赤字企業率は47.2% 代表者60代以上の退出が加速
公開日 /-create_datetime-/