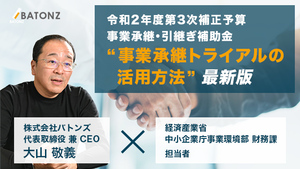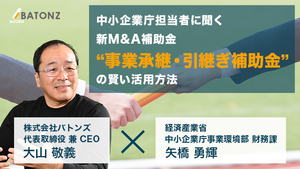公開日 /-create_datetime-/
ビジネスパーソンが知っておきたい節税の知恵

3/15をもって、確定申告の期間が終了しました。会社勤めの場合は、会社が本人に代わって税金の手続きをしているため、自営業者に比べると、あまり「節税」という意識をもっていないかもしれませんが、会社員でも確定申告をすることで、払いすぎた税金が戻ってくることがあります。
今回は、簡単にできる賢い節税対策についてご紹介します。
給与所得者もできる節税対策
1月1日から12月31日までの1年間に得た総収入(所得)に応じて課せられるのが所得税です。会社にフルタイム勤務の場合は、所得額が明確なため、何もしなければ、ほぼ機械的に税額が決まってしまいます。
しかし、人によっては、所得金額から一定の金額が控除されることがあります。所得から控除される額が多ければ多いほど、税額は低くなるので、受けられる所得控除をしっかりと受けることが節税につながることとなります。
所得から控除される所得控除
所得金額から、以下の14の控除額を差し引いて、所得税額が決まりますが、所得控除は、それぞれの生活状態によって変わってきます。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄付金控除
- 障害者控除
- 寡婦・寡夫控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
課税所得から差し引かれる税額控除
所得額から所得控除を引いたものが課税所得となり、そこに税率をかけて税額が算出されますが、その金額から税額控除を差し引いて、実際に納める税額が確定します。給与所得者である会社員に関係のある税額控除となるのは、以下の10項目です。
- 配当控除
- 住宅借入金等特別控除
- 認定住宅の新築をした場合の特別控除
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除
- 特定の改修工事等をした場合の特別控除
- 耐震改修工事をした場合の特別控除
- 政党等寄付金特別控除
- NPO法人等に寄付をした場合の特別控除
- 公益社団法人等に寄付をした場合の特別控除
- 外国税額控除
節税効果の高い住宅ローン減税
給与所得者の節税効果が、もっとも高いのが住宅ローン減税です。住宅ローンを利用して、マイホーム新築・購入、増改築をしたときは、10年間、一定金額を控除することができます。
控除の適用となるのは、新築住宅の取得のケース、中古住宅の取得のケース、住宅の増改築等のケースによって適用条件は異なります。ただ、通常のマイホーム取得なら、ほぼ条件を満たすことになりますので、住宅ローン減税の恩恵を受けることができます。
いつ購入し、いつから居住するようになったかによっても減税額は変わってきますが、平成26年4月~平成33年12月の場合、住宅ローンの年末時点での残高(限度額4,000万円)の1%が10年間控除されます。年間最高控除額は40万円で、10年間の合計額の最高は400万円となりますから、きわめて高い節税効果となります。
見逃せない生命保険料控除・地震保険料控除
意外に見逃せないのが、生命保険や地震保険などの保険料です。生命保険、火災保険、損害保険、地震保険など、数種類の保険に加入している方も多いのではないでしょうか。
保険料の控除は、支払額の全額ではなく、一定額を控除するものですから、それほど節税効果は期待できないと思っているでしょうが、年末調整のときに、保険会社から送付されてくる「証明書」を、会社に提出するだけですから、これは忘れずにやっておきましょう。
生命保険料控除の対象となるのは、保険会社と契約している生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料です。契約した日や保険料の額によって、控除額は違ってきますが、塵も積もれば…です。
地震保険料控除の対象となるのは、損害保険会社や外国保険会社と契約した損害保険契約、農協、漁協、生協などと契約した火災共済・自然災害共済にかかる契約、財務大臣が指定した教職員共済生活協同組合などの各種共済生活協同組合の保険で、常時居住する家屋や生活用資産にかけられたものです。
事業用の建物や機械、器具などは、地震保険の対象とはならず、事業の場合は、必要経費に算入することができます。
その他にも、節税につながる控除がいろいろあります。たとえば、納税者本人はもちろん、家族の病気やケガなどで、多額の医療費を支払った場合も、所得金額から控除することができますので、医療費の領収書や明細書は、残しておく習慣をつけましょう。
まとめ
給与所得者である会社員の節税対策の手続きには、年末調整のときに書類を提出するだけでいいもの、確定申告が必要なものがあります。控除の対象となる項目や、条件もそれぞれ違って複雑です。経理担当者は、もし、社員から節税についての問い合わせがあったときには、わかりやすく説明できるようにしておくと親切でしょう。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください。
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

郵便DXによる業務効率化事例 - 郵便物受領の外注化とDX化による部署別の効率化事例 -
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
おすすめ資料 -
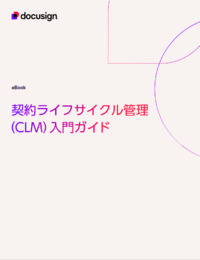
法務部の負担を軽減!「契約ライフサイクル管理システム(CLM)」のキホンを徹底解説
おすすめ資料 -

【累計視聴者数73,000人突破】『ManegyランスタWEEK -2025 Spring-』開催決定!
ニュース -
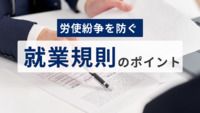
労使紛争を防ぐ就業規則のポイントとは!?弁護士が解説【セミナーレポート】
ニュース -

【税理士事務所執筆】税務調査とは?管理部門向けチェックリストと対応方法を解説
ニュース -

認知度がいまいちでも人が集まる!「採用マーケティング」の始め方【前編】
ニュース -

企業間で広がる「旧姓の通称使用」への理解、約6割が容認 課題は社外手続きの負担 TDB調査
ニュース -
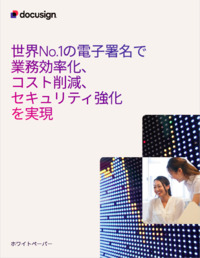
世界No.1の電子署名で業務効率化、コスト削減、セキュリティ強化を実現
おすすめ資料 -

【無料】データ活用をスマートに、強力に、簡単に行うには
おすすめ資料 -

BillOneの導入で請求書業務はこう変わる
おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -

押印に合わせた電子署名形態の選択
おすすめ資料 -

【会計】新リース会計基準に伴う改正財規等、公布─金融庁 旬刊『経理情報』2025年4月10日号(通巻No.1740)情報ダイジェスト①/会計
ニュース -

IPO(新規株式公開、株式上場)とは?上場の意味・目的・経営者の心構えを解説
ニュース -
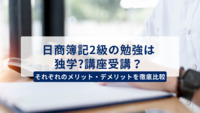
日商簿記2級の勉強は独学?講座受講?それぞれのメリット・デメリットを徹底比較
ニュース -

コーチングを職場で実践するには?適した場面や必要なスキルについて詳しく解説
ニュース -
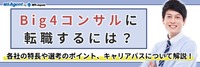
Big4コンサルに転職するには?各社の特長や選考のポイント、キャリアパスについて解説!
ニュース