公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

2023年4月、デジタル給与(給与デジタル払い)が解禁されました。しかし、その後1年以上経過しても、デジタル給与が実用化されたというニュースは聞こえてきません。
ところが、2024年8月9日になって初めて、デジタル給与の指定資金移動業者が認定されました。いよいよデジタル給与の運用が始まるのか、この記事ではデジタル給与の基本について解説します。
デジタル給与とは、給与を電子マネーで支払う仕組みです。具体的には、従業員が特定の資金移動業者に口座を開設し、そこに会社側が給与を振り込むという方法であり、従来の銀行口座振り込みとは異なります。ただし実際に利用する場合は、資金移動業者の口座と銀行口座をひも付ける必要があります。
2024年7月31日時点で、金融庁財務局に登録されている資金移動業者は82社ありますが、デジタル給与のサービスを提供するためには、厚生労働省による審査で認定されなければなりません。今回PayPayが第一号に認定されたことで、ようやくデジタル給与が実用段階に入ったといえます。
今後デジタル給与の運用が開始されると、会社と従業員の双方にとって次のようなメリットが生じます。
会社にとっては、これまでの銀行口座への振り込みよりも、デジタル給与のほうが手数料コストを削減できる可能性があります。一般的に資金移動業者のほうが、手数料が低く設定されているからです。
また、従業員ごとに異なる銀行口座に振り込む手間も省けるでしょう。
すでにキャッシュレス決済が一般的になっているため、デジタル給与が可能になると、銀行口座から決済サービスへのチャージが不要になります。給与の一部だけをデジタル給与にすることもでき、生活に合わせた利便性も向上するでしょう。
一方でデジタル給与には、以下のようなデメリットも考えられます。
デジタル給与には、支払方法にいくつかの選択肢があり、従業員は自分の意思で選べます。そのため会社側は準備や管理の手間が増大する可能性があります。場合によってはシステム化を検討するべきかもしれません。
給与計算システムの詳細については、以下のページでご確認ください。
https://www.manegy.com/service/payroll/
今後運用が開始されても、デジタル給与の資金移動業者が限定される可能性があります。その場合、会社が決めた資金移動業者に口座をまとめる必要があるでしょう。
デジタル給与を導入する場合、会社側は以下に挙げる手順に沿って手続きを進める必要があります。
・従業員の意向調査/アンケート
・資金移動業者の選定
・労使協定の締結
・就業規則の改定
・従業員への説明
・従業員の同意確認と同意書の作成
・導入に関わる事務処理
デジタル給与導入の詳細な手続きについては、以下のページでご確認ください。
運用開始に向けて一歩前進、給与デジタル払いの導入に必要な準備と手続きとは?
国内でもキャッシュレス化が進み、今後デジタル給与が普及するのも時間の問題でしょう。ただし、デジタル給与の導入は各企業の任意であり、従業員も各自の希望で利用が決まります。また現状では、いつから開始されるのかも明らかになっていません。
企業と担当者はメリットとデメリットを比較し、従業員の意向も確認したうえで、デジタル給与の導入を検討する必要があるでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

経理業務におけるスキャン代行活用事例

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

英文契約書のリーガルチェックについて

外国人を雇用する際の雇用保険はどうする?注意点について国際業務に詳しい法律事務所が解説

ダイバーシティ推進の現在地―人事1000名の声から読み解く現状と未来予測―

労使および専門家の計515人に聞く 2026年賃上げの見通し ~定昇込みで4.69%と予測、25年実績を下回るも高水準を維持~

労基法大改正と「事業」概念の再考察② ~場所的観念から組織的観念へのシフト~
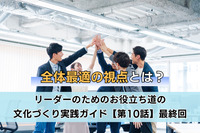
全体最適の視点とは?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第10話】最終回

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

【1on1ミーティング】効果的な実践方法と運用時のポイント

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

新入社員の育成・活躍を促進するオンボーディングとは?

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に

AI時代のスキルと人材育成 ~AIが代替できない「深化」の正体とは?~
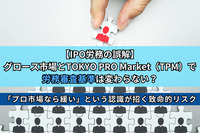
【IPO労務の誤解】グロース市場とTOKYO PRO Market(TPM)で労務審査基準は変わらない?「プロ市場なら緩い」という認識が招く致命的リスク
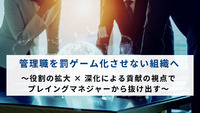
管理職を罰ゲーム化させない組織へ ~役割の拡大 × 深化による貢献の視点でプレイングマネジャーから抜け出す~
公開日 /-create_datetime-/