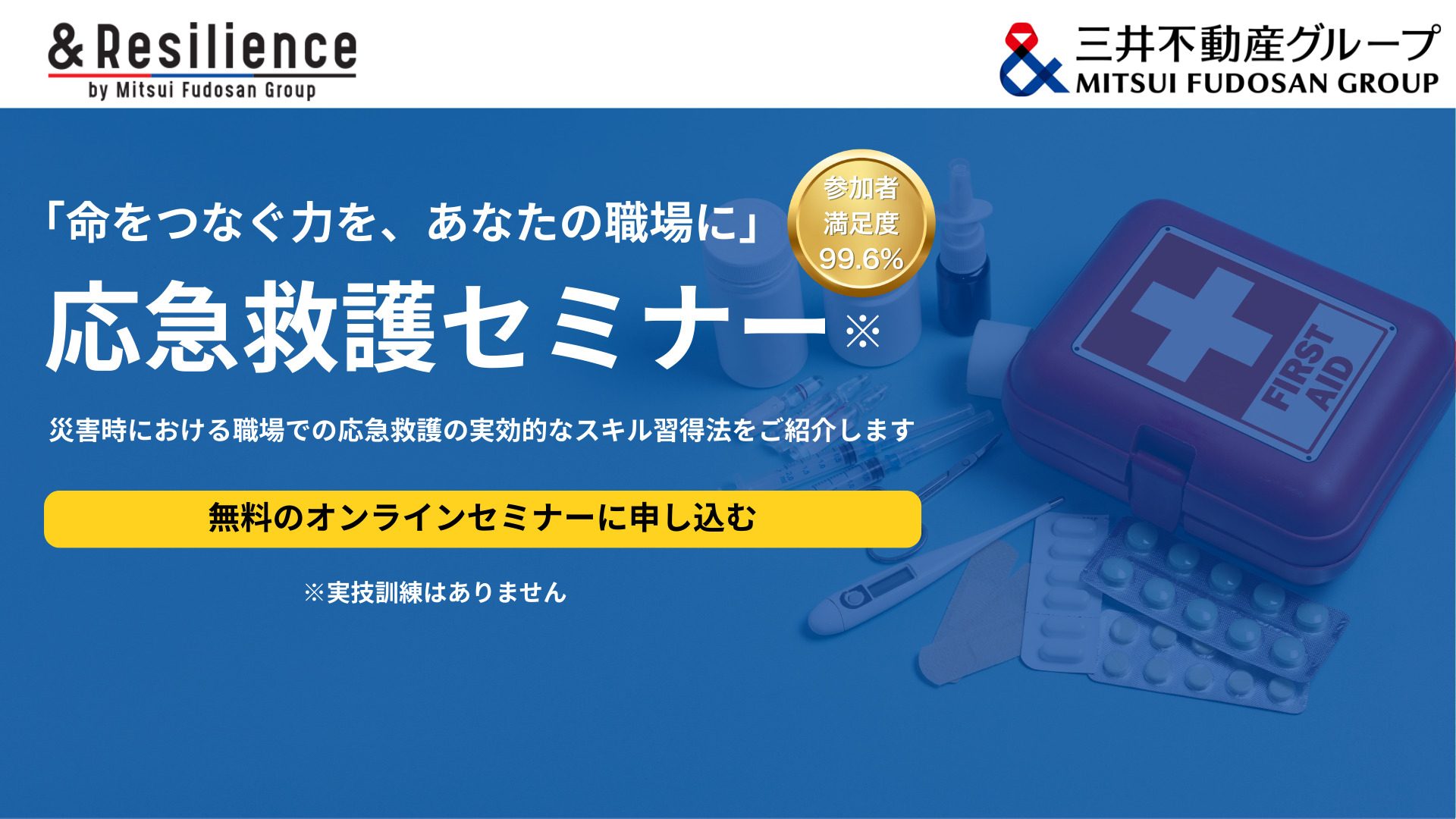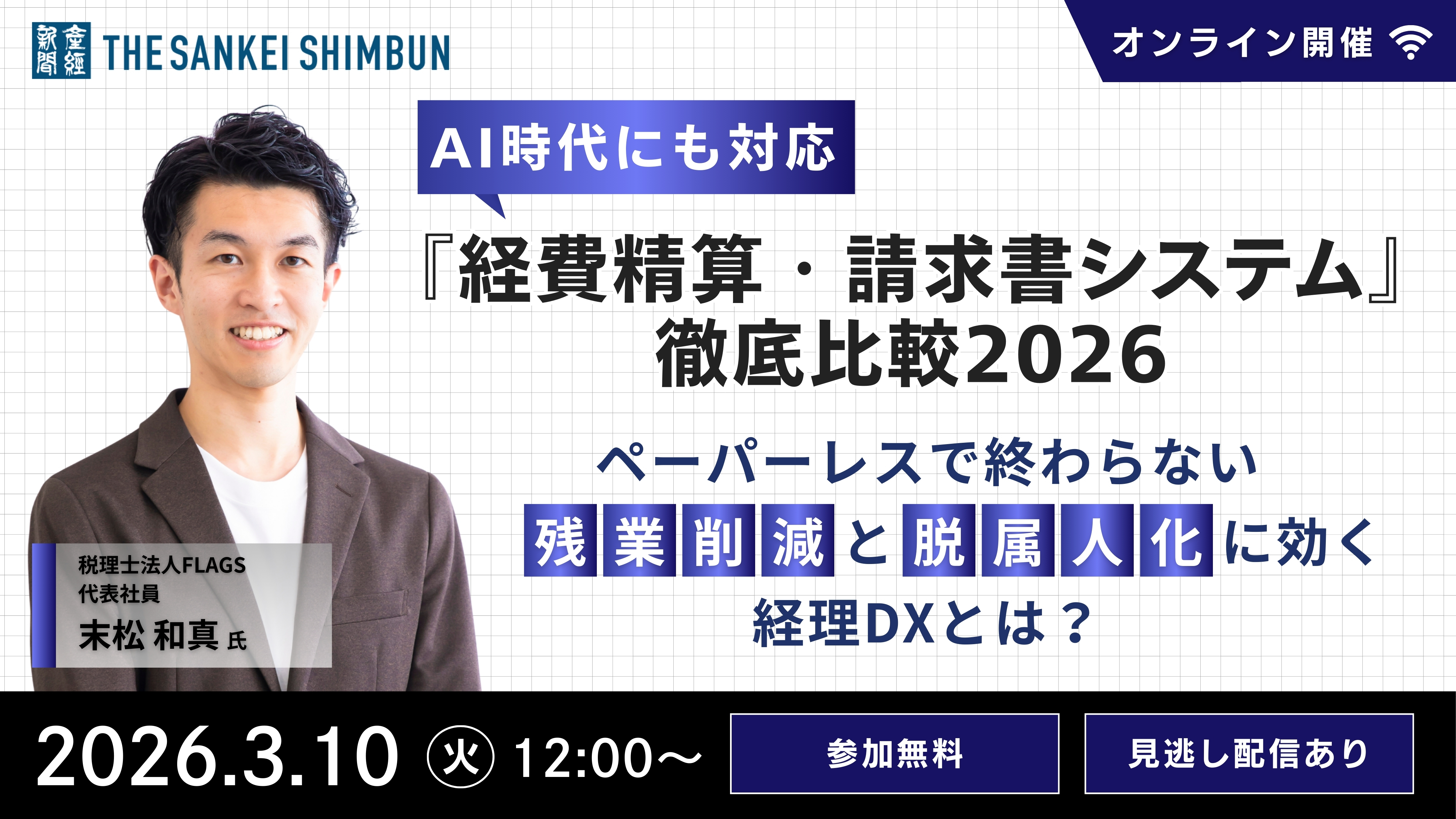公開日 /-create_datetime-/

目次本記事の内容

▼この記事を書いた人
寺山 晋太郎
社会保険労務士
社会保険労務士法人 宮嶋社会保険労務士事務所
福島県出身。一橋大学社会学部卒業。大手鉄道会社にて現業や本社勤務など様々な業務を経験。2014年第一子誕生を機に育休を取得。その後現職に転じ、働きながら社労士資格を取得。社労士業の傍ら、3児の父親としても奮闘中。
1.リモートワークの現状と労務管理の課題
リモートワークとは、テレワークとも呼ばれ、ICT(情報通信)技術を活用して多様な就業場所で仕事をすることを指します。2020年以降に世界中で流行した新型コロナウイルスをきっかけに、日本においてもこれまでのような「決まったオフィスに出勤して働く」という働き方が難しくなったことを受け、普及が進んだことは記憶に新しいかと思います。
ただ近年は新型コロナウイルスの影響も限定的となり、リモートワーク熱も冷めつつあるような印象です。例えば米大手企業Amazonは、つい先日に現状週3日の出社義務を2025年1月2日から原則週5日に戻すことを宣言し、大きな話題となっています。
そういった情勢の中、では日本におけるリモートワークの現状はどうかといいますと、国が行った「テレワーク人口実態調査(令和5年度」によると、「直近一年間のテレワーク実施率」はデータがある令和3年度から右肩下がりに低下しており、首都圏においては令和3年度において42.3%であったのが28.0%となっております(地方になると非常に低く、首都圏・近畿圏・中京圏を除くと直近の実施率は8.8%にとどまります)。
では、どうしてリモートワークを実施しないかという理由ですが、これも同調査によれば「会社からテレワークを実施することが認められていない、または出勤するよう指示等がありテレワークを実施できないため」という理由が大きな割合を占めており、会社としてリモートワークをあまり推奨していない現状となっている実態が読み取れます。
もちろん、そもそもリモートワークに適さない業種(販売、営業など)もあるでしょうが、一般的な事務においてリモートワークを適切に実施しようとすれば、社員同士のコミュニケーションの問題、労務管理の問題、情報セキュリティの問題など、解決すべき問題が山積しております。また労務管理の問題一つをとっても、例えば出退勤はどのように管理すればよいのか、会社の目を離れたところできちんと仕事をしてくれるのか、等さまざまなお悩みがあり、リモートワークの実施に二の足を踏まれている現状もあろうかと思います。
そこで本記事では、社労士の視点から、リモートワークにおける労務管理のポイントをご説明していきます。
lockこの記事は会員限定記事です(残り6144文字)
会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

フリーアドレスの成功事例 ご紹介
おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -
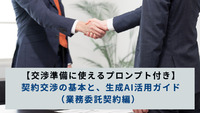
【交渉準備に使えるプロンプト付き】契約交渉の基本と、生成AI活用ガイド(業務委託契約編)
ニュース -
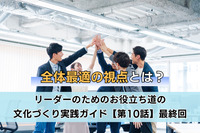
全体最適の視点とは?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第10話】最終回
ニュース -

不登校やきょうだい児も対象に 住友林業が最大3年の「ファミリーケア休業」新設、離職防止へ
ニュース -
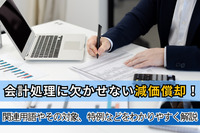
会計処理に欠かせない減価償却!関連用語やその対象、特例などをわかりやすく解説
ニュース -

契約審査とは?担当者が迷わない流れとチェックポイント
ニュース -

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
おすすめ資料 -

新入社員の育成・活躍を促進するオンボーディングとは?
ニュース -
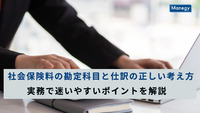
社会保険料の勘定科目と仕訳の正しい考え方|実務で迷いやすいポイントを解説
ニュース -

法務FAQ構築の手順とポイントを解説|AIを活用した効率的な運用・更新手法も紹介
ニュース -

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に
ニュース -

AI時代のスキルと人材育成 ~AIが代替できない「深化」の正体とは?~
ニュース