公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
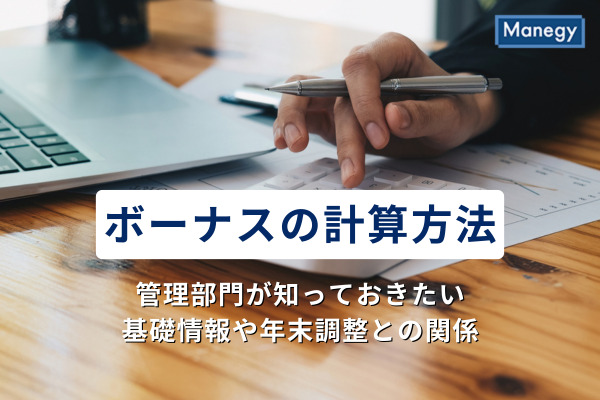
本記事ではボーナス計算の業務で知っておくべき基礎情報や今の時期押さえておきたい年末調整との関係などを紹介します。
ボーナスとは、従業員に対して通常の給与とは別に支給される特別な報酬のことを指し、多くの企業では、年に1〜2回、主に夏と冬に支給されます。
ただ、会社の経営方針や業績によって支給される額が大きく変わることがあるため、企業によっては業績が芳しくない場合にボーナスを支給しないこともあります。そのため企業は支給基準や金額を明確にしておくことが重要です。
「ボーナス」と「賞与」は、一般的に同じ意味で使われることが多いですが、厳密には少し違います。
ボーナスは、通常、広く一時的な報酬として使われる言葉であり、会社の業績や従業員の個人評価に基づいて支給されることが多いです。
一方、賞与は法律や契約上で定義されている特定の報酬の形を指し、会社が労働契約や就業規則で明示している義務的な支給となるケースもあります。
例えば、賞与が明確に支給基準として定められている場合、企業はその基準に従って賞与を支払う必要があります。
ボーナスは会社の裁量によって支給されることが多く、業績やその他の要因に基づいて変動します。この違いは、特に経理・人事・総務などの給与計算を行う部署が従業員に対する報酬を計算する際に重要なポイントとなります。
企業によっては、社内の規定や慣例によって「ボーナス」と「賞与」を区別せずに同じように扱うこともありますが、制度としては異なる意図や法律的背景があるため、その違いを理解しておきましょう。
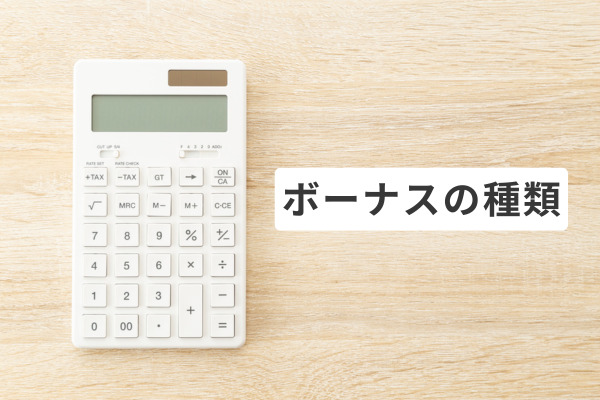
ボーナスにはさまざまな種類があり、企業の方針や制度によって異なります。ここでは代表的なボーナスの種類を紹介します。
1. 定期賞与
定期賞与は、一般的に夏と冬の年2回、決まった時期に支給されるボーナスです。支給額は「基本給の○ヶ月分」や「基本給に業績評価を反映した金額」など、企業ごとの支給基準に基づいて決まります。この定期賞与は、多くの企業で給与体系の一部として組み込まれており、従業員も支給を前提に計画を立てていることが多いです。
2. 業績連動型ボーナス
業績連動型ボーナスは、会社の経営成績や利益の達成度に応じて支給額が決まるボーナスです。特に営業職や経営層など、業績に直接影響を与える職種ではこのボーナスが採用されることが多いです。このタイプのボーナスは、従業員にとって会社の成功と自身の努力が反映されるため、モチベーション向上につながります。
3. 特別賞与
特別賞与は、業績が特に好調だった年や、会社の特定の節目(創立記念、IPO成功など)に支給される一時的なボーナスです。特別な努力や成果に対して報いるために支給されることが多く、従業員の満足度向上や、会社への帰属意識を強める目的で利用されます。
4. 決算賞与
決算賞与は、決算時の利益に応じて支給されるボーナスです。企業が利益を確保できた場合に、その一部を従業員に還元する形で支給されます。このボーナスは、業績連動型と似ていますが、年次の決算状況を反映するため、必ずしも定期的に支給されるわけではありません。
5. インセンティブボーナス
インセンティブボーナスは、特定の目標を達成した際に支給される成果報酬型のボーナスです。売上目標の達成、プロジェクトの成功など、個別の業績に応じて支給されるため、企業によっては評価制度の一環として設けられています。
ボーナスの計算方法は企業ごとに異なりますが、ここでは、代表的なボーナス計算の方法を紹介します。
1. 基本給を基準にした計算
最も一般的な方法は、従業員の基本給を基準にボーナスを算出するものです。たとえば、「基本給の2ヶ月分」といった形で計算されるケースが多く、以下のように計算されます。
計算方法:
基本給 × 支給月数 = ボーナス支給額
例:
基本給が30万円で、支給月数が2ヶ月の場合、
30万円 × 2 = 60万円(ボーナス支給額)
2. 評価制度を反映した計算
多くの企業では、従業員の業績や評価に基づいてボーナスを決定します。この場合、評価点数や貢献度などが加味され、基本給に評価係数を掛け合わせて支給額が決まることが一般的です。
計算方法:
基本給 × 評価係数 × 支給月数 = ボーナス支給額
例:
基本給が30万円、評価係数が1.2、支給月数が2ヶ月の場合、
30万円 × 1.2 × 2 = 72万円(ボーナス支給額)
3. 業績連動型の計算
企業全体の業績に応じて支給額が変動する業績連動型ボーナスも多く採用されています。この方法では、会社の利益や売上目標の達成度に応じてボーナスが決まります。たとえば、目標達成率に応じた係数を設定し、それを元に支給額を調整します。
計算方法:
基本給 × 業績達成率 × 支給月数 = ボーナス支給額
例:
基本給が30万円、業績達成率が110%、支給月数が2ヶ月の場合、
30万円 × 1.1 × 2 = 66万円(ボーナス支給額)
4. プロジェクトやインセンティブボーナスの計算
特定のプロジェクト完了や目標達成に対して支給されるインセンティブボーナスは、事前に決められた金額や割合に基づいて計算されます。個々のケースによって計算方法が異なるため、支給条件をあらかじめ明確にしておくことが重要です。
例:
基準: 売上目標の達成度に応じたインセンティブ
支給条件: 売上目標の100%達成で30万円、120%達成で40万円
プロジェクト売上が120%達成された場合、
ボーナス支給額 = 40万円
ボーナスは通常の給与と同様に、税金や社会保険料の対象となります。従業員が受け取る手取り額は、これらの控除後の金額となるため、計算時には注意が必要です。ここでは、ボーナスにかかる代表的な税金と社会保険料について解説します。
1. 所得税
ボーナスには所得税がかかり、源泉徴収として事前に控除されます。ボーナスの源泉徴収税額は、通常の給与とは異なり、給与所得の累進課税を基に計算されるため、金額が高くなる場合があります。税額は「賞与に対する源泉徴収税額の算出方法」に基づき、次のように計算されます。
計算方法:
支給額 × 源泉徴収税率 = 所得税控除額
税率は個々の所得状況によって変動するため、正確な税額を算出するためには、各従業員の給与や所得状況を確認する必要があります。
2. 住民税
住民税は、毎月の給与から控除される形で支払われますが、ボーナスの支給額自体には影響しません。ボーナスに対する住民税の特別な計算は必要ありませんが、ボーナスを含めた総所得に基づいて翌年度の住民税が決定される点に注意が必要です。
3. 社会保険料
ボーナスからは、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料が控除されます。これらの保険料は、通常の給与とは異なるボーナス専用の計算基準で決定されるため、特に以下のポイントを理解しておくことが重要です。
健康保険料・厚生年金保険料:
ボーナス支給額に対して一定の率で計算されます。ただし、標準報酬月額の上限があり、一定の金額を超える場合は、その超過分に対して保険料はかかりません。
雇用保険料:
支給額に対して一定の保険料率をかけて計算されます。
4. 手取り額の計算
これらの税金や社会保険料を控除した後に従業員が実際に受け取る金額が、手取り額です。ボーナス計算時には、事前にこれらの控除額を計算し、正確な手取り額を提示することが求められます。
計算例: ボーナス支給額が60万円の場合、以下の控除が発生します。
所得税:6万円
健康保険料:3万円
厚生年金保険料:4万円
雇用保険料:0.5万円
この場合の手取り額は、
60万円 - (6万円 + 3万円 + 4万円 + 0.5万円) = 46.5万円となります。
主なボーナスのタイプは、固定額ボーナスと業績連動型ボーナスになります。この2つは計算方法に違いがあるため、それぞれ解説します。
1. 固定額ボーナスの計算方法
固定額ボーナスは、企業があらかじめ定めた基準に従って、毎回同じ金額または一定の計算基準に基づいて支給されるボーナスです。従業員の業績や会社の業績に関わらず、支給額があらかじめ決まっているため、予測がしやすく、安定した報酬としての役割を果たします。
計算例:
基準: 基本給の2ヶ月分
計算式: 基本給 × 支給月数
例: 基本給が30万円の場合、
30万円 × 2 = 60万円(ボーナス支給額)
固定額ボーナスは、従業員の役職や勤続年数、基本給に基づいて算出されることが一般的です。そのため、支給額が事前にわかりやすく、従業員にとっても予測が立てやすいという利点があります。
2. 業績連動型ボーナスの計算方法
一方、業績連動型ボーナスは、企業の業績や従業員個々の評価に基づいて支給額が決まります。これは企業の利益や売上、達成目標に応じてボーナスの額が増減する仕組みで、会社の成功が従業員の報酬に直接影響を与えるため、モチベーション向上に効果的です。
計算例:
基準: 基本給に加え、業績評価や目標達成率による加算
計算方法: 基本給 × 業績係数 × 支給月数
例: 基本給が30万円、業績評価係数が1.2、支給月数が2ヶ月の場合、
30万円 × 1.2 × 2 = 72万円(ボーナス支給額)
業績連動型ボーナスは、企業の目標達成度や従業員の貢献度に応じて調整されるため、毎回の支給額が変動する特徴があります。従業員の評価制度や会社の目標設定がボーナス額に直結するため、公平かつ透明な評価基準の設定が求められます。
3. 違いのまとめ
固定額ボーナスは、あらかじめ決まった金額や基準に基づいて支給されるため、計算がシンプルで予測しやすい反面、従業員の業績や会社の業績に応じた調整はありません。
業績連動型ボーナスは、企業の業績や個々の従業員の成果に応じて変動するため、モチベーション向上に寄与する一方、計算が複雑で支給額が変動することがあります。

ボーナスの計算は、通常の給与計算に比べて多くの変数が関わるため、ミスが発生しやすい作業です。特に、税金や社会保険料の取り扱い、評価制度の反映、業績連動型ボーナスの計算など、複雑な要素が絡む場合、注意が必要です。ここでは、ボーナスの計算でよくあるミスと、それらを防ぐための対策を紹介します。
1. 支給基準の誤り
ボーナスの支給基準が正しく設定されていないと、計算ミスが発生しやすくなります。例えば、基本給の○ヶ月分と定めているにもかかわらず、誤って他の手当を含めた金額を基に計算してしまうことがあります。
防止策:ボーナス支給基準を明確にし、基本給や評価項目を正確に確認する。
計算前に、支給対象となる金額や基準を再確認する。
2. 税金や社会保険料の計算ミス
ボーナスには所得税や社会保険料がかかりますが、これらを誤って計算してしまうことがあります。特に、源泉徴収税額や健康保険料、厚生年金保険料の控除額の計算を間違えると、従業員に不利益が生じる可能性があります。
防止策:最新の税率や保険料率を確認し、正確に反映する。
自動計算機能を備えた給与計算ソフトを活用し、人為的ミスを防ぐ。
3. 評価制度の反映漏れ
業績連動型ボーナスや評価制度に基づくボーナスでは、従業員の評価結果を正確に反映させる必要があります。しかし、評価の記録漏れや誤ったデータの入力によって、評価に基づくボーナス額が正しく計算されないことがあります。
防止策:評価データを一元管理し、ボーナス計算時に最新の評価結果が反映されるようにする。
計算前に人事部門や評価者から評価結果を確認するフローを取り入れる。
4. 締め日や支給日の取り扱いミス
ボーナスの計算期間や支給タイミングを誤ると、対象期間に含まれる従業員が正しく反映されないことがあります。特に、退職者や新入社員に対するボーナス支給を誤るケースがあります。
防止策:支給対象期間を明確にし、退職者や新入社員のボーナス支給対象を確認する。
支給日と締め日を把握し、事前に確認するスケジュール管理を徹底する。
5. 計算ミスのチェック不足
複数の従業員に対して異なる基準でボーナスを計算する場合、誤差やミスが生じやすくなります。
防止策:計算結果のダブルチェックを徹底し、複数の担当者で確認するプロセスを導入する。
給与計算ソフトの検証機能を活用し、計算ミスの自動検出を行う。
年末調整は、従業員の年間の所得税を正しく計算し、過不足を調整するための手続きです。ボーナスは、通常の給与と同様に所得税の対象となるため、年末調整と密接な関係があります。正しくボーナス計算を行わなければ、年末調整時に誤った税額が適用される可能性があり、従業員に負担をかけることになります。ここでは、年末調整とボーナス計算の関係について詳しく解説します。
1. ボーナスに対する源泉徴収税額の扱い
ボーナスに対する所得税は、通常の給与とは別に、支給された時点で源泉徴収されます。この源泉徴収額は、ボーナスの額に応じて定められた税率に基づいて計算されますが、年末調整時に年間の総所得を基に最終的な税額が確定されます。そのため、ボーナスに対する源泉徴収額が多すぎたり少なすぎたりした場合、年末調整で過不足が調整される仕組みです。
ポイント:年末調整では、ボーナスを含めた年間総額に基づき、最終的な所得税額を確定します。年末調整によって、過剰に源泉徴収された税金が返金されるか、不足分が追加徴収されます。
2. 年末に支給されるボーナスの影響
年末にボーナスが支給される場合、年末調整とボーナス支給が重なることがあります。特に12月に支給されるボーナスは、その年の収入として年末調整に反映されるため、正確なタイミングで支給額を反映させる必要があります。
ポイント:年末に支給されるボーナスは、その年の年末調整に含まれ、最終的な税額計算に影響します。
ボーナス支給額が大きい場合は、源泉徴収税額が増加するため、従業員に対する事前説明が重要です。
3. 扶養控除や各種控除の反映
年末調整では、扶養控除や配偶者控除、生命保険料控除など、各種の控除が適用されます。ボーナスもこの控除額に影響を与えるため、年間の総収入に基づいた正確な控除額を適用する必要があります。特に、扶養家族の有無や控除内容の変更がある場合、年末調整に反映されることでボーナスに対する税金が調整されることがあります。
ポイント:各種控除が年末調整で反映されるため、ボーナス支給額が年間総所得に影響を与える。
扶養家族や保険料の変動を正確に把握し、ボーナスに対する税金を適切に調整する。
4. 社会保険料控除との関連
ボーナスには社会保険料もかかるため、年末調整時に年間の社会保険料額が正確に反映されることが重要です。社会保険料の控除額が正確でないと、最終的な所得税額にも影響が出るため、ボーナスの支給額に応じた社会保険料の適切な計算が求められます。
ポイント:年末調整で社会保険料控除が適用される際、ボーナス分の社会保険料も正確に反映させる必要がある。
社会保険料の控除額を正しく計算し、年末調整に反映させることで、最終的な所得税額が調整される。

印刷・用紙代、郵送費などの経費、明細書の作成から配付までの業務人件費を大幅に削減できます。
クラウドサービスなので、サーバー費用不要
給与明細、賞与明細など月間の発行上限はありません。

「クラウドハウス労務」は、入退社手続き・年末調整・雇用契約などの労務手続きをオンラインで自動化・ペーパレス化する労務管理クラウドシステムです。また、「クラウドハウス」シリーズが展開するHRプラットフォームの入口となる一元的な人事データベースにもなります。
「定着すること」にこだわった直感的な操作画面・初期設定から運用定着まで各社専任の担当者による伴走フォローが特徴です。本サービスを用いて煩雑な労務手続きをすべて電子化することで、業務効率化・コストカット・ペーパレスなど様々な企業課題を解決し、本質的な人事・労務業務に向き合う環境を構築できます。

出所:ジンジャー給与参考サイト
ジンジャー給与は、従業員情報と自動連係し、給与に関わる情報の確認などを大幅に削減できる給与システムです。
毎月課題と感じている給与計算業務を改善します。
・給与計算ソフトの使い方が難しくてストレスを感じる
・毎月の明細書発行に手間がかかる
・給与計算に必要な情報の収集とシステム反映が手間
・給与関連書類の確認を人の目で何回もしていて疲れる
⇒これらのお悩みをジンジャー給与でまるっと解決いたします。

出所:SmartHR公式サイト
SmartHRは人事情報が「集まる・蓄まる・活用できる」クラウド型ソフトウェアです。入社手続きや年末調整などの多様な労務手続きをペーパーレス化し、データとして蓄積。勤怠や給与計算システム等との連携により、様々なデータの一元管理も可能です。さらに蓄積した従業員データを活用できる人材マネジメント機能により、働きたい職場環境の創出に貢献します。

出所:ピタット給与公式サイト
【「ピタット給与」6つの特徴とは?】
◆システム運用導入コストゼロ!
弊社のシステムで運用するため、自社でシステムを管理・運用するタスクやコストから解放されます
◆書式やフォーマットはそのまま!
両社の連絡に必要な書類のフォーマットは御社の使用に合わせます
弊社にてテンプレートもご用意しております
◆前処理からお任せください!
勤怠データの収集からお手伝いいたします
◆スピーディーな中間処理
お客様のご都合に合わせて、毎月の処理スケジュールを調整いたします
◆ご契約中のお客様の満足度90%以上
担当者の対応スピード、業務品質について高い評価をいただいております
◆各士業との連携実績多数
税理士、社会保険労務士をはじめとする各士業と連携し対応しております
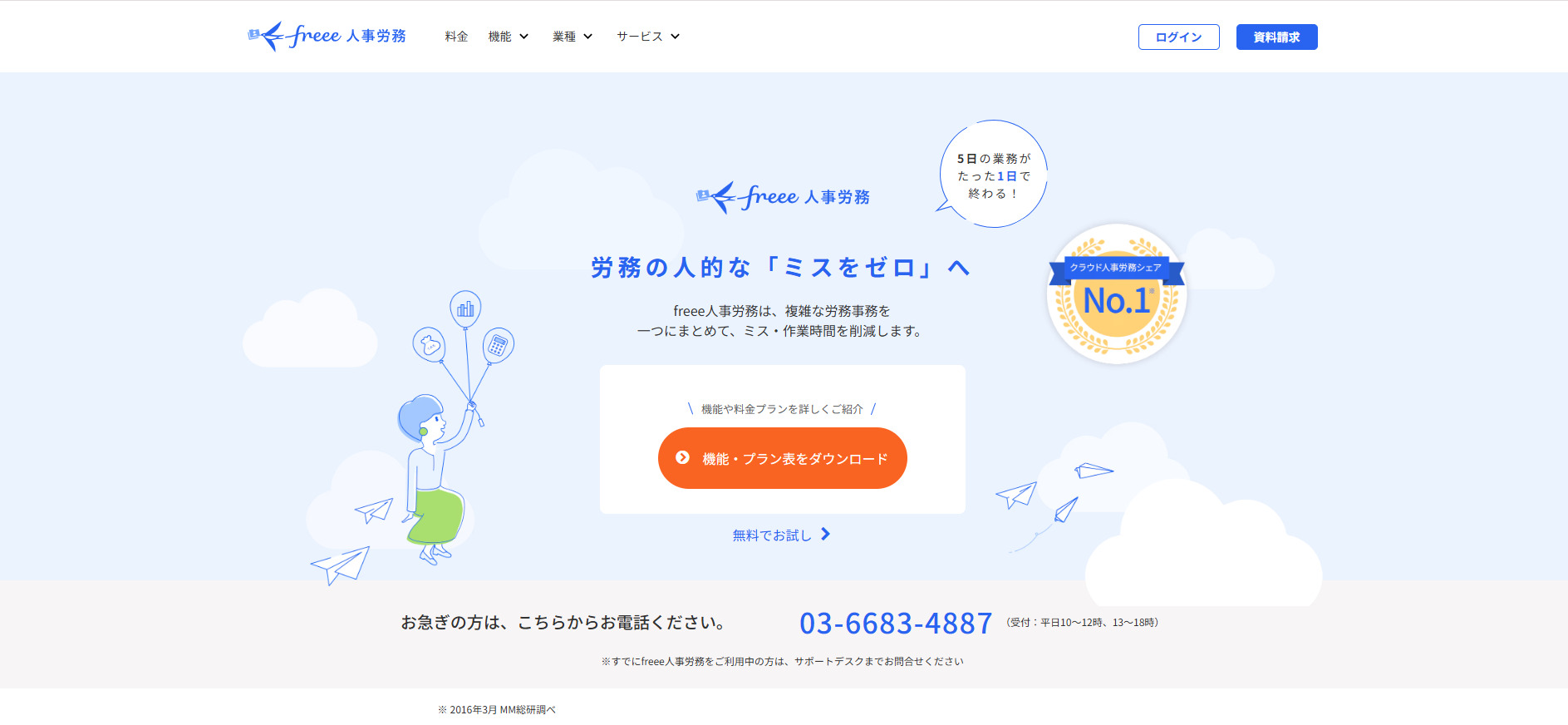
給与計算機能をはじめ、年末調整や勤怠管理などの労務業務を一元化!
「人事労務freee」なら、人事・労務業務の自動化でミスを無くして作業時間を大幅削減!

マネーフォワード クラウド給与を使えば、給与計算から振り込みまでオンラインで完結。従業員への給与明細もwebで発行できるので印刷や配布の手間を削減できます。
また他社の勤怠管理システムや人事労務ソフトとも連携でき、クラウドソフトなので自宅でも業務が行なえます。
クラウド給与が貴社の給与計算業務をもっと便利にかんたんにします。
【主な機能】
・社会保険や税の自動計算
・web給与明細の発行でいつでもどこでも確認可能に
・専門家も満足できる給与計算ソフト

給与奉行の多様な業務メニューときめ細やかな手当項目をクラウドで手軽に利用できます。
さらに、明細配付や年末調整申告、人事労務手続きなどの業務をデジタル化することで
担当者と従業員双方の業務時間を削減。
社外にいる専門家とつながることができるため、リスク対策を強化することも出来ます。
【こんな方にオススメのサービスです】
・自社の運用やルールを変えることなく正しく効率的な給与計算がしたい
・テレワークや在宅勤務で給与業務を行える体制を整えたい
・給与明細書や源泉徴収票などのペーパーレス化を図りたい
・従業員の業務時間を削減して働き方改革を実現したい
・社会保険労務士や税理士との情報共有のやりとりをなくしたい

ジョブカン給与計算は、給与計算担当者の負担を減らすための豊富な機能を持ったクラウド給与計算システムです。かんたん勤怠連携・計測自動化で作業時間を大幅に削減します。給与賞与明細・源泉徴収票はWEBで自動交付可能。年末調整もジョブカン給与計算で完結!計算後の法定調書の作成まで完備しています。

「ペイスリッププロ」は、お手持ちの給与計算ソフトからカンタンに給与明細・賞与明細を電子化(Webで閲覧)出来るサービスです。PCは勿論、スマホやタブレットでも閲覧可能で便利です。セキュリティ対策も万全なので、安心して利用できます。

出所:COMPANY公式サイト
継続利用率98%。日本の大手企業の約3社に1社が採用。10年超利用ユーザーは600法人グループ。「COMPANY」は、リーディングカンパニーが選んでいる統合人事システムです。

給与明細書だけでなく、賞与明細書や源泉徴収票、
通知が義務付けられている標準報酬改定(決定)通知書を電子化できるため、
給与業務で発生するすべての配付作業とコストを削減できます。
給与奉行クラウドと完全連携しているため、データ連携の手間は一切必要ありません。
【こんな方にオススメのサービスです】
・テレワークや在宅勤務で業務を行える体制を整えたい
・給与明細書や源泉徴収票などのペーパーレス化を図りたい
・従業員の業務時間を削減して働き方改革を実現したい
ボーナスの計算方法には固定額や業績連動型などがあり、それに伴う税金や社会保険料の正確な控除も必要です。
また、ボーナスは年末調整にも影響するため、支給時期や源泉徴収額にも注意しましょう。
経理・人事・総務などの給与計算を行う部署では、評価制度の軸を定めること、計算ミスの防止策を徹底し、給与計算ソフトの活用で効率化を図ると良いでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

オフィスステーション年末調整

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

新聞図書費とは?経理が押さえておきたい対象経費と仕訳の基本

旬刊『経理情報』2026年2月20日号(通巻No.1768)情報ダイジェスト①/税務
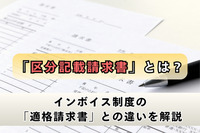
「区分記載請求書」とは?インボイス制度の「適格請求書」との違いを解説

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト②/会計

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

棚卸評価損の仕訳とは?計算方法・仕訳例・評価方法をわかりやすく解説

ESG・業種特化で差をつける!30代公認会計士が選ばれる理由(前編)
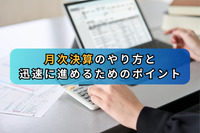
月次決算のやり方と迅速に進めるためのポイント

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増

軽減税率導入で複雑化する請求書の消費税処理、経理担当者の手間を軽減するには?
公開日 /-create_datetime-/