公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。
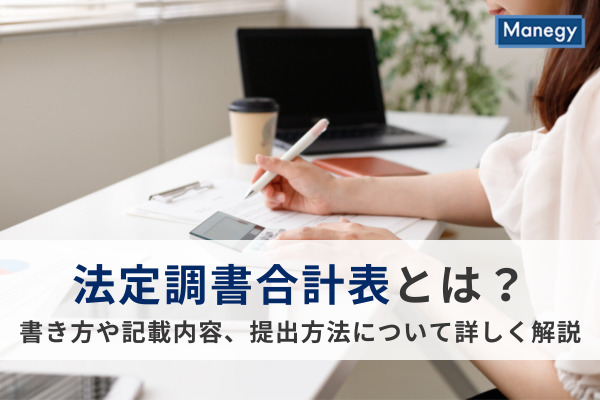
法定調書合計表をご存じでしょうか。経理部門や人事・労務部門などで勤務経験がある方なら理解している方も多いはずです。しかし「今年度から業務未経験で経理、労務に配属された」「これから経理、労務の勉強をしたい」といった方にとっては、あまり耳慣れない専門用語でしょう。
そこで今回は、法定調書合計表とは何か、記載内容や提出方法などについて詳しく解説します。
法定調書合計表とは、源泉徴収票、支払調書など収入に関わる法定調書とあわせて税務署に提出する書類のことです。正式には「給与所得者の源泉徴収票等の法定調書合計表」といいます。
そもそも法定調書とは、所得税法、相続税法、国外送金等調書法(内国税の適切な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書)、租税特別措置法などの法律に基づいて提出が義務付けられている書類を指します。一言でいえば、企業が1~12月までの事業活動の中で、誰に対していくらのお金を支払ったのかを把握するための書類です。
法定調書の代表例として、「従業員への給与支払いに関わる源泉徴収票」、「フリーランスなど契約相手への報酬・料金の支払いに関わる支払調書」などが該当します。ほかにも、「退職所得の源泉徴収票」「不動産の使用料等の支払調書」「不動産等の譲り受けの対価に関する支払い調書」「不動産等の売買または貸付の斡旋手数料の支払調書」などもあり、合計で6種類あります。
法定調書にはお金を支払った相手も記されているので、支払側と受領側の両方の申告情報を照らし合わせつつ、税務署は脱税・申告漏れがないかをチェックします。
ただ、法定調書である源泉徴収票や支払調書などは、その内容を一括してもらわないと、税務署としては確認が大変になります。源泉徴収票の合計表と支払調書の合計表を別々に扱っていたら、その内容を統合する作業に膨大な時間がかかってしまいます。そこで企業側が税務署に法定調書を提出する際、その法定調書の金額をすべて記載し、一枚の書類にまとめられた「法定調書合計表」の提出もあわせて求めているのです。
各種法定調書をまとめて記載した法定調書合計表は、所定の書類があるので、そこに必要事項を記入する形となります。テンプレートは税務署のe-Taxをはじめ、ネット上で簡単にダウンロードできるので、書類形式を一から作成する必要はありません。
記入する情報は、「提出者の情報」「事業項目」「作成担当者の氏名」「各種法定調書の合計表」などです。
提出者である企業(個人事業主)の住所・所在地、名称または氏名、法人番号またはマイナンバーカードの個人番号、代表者氏名などを記載する必要があります。
事業種目を記入する箇所があるので、事業内容を記入します。すでに提出した法定調書合計表の追加、訂正をする際は、「追加の法定調書を提出」などの項目が記載されているので、そちらにチェックを入れます。
法定調書合計表を作成した人の氏名です。税理士に作成をお願いしている場合は税理士の氏名が記載されます。なお、2021年度から税務書類の押印義務が廃止されているので、現在では押印欄はありません。
前述した6種類の法定調書の表を作成している場合は、項目ごとに金額を記載します。それぞれ記載箇所が規定されているので、そちらに正確に金額を記入します。
法定調書と法定調書合計表は、書面に記載された支払いが確定した日を含む年の翌年の1月31日が提出期限です。
提出方法としては、下記があげられます。
クラウドサービスを利用した提出は、2022年1月から可能となりました。2024年現在、利用できる認定サービスとして「e-私書箱法定調書提出クラウドサービス」「法定調書クラウド」の2つがあります。
法定調書合計表は制度上、提出が義務付けられている税務書類なので、未提出だと法令違反となり罰則対象です。期限内に提出が間に合わなかった場合でも、提出依頼・注意などが行われ、すぐに罰せられるわけではありません。しかし催促しても未提出のままだと、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
給与計算ソフトなどを使用している場合、法定調書合計表は自動で計算されているケースが多いです。ネット上からダウンロードでテンプレートを入手して作成する場合は、エクセルファイルにて簡単に作成できます。
法定調書合計表の作成には、その前段階である源泉徴収票合計表や支払調書合計表などの各種法定調書の作成が必要です。法定調書の作成には、従業員のマイナンバーや住所を把握することも求められます。
最終的に法定調書合計表としてまとめ上げるには相応の時間と労力が必要となるため、もし作成担当となった場合、早めの準備が望ましいでしょう。また、対応した会計ソフトを使用すると、ミスなく効率的に、法定調書合計表作成作業を進められます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

英文契約書のリーガルチェックについて

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築

地方公務員の男性育休取得率、過去最高を更新 人材確保には課題も 総務省が調査結果を公表

2025年、上場廃止への「TOB・MBO」は112社 TOBの買い手は約30%がアクティビストを含む「ファンド」
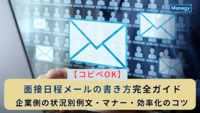
【コピペOK】面接日程メールの書き方完全ガイド|企業側の状況別例文・マナー・効率化のコツ
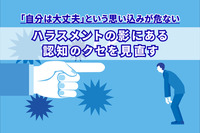
「自分は大丈夫」という思い込みが危ない ─ ハラスメントの影にある認知のクセを見直す

ファイル共有のセキュリティ対策と統制

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

1月23日~1月29日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

「叱る・注意する」が怖くなる前に ─ ハラスメントを防ぐ“信頼ベース”の関係づくり

【最大16,000円】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』に参加してAmazonギフトカードをGET!
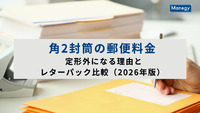
角2封筒の郵便料金|定形外になる理由とレターパック比較(2026年版)

日本のダイバーシティの針はどちらに振れるのか ―人事1000名の声から読み解く現状と未来予測―
公開日 /-create_datetime-/