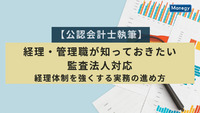公開日 /-create_datetime-/
【社労士解説】政府が「ジョブ型人事指針」を公表!人事労務向けに解説
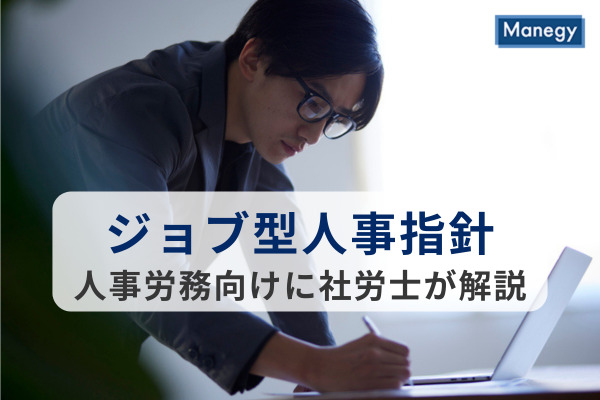
目次本記事の内容

▼この記事を書いた人
寺山 晋太郎
社会保険労務士
社会保険労務士法人 宮嶋社会保険労務士事務所
福島県出身。一橋大学社会学部卒業。大手鉄道会社にて現業や本社勤務など様々な業務を経験。2014年第一子誕生を機に育休を取得。その後現職に転じ、働きながら社労士資格を取得。社労士業の傍ら、3児の父親としても奮闘中。
1. ジョブ型人事制度とは
ジョブ型人事制度とは、一言で表すと「仕事そのものを基軸とした人事制度」で、世界的に主流を占めるものです。これだけでは分かりづらいかと存じますので、日本においてメジャーである職能型人事制度と比較する形でその特徴をまとめてみます。
職能型人事制度とは「社員の能力を基軸とした人事制度」であり、評価基準も「社員の能力」となります。そのため極端な例を挙げれば、全く同じ仕事をしている二人がいても、それぞれ能力が異なっていると評価されれば、その二人の待遇も異なるものとなってくるのが職能型人事制度となります。それに対しジョブ型人事制度は「従事する仕事」を評価の基軸としますから、仕事が同じであれば両者の評価・待遇も全く同じものとなり、個人の能力は考慮されないのが原則となります。
近年、日本においてもジョブ型人事制度の導入が進められておりますが、それは企業レベルではなく、国を挙げて進めている感すらあります。その証左として国は今年8月に『ジョブ型人事指針』というものを策定・発表しており、その中で「日本企業の競争力維持のため、ジョブ型人事の導入を進める」と明確なビジョンを打ち出しております。国がジョブ型人事制度の導入を進める背景には、職能型人事制度が持つデメリットである「自律的なキャリア形成が困難である」ことがあります。
新卒一括採用された社員が会社の指示に従って異動を繰り返し、そこで与えられた仕事を頑張っていくことで昇給・昇格していくという従来の姿では、キャリア自律志向のある従業員にはマッチしませんし、そもそも会社の示す道が正解であるという保証もありません。また職能型人事制度はその性質上、どうしても評価基準が曖昧となりがち(なんであの人があのポストに?ということは割とありがちな現象です)ですから、従業員も何を頑張れば良いのか、どのスキルを伸ばせばよいのかが分からず、結果としてモチベーションに影響してしまうのです。
ついては、ジョブ型人事制度の詳細や注意点、リスクなどをご説明していきます。
lockこの記事は会員限定記事です(残り4740文字)
会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -
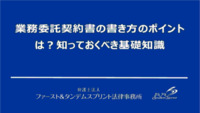
業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -
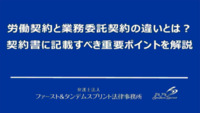
労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

【2026年新春】総勢300名様にAmazonギフトカードが当たる!Manegyお年玉キャンペーン開催中
ニュース -
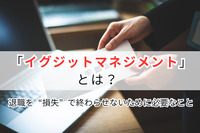
「イグジットマネジメント」とは? 退職を“損失”で終わらせないために必要なこと
ニュース -

管理部門担当者は何学部が多い?アンケート調査で見えた管理部門の出身学部とキャリアの関係
ニュース -
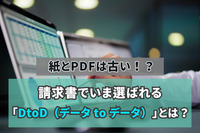
紙とPDFは古い!?請求書でいま選ばれる「DtoD(データ to データ)」とは?
ニュース -
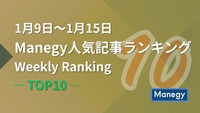
1月9日~1月15日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料
おすすめ資料 -

ランサムウェア感染経路と対策|侵入を防ぐ
ニュース -

エンゲージメント向上のポイントとサーベイの活用術
ニュース -
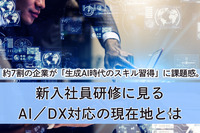
約7割の企業が「生成AI時代のスキル習得」に課題感。新入社員研修に見るAI/DX対応の現在地とは
ニュース -
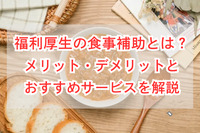
福利厚生の食事補助とは?メリット・デメリットとおすすめサービスを解説
ニュース -

2026年の展望=2025年を振り返って(13)
ニュース