公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。
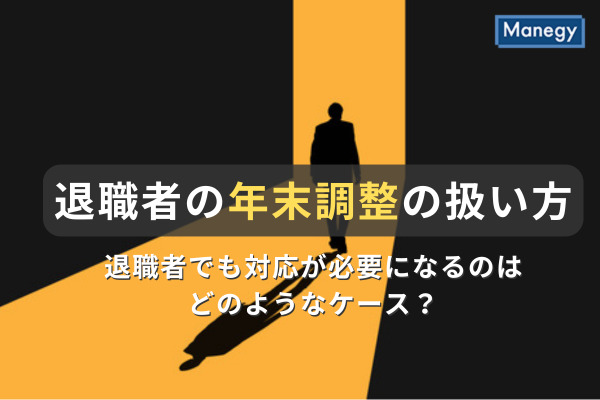
毎年やってくる年末調整の時期、経理部門をはじめ各部門では業務負担が増えると思います。近年は転職が一般的になっているため、年末調整の手続きが以前より複雑になっているかもしれません。今回の記事では、退職者や転職者の年末調整について注意点を解説します。
年末調整の目的は、毎年1月1日から12月31日の間に支払った給与に対して、源泉徴収額と本来の所得税額を清算することです。そのため基本的には、12月31日の時点で会社に在籍していない元社員は年末調整の対象になりません。
ただし転職が決まっている社員でも、12月の給与を転職前の会社が支払っている場合は年間の給与額が確定しているため、転職先の会社ではなく転職前の会社が年末調整を行うことになります。
また一部例外として、以下に該当する場合は年末調整の対象になりません。
出典:「年末調整の対象となる人」国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
基本的に退職者の年末調整は不要ですが、国税庁の指針によると以下に該当する場合は、例外的に退職前の会社で年末調整を行います。
出典:「年末調整の対象となる人」国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
ここまでをまとめると、一部の例外を除けば、退職前の会社で12月分の給与まで受け取り、年内には次の転職先などからの給与が発生しない場合、原則的に退職前の会社が年末調整をすることになります。
特殊なケースですが、もしも退職した社員から源泉徴収票の再発行を依頼された場合、会社側に発行の義務はあるのでしょうか?
通常は社員が退職すると、その後1カ月以内に源泉徴収票を発行します。しかし紛失などの理由で、再発行を依頼されるケースがあるかもしれません。本来こうした場合に、転職前の会社に発行義務はありません。ただし依頼を拒否すると、今度は退職者が税務署に相談する可能性があるため、トラブルを避けるためにも再発行に応じるべきでしょう。
ほかにも12月より前の退職者から、年末調整を依頼されることがあるかもしれません。このケースでは法的に見ても、会社側が対応する必要はありません。
事業規模にもよりますが、もしも年末調整の負担が大きすぎる場合には、システムの導入を検討したほうがよいでしょう。
年末調整ツールに関しては、以下のページで詳しく紹介しています。
https://www.manegy.com/service/year_end_adjustment/
1年間の給与総額が確定した時点で、はじめて年末調整の義務が生じます。原則的には12月の給与を支払った会社が、その社員の年末調整を行うことになるでしょう。その他のケースでは、会社側に年末調整の義務はありません。一部の例外については、国税庁の指針に従って対応してください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

消費税仕入税額控除の計算方法2つと、個別対応方式と一括比例配分方式、変更のタイミングを解説

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第4回 ソフトウェアの導入費用の取扱い

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』

「円安」倒産 1月では10年間で最多の6件 43カ月連続で発生、負債は11倍に大幅増

消費税課税事業者とは?免税事業者や届出書の違い

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

オフィスステーション年末調整

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第3回 自社利用のソフトウェアの定義と会計処理等(企業会計と税務会計の違い)

新聞図書費とは?経理が押さえておきたい対象経費と仕訳の基本

旬刊『経理情報』2026年2月20日号(通巻No.1768)情報ダイジェスト①/税務
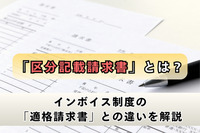
「区分記載請求書」とは?インボイス制度の「適格請求書」との違いを解説
公開日 /-create_datetime-/