公開日 /-create_datetime-/
管理部門で働かれている方の業務課題を解決する資料を無料でプレゼント!
経理・人事・総務・法務・経営企画で働かれている方が課題に感じている課題を解決できる資料をまとめました!複数資料をダウンロードすることで最大3,000円分のギフトカードもプレゼント!
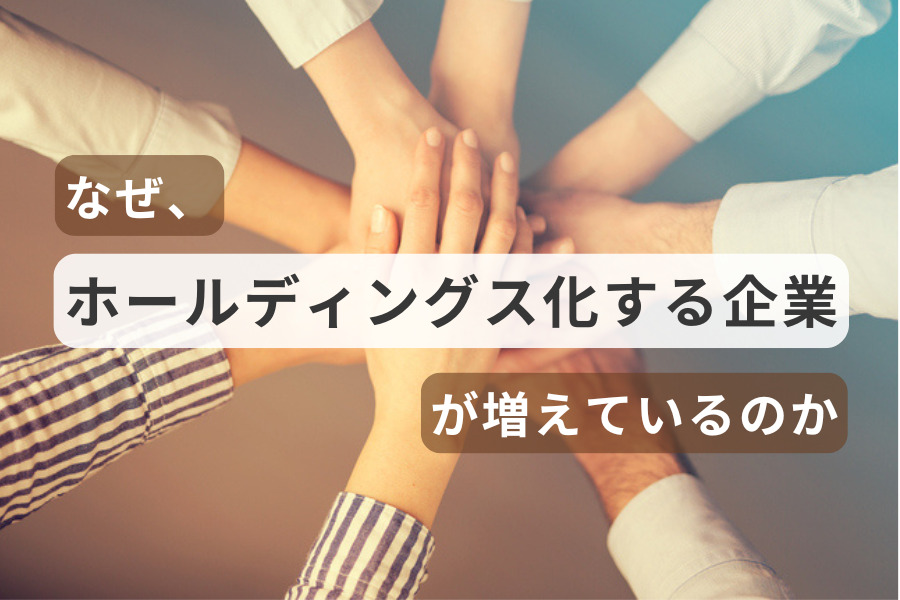
本コラムは『THE GOLD ONLINE』の寄稿原稿です。
ホールディング経営とは、持株会社を中心に複数の事業会社でポートフォリオを形成し、グループで成長する経営体制のことを言う。ここ数年、筆者らのクライアントの中でもホールディングス化に踏み切る企業が増加しており、その規模感も上場企業からオーナー系の中堅企業、中小企業へと広がっている。これからの時代において、成長するための経営体制のスタンダードとして定着しつつある、と実感せざるを得ない。
ホールディング経営に移行する目的は様々である。グループとして持続的に成長していきたいというのは大前提となるが、その中で多くの経営者を育てたい、複雑化するグループの資本系列を整理したい、あるいは今後M&A戦略を展開するための受け皿にしたい、資本である自社株を円滑に承継したい、などが挙げられる。
本稿では、その中でも成長戦略としての目的感、そして、その成長を支えるグループ経営の組織づくりという着眼でホールディング経営を考えていきたい。
まずは、成長戦略としてのホールディングスについて説明する。企業は長期的に存続することを目的としているが、そのためには常に変化し、成長し続けなければならない。このことは経営者の方であれば、実感として持っているであろう。現状維持のスタンスを取っても、世の中は激しく変化しているので、取り残されてしまうのである。
ただ、「成長する」と言っても経営環境は逆風だ。特に国内マーケットを主戦場とする多くの企業は、人口減少に伴ってマーケットが縮小していく中で、これまでの延長線上では成長戦略を描き切れない。言い換えれば、1社で1つの事業を守って生き残っていくには、あまりにも厳しい時代になっていくということである。
これからの時代には、1社1事業ではなく、複数の事業を組み合わせることで新たな事業価値を生み出したり、新たなバリューチェーンを構築したりなどの発想が有効であろう。複数の事業が横で繋がり、その幅を広げていくと、そこには「遠心力」が効き始める。これからの時代の成長の原動力は、まさにこの遠心力である。遠心力を強く効かせ、事業の幅を広げていく、または輪を広げていくことでスケールアップしていくイメージである。
ある建設会社の事例を紹介したい。この会社は……
記事提供元

タナベコンサルティンググループは「日本には企業を救う仕事が必要だ」という志を掲げた1957年の創業以来67年間で大企業から中堅企業まで約200業種、17,000社以上に経営コンサルティングを実施してまいりました。
企業を救い、元気にする。私たちが皆さまに提供する価値と貫き通す流儀をお伝えします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
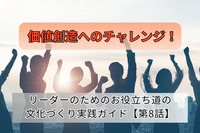
価値創造へのチャレンジ!/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第8話】

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』
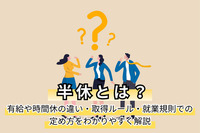
半休とは?有給や時間休の違い・取得ルール・就業規則での定め方をわかりやすく解説

「円安」倒産 1月では10年間で最多の6件 43カ月連続で発生、負債は11倍に大幅増
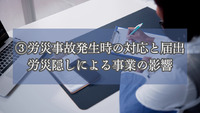
③労災事故発生時の対応と届出│労災隠しによる事業の影響

サーベイツールを徹底比較!

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
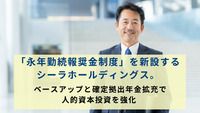
「永年勤続報奨金制度」を新設するシーラホールディングス。ベースアップと確定拠出年金拡充で人的資本投資を強化

『不調になってから』では遅い Smart相談室が描く、個人と組織の成長が一致する職場のつくり方

2026年版「働きがいのある会社」ランキング発表 全部門で日系企業が首位を獲得

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも

労基法大改正と「事業」概念の再考察 ~事業場単位適用の実務~
公開日 /-create_datetime-/