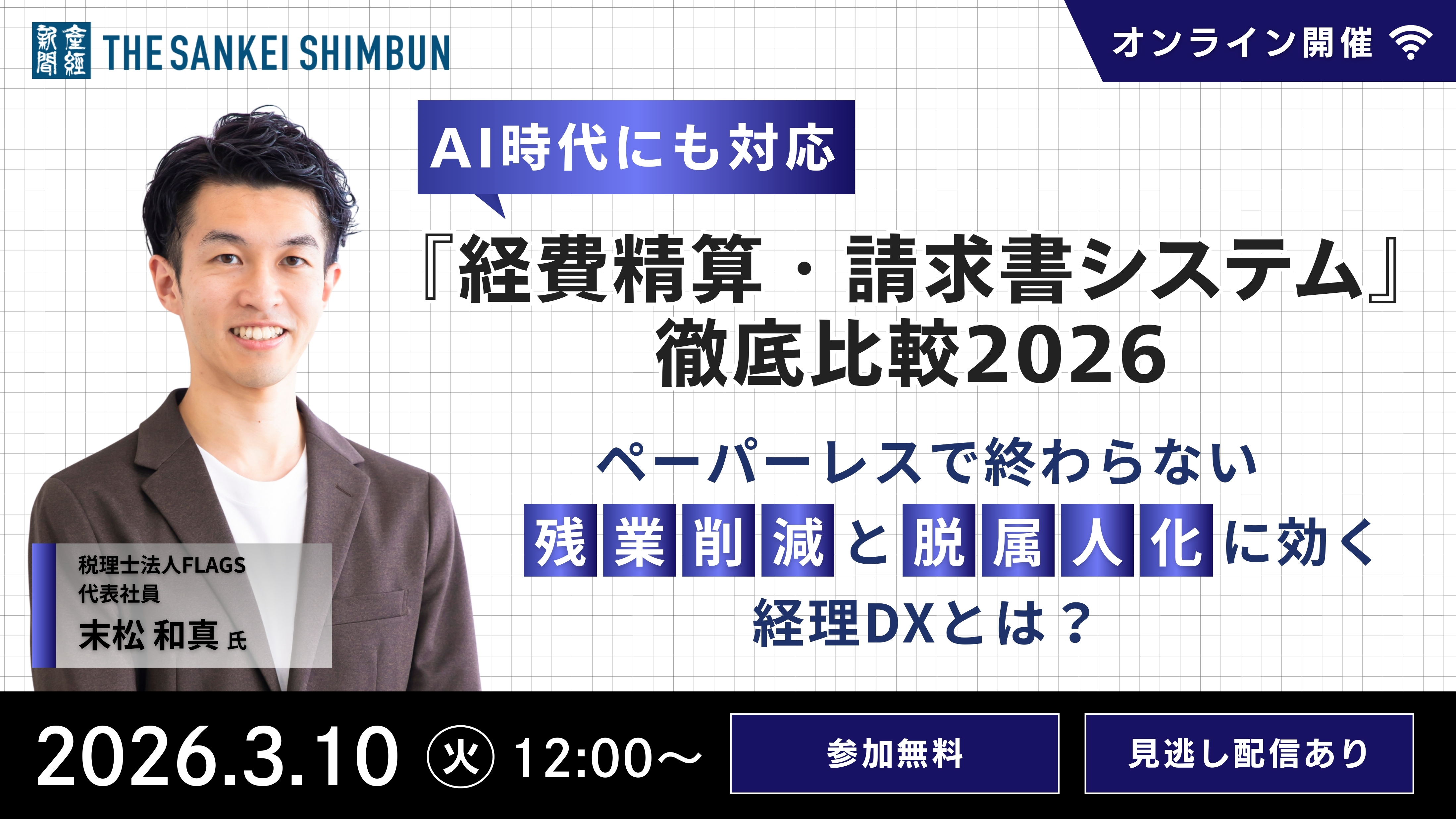公開日 /-create_datetime-/
割増賃金の計算ミスが命取り?「代休」と「休日振替」の運用ルールを徹底解説
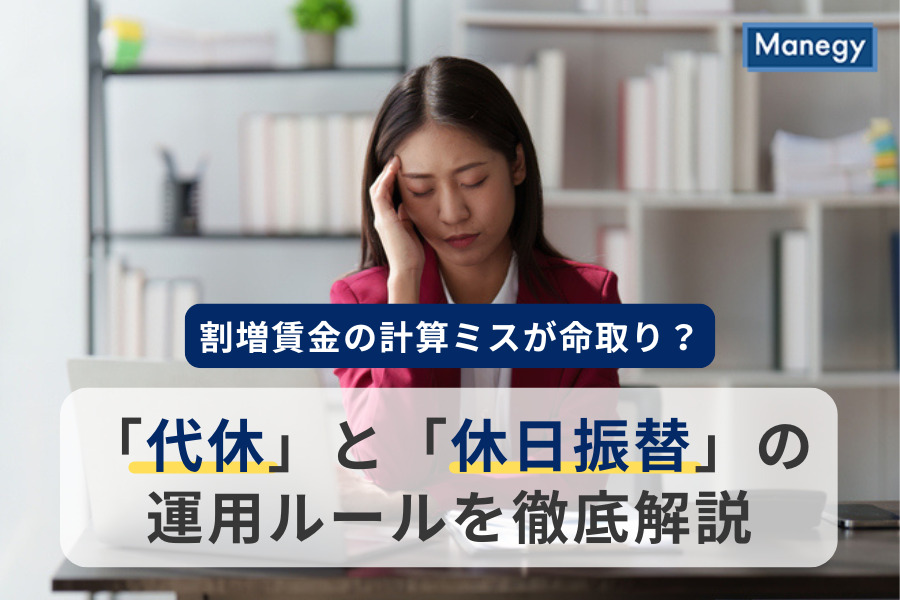
目次本記事の内容

▼この記事を書いた人
寺山 晋太郎
社会保険労務士
社会保険労務士法人 宮嶋社会保険労務士事務所
福島県出身。一橋大学社会学部卒業。大手鉄道会社にて現業や本社勤務など様々な業務を経験。2014年第一子誕生を機に育休を取得。その後現職に転じ、働きながら社労士資格を取得。社労士業の傍ら、3児の父親としても奮闘中。
1. 休日とは何か
まずは「休日」という概念をはっきりさせておきましょう。法令上明確に定義されているわけではないのですが、一般的には「労働契約上あらかじめ労働義務がないとされている日」のことを指します。
この休日の日数については、労基法第35条1項で「少なくとも1週間に1回」与えなければならない、とされておりますので、毎週必ず1回は休日があることになります。この労基法上必ず与えなければならないとされている休日のことを「法定休日」と呼びます。
ただ「週休二日制」という言葉があるように、休日が毎週2日あることも珍しくありません。この場合、法定休日ではない方の休日は「会社が任意に与えている」ものとなり、「法定外休日」もしくは「所定休日」などと呼称します。
労基法上は週1回で良いのに、なぜわざわざ週2回の休日を与える必要があるのかという点については、週の法定労働時間が40時間とされていることに関係します(労基法第32条1項)。つまり、所定労働時間が1日8時間であれば、5日間で週40時間となってしまうためそれ以上労働することができず、残り2日間は休日にしなければ法令違反となってしまうからです。
そのため、例えば月曜~金曜まで1日7時間労働なのであれば、土曜日に5時間働いてもらい、休日は日曜日のみにするという運用も法令上問題ありません。
「法定休日」と「法定外休日」を峻別する意味は、給与計算時の割増率に関係します。というのも、法定休日に労働させた場合は3割5分以上の割増率で計算しなければならないからです。これが法定外休日での労働であれば2割5分以上の割増率で良いので、法定休日の方が、割増率が高いことになります。
lockこの記事は会員限定記事です(残り4043文字)
会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-
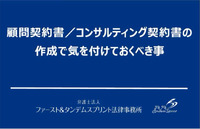
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

中堅企業はココで選ぶ! 会計システムの選び方ガイド
おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

又は・若しくはの違いとは?意味・使い分けと契約書での注意点を例文で解説
ニュース -

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下
ニュース -
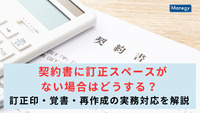
契約書に訂正スペースがない場合はどうする?訂正印・覚書・再作成の実務対応を解説
ニュース -
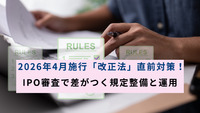
2026年4月施行「改正法」直前対策!IPO審査で差がつく規定整備と運用
ニュース -
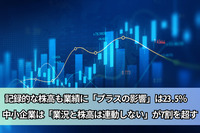
記録的な株高も業績に「プラスの影響」は23.5% 中小企業は「業況と株高は連動しない」が7割を超す
ニュース -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

【1on1ミーティング】効果的な実践方法と運用時のポイント
おすすめ資料 -

【離職率を改善】タレントマネジメントシステムの効果的な使い方
おすすめ資料 -
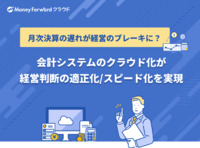
会計システムのクラウド化が経営判断の適正化・スピード化を実現
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

契約書の条ずれを発見したらどうする? 正しい修正方法と注意点を解説
ニュース -
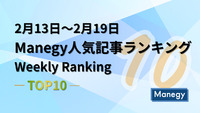
2月13日~2月19日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -
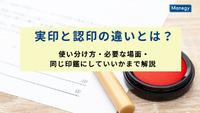
実印と認印の違いとは?使い分け方・必要な場面・同じ印鑑にしていいかまで解説
ニュース -

業務改善とDXの基本から実践まで|成功事例と進め方をわかりやすく解説
ニュース -

契約書のコンプライアンスチェックとは? 独禁法・2026年施行「取適法」・反社条項の論点とAI活用
ニュース