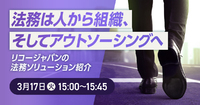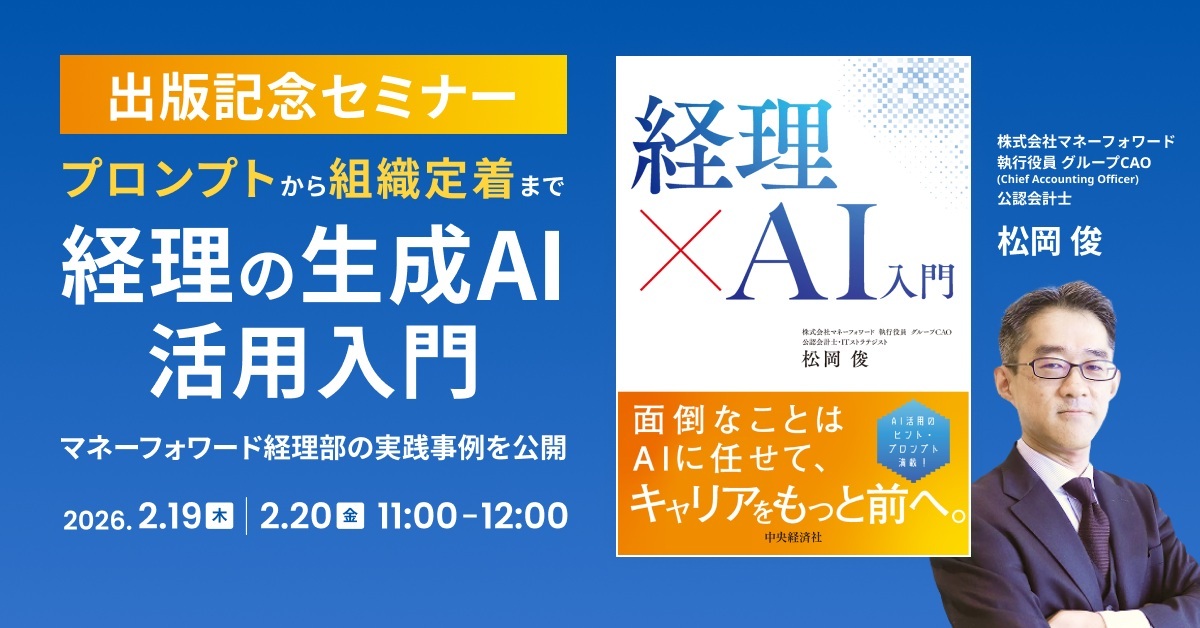公開日 /-create_datetime-/
【社労士執筆】時間外労働規制の最新動向と実務的対応策を労務担当者向けに解説
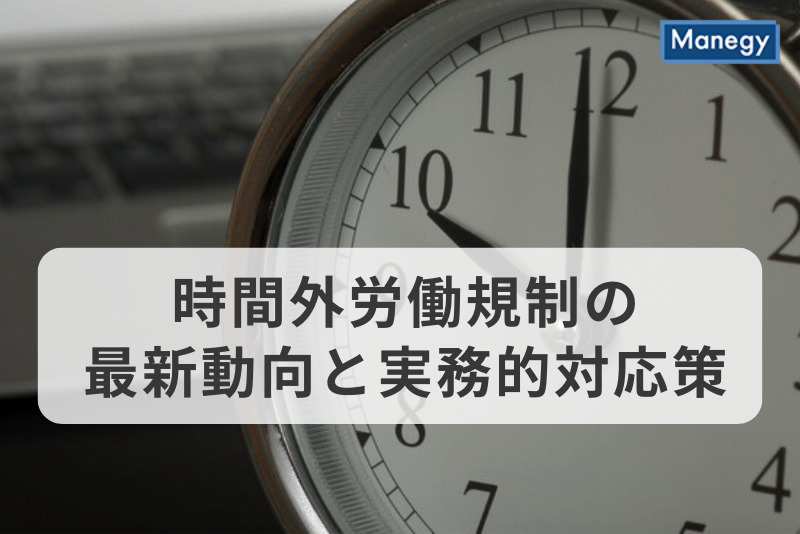
目次本記事の内容

▼この記事を書いた人
寺山 晋太郎
社会保険労務士
社会保険労務士法人 宮嶋社会保険労務士事務所
福島県出身。一橋大学社会学部卒業。大手鉄道会社にて現業や本社勤務など様々な業務を経験。2014年第一子誕生を機に育休を取得。その後現職に転じ、働きながら社労士資格を取得。社労士業の傍ら、3児の父親としても奮闘中。
1.時間外労働規制の基本
まず大前提を確認しておきましょう。使用者が労働者を働かせることができる時間は、労基法により1日8時間、1週間40時間までと決まっております(労基法第32条。ただし業種による特例有)。しかしながら、労働者の過半数を代表する者(過半数組合、過半数代表者)と使用者とが労使協定を締結し、労基署に届け出た場合に限り、その協定で定めるところにより時間外又は休日に労働させることができるようになります(労基法第36条)。
この労使協定は、条文にちなんで「36協定」と呼称されます。つまり、36協定を締結しない、もしくは締結したが労基署へ届け出ることをしないで法定労働時間を超えた労働を行わせた場合は、法令違反となってしまいますので注意が必要です。
また、36協定もいわば2種類あり、原則的な上限時間まで法定外労働が可能となるものと、トラブル対応など臨時の場合に原則的な上限時間を超えて時間外労働が可能となるものとがあり、後者を特に「特別条項付き36協定」と呼称します。特別条項付き36協定を成立させずに、原則的な上限時間を超えて法定外労働をさせてしまった場合も同様に法違反となります(上限時間の詳細は2で後述いたします)。
なお、かつては36協定さえ有効に成立してしまえば、実質的に時間外労働をさせ放題という状況でしたが、働き方改革の流れを受け、2024年4月よりすべての業種において、36協定が成立したとしても超えられない法的上限が設けられました。ただ、この法的上限の枠組みは少々複雑ですし、特定の業種(自動車運転の業務、医師、建設事業)には異なる規制が適用される部分もありますので、本稿ではあくまで一般的な業種に適用される原則的な規制について、次項以降でなるべくかみ砕いて解説していきます。
lockこの記事は会員限定記事です(残り4138文字)
会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-
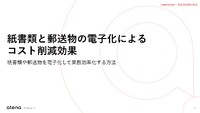
紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
おすすめ資料 -

優秀な退職者を「もう一度仲間に」変える 人材不足時代の新採用戦略
おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』
ニュース -

「円安」倒産 1月では10年間で最多の6件 43カ月連続で発生、負債は11倍に大幅増
ニュース -

消費税課税事業者とは?免税事業者や届出書の違い
ニュース -

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも
ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第3回 自社利用のソフトウェアの定義と会計処理等(企業会計と税務会計の違い)
ニュース -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
おすすめ資料 -

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ
おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -

新聞図書費とは?経理が押さえておきたい対象経費と仕訳の基本
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月20日号(通巻No.1768)情報ダイジェスト①/税務
ニュース -
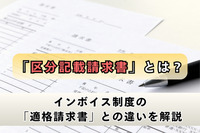
「区分記載請求書」とは?インボイス制度の「適格請求書」との違いを解説
ニュース -

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト②/会計
ニュース