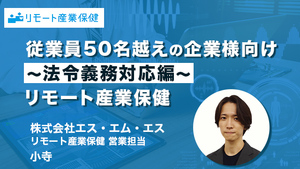公開日 /-create_datetime-/
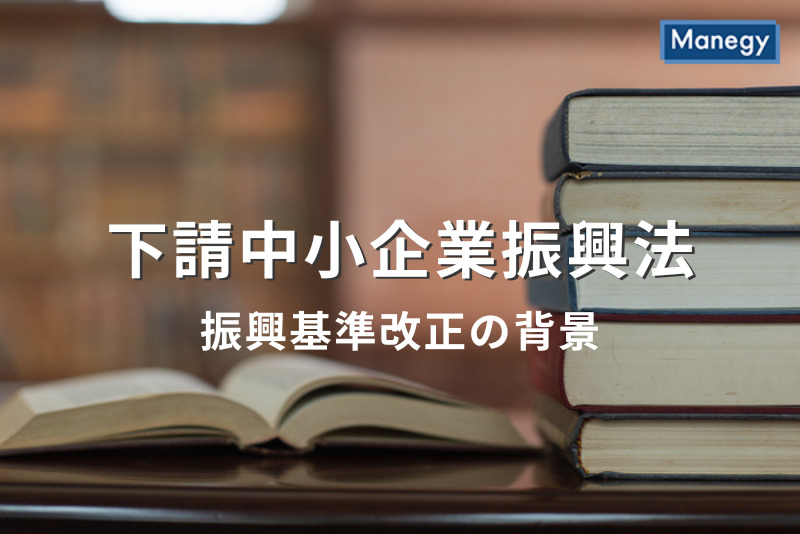
目次本記事の内容
この記事の筆者

牛島総合法律事務所
弁護士
猿倉 健司
牛島総合法律事務所パートナー弁護士。CSR推進協会環境部所属。 環境・エネルギー・製造・不動産分野では、国内外の行政・自治体対応、不祥事・危機管理対応、企業間紛争、新規ビジネスの立上げ、M&A、IPO上場支援等を中心に扱う。 「不動産取引・M&Aをめぐる環境汚染・廃棄物リスクと法務」「ケーススタディで学ぶ環境規制と法的リスクへの対応」のほか、数多くの著書・執筆、講演・ 研修講師を行う。
冨永 千紘
牛島総合法律事務所シニアアソシエイト弁護士。 コーポレート・M&A一般を取り扱うほか、独禁法・下請法等のコンプライアンス、ベンチャービジネス、ITサービス、支配権争奪、不祥事対応等に中心に取り扱う。
①:下請中小企業振興法とは?振興基準改正の背景
(1)振興法の概要(下請法との相違点)
(1)振興法の適用対象と下請法との相違点
下請中小企業振興法(以下「振興法」といいます。)は、親事業者の協力のもとに、下請事業者自らが、その事業を運営し、その能力を最も有効に発揮することができるよう体質を強化して独立性のある企業への成長を促すことを目的とする法律です。
下請事業者との取引の適正化を図ることを目的とする点で、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)と類似点も多いですが、下請法が規制法規(不適切な行為を取り締まるためのルール)であるのに対し、振興法は下請中小企業を育成・振興する支援するための規制である点で異なっています。
振興法上の「親事業者」とは、資本金又は出資金(個人の場合は従業員数)が自己より小さい中小企業者に対し、振興法が定める一定の行為を委託することを業として行うものをいいます(振興法2条2項)。「下請事業者」とは、中小企業者のうち、資本金等が自己より大きいものから委託を受けて,振興法が定める一定の行為の業として行うものをいいます(同条4項)*1。上記のとおり、振興法と下請法では法令の目的が異なることから、それぞれの法令が適用される取引は完全に一致していません。そのため、下請法が適用される取引であると同時に振興法が適用される取引となる場合もあれば、下請法は適用されないが振興法は適用される取引となる場合もある点には注意が必要です。
(2)したがうべき振興基準
振興法の内容は多岐にわたりますが、その一つに、下請中小企業の振興のための下請事業者、親事業者のよるべき一般的な基準(以下「振興基準」という。振興法3条)があります。振興基準が定める事項は概要以下のとおりです。
1.下請事業者の生産性の向上及び製品・情報成果物の品質・性能又は役務の品質の改善に関する事項
2.発注書面の交付その他の方法による親事業者の発注分野の明確化及び親事業者の発注方法の改善に関する事項
3.下請事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項
4.対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項
5.下請事業者の連携の推進に関する事項
6.下請事業者の自主的な事業の運営の推進に関する事項
7.下請取引に係る紛争の解決の促進に関する事項
8.下請取引の機会の創出の促進その他下請中小企業の振興のため必要な事項
振興基準には、下請法における規制と内容が重複するものも含まれています。そのような内容は、振興基準では「~することを徹底する」との形で規定されており、振興法が適用される取引においては、これを遵守しなかった場合に、振興法の指導・助言の対象となる場合があります*2。
(2)2024年11月振興基準改正の概要とポイント
今般、下請法に関して行われた直近の運用見直し等を踏まえ、振興基準のうち上記4(対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項)の内容について、以下のとおり一部改正が行われました(以下「本改正」といいます。)。 本改正は同年11月1日から施行されています*3。
1.買いたたきの解釈の明確化
2024年5月27日に公正取引委員会が「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(以下「下請法運用基準」という)を改正し、買いたたき(下請法4条1項5号)の解釈の明確化したことを踏まえたもの
2.手形等の支払サイトを60日以内とすることを徹底化
2024年4月30日に公正取引委員会が手形等の指導基準について、手形等の交付から満期日までの期間を120日から60日に見直したことを踏まえたもの
*1鎌田明『下請法の実務(第4版)』208頁(2017年)
*2なお、振興基準で「~するものとする」との形で規定されているものについては、規範性が高く、個別事案の問題性の大きさ等を踏まえ、場合によって下請中小企業振興法上の指導・助言の対象となり得るとされています。他方で、「~するよう努めるものとする」との形で規定されているものについては、 全ての事業者が必ず行う取組ではないが、ベストプラクティスとして事業者に目指してほしい取組とされ、直接的に指導・助言の根拠とすることは想定されていません(中小企業庁ウェブサイト(https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq13B_shinkoukijyun.html#q7))。
*3経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/press/2024/11/20241101001/20241101001.html)
lockこの記事は会員限定記事です(残り6867文字)
会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-
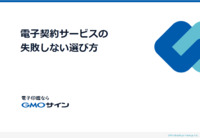
「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割
おすすめ資料 -
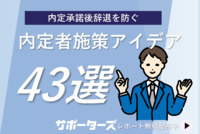
【内定者フォロー施策】内定承諾後辞退を防ぐ 内定者フォロー施策アイデア43選
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料
おすすめ資料 -
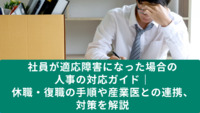
社員が適応障害になった場合の人事の対応ガイド|休職・復職の手順や産業医との連携、対策を解説【医療法人社団惟心会/株式会社フェアワーク】
ニュース -
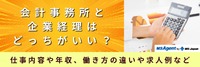
会計事務所と企業経理はどっちがいい?仕事内容や年収、働き方の違いや求人例など
ニュース -

初めての障害者雇用を支援!東京都中小企業障害者雇用スタート支援奨励金とは
ニュース -

育休明けの有休付与|付与日数計算・年5日取得義務・2025年10月法改正まで人事担当者向けに徹底解説!
ニュース -

高齢労働者の「転倒」を防ぐために~2025年度の全国安全週間が始まりました~
ニュース -
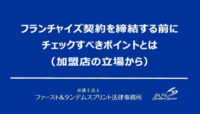
フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -

Docusign CLM 導入事例(ウーブン・バイ・トヨタ株式会社)
おすすめ資料 -

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築
おすすめ資料 -
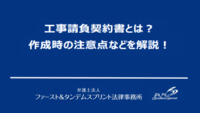
工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -

Adobe Acrobatで電子署名する方法とその見え方
おすすめ資料 -

中堅・中小企業における海外進出のメリットとは
ニュース -
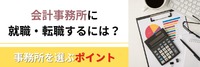
会計事務所に就職・転職するには?事務所を選ぶポイント
ニュース -

共有リンクの有効期限設定が重要な理由とは?安全なファイル共有を実現する設定方法と注意点
ニュース -

【企業向け】動画ファイル管理の課題と解決策
ニュース -

令和7年度税制改正のポイント 第1回 税制改正の概要と「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行の実現に向けた税制措置
ニュース









 ポイントをGETしました
ポイントをGETしました