公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
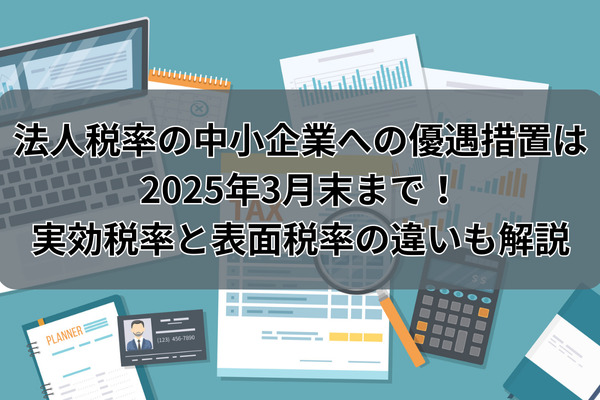
企業に対して課せられる代表的な税の1つが法人税です。法人税率については、経理部門の人にとって理解は必須ですが、他部署の人もビジネスマンの基本知識として理解しておくと、企業組織に対する認識をより深められます。
そこで今回は法人税とその税率について深掘りし、中小企業に対して取られている優遇措置や、実効税率と表面税率の違いなどについて詳しく解説します。
法人税とは、法人の事業活動で得た所得に課せられる国税のことです。ここでいう所得とは、「法人税の課税所得=益金(売上・売却等で得た収入)-損金(売上原価・販売費・損失費用等)」で算出されます。益金、損金は税法上の表現で、会計上で当てはめると益金は収益、損金は費用におおむね該当します。
法人であっても公共法人(自治体、日本年金機構、地方独立行政法人、日本政策金融公庫、NHK、日本中央競馬会、国立大学法人など)は課税対象外です。また「法人」を対象とする課税なので、所得税が課税される個人事業主は対象外となります。
法人を対象とする税金には法人税以外に地方税である法人事業税、法人住民税などもあり、会計関連の書類等ではこれらをひっくるめて「法人税等」と略されて表記されるのが通例です。
法人が得た所得に課せられる具体的な法人税率は以下の通りです。
・中小法人・・・年間所得の800万円以下の部分については、軽減税率の適用事業者だと15%、適用除外事業者だと19%。800万円超の部分については23.20%。
・中小法人以外の法人(大規模法人等)・・・23.20%。
軽減税率とは所得が低い課税者に配慮して軽減された税率のことで、法人税の場合は中小法人が対象となります。
中小法人の要件は2019年度の税制改正で変更されていて、今後も変わる可能性もありあますが、2024年現在は以下をすべて満たす法人が対象です。
・資本金が1億円以下
・大規模法人によって、発行株式数の2分の1以上所有されていない
・複数の大規模法人によって、発行株式数の3分の2以上所有されていない
・常時雇用する従業員数が1,000以下
以上の要件に当てはまる場合は軽減税率が適用され、年間所得800万円以下の部分については法人税率が15%となります。ただし以上の要件を満たす中小法人であっても、「過去3年間の平均所得金額の平均が15億円超」だと「適用除外事業者」とされ、その場合は年間所得800万円以下の部分における法人税率は19%です。
中小法人に当てはまる場合でも、課税所得額は法人によって大きく異なります。「年間所得800万円以下の部分」という軽減税率対象の設定は、たとえば年間所得1億円規模の中小法人にとっては微々たる負担減効果しかありません。しかし年間所得1,000万円程度の法人にとっては、大きな負担減です。その意味で、同じ中小法人でもより小規模の法人を救済するのが、法人税率における軽減税率導入の目的といえます。
この中小法人を対象とする軽減税率は2023年3月31日で終了する予定でしたが、令和5年度税制改正大綱において2年間の延長が決まり、2025年3月31日まで継続されています。つまり令和6年度をもって終了するため、軽減税率の恩恵を受けていた小規模の法人には今後大きな影響が生じます。
法人税率においては「実効税率」と「表面税率」の区別について理解しておくことも重要です。
先にも述べた通り、法人に課せられる税率には法人税のほかに、法人事業税と法人住民税があり、会計上の書類などでは、「法人税等」としてまとめられて記載されるのが通例です。その「法人税等」の税率を考える上で、実効税率と表面税率の違いの理解が必要になります。
表面税率とは税法上定められた税率のことです。つまり法人の年間所得に課せられる法人税、法人事業税、法人住民税について、税法で規定されている税率を税法上通りに合計したものが表面税率とされます。
一方、実効税率とは、企業が実際に負担する税金額を正確に導き出すために使われる税率のことです。
実効税率を考える上で重要になるのが、「損金」の扱いです。先述の通り、課税所得の計算は益金(収益)から損金(費用)を差し引いて算出されます。つまり法人側としては損金が大きいほど節税につながります。
そして現行の税制上においては、法人税、法人事業税、法人住民税のうち、法人税と法人住民税は翌期の損金として扱うことはできませんが、法人事業税については翌期の損金として扱うことが可能です。法人事業税を損金として扱うと、法人税と法人住民税を計算する際に用いられる課税所得の額が減少するため、実質の税率は税法上の税率よりも減少します。
つまり、法人事業税を損金として扱った上で算出された法人税等の税率が、実効税率であるのです。実効税率は表面税率よりも低くなり、計算される税額は実際の税負担額により近い金額となります。
とくに人的資源に限りがある中小企業にとっては、法人税をはじめとする税務申告関係の作業はアウトソーシングした方が、人材を本業に集中させられるのでより合理的です。
税務申告サービスを選ぶ際は、以下の点に注意しましょう。
税務申告サービスの利用方法としては、社内に提供システムを導入して自社で運用するオンプレミス型、提供されるクラウドサービスを利用するクラウド型、ソフトをPCにインストールするパッケージ型などがあります。どの方法が自社に適しているのかを検討して選択しましょう。
一定規模以上の法人向けのサービスの場合、経理部門にある程度人員がいることを想定したサービス内容なので、経営者が経理も担うような小規模法人には適しません。サービス内容がどのような企業を対象としたものかを把握しておく必要があります。
導入時の支援やアフターサービスの内容など、サポート体制がどの程度充実しているかを検討した上で、税務申告サービス事業者を選びましょう。
税務申告サービスはこちらからご確認ください。
https://www.manegy.com/service/tax_system/
中小法人を対象とした法人税の軽減税率は、2025年3月31日が期限です。対象の企業は税務内容の変更に注意しましょう。また税制の内容は改正によって大きく変更するため、経営者・経理担当者は改正が行われるたびに変更点をチェックすることが重要になります。法人税をはじめ税額計算は複雑なので、人員に限りがある場合は税務申告サービスを利用することをおすすめします。
【参考サイトまとめ】
税務のサービス一覧
JINJER Blog
いっしょに税理士法人
マネーフォワード
国税庁
三菱UFJニコス
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも

労基法大改正と「事業」概念の再考察 ~事業場単位適用の実務~

AIの反社チェック・コンプライアンスチェック 信じちゃダメです。本当に絶対ダメです。

②労災事故発生時の対応と届出│労働者死傷病報告提出のタイミング~労働者死傷病報告の方法と内容

採用計画で市場価値を上げる8つのスキル|戦略人事へのキャリアパスを徹底解説【転職成功事例つき】(前編)

経理業務におけるスキャン代行活用事例

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

フランチャイズ契約とは?ロイヤリティ・テリトリー・競業避止など契約条項を徹底解説
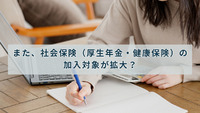
また、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象が拡大?

自己理解の深化が退職予防に影響、2306人を調査

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ

①労災事故発生時の対応と届出│「労災隠し」とは
公開日 /-create_datetime-/