公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。
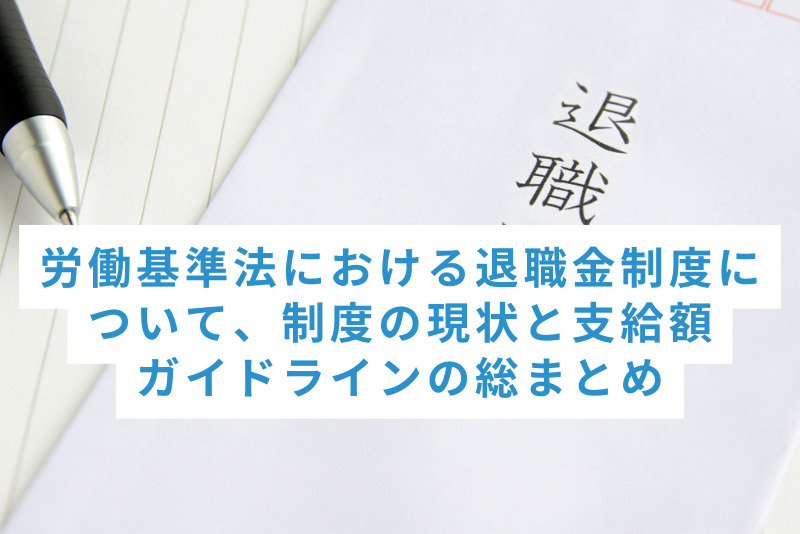
転職が一般的になった現在でも、長期間勤続する社員にとって退職金の額は依然として重要です。その退職金の相場はどのくらいで、実際にはどの程度の金額が支給されているのでしょうか。今回の記事では退職金制度の仕組みや計算方法について解説します。
退職金そのものは各企業の判断による任意の制度ですが、多くの企業は現在でも退職金制度を継続しています。制度のある企業では就業規則もしくは退職金規程の中で、対象になる社員、計算方法、支給方法などを定める必要があります。
退職金制度は労働基準法で規定されており、所得税法でも所得控除などの優遇措置の対象になっています。ただし、法的に義務化されているわけではありません。支給方法にも決まった形はなく、それぞれの企業が独自の基準で計算・支給を行います。
厚生労働省の2023年調査によると、退職金制度を設けている企業は全体の74.9%でした。5年前の調査では80.5%だったことから、やや減少傾向にあるといえるでしょう。制度の有無は企業規模によって異なり、1,000人以上の企業では約90%なのに対して、100人以下の企業では約70%と開きがあります。
また、同じ調査による退職金の平均支給額は、勤続20年以上で45歳以上の退職者の場合、大学・大学院卒が1,896万円(月収×36ヶ月)で、高卒は1,682万円(月収×38.6ヶ月)でした。どちらも管理・事務・技術職の数値です。
【出典】
「退職給付(一時金・年金)の支給実態」厚生労働省上記の資料では、月収で何ヶ月分かという目安で支給額を示しましたが、退職金の計算方法は複数あり、主に以下のような基準で算出されています。
● 勤続年数ごとに決められた金額を支給する定額制
● 基本給に勤続年数ごとの支給率を掛けて算出する方法
● 基本給とは別に退職金基準額を決め、その額に勤続年数ごとの支給率を掛ける方法
● 基本給、勤続年数、役職などを総合的に判断して算出する方法
基本給は勤続年数に合わせて上がるため、基本給を基準にすると企業の負担が重くなります。一方で定額制にすると、役職や実績などが加味されません。判断が難しいところですが、企業規模や過去の実績などに準じて計算方法を選ぶことが一般的です。経理や総務の業務負担が大きい場合には、給与計算システムの導入も検討してみましょう。
退職金は計算方法と同様に、支給方法にも種類があります。退職時に一括で支給する一時金という方法が一般的ですが、退職後に年金のように支給する方法もあります。しかし現在はキャリア途中での転職が増えているため、退職金制度を設けない企業も徐々に増加しているようです。
企業の経営資金だけでは退職金の準備が難しい場合、中小企業退職金共済制度(中退共)を利用するという方法もあります。これは毎月納付する掛金に、国が助成金をプラスして退職金に充当する制度です。多くの企業が活用しているので、必要であれば一度相談することをおすすめします。
一昔前のように、新卒で入社して定年退職を迎えるという働き方は減りつつあります。しかし退職金制度の有無が、職場定着率の向上と勤続年数の長期化に影響することも事実です。これからの企業には、多様なキャリア形成を踏まえた、柔軟な退職金制度が求められるのではないでしょうか。
【参考サイト】
「労働基準法における退職金の規定とは?」咲くやこの花法律事務所 「退職給付(一時金・年金)の支給実態」厚生労働省※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

【離職率を改善】タレントマネジメントシステムの効果的な使い方

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説

サーベイツールを徹底比較!

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
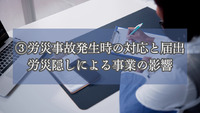
③労災事故発生時の対応と届出│労災隠しによる事業の影響
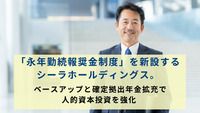
「永年勤続報奨金制度」を新設するシーラホールディングス。ベースアップと確定拠出年金拡充で人的資本投資を強化

法務の転職は「コンプライアンス経験」が武器になる!履歴書・職務経歴書でのアピール方法と成功事例(前編)

『不調になってから』では遅い Smart相談室が描く、個人と組織の成長が一致する職場のつくり方
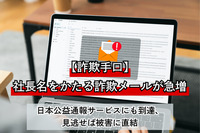
【詐欺手口】社長名をかたる詐欺メールが急増 日本公益通報サービスにも到達、見逃せば被害に直結

優秀な退職者を「もう一度仲間に」変える 人材不足時代の新採用戦略

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

2026年版「働きがいのある会社」ランキング発表 全部門で日系企業が首位を獲得

消費税課税事業者とは?免税事業者や届出書の違い

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも

労基法大改正と「事業」概念の再考察 ~事業場単位適用の実務~

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第3回 自社利用のソフトウェアの定義と会計処理等(企業会計と税務会計の違い)
公開日 /-create_datetime-/