公開日 /-create_datetime-/
【弁護士執筆】2025年5月までに施行|重要経済安保情報保護活用法のポイントをわかりやすく解説

目次本記事の内容
1. 重要経済安保情報保護活用法とは?法律の背景や目的
重要経済安保情報保護活用法は、いわゆるセキュリティ・クリアランス制度を定めた法律といわれています。「セキュリティ・クリアランス」とは、国家における情報保全措置の一環として、政府が保有する情報のうち安全保障上重要な情報を指定し、政府職員や民間事業者のうち、その情報にアクセスする必要がある者について、政府が調査を実施した上で、情報を漏らすおそれがないことが確認できた場合に限り、その情報へのアクセス権を認めることが通例とされています。
このようなセキュリティ・クリアランスに関する法制度は、日本以外の多くの国では既に整備されているものです。そのため、民間事業者においては、同盟国・同志国との間で国際的な共同研究を推進したり、政府案件の入札に参加しようとする際に、日本ではセキュリティ・ クリアランス制度が整備されていないことを理由としてこれらから排除されるといった支障が生じていました。
重要経済安保情報保護活用法が施行されることによって、そのような支障が解消されることが期待されます。
lockこの記事は会員限定記事です(残り7102文字)
会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス
おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ
ニュース -

①労災事故発生時の対応と届出│「労災隠し」とは
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト②/会計
ニュース -

不動産業界の定説を覆す「営業社員の土日祝休み」導入 三井不動産レジデンシャルのデジタル改革
ニュース -

役職定年・定年延長時代に問われる「シニア人材マネジメント」 ―45〜60歳を“戦力”にできる組織、できない組織の分かれ道
ニュース -

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説
おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
おすすめ資料 -

産業医の探し方|初めての選任で失敗しない4つのポイント
ニュース -

棚卸評価損の仕訳とは?計算方法・仕訳例・評価方法をわかりやすく解説
ニュース -

人事異動はどう考える?目的別の判断軸と現場に納得される進め方
ニュース -
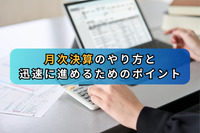
月次決算のやり方と迅速に進めるためのポイント
ニュース -

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増
ニュース






































