公開日 /-create_datetime-/
管理部門で働かれている方の業務課題を解決する資料を無料でプレゼント!
経理・人事・総務・法務・経営企画で働かれている方が課題に感じている課題を解決できる資料をまとめました!複数資料をダウンロードすることで最大3,000円分のギフトカードもプレゼント!
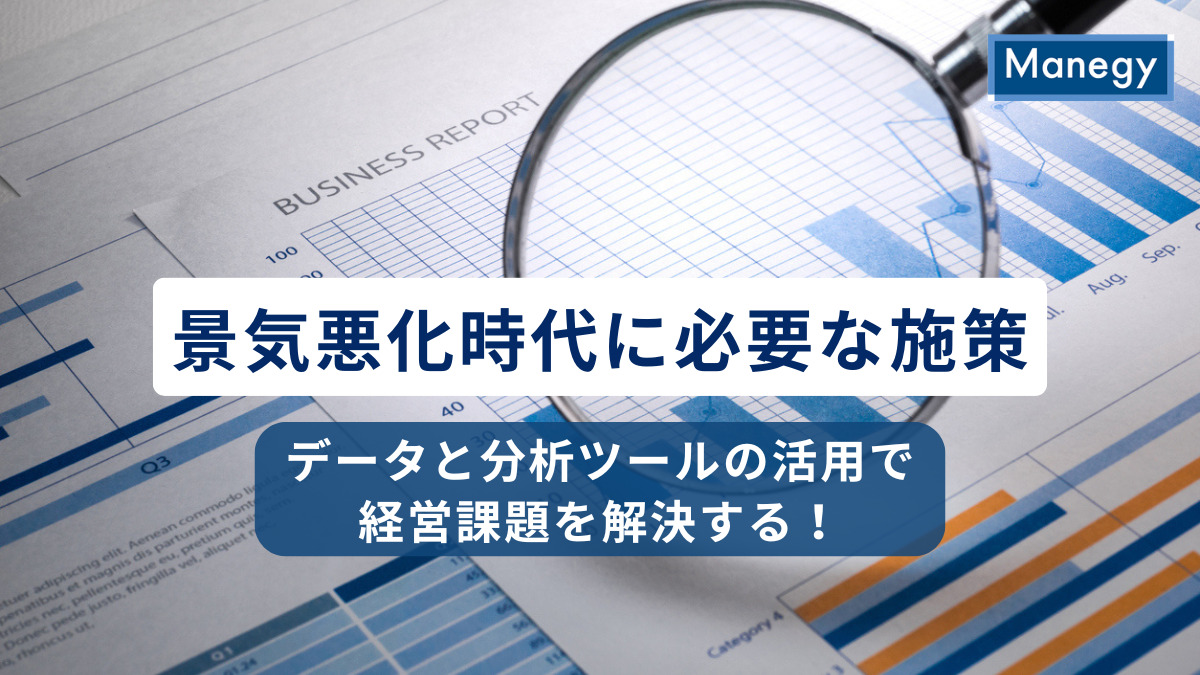
クラウド型業務システムを無料で提供している株式会社フリーウェイジャパン(本社:東京都中央区)は、「2024年下期経営状況に関するアンケート」を実施しました。対象は、中小および零細企業の代表取締役・個人事業主256人と従業員83人の計339人です。
アンケートではまず、回答者自身が働いている会社・業界の景気について、どのように感じるかを聞きました。
結果は、「悪くなっている」が29.5%、「やや良くなっている」が24.5%、「変化なし」が22.4%、「やや悪くなっている」が19.5%、「良くなっている」が4.1%でした。 「悪くなっている」と「やや悪くなっている」を合わせると49.0%で、この数字は2023年度下期に行われた同調査と比べると10.9ポイント増えています。「良くなっている」と「やや良くなっている」を合わせた28.6%よりも20ポイント以上高い数値です。
また、2024年度下期の営業利益は同年度上期と比較してどうだったか聞いたところ、「変化なし」が53.4%、「悪化」が23.9%、「改善」が22.7%でした。
上記の結果から、中小および零細企業の2024年度の経営状況は厳しいものだったことが明らかになりました。
中小および零細企業は日本の全企業数のうち99.7%を占めており、そのなかで景気悪化を感じる企業が増えています。本記事では、厳しい局面に立つ企業がすべきこと、とるべき対策は何かを解説していきます。
【参照調査概要】
調査名:2024年下期経営状況に関するアンケート
調査元:株式会社フリーウェイジャパン
(掲載サイト https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000061444.html)
フリーウェイジャパン社の「2024年下期経営状況に関するアンケート」の結果によると、中小および零細企業においては景気悪化を感じているところが増加しています。ただし、景気悪化を感じる根拠が何によるものなのかを見極める必要はあります。ここでは、その根拠を見極めるためにすべきことについて触れましょう。
自社の景気や経営状況を判断する際には、景気や経営状況を「肌感覚」で判断するのではなく、現状を正しく把握するために「定量的なデータ」を用いることが重要です。経営状況を判断するための定量的なデータとは、主に「売上」「利益率」「受注量」など。例えば、営業利益が黒字でも、キャッシュフローや固定費の増加によって経営が圧迫されているケースがあります。経営状況を分析するには、以下のデータを用いるのが望ましいでしょう。
これらのデータを定期的に分析することで、現状の自社の正確な経営状況を判断できます。
では、なぜ「定量的なデータ」を分析すると経営状況を判断できるのでしょうか? 主な理由は以下の2つです。
(1)経営戦略の方向性を見極める基礎となるから
データの分析結果は、経営層が正しい意思決定を行なうための土台となります。例えば、経営戦略を現状維持する企業が多いときに、自社のデータを分析すると、どの事業領域を拡大すれば売り上げ増につながるかという「軸」を見出すことができるでしょう。また、データ分析によって、コスト削減の対象や優先順位を明確にすることもできます。
(2)リスクを早期に察知することができるから
データ分析によって、自社の経営状況におけるリスクを早期に察知できます。例えば、売上や利益率などの数字を分析した結果、販売価格の問題点や取引先の経営異常を見つけられるかもしれません。その問題点や異常に早めに対応することで、自社の損失を最小化できるでしょう。また、業界平均値との比較による「自社の立ち位置」も把握でき、今後の事業展開を決められます。
以上のことから、現状の自社の景気や経営状況を判断する際は、「定量的なデータ」を分析し、活用することが大切なのです。
前述のフリーウェイジャパン社のアンケート結果によると、「2024年度下期の営業利益は悪化した」と回答した企業は23.9%、「2025年度上期の営業利益の見通しは赤字」と回答した企業は28.0%でした。この結果から、多くの企業が収益性に課題を抱えており、競争環境や市場の変動が利益率を圧迫していることがわかります。
営業利益の悪化には、以下2つの大きなリスクがあります。
・短期的な影響
キャッシュフローの悪化による運転資金の不足。特に、中小企業ではこの影響が顕著です。また、経費削減圧力が高まり、必要な投資(設備更新や人材採用)が停滞しがちになります。
・長期的な影響
収益率の低下は、競争力の喪失につながる恐れがあります。また、利益が減少することで、新たな事業開発やイノベーションが鈍化し、成長の機会を失います。
では、収益性に課題を抱えないために必要なことは何でしょうか? それは「経営戦略に必要な分析視点」を持つことです。分析の際には特に注視すべき指標があり、管理部門がこれらを提示することで各部門も判断しやすくなります。主な指標は以下の4点です。
管理部門は経営戦略を先導する立場ではありませんが、さまざまな対策を講じて各部署をサポートすることが求められています。主に、以下3つの対策をとることができます。
(1)データを収集し、可視化できるようにする
営業利益悪化の原因を明確にするため、データ収集や可視化ツール(BIツールや分析ツール)の導入を提案する。
(2)早期警戒システムの構築
営業利益が一定の基準を下回った場合の早期アラートや迅速な対策立案を可能にする仕組みを構築する。
(3)コスト削減と投資の最適化を図る
固定費の削減に取り組みつつ、必要な領域(デジタル化や成長事業)には積極的に投資する。

フリーウェイジャパン社のアンケート結果によると、2024年度下期に事業戦略やビジネスモデルの見直しを実施した企業は25.4%のみでした。この数字は、2023年同時期と比べて6.4ポイント減少しています。見直しを実施しなかった、つまり事業戦略が停滞している企業は74.6%も占めているのです。
企業の事業戦略停滞には、いくつかのリスクがあります。まず、市場競争に遅れること、つまり競合他社に対する競争力の喪失です。また、新たな収益源の創出機会を失う恐れもあります。事業戦略は新規事業の創出につながるため、その機会がなければ新たな収益源も生まれません。さらに、事業戦略の停滞は顧客満足度や従業員のモチベーションの低下も引き起こします。既存の事業のみの経営はサービス向上につながらず、社内外からの期待に応えられない状態となります。
事業戦略の停滞には複数の要因があります。管理部門が以下の要素に注目して対策を講じることで、停滞は避けられます。
また、事業戦略やビジネスモデルを見直す際に必要なデータを管理部門が把握し、各部署にそのデータを共有することも有効でしょう。必要なデータの一例は以下のとおりです。
フリーウェイジャパンのアンケート結果では、賃金を「引き上げ予定(引き上げ済み)」と回答した企業は29.2%にとどまり、最多回答は「変動はない」(44.2%)でした。このことから、多くの企業では給与面での改善が難しい状況と言えます。
人材不足の時代において、企業が従業員の離職防止や新たな人材の確保を実現させるためには、給与面以外で従業員満足度を上げる対策が必要です。特に、人材不足が経営悪化に直結しやすい中小企業では、従業員満足度の向上は経営課題として必要不可欠でしょう。
従業員の満足度は企業の業績に大きな影響を与えます。従業員の満足度が高ければ、生産性向上や離職率低下、顧客満足度の向上につながります。しかし、自社の従業員の満足度がどの程度なのかを知ることは容易ではありません。
そこで、従業員満足度向上の施策に向けて有効なのが、各種データを活用することです。データによって施策の効果が表れているかを測ることができます。一例として、以下のデータが参考になるでしょう。
ここでは各種データのほか、従業員アンケートも加えて活用する具体例をご紹介します。
(1)従業員アンケートと業績データの連携分析
従業員アンケートの結果(例えば、働きがいや福利厚生への満足度など)とデータを結び付け、施策の優先順位を明確化。
(2)離職防止のためのデータドリブンアプローチ
離職者データ(年齢層、勤続年数、部署など)を分析し、離職のリスクが高い従業員の特徴を特定。離職防止に向けた早期介入策(キャリアパスの見直し、柔軟な勤務形態の導入など)を提案する。
(3)パフォーマンス評価データと報酬の最適化
パフォーマンス評価データを活用し、成果に基づいた公平な報酬制度を設計。評価結果が給与やインセンティブにどの程度反映されているかを可視化することで、透明性を向上させる。
従業員満足度向上の施策において、管理部門ができることは主に以下のとおりです。
(1)KPIの設定とモニタリング
離職率や生産性、従業員満足度のスコアなど、定量的な指標を設定し、定期的にモニタリングを実施する。
(2)データの収集と活用フローの整備
経営データを収集・分析するためのツール(※後述参照)や人事管理システムの導入を検討する。
(3)施策効果の検証
実施した施策がどの程度、経営指標や従業員満足度に影響を与えたかを継続的に検証する。
前項でご紹介したとおり、従業員満足度向上の施策で管理部門ができることのひとつとして、経営データの収集・分析用のツール(※経営分析ツール)を導入することがあります。経営分析ツールは、経営管理に関する膨大な量のデータを、短時間で集計・分析して結果のレポートを出力できるものです。
利用する最大のメリットは、経営判断や経営課題の解決をリアルタイムで実現できること。経営分析ツールはさまざまな製品があり、導入時は迷うかもしれません。そこで、各製品を比較する際は以下の点に注目してみるとよいでしょう。
なかでも「マネジー」がおすすめするのは下記4製品です。

出所:Sactona公式サイト
アウトルックコンサルティング株式会社
クラウド版をご用意!利用しやすい価格プランで迅速に導入。規模・業界不問。「Sactona」は、経営管理を高度化・効率化するための経営管理システムです。Excelそのものの操作感で即定着を促し、貴社が描く経営サイクルを実現化するためのサポートをいたします。

「CCH Tagetik」は、統合型の企業経営管理プラットフォームです。グループ全体から個別の事業まで、一つのシステムで管理可能!従来製品にはない圧倒的な使いやすさと柔軟性で、次世代の経営企画、経理、財務部門の予算管理業務を統合的に支援。経理・経営管理部門が直面している課題を理解し、ビジネスプロセスの効率化と高度化を支援します。

出所:補助金コモン公式サイト
「補助金コモン」は、戦略的な補助金・助成金申請をサポートする顧問サービスです。プランは月額5万円から。年間における設備投資・採用コストを最大90%削減し、貴社の強みの最大化に貢献します。

出所:SoLabo公式サイト
融資支援業務をサポート!3,700件以上の実績!「SoLabo」(ソラボ)は、国の認定支援機関として融資支援サービスを完全成功報酬で提供。融資申請に必要な書類作成や金融機関とのやり取りの補助、面談対策など、面倒な融資に関する手続きを全面サポート。豊富な経験と知見から最適な調達方法をご提案いたします。
本記事では、中小および零細企業において景気悪化を感じるところが増えている厳しい局面で、企業がすべきことやとるべき対策について解説しました。
まず、自社の景気や経営状況を正しく把握するためには、「定量的なデータ」を用いることが重要です。そして、収益性に課題を抱えないために必要なのは「経営戦略に必要な分析視点」を持つことで、分析の際に注視すべき指標を管理部門が提示することで各部門が判断しやすくなります。
また、企業は給与面の改善が難しい場合、従業員の離職防止や新たな人材を確保するために、給与面以外で従業員満足度を上げる対策が必要です。 2025年は景気悪化を感じない経営を目指すべく、ぜひ自社で対策に取り組んでみてはいかがでしょうか?
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料
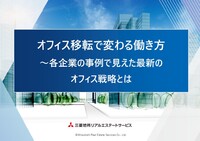
オフィス移転で変わる働き方

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

【最大16,000円】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』に参加してAmazonギフトカードをGET!
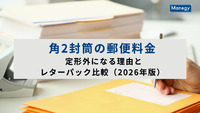
角2封筒の郵便料金|定形外になる理由とレターパック比較(2026年版)
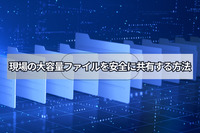
現場の大容量ファイルを安全に共有する方法

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!

セキュリティ対策評価制度自己評価の進め方

サーベイツールを徹底比較!

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念

ヒエラルキー組織における意思決定の高速化と最適化

なぜ使われない?クラウドストレージ定着を阻む3つの壁

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く

大容量ファイル同期の課題を解決!法人向けオンラインストレージ選定ガイド
公開日 /-create_datetime-/